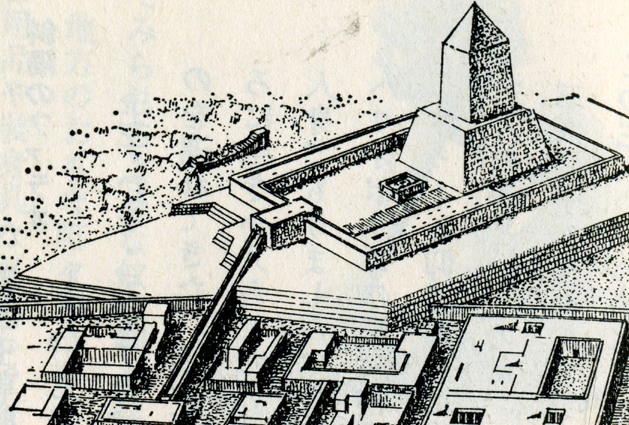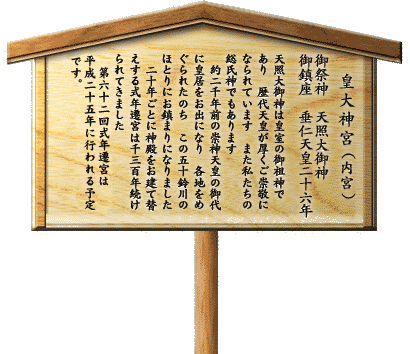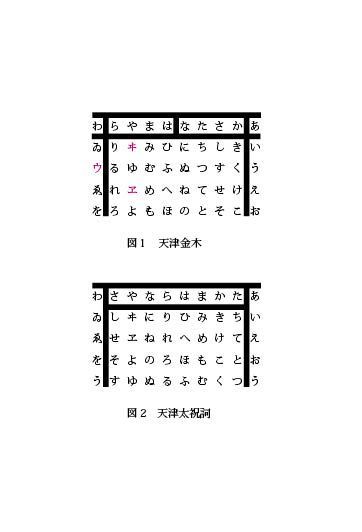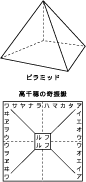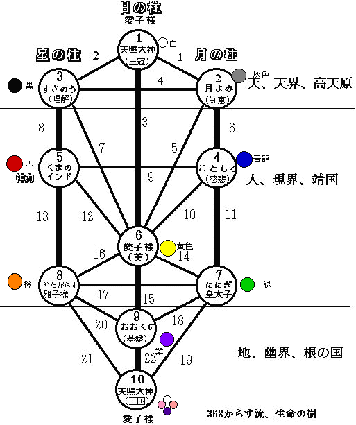『聖櫃』が有るとしたら秦河勝の墓が有り坂越大避神社や妙見寺前の海に有る無人島『生島』(いくしま)が怪しい!ここは神域とされ、国保護の原生林を保持、無断で入ると神罰が有るとされています。坂越の大避神社の秋祭りには、神社から生島に渡る神事も有ります。船渡御(ふなとぎょ)と言います。もしかすると『聖櫃』を運んだ時の状態を祭りにしているのかも?』 http://home10.highway.ne.jp/ikko/Japanese/Frame_N_... 

この紹介されている生島(いくしま)が昔から社の禁足地だったことは驚くべきことだ。生島の何かを守るためであろう。廣門氏が推理するように『聖櫃』を隠すには条件が整っている。神社の禁足地は、単に自然を守るためだけではないからである。秦河勝が南波尺師の浦で治水干拓、開墾を行った記録から、一体、それがどのように事跡となっているのか疑問となるのである。生島に河勝の墓があるということで、ますます、秘密めいた島になってきた。河勝はこの地で没した。秦河勝の墓が生島にあって、ほっとした。 「私は赤穂市在住のモノです。少し発見したので御報告させて下さいませ。坂越の事を昔は佐古志と言っていた…しゃくしと読んでいた…との事ですが、私は赤穂市の地図を見て発見したのですが、千種川は北斗七星です。 秦氏が作ったとされる千種川は北斗七星です。現在、大酒も含め川沿いに七つの社が存在します。川の形も北斗七星の形に似ており、故に『しゃくし』だったのではないでしょうか?ちなみに大避神社の横の寺は『妙見寺』です。妙見は北極星です。北斗七星の横に北極星が有るというのは 出来すぎていないでしょうか?(続く)」 ○十字を中心にしてほぼ90度川が蛇行している。不思議なことに川が、尺定規のように見える。 「赤穂八幡宮の特異な神事としては、化粧をした大人の男性(頭人とうにん)が『御稚児さん』という子供を肩車して町内を歩く…というのが有ります。応神天皇と保護した村人?だと思います。それから、赤穂市の祭りのパターンですが天狗(鼻高はなだか)と獅子の対決が有ります。赤穂御崎の『伊和都比売神社』の祭りには童子二人も登場します。 赤穂市の北部の有年(うね)という地区では古墳時代の遺跡、古墳が多数発見されており、県下一大きい建物の遺跡も有るそうです。『はりま伝説散歩』という本の中には『秦』とヘラ書きされたモノが、発見された…とも書いてありました。あと坂越大避神社の近く(浜側)に『みかんのへた山古墳』という(御粗末な名前です)円墳が有ります。直径38m5世紀後半の海人の首長墓とされています。また、その浜の延長線上にも大塚古墳という古墳が有ります。大塚という割に普通の古墳ですが…しかしこの一帯には、お城の石垣みたいな石積が沢山有ります。もしかすると発見されていないけど大きな古墳なのかも知れませんね。大きすぎて気が付いてないとか。元来『塚』という言葉は墓の事らしいですし。私の考えなのですが、昔の赤穂は現在町の部分を大半が浅瀬の海で、北部や海岸沿いの山深いところに村が有ったのでは?と思います。赤穂は秦河勝が落ち延びた場所…と言われていますが活動の拠点としていたかも?しれませんね。四国、九州、淡路、大阪、奈良方面には海路で行けますし、陸路では 日本海側へ行けるし、岡山の吉備にも近い。瀬戸内海は波穏やかで航海もしやすく地域的にも温暖で雪の降る地方に比べれば住み易かったと思います。他国が責め込んで来るにしても、赤穂に辿り着くまでには何処からでも距離が有り、戦うにしても逃げるにしても便利な土地だったと思います。赤穂には『唐船サンビーチ』という海岸が有ります。そこには『唐船山』という山というよりは丘の様な小山が有ります。昔に唐船が来て座礁し長い歴史の中で山となった…という話です。中が空洞なのか音がポコポコするとの事ですが…。ちなみに何で『唐』なのでしょうか?唐の時代と言えば秦河勝の時代ですよね。その時に唐の船が赤穂に来ていたとなると何か交流が有ったからなのではないでしょうか?」