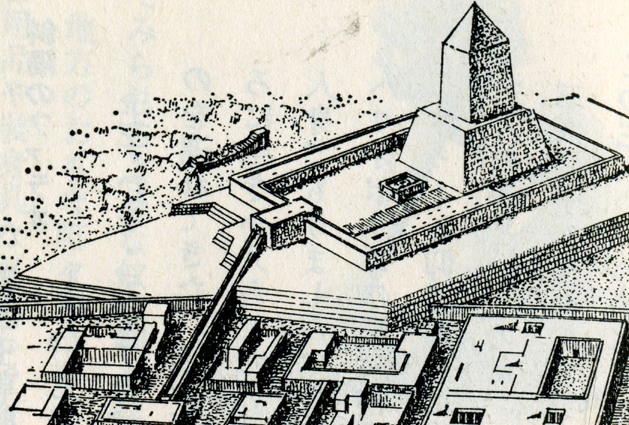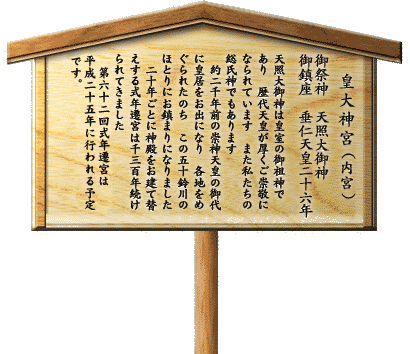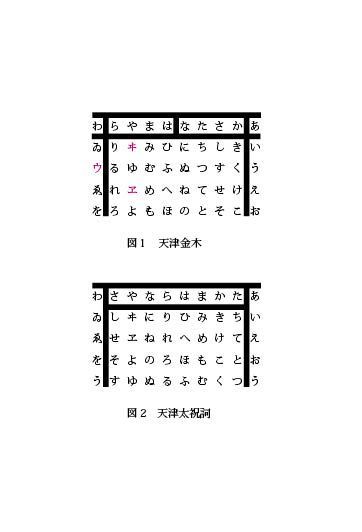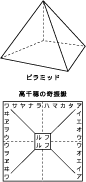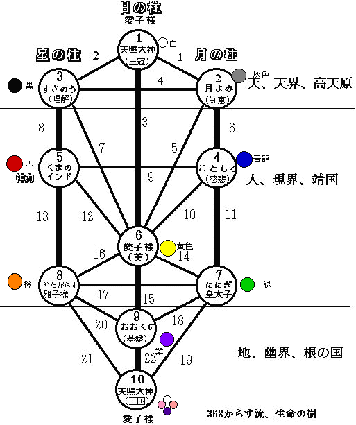○佐越の大避神社は猿楽の伝承地だった
この佐古志の大避神社が猿楽の宮だというのは、世阿弥が「風姿花伝」で河勝について、次のように書き記したからである。 「秦河勝が猿楽を子孫に伝え、そして、化人は跡を留めないように、摂津国難波(大阪)からうつほ船に乗って、風にまかせて西海にでた。播磨国の坂越(しゃくし)の浦に着いた。浦人が船を上げてみると、船が人間に変わった。諸人に憑きたたりて奇瑞をなす。すなわち、神とあがめて、国が豊かになった。」
伎楽のルーツは、外来であることだけは学問的にも認められているが、ルーツはインド・チベット地方で発生したと推測されている。ようするに、それはシルクロードと言ったほうが正しいだろう。伎楽の14種23の面には、インドやペルシャに因んだ面が多いからである。
また、伎楽は仏生譚なども含み仏教の影響が明らかである。この2つの条件を満たすのはホータンである。そして、なによりもホータンは絹織物の生産地でもあった。伎楽に使用された装束は、非常に高度な絹織物であった。
笛・三鼓・銅拍子の伴奏による仮面をつけた無言劇である伎楽は、後の田楽や猿楽などに受け継がれ、能、狂言の源流となった。秦河勝は、子供たちを始めとして一族郎党をもって味摩之(ミマシ)に弟子入りして伎楽を学んだ。味摩之(ミマシ)らは、秦寺(広隆寺)と四天王寺に寄宿していた。なんと、秦河勝が、彼らを自分が創建した膝元の広隆寺で手厚く保護していたのである。おそらく雑技だった秦氏の芸能に、なんらかの構成と様式を与えたのが味摩之(ミマシ)なのだろう。味摩之(ミマシ)が、どんな人物であれ、伎楽が西域の発祥芸能であることは明らかだ。では、秦氏がこの西域の芸能である伎楽を一族郎党に熱心に学ばせたのは何故だろうか。その理由はもう明らかだ。先祖の芸能だったからである。これは、秦氏がホータンの出身であるとの裏付けが一つ取れたことになるだろう。
さて、奈良の都は国際都市であった。シルクロードの大遺産である正倉院宝物(ほうもつ)の「紫檀木画槽琵琶」に施されている木画は、エジプト発祥の技術である。なんと、あのツタンカーメンの棺、飾り箱などは木画の技術がふんだんに施されている。木画とは、木の表面に象牙、鹿の角、つげ、黒檀など異種の材料を寄せ木細工のように細かい紋様を描く高度な技術であるが、エジプトーペルシャー中国を経て、日本にもたらされている。そして、まちがいなく木画を製作できる職工が奈良の都にもいたのである。
この佐古志の大避神社が猿楽の宮だというのは、世阿弥が「風姿花伝」で河勝について、次のように書き記したからである。 「秦河勝が猿楽を子孫に伝え、そして、化人は跡を留めないように、摂津国難波(大阪)からうつほ船に乗って、風にまかせて西海にでた。播磨国の坂越(しゃくし)の浦に着いた。浦人が船を上げてみると、船が人間に変わった。諸人に憑きたたりて奇瑞をなす。すなわち、神とあがめて、国が豊かになった。」
*化人;鬼神などが人間に姿を変えたもの。大避神社が「猿楽の宮」と言われるのは、猿楽の祖がほかならない秦河勝だからだ。滑稽な物まねや言葉芸が中心で、御神楽の夜などに演じた。ところで、広隆寺を建立した秦河勝は弓月の民の子孫である。この彼が、猿楽(さるがく)を起こしたと言われている。広隆寺を河勝が起こしたのは603年で、味摩之(ミマシ)来朝した時と時を同じくする。しかし、もともと、猿楽はホータンから連綿と続いていた秦氏のファンダメンタルな民族芸能だったと言えないだろうか。なぜなら、芸能は大衆文化であり、そうとうな集団に託されていなければならないからだ。猿楽は弓月の民とともにシルクロードから伝えられたと考えられるのである。そもそも外来芸能である伎楽(ぎがく)は、呉の国で学んだ味摩之(ミマシ)が612年に日本に伝えたとされ、そのため呉楽(くれがく)とも呼ばれていた。
伎楽のルーツは、外来であることだけは学問的にも認められているが、ルーツはインド・チベット地方で発生したと推測されている。ようするに、それはシルクロードと言ったほうが正しいだろう。伎楽の14種23の面には、インドやペルシャに因んだ面が多いからである。
また、伎楽は仏生譚なども含み仏教の影響が明らかである。この2つの条件を満たすのはホータンである。そして、なによりもホータンは絹織物の生産地でもあった。伎楽に使用された装束は、非常に高度な絹織物であった。
笛・三鼓・銅拍子の伴奏による仮面をつけた無言劇である伎楽は、後の田楽や猿楽などに受け継がれ、能、狂言の源流となった。秦河勝は、子供たちを始めとして一族郎党をもって味摩之(ミマシ)に弟子入りして伎楽を学んだ。味摩之(ミマシ)らは、秦寺(広隆寺)と四天王寺に寄宿していた。なんと、秦河勝が、彼らを自分が創建した膝元の広隆寺で手厚く保護していたのである。おそらく雑技だった秦氏の芸能に、なんらかの構成と様式を与えたのが味摩之(ミマシ)なのだろう。味摩之(ミマシ)が、どんな人物であれ、伎楽が西域の発祥芸能であることは明らかだ。では、秦氏がこの西域の芸能である伎楽を一族郎党に熱心に学ばせたのは何故だろうか。その理由はもう明らかだ。先祖の芸能だったからである。これは、秦氏がホータンの出身であるとの裏付けが一つ取れたことになるだろう。
さて、奈良の都は国際都市であった。シルクロードの大遺産である正倉院宝物(ほうもつ)の「紫檀木画槽琵琶」に施されている木画は、エジプト発祥の技術である。なんと、あのツタンカーメンの棺、飾り箱などは木画の技術がふんだんに施されている。木画とは、木の表面に象牙、鹿の角、つげ、黒檀など異種の材料を寄せ木細工のように細かい紋様を描く高度な技術であるが、エジプトーペルシャー中国を経て、日本にもたらされている。そして、まちがいなく木画を製作できる職工が奈良の都にもいたのである。