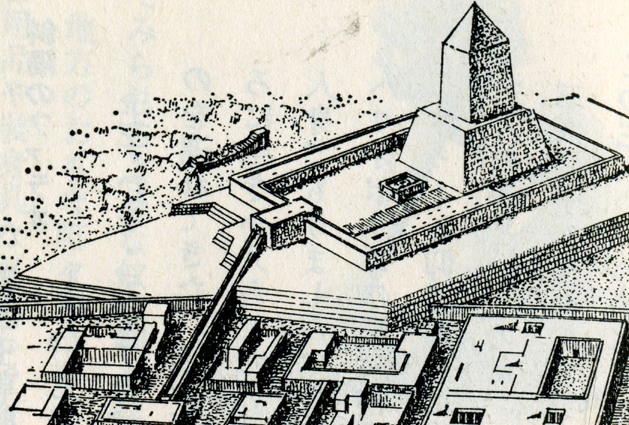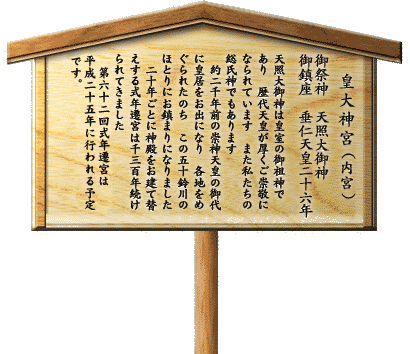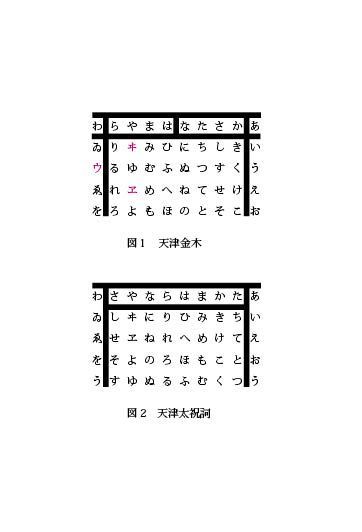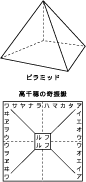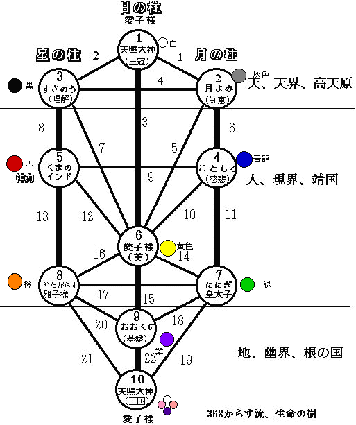秦河勝は、秦酒公(はたのさけきみ)の六代目の孫になるという。
この弥勒菩薩像は新羅国が太子に献上したものといわれ(日本書紀)、弥勒菩薩半跏思惟像(はんかしいぞう)、第一号の国宝で、その静寂で柔和な美しさはたいへん有名である。(べそをかいているようにみえる「なきみろく」は百済伝来であるとされる。) 広隆寺は山号を峰岡山とし、別名が多数あり、峰岡寺(はちのおかでら)、秦寺、大秦寺、秦公寺、太秦寺、葛野寺、桂林寺、草野寺など。しかし、特筆すべきは、もう一つ「景教寺」とも呼ばれていたことだろう。 太子建立の七寺のうちの一つとされるも、秦河勝の建立がために、秦寺(うずまさでら)と言われていた。秦は、「はたおり」の「はた」からつけられたともいわれるように、絹、麻、木綿織物はもちろんだが、土木建設、瓦の製造、金工、刀剣、酒造のテクノロジーを駆使して、巨大な財を築いたのである。河勝の後、秦氏族は平安京を造営したとも言われていることから、彼らが土木、建築においておおきなウェイトを占めていることは明かだ。秦始皇帝の末裔が新羅国から来朝し、高度な絹織物技術がもたらされた。(大酒神社伝)。漢織(あやはとり)呉織(くれはとり)という言葉はここから発祥した。秦の一族は、主として韓半島から、そして中国から海路で来島する2つのルートでやってきたことを知っておくべきだろう。つまり、共通なことは始皇帝の末裔であることだ。 秦氏一族の首長で、太子の軍政を司ったといわれているのが、この河勝(かわかつ)である。山城だけで当時およそ92の住居に分かれて住み、5千戸およそ7万5千人とされる。(一戸15人に数える)その河勝は、流罪のようなかたちで赤穂に入ったともいわれる。聖徳太子が亡くなられたのち、太子の長子、山背大兄王(やましろのおおえのおう)が蘇我入鹿に急襲され自刃(643年)する。こうして太子一族が滅亡したあと、こんどは、その蘇我入鹿が暗殺される。(645年6月) 河勝は644年7月に*富士川の常世虫信仰を討つため東国にでている。また、河勝が朝廷から消えたのは、蘇我入鹿が暗殺された645年6月以後のことである。このときに仏教を推進してきた豪族がことごとく難を受けたのである。河勝は今の兵庫県赤穂郡にひそかに難を逃れた・・・。[業ヲ子孫ニ譲リテ、世ヲ背キ、空船ニ乗り、西海ニ浮カビ給イシガ、播磨の国 南波尺師ノ浦に寄ル。蚕人船ヲ上ゲテ見ルニ、化シテ神トナリ給フ。当初近離ニ憑キ祟リ給シカバ、大キニ荒ル、神ト申ス」<明宿集> 河勝公が、空船に乗って辿り着いたのは、播磨の国、南波尺師の浦その地で、河勝の集団は千種(ちくさ)川の治水土木と開墾を行ったといわれている。 河勝がなぜ、兵庫県赤穂に難を逃れたのか・・・そもそも推古天皇が聖徳太子が勝鬘経(しょうまんぎょう)を講じた褒美に播磨国に3百町の土地を贈ったと書紀に記されている。(巻二十二)播磨国は、今の兵庫県南西部である。驚くべきことに、赤穂郡は聖徳太子に与えた恩賞地であった。しかし、その土地は実際には誰が支配したのだろうか。秦河勝だったのである。金春禅竹(1405−1470)の『明宿集』に書かれた河勝は、まさしくともに聖人である。世阿弥が書いた風姿花伝では、河勝は、欽明・敏達・用明・祟瞬・推古・上宮太子(聖徳太子)に使え奉ったと書いているが、聖徳太子は、秦河勝自身でなかったのか疑わしめるほどである。赤穂には秦河勝を祭神とする分祀は三十余社あり、この千種川沿いに末社が点在するのはそうしたわけである。上流の千種町は鉄を産するほか、一帯は金、銀、銅、砂鉄など鉱物資源が豊富だった。「金出地八幡宮大避神社」があり、その名の通り、金を産出していたという。秦河勝集団は、冶金、鋳物、鍛冶工、大工など、テクノクラートに徹していたのだろうか。それらの神社で「大避大明神」として祀られているのが、まさしく秦河勝だった。そして、「北極星を宿神とお呼びもうしあげている」<明宿集・竹禅>ので、北斗七星の本体が「大避大明神」であり、それが、秦河勝公である。摩多羅神と河勝、河勝と秦始皇帝が北斗七星でしっかりと結びついている。 秦河勝の出生譚は、彼がそもそも並みの人間ではないことを物語る。 「そもそもこの河勝のことは、その昔推古天皇の時代に、泊瀬川(初瀬川)に洪水がおこり、上流からひとつの壷が流れてきたったことが発端となった。人々はこの壷を不審に思い、磯城島(しきしま・式島、敷島とも書く・桜井市外山)あたりで拾い上げてみると、壷の中にはたった今生まれたばかりの子供が発見されたのである。急いでその子供を抱き取ってみると、そばにいた大人の口を借りて、こう語りだした。『僕は秦始皇帝の生まれ変わりだよ。日本に生まれる機縁があって、こうして出現しました。急いで朝廷にこのことを報告してください。』しばらくしてこの報告は、天皇の耳にも入った。天皇もこの子供の出現をいたく奇特なことと思し召して、自分のおそば近くにお召し寄せになり、親しくお育てになることになった。その子供は成長するにしたがって、抜群の才能と知恵をしめすようになり、賢臣よ忠臣よとたいへんな栄誉を受けるようになった。」(精霊の王 中沢新一著 巻末付録 現代語訳「明宿集」より) 秦河勝が、自ら「秦始皇帝」の生まれ変わりであると述べた逸話は、驚きである。秦始皇帝が霊山・泰山で封禅(ほうぜん)の儀式(前219年)をおこなったこととも結びつく。封禅(ほうぜん)の儀式は天帝(太一神は北極星)と地上の皇帝との天と地の同一化である。北極星がなぜ河勝と結びつくのか、ようやく原因が分かりかけてきた。 さらにまた、この逸話は、川に流され、エジプト王家で育ったモーセの話と酷似する。河勝が、”奇跡を起こせた”聖人だったことを示している。「玄なる聖の徳をもって、日本の国に生まれませり」、(恵慈)は、聖徳の死を惜しんで残した言葉だが、河勝もまた、神の化身であった。 京都で秦河勝が一族の氏神、秦始皇帝(しんのしこうてい)を祀ったのが大酒神社、晩年を過ごした赤穂(あこう)で自身が祀られたのが大避神社(赤穂郡坂越(佐古志))ということになる。この佐古志という地名は、かつて「しゃくし」と読ませていたという。石神の意だろうとされる。が、他方、「しゃく」は「尺」で、北斗七星のことになる。杓子(しゃくし)の尺(しゃく)をとったものである。北極星は、皇帝のシンボルであり、同時に、摩多羅神=秦河勝である。秦河勝は「尺師様」と呼ばれていたのであろう。 この社は、古くから「猿楽ノ宮」と呼ばれていた。世阿弥が「風姿花伝」で、猿楽の祖は秦河勝であると書いている。世阿弥は、「せあ」と、皆から呼ばれていた。ところが、足利義満が「ぜあ」と訛ってしまうので、しかたなく「ぜあ」と自らも称す驍アとになった。観世弥、世阿弥親子は秦河勝の直系子孫である。