編集日時:2019年04月30日(火) 11:35:46履歴
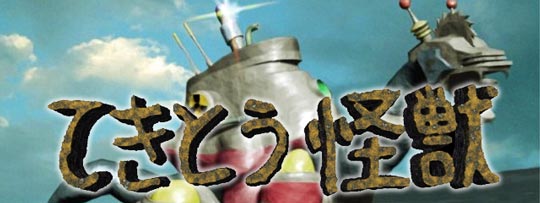
なんかabout-18.12からの続き

 ●2018.12.31 消えたああああ
●2018.12.31 消えたああああ悩みどころである3DCGソフトウェアVueの販売ページが消えたああ。
最近、価格が2万まで下がって、ほんと悩みどころだったんだが・・・・まあVue2019に移行するってことでしょうね。
心配なのは、すでに海外ではクリエイティブクラウドが一般になっているようで・・そいやSketchBookProもそうだよね、アレは長期的にみれば高いので、従来の製品パッケージにもどしてほしいのだが。
いま、Vueのクリエイティブクラウドは月額二千円くらいだっけ、CCオンリーになったら目も当てられん。
日本はあまり流行っていないようで、このVueCCプランは聞いたことがない。 これが来年くるんか?
あーでも動画を作っている一月くらいは課金して利用、ってのもアリかな・・・ホントたま〜にしかやらんからね動画は。
うーんそれにしても惜しいな、欲しかったのだがVue2016。
とっとと買っておけば・・・といっても無い袖は振れないし、仕方ない。
来年でると予測されるVue2019が、フツーのパッケージ版であることを祈るばかり。
ゆうても2016が27000円、2006の倍以上高いわけで、さらなる値上げもありうるな。
つかいーかげん、背景を描けるようになれば、景観作成3DCGなぞ必要なくなるんだけど。
という雑談。
※追記
と、思ってなにげなーくAppストアのSketchBookみたら・・・・。
「全機能を備えたバージョンのSketchBookをすべてのユーザに提供することにしました」となっており。
え、SketchBookが無料?
2006年に24000円くらい出して買ったSketchBookがっ!?
2013年には3600円でバージョン6買って、以降いまでも大事に使ってるんだけど。
と、考える前に反射神経でダウンロードしましたとさ。
これから起動して使ってみます。
※さらに追記:
なんかSketchBookPro6が130メガで、近年のソフトウェアとしては軽い部類なんだけど、今回ダウンロードした無償版バージョン8は77メガとさらに軽く、立ち上げてみてもやっぱサクサクと動く感じが。
まあこれから使い倒して、実態は明らかになるだろうけど最初の印象はいい。
選択範囲を動かしたり拡大縮小するときのパレットが別腹となっており、そこは不便ではありますね。
要はこれまで、選択範囲が決まったら自動的にパレットが起動して、すぐ編集できたんだけど、新しい版ではそっからの選択肢が増えて、逆にパレットは手動になったようです。
いっぽうブラシは垂涎モノですな。
垂涎モノがもう自分の所有になったという感動。
なんかこんだけ優れたブラシが揃うと絵がうまくなりそう。
軽いというのは速いってことで、これまで残像的に遅くしていた各動作の描画もテキパキと速くなり、まあワタシは動体視力が高いからいいけど、より使い手を選ぶようになったかもしんない。
あ、基本的な使い方は最初に買ったバージョン2からずっと同じなんで、とくに困ることはありませんでした。
先述した拡大縮小パレットみたいに、ちょい仕様がかわったとこ探すくらいで。
というレビュー。
※さらにまた追記:
拡大縮小パレット、1工程で使えるわ、別腹と思っていた拡大縮小のボタンを押せばすぐ前回の選択ツールから動いて従来どおり。
つまり選択範囲ツールのほうが別腹になったわけかなるほど。
それにしても面白いわ、バージョン6からの変更はそんなに多くないとは思うけど、ブラシが増えたんでマジ楽しい。
またバージョン重ねるごとに何故か描き味がよくなっているんだよね不思議と。
何らかの工夫で、紙に描いたような感触を再現できるのかもしれない。
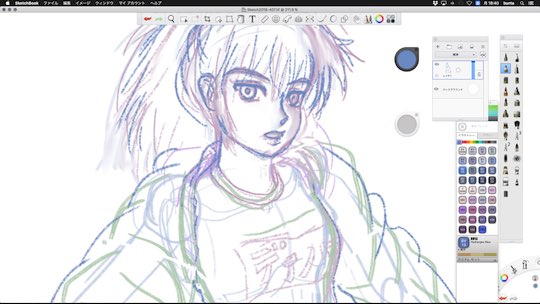
ちなペンタブレットはIntuos・・・読みはいんてゅおすで、これがなかなか覚えられないのだが・・・。
とにかくIntuos3です。 もうじゅーねん以上まえの製品。
これまた、以前に使っていたFAVOと比較して、スゲー描きやすいと感じたもんです。
じゃあ、今のIntuosはもっとスゴいのだろうか。
という追記。
●鉄のラインバレル
ヴァルヴレイヴで味をしめて、名前くらいは聞いたけど知らないロボアニメをバンダイチャンネルで物色。
ともあれそれっぽいのがあったので、予備知識もないまま視聴しはじめたとゆう。
カンケーねーけど、バンダイチャンネルの「ジャンルで探す」にはロボアニメの項目あるんで、そこから見つけ出したんだけど、同時に「鉄血のオルフェンズ」というタイトルもあってややこしい。
うろ覚えだが鉄血のオルフェンズはガンダム類らしく、優先順位が低いのでラインバレルにした次第。
まづ、予備知識ないんで製作年がわかりませーん。
しかし出だしからイキナリCGだったので、わりと最近っぽい。 絵柄は90年代なんですけどね。
先程のジャンル=ロボアニメからさらに細分化して、コミック原作のところにあったので、原作がかような絵柄なのだろう。
肝心のロボはもう20年以上の歴史がある、新世紀エヴァンゲリオン以来の定番、細身ロボです。
しかしヴァルヴレイヴと違って首に筋肉がついたようなデザインで、まあかろうじて個性的かもみたいな。
あー定番といえば、いま作った造語で「タナボタロボ」というものがあって。
とくに操縦訓練もしていない一般市民の前にロボが置いてあったり、あるいは降ってきたりして操縦者の運命みたいな、もちろん代表例はなんつても機動戦士ガンダムです。
そしてもうひとつの代表例がガンダムMk-IIで・・・どちらも富野監督やん。
富野監督は大人と対立する少年というテーマにミョーにこだわりがあり、なーんか今のロボアニメの主人公が少年少女ばかりなのはその影響だと思うよ、それ以前の、ヒーロー然とした子供が主役のスーパーロボット系はまた別だと考えている。
そんな富野監督の功罪、もひとつが「タナボタロボ」とゆう。
ほらほら、ヴァルヴレイヴも同じやん、ガンダム然としていて、空襲のドサクサにまぎれて突然出てきたロボに乗る、実はギガンティック・フォーミュラと同じで適合者学園だったため、乗るのは宿命だったんだけど。
で、今回の鉄のラインバレルが面白いのは、はじめて「タナボタロボ」を逆手にとったような主人公という感じが。
心の準備ないのに不意にパワーを与えられて・・・っつーいつものタナボタロボではなく、チカラさえあればと常に念じていた一般人がってこと。
いや平成仮面ライダーや戦隊シリーズで、とくに追加戦士にはありきたりな話なんだけど、主人公ですよ今回は。
ということは、最初から荒れ模様で暴走気味ってわけです、そこが面白いな。
ロボが内包する巨大チカラに飲み込まれて、とかじゃなくて、そもそも中学生の少年が歯止めきいてないわけ。
「もしも力に飢えている少年に無敵ロボを与えたら」っつーコントを、しっかり描いている。
ちなみにいま四話まで観たけど、そんな暴走もマジメに取り組んで、ちゃんとしたストーリーになる様子。
危うく鉄雄になるところを、救われて進むみたいな。
まーただ、チカラの欲求が理屈っぽくなってきたけど、そこはたぶん通過儀礼。
あとで五話から観るわけだが、仕切り直して新しくストーリーがはじまるに違いないとみている。
そーいやロボアニメのハーレム化っていつからだっけ・・・超時空要塞マクロスはオペレーターがギャルという不自然さで、例えば戦闘メカ・ザブングルとは意味合いがぜんぜん違う。 ザブングルは無法地帯のドサクサだが、マクロスのばあいは正規軍の、ちゃんとした研修をうけているはずの人員がなぜ、というおかしさがある。
その後の途中が思い出せないのだが、2000年代に入って超重神グラヴィオンが「メイド千人」という、要らないサービス・・・ちょっと嬉しいかもだが、そんなムチャをはじめて、でも整備員から事務までぜーんぶメイドって信用できねえ組織だな。
そっから先は、なーんか「当たり前」になっているような気がして。
そいやギガンティック・フォーミュラでもムリヤリ少女布陣をかためていたね、技術主任が天才少女でヒロインが巫女でニンジャという・・・なぜそうなのかは、「この世界ではそーゆー少年少女ニンジャ部隊があるから」と理由づけして・・・なんかギガンティック・フォーミュラって学校の秘密エレベーターから地下基地に、というくだりとエンディングの絵柄から、もとはライトノベル風味を目指したのでは、と思うのだが・・まあいいや。
まあともあれ、鉄のラインバレルもハーレム化しているわけです。
ただ全体的なキャラクターの布陣がいかにもコミックらしく、少し安心感があって。
後はアレだ、この鉄のラインバレルみて、やっとヴァルヴレイヴの不自然さがわかった。 世界を暴く、という大風呂敷に畳む側が巻き込まれて、肝心の革命後の様子をナレーションでしか語れなかった。
話でかすぎたんだよきっと。
とりま鉄のラインバレルはひとつの街からはじめているので、そこは順当だと思える。
例えば天元突破グレンラガンはスゲえ超展開アニメと思われているが、実は丁寧にドラマを積み重ねた作品で、その証拠に第一話は村を出るか出られるか、というストーリーになってるやん。
たぶんロボットアニメは、最終的にどんなに話がでかくなるとしても、辿るべき道筋があるんだよきっと。
他の感想としては・・・なんかARMSのロボット版、みたいな雰囲気もある。
ARMSと違ってマキナつまりラインバレルは喋らないけどね。 いまのところは。
とゆうわけで。
まだまだ四話、はじまったばかりなんで、続きはまた。
●続きみた
えっと、十話くらいでしょうか。
まー面白くなってきたよね。 救急搬送のリピートでは大爆笑したし。
あ、それとタイトルリストみてふと思ったのだが、鉄のラインバレルって読みは「クロガネのラインバレル」なのでは・・・と思い、iMacにインストールしてあるグーグル日本語でもってクロガネの・・・と入力したら出た出た。
テツの、でも出るんだけどね、第一話がクロガネと少年だから。
つか、いまウィキペディアでみたらやっぱクロガネで正解だそうな。
そこ、ハッキリオープニングタイトルで書いてほしかったね、巨神ゴーグ(ジャイアントゴーグ)みたいに。
後述:あとで観たらちゃんとタイトルにひらがなでふってありますな。 最初からそうだったっけ?
あー・・オープニングといえば、鉄のラインバレルはなかなか良いオープニングなのだが。
つかぶっちゃけ、このくらいが当たり前だと思うんだけどね。 前回みたヴァルヴレイヴのオープニングがイマイチだったので、冴えてみえるという。
ヴァルヴレイヴのどこがダメつーか、昨今のアニメにありがちなんだけど。
テーマもメッセージも見えてこない、という問題点が。 なーんか「それっぽく」フルアニメで動かせばいいと思っているのだろうか、でも画面からなんも読み取れないんだよね、チャカチャカ目まぐるしいだけで。
いやヴァルヴレイヴ後期オープニングのばあい、それすらももったりしてたけど。
↑前期はまだいい
なんかテーマとかメッセージとか御大層に聞こえるけど、要は作品の設定やキャラ紹介、とゆーだけの話。
それがダメだったことで印象深い作品に機動戦士ガンダム00があるが、ヴァルヴレイヴと同じようにチャカチャカやってるだけでなーんも伝わらないオープニングでした。
このwikiに書いたと思うけど、機動戦士ガンダム00のばあい伝えるべきテーマ、メッセージは9つに絞るべきで、つまり四人の主人公と四機のガンダム、あとはヒロインなど重要素をひとつ、これで9つ。
多くのアニメオープニングは90秒しかないから、それでもひとつあたり十秒しか時間がない。
それをぜーんぶ詰め込もうとするから意味不明なのがガンダム00とヴァルヴレイヴ、そして多くのアニメってわけ。
最初はチャカチャカと速すぎるのも問題と思ったけど、烈車戦隊トッキュウジャーのオープニングみてそれは違うとわかった。 トッキュウジャーもそーとー速いが、ちゃーんと伝わってる。 動きのチャカチャカはあまり関係ないっぽい。
おっと話がガンダム00とヴァルヴレイヴでたついでに、ヴァルヴレイヴでガンダム00のパロディやってなかったか。 オープニングで刹那が地球に落下するようなイメージ。 まあサンライズだからセルフパロなんだけど。
話を鉄のラインバレルにもどして。
オープニングといや、曲がなにかに似ているかなと思い、けっこーあとになって「あ、無限の住人か」となったのだが・・・Youtubeで無限の住人(あっちじゃブレード・オブ・イモータルっていうんだカッコええw)オープニングをみてみると、そうでもないかな、と思い直したりした余談。
さらに余談いうと、そのYoutube検索で「映画:無限の住人予告」というのが出てきて・・・実写映画化されてんのかアレ。 誰が卍さん演じてるんや? いやクリックしてその予告観ればわかるんだろうが。
さっきクリックして観たが、卍さんは木村拓哉か、アクションだいじょうぶなんすか、という。 宇宙戦艦ヤマト実写の古代進は悪くなかったが、悪くないだけで良くもなかったわけだし・・・それとツッコミどころゆうか、気のせいかもだが、卍さんの背中に書いてあるマンジが万の字に変更されね? なんか卍は何かを連想させるとかで実写映画としてマヅいんでしょうかね。
まあいいや。
こんどこそラインバレルにもどして。
内容的には第一話からやってたタナボタロボという題材をはじめ、けっこう普遍的なネタで構成されているのだが、単にパターンをなぞってるだけではなく、おそらく原作者なのだろう「俺ならこうする!」という差別化がハッキリ出ているのがとても好印象です。
つまりガンダムMK2みたいなタナボタロボをどう扱うか、巨大な防衛組織をどう描くか、ありがちなハーレムアニメをどう料理するか、少年の成長を描くとか、どれもこれも普遍的な素材だけど俺ならこう盛り付ける! という意識があるっぽい。
つか恋のライバル的な展開で、可愛らしさで勝負とか、ありがちな展開も徹底しているため、確かに爆笑したw
燃えるところは燃えるんで、やっぱり造り手のこだわりがあるんでしょうね、見ごたえある。
ただまあ、苦言申したいところもふたつあって。
ひとつはロボット、かなり用途別になっていて楽しめる、ここでもコダワリがある造りなんだけど、肝心のバトルシーンになると急に予算不足みたいな雰囲気になって。 スピード感はあるんだけど、ただロボだけ速く動かしても物足りないんですよ、ジャイアントロボ(今川版)を引き合いに出すと、ロボの一挙動でビルの窓ガラスがピシッとかなるやん、そーゆー描写の積み重ねがロボ迫力なわけで。
あともうひとつは、意図的なハーレムアニメ類ではあるが、中学生がみーんなトランジスタグラマー(死語)ってどうよ、と思う。 例えるなら男子生徒がぜーんぶ細面で長身のイケメンばかりなホストアニメみたいな違和感がある。
ハッキリいうとソレを可愛いとは思えない。 ベティ・ブープみたいでなにかヘンです。
続けて観たため、どうしてもヴァルヴレイヴとの比較になるのは仕方ないが、やっぱラインバレルは冴えてますね、同じように波動砲のような斬撃があるけど、ラインバレルはとりま日本刀が一本ですから。 二本だっけ?
繰り返すけどヴァルヴレイヴの獲物は観ていて頭に入らず、ライフルをもっていることに話し途中のセリフで気づいたくらいであり、他にも爪とかでも戦ってなかった? と思うがハッキリ思い出せず。 また腰の日本刀四本差は無駄設定でしたねけっきょく。 あと、当たり前のように飛んでいるけど、どこにノズルがあるのか、どんな推力なんか、まったく魅力がないんですねメカ設定に。 困ったもんですヴァルヴレイヴ・・・プラモデルは売れたそうだけど、どうやらサンライズの営業が力入っていたらしい。
鉄のラインバレル・・。
まだ全話のうち半分だけど、ロボットアニメへのコダワリは確かに受け取りましたとさ。
●最後まで観た
いやー面白かった。
まー基本的に、パターン通りなんだけどね、そこをどう料理するかってのがキモなわけで。
だいたいパターン破りは戦闘メカザブングル・・・1981年だっけ、もう伝統なのだからソレ含めてパターンなわけ。
最後はまあだいぶん息があがって駆け足になったけど、なんとか勢いは失わずにって感じで。
息があがってって、例えば頼みの綱である旗艦フラッグだっけ・・もうモデリングが間に合ってなかったよね。 また加藤の最後も「そんだけ?」みたいなあっさりと。
前回観たヴァルヴレイヴと違って、前半で遊んでいないので、ホントに全力で駆け抜けたっていう感じで好感は持てる。
コミック原作ということで「俺ならこう描く!」という鼻息もまた好感が持てる部分だが、しかしさらに自分自身がもし作家だったら・・・「俺ならこう描く!!」という点はありますね。
ズバリ「生き返りすぎ問題」で。
カンタンに生き返ったら、話に重みがないやん、ハラハラもないし。
とくに最後の敵が「みんなひとつになれ〜」って人間を集めてまぜまぜしようとするくだり、ボスを倒すと回収していた端末機もバタバタ落ちて、中からみーんな出てきて無事。
自分だったらもとに戻るのに時間がかかる設定にしますな。
余談ながら生物彗星WoOっつー、あのウルトラマンの前企画ウーを映像化した特撮があるんだけど、これまた最後にボス敵倒すと、これまで食われていた連中がぜーんぶ河原に戻ってるという・・・。
このとき自分はとあるネット上で、「みんな無事でもどってくるのではなく、敵は倒して食われた連中は意識集合体として宇宙を旅するほうがよくね?」と発言しました。
何もかも元通りって、あまりにご都合主義に思えたんで、宇宙の何処かでまた別な人類史をはじめる的な方が映画みたいでカッコよくね? ってわけです。
それと鉄のラインバレルで思ったのは、ロボの活躍がもーちょい欲しかったという。
せっかく個性豊かな、戦略的に専門化されたロボ部隊なんだから「勝ち戦」を見せてほしいって話です。 なーんかラインバレルの引き立て役みたいなんだよね、他のマキナは。
ネーミングもカッコいいですね、最近のロボットアニメでは突出して。 原作者知らんけど大した才能や。
ちなラインバレルが特別とくべつゆうてたけど、マキナ殺しがあるためかな。
最初に登場したときは「ARMS殺しか?」オモタら、ホントにマキナ殺しって劇中で語ってて、ここオマージュかな。
たぶん原作者はARMS好きなんでしょうね。
こーゆー「俺ならこう描く!」という熱い作品みると、自分も作家になりてーなーと思いますね。
まあいくつか才能に問題があるので(例えば納期を守れるスピードがないとか)、pixivなどでアマチュア活動しているわけですが、イチバンの問題は、たぶん今どきの老若男女にウケる、という自信がないw
戦後すぐくらいならちょっとはウケるのでは・・という旧いセンスですはい。
そんな感じで、かなり楽しめたアニメ。
●勇者王ガオガイガー
なんかロボットアニメの歴史を考えるとき、ひとつの頂点ではと思えるのがガオガイガー。
ロボアニメは鉄人28号アニメ版が1963年だそうで、50年以上の歴史があるのか・・・。
いくつかエポックメイキングな作品があり、例えばマジンガーZは人間がとーじょーし(ひらがな表記なのは、漢字にすると登場とか誤変換されるため)、必殺武器を振るって巨大な組織と戦うという・・もうほとんど基本ができてますねロボアニメの。
あとは玩具会社が主導権を握れるようなデザインはいつからだろ、少なくとも超電磁ロボ コン・バトラーV時代には完成していたのかな。 でもってガンダム。
ガンダムがストーリー優先のリアルロボット系を生み出したというか、まあじっさいアニメ作家の立場からすると「解放」でしょうな、こんなんやっていいんだ、みたいな。 解禁、という言い方もある。
俺もストーリーもってんだ、いや俺もアイデアあるぜよ、俺も俺もみたいに、みんなが解放されたと自分では思ってる。
でもってリアルロボットという発明で、ロボアニメが大量に生産、特撮ヒーローのピークは1973年だそうだけど、ロボアニメのピークは1983年でした。 もうその年に何本のロボットアニメがあったやら、です。
スーパーロボット系も負けてなかったのですが、やがて超獣機神ダンクーガという、スーパーロボットとリアルロボットの文芸をあわせたものが登場し・・・つまりリアルロボットのストーリーに神秘的なスーパーメカを出すわけ。
ダンクーガは1984年だっけ、実はこの時点でスーパーロボット、リアルロボットという区分は意味をなさなくなってきているのだが、まあ使いやすい表現なので、謎の神秘力があるのがスーパーロボットとよんでいます、自分的には。
それと新世紀エヴァンゲリオンも、何らかのエポックメイキングだと思うのだが・・・ちなみにあの時代だとじっさい、エヴァンゲリオンのアイデアは独自のものありません。 新しいものなどひとつもないのではないかと思う。 エヴァが売れたのはただひたすら面白かったから、かと。
要は洗練されていたんだろうね、あらゆる設定が。
でもって、あらゆるアイデアが出揃った90年代において、やるべきことをぜーんぶやり切ったのがガオガイガー、では。
だからある意味、ひとつの頂点であり、それ以降の作品はすべて派生型みたいな。
まあガオガイガーは、スーパーロボットとリアルロボットの融合、そしてファンタジーも付け加え、ほぼ完璧やん。
絵柄が古臭いのが玉にキズだが。
あと運営的にも、さすがに二十年以上ロボアニメで仕事してると洗練されてくるんですかね、もう中盤以降、予算的にもスケジュール的にも作画が苦しくなっていくることを見越して、ディバイディングドライバーっつー、作画楽ちん空間を生み出すアイデアを用意していて。
ちな自分史をちょい語ると、ガオガイガーはリアルタイムで観てませーん。
ネットで評判を聞いて、そんなに面白いなら借りてみようと・・・DVDだったかVHSレンタルだったか覚えてないが、たぶん2007年前後だと思うのでDVDレンタルでしょう。
最後まで絶望的な決戦を繰り返し、スゲーと思いました。
よっていったん、全話みてます。
だから今、バンダイチャンネルで二度目の視聴という次第。 いまこれ書いてる時点で二話まで観ました。
さすがに一話二話は作画が凄いですなw
なんだか勇者シリーズという一連の、最後を飾る作品だそうで、そんな後なのに気合もまた凄いっすね。
時期的に言うとサンライズではこのあとザ・ビッグオーやらカウボーイビバップやら∀ガンダムやら出たころ。
ホントにスゴい作画スタッフが揃ってたんだなと感心する。
バンダイチャンネルでは第一話が無料となっているが、どんだけ濃い第一話だよw という。
しかも最初みたときは衝撃的なラストで・・・あ、つまりネタバレ無しで観てたわけです、そら第二話まで観ますよあの展開。
その後の驚きもさることながら、これまで名前だけは知っていたが、観ていないというのが惜しまれて。
ドラマ版のセクシーボイスアンドロボでもよくネタにされるんで、ロボアニメの歴史を語る上でおさえておくべき作品。
ついでに主題歌にもふれておくと、最初はくどくて洗練されない曲だと思いましたが、もう慣れたw
慣れるとくっそ熱い良い曲ですね。 まあこの時代はこんなもんで、例えばウルトラマンダイナ主題歌はまあ、わりと良いほうだけど、ウルトラマンネクサスくらいになると「くっそ熱い曲」という目的が空回りしている感じが・・いや悪くないけど。
とまあ、書きたいことは多々あれど、とりまこのへんで。
●最後まで観た
いやー凄かった。
繰り返すが絵柄が旧いのが玉にキズだが、まあ絵柄が90年代ってガオガイガーが90年代ですから、まあいいかみたいな。
しかし内容において、文句なしのアニメですね、昨今の作品も見習ってほしい。
特にラストの、護が旅立つところは、名作である星獣戦隊ギンガマンや烈車戦隊トッキュウジャーでさえも再現できなかったシーンで、まあ今日びの作品は「行かないで〜」「どこにも行かないよ!」ですからね。
以前に韓国映画「スパークマン」や島本和彦先生の「バトルサンダー」が「旅立ち系」ラストであり、本来こうあるべきなんですわ。
コレ書いてる自分自身が極端な出不精(デブ症ではない)ですからね、旅立ち系は身に沁みるんです。
あとはすべての出来事にカンタンでもなんでもいいから理屈をつける、これもとうぜんの話で。
「コレはこーゆー現象だから対応策はこうだ1」というのを徹底している、だから良いのですガオガイガー。
そしてラストは全員、ボロボロになって戦うシーンは、第一話と対になってるのも感心する。
そんなこんなで、いろいろ語りたいが、とりあえずこのへんで。
●アリータ:バトル・エンジェル
いつもの港北イオンシネマで視聴。
いやーレイトショーとはいえ、3Dなのでメガネ代ふくめて1700円は出費イタいな〜という、ものすごい貧乏性に襲われたんですけどね、そんなときはちょい昼寝して、もし時間的に寝過ごしたら次の機会とか、そんな風にしてみたわけです。
そしたら間に合う時間にパチっと目覚めて「1700円安いやん」とイキナリ思えた次第。
まあわからん人、多いかもだが、かつて数万円したといわれる映画ビデオソフトが14800円くらいに落ち着いて、そのまま数年間この値段が当たり前とされていたが突如、本屋などで3800円くらいのが出回るようになり、それも1500円とか下がってDVDに受け継がれたり、あるいは当初1500円とかしたレンタルビデオがわずか数年で380円くらいが相場となり、やがて百円時代になるとか、そーゆー経緯を知っていて、なおかつ今は配信の発達で工夫すればカナーリ安上がりにコンテンツを楽しめるため、映画が割高に思える瞬間があるっつー話です、はい。
3Dは面白かったです、品質も高いし、奥行きがあるのでわかりやすいところもある。
しかし二時間もある映画なので、目が疲れないかという心配もあり、まあ今回は無問題だったけど、疲れているのに駆け込みで映画館に飛び込むこともあり得るんで、やっぱ2Dのほうが有り難いような。
3Dよりもハイフレームレートのほうが興味深いですね、もしこのアリータ:バトル・エンジェルがハイフレームレートだったら、そーとー面白い絵になったのではと、例えば水中を歩くシーンとかで思った次第。
まあホームビデオなんかでハイフレームレートは体験できるんだけど、大型商業映画では未体験っつーか、まあだいぶん先になるんでしょね。
個人的なこと話すと、最近サイボーグ義手とかよく描くんで、サイボーグ観たかった、ということもあり。
その点は大満足でした、ブサイクなサイボーグ、美しいサイボーグ、いろいろ見れてよかった。
内容的にも、原作のエッセンスをうまくまとめて一本の映画にしているので、高く評価できますね、観ながら気になったのは「どこで話を区切るか」でしたが、とても納得できるところで終わり・・・まあ続編ありきな感じになるのは仕方ない。 原作ではまさかのザレムに勝利、っつーか、地上とザレムをつなげる「横暴な」物語を最後まで一本の映画で付き合うのはムリなんで。
そいや銃夢はいっぺんアニメ化されていた、それが非常に残念に思ったのは、ガリィが使う機甲術パンツァークンストを、アニメスタッフがぜーんぜん理解していないことで・・。 この機甲術には回転体術という基本があり、それがわかってないため、フツーのアクションアニメとなっている次第。
今回の映画化でも、そこが心配だった。

結論から言うと、まあ杞憂ではなかったというか・・。
ま、アニメ版ほどベタな動きではなくて、多少は回転します。 だからいいとしようか。
自分的には回転体術はヒジョーにジューヨーに思っていて、回転力を破壊力に転化すると解釈すれば、ジャシュガンの強さとか「機」つまり機会の機で、タイミングという要素の大切さがわかるやん。 回転グラインダーで金属片とか削るとき、うまく当てればジー・・ってスムーズに削れるんですが、下手なタイミングで当てると削るべきものがぶっ飛んで欠けたりする。
裸の銃を持つ男の前に制作されたテレビ版の「ポリススクワッド」で、ドレビンが鍵屋に化けておとり捜査してるけど仕事ヘタ過ぎて、鍵がぜーんぶぶっ飛んで天井にたくさん刺さっている光景を思い出しますがこれは余談。
逆にいうと回転しながら適切なタイミングで対象を殴ると、とんでもない破壊力を生み出す・・・そう考えてます。
だいたい回し蹴りって実在する技やん、やっぱ回転は強いんだよきっと。
ちなみにロケットハンマーのパクリ創作もやったことあって。

斧はまあ、上に跳ね上がるパワーを機械化って話だけど、銃夢のロケットハンマーは回転体術と同じ、独特の殺陣があるんですが、そこもちょい残念な部分ですはい。
あ、目が大きいというのも話題になったけど、単に大きいだけではなくヘンにアジア人顔だから余計、特徴が文字通り目立つのでは。 パグみたいな横顔になるからw でも正面からみればなかなか凛々しいです。
でもって観ていて気になったのは、原作知ってる自分はじゅーぶんついてこれるというか、よりシンプル化された世界観なんで無問題なんだけど、銃夢を知らない人はダイジョウブなのかな、という。
街の壁が動いているのはハイドロウォールだっけ、流体だからというのも原作ファンはわかる。
ちゃんとルール説明とか間に合ってるのか、すでに原作馴染んでいるため逆にわからんのです。
だもんで映画としての出来不出来は語りにくい。
ちな観おわってから、Youtube岡田斗司夫チャンネルで同映画の話を聞いたんだけど、街に広告がまったくないのがイカンとダメ出ししてましたね、まあ自分ふくめて、たいていの人は3Dに酔っているので気づかないかもだけど。
また街の撮り方も平凡でダメゆうてたけど、昨今の超大作はだいたいそうかもね。 ゴースト・イン・ザ・シェルもなーんかワクワク感がないなあ、という感じだったし。 じゃあ世間で評価されているヘルボーイ/ゴールデンアーミーのトロール市場はかなり上手かったんでしょうね撮り方が。
あートロール市場といや、あの敵が巻き込まれた歯車みたいなの、クズ鉄町にもあるのが笑えるw 元ネタはインディージョーンズなのか、もっと旧い原点があるのだろうか。
良い意味で悪い趣味なのだが、同じように悪い趣味なファクトリーの連中、人間の顔つまり皮を貼り付けたロボみたいなのは、フツーに機械っぽかった。 とっさにぐぐったがそうそう、デッキマンね。
もひとつ余談ながら、ファクトリーの前に立つガリィという絵は、3DCGだと20年ぶりくらいになります。
そんなん1999年前後にあったかって? あるんです、木城ゆきと先生本人が、Shade3Dで作ったものが。 いつか画像検索したら出てこなかったので、おそらくShade3DのおまけデータとしてShadeユーザは知ってるが、一般には出回っていない可能性・・・いや原作者がShadeで作ったんなら、雑誌などに載っても良さそうなもんだと思うのだが。
サイボーグ見たさに行ったようなもんだけど、そこはホント、3Dで堪能しました。
アリータの前期ボディは、なんか華奢で良かったですね、はかなさが可愛い、というか。 でもってバーサーカーボディになると急に大人っぽくなるんだけど、そこ実は原作と同じというか。 まあ原作では身長が低いのと、周りにデカいサイボーグ多いんで、子供っぽく見えるんでしょうね、設定上も童顔らしいし。
あー、そいや「バーサーカーボディのひみつ」は明かされないままかーい!
なんか続編ありきなのはいいけど、ヒミツ持ち越しすぎでないか。 戦闘では主にプラズマジェットを利用した技が見どころでしたが、つまり今回の映画ではソレがないわけで。
他の隠し機能もだから、なーんも語られず・・・まあ受け入れますよ続編体制は。
元の話長いから。
あとは・・・向こうの評判どうなんでしょう。
いちおうアメリカであっても「小さいヤツが勝つ!」という燃え要素はウケるみたいだけど。
という感じで。
個人的な感想をのべるなら、「FINAL FANTASY VII アドベントチルドレン」みたいな立ち位置です自分の中で。
つまり壮大な同窓会ゆうか、まあ今回のアリータは物語仕切り直しなんだけど、とにかく原作で馴染んだ風景や人物を、最新の技術で見せてくれた、というような。
要は嬉しい実写映画化ですね。
●ベターマン
繰り返し耳にするタイトルをとりまバンダイチャンネルで。
いま一話を観たとこだけど、作画はスゲーな、おかげで怖すぎて笑えるみたいなw
要するにそれが演出意図なので、よくできているんでしょうね。
で、繰り返し耳にするっつー部分ももうちょい語ると、要はガオガイガーとの関連です。
ウィキペディアだっけ、「ガオガイガーの世界観と同一であることが明らかになった」という文脈。 つまり最初のうちは同じ世界ってことは知られてなかったんですかね。
まあ今では「ガオガイガーvsベターマン」だっけ、そんな話もあるようなんで、とにかく必読もとい必視聴と思った次第。
制作はどうやら1999年っぽい。 つまりガオガイガー放送のすぐあとと思われる。
でもって劇中の年代は2006年らしく、つまりこれまたガオガイガー最終回で復興した世界のすぐあとみたいな。
でもって「ガオガイガースタッフ」なので、まあ誰でも関連性は考えていたでしょうね。
で、ガオガイガーもそうだけどベターマン第一話も作画などのクオリティが高いため、ビデオアニメってなんだろう・・ってなります。
まあビデオアニメがたくさん作られるようになってから十年以上は経過しているので、テレビアニメも進化したのか。 あるいはビデオアニメだったのかもしれん。 ビデオアニメゆうても後々、テレビ放送も考えてテレビフォーマットな作品も多いから。
そのへん、ずいぶんあとというか、最近になってわかってきたことなんだけど、要するにテレビ放送ってのはものすごい大事業らしいということで、しかもまず枠を勝ち取ってそこに当てはまるように話数を逆算しなくちゃならんし、なかなか自由度は低そう。
うっかり放送に穴開けちゃったら、アニメ会社は切腹・・・とまではいかないまでも、放送局に怒られるでしょうね。
つまり、ビデオアニメのほうがある意味では楽であるという。
まあ採算を考えるとまた別な話になると思うけど。
余談になるが、だから映画でもテレビドラマより低予算な作品もあるってことでしょう。
テレビドラマみたいに苦労して放送枠を勝ち取るより、とりま撮影して上映館はあとで考える、ということもできるだろうし。
昔は映画イコール、テレビドラマより制作費多いと思っていたのだが。
テレビに割り込めない制作会社が映画やビデオ作品ということもあるんだという推論。
まあいいや、ベターマンにもどすと。
まだ何もわかりませんね、とゆかレスキューロボも登場しないので、なるほど、すぐにガオガイガー世界とは気づかない。
また、出だしからイキナリ大量事故死とか、ガオガイガーじゃあ、出てこない話ですし。
内容とはあまり関係ない点として、画質の悪さがあります。
まさか16ミリフィルムなんですかね・・・東映特撮では知っている限り、百獣戦隊ガオレンジャーまでは確実に16ミリフィルム使ってたっつーか(メイキングシーンで確認済み)、轟轟戦隊ボウケンジャーから35ミリフィルム、ワイドスクリーンになったので、マジレンジャーまでは16ミリフィルムだったと推測。
オーバーマン・キングゲイナーもちょいと画質悪いやん、悪いっつーか、なんとなく解像度が足りていない雰囲気。 でもってキングゲイナーは確か2002年だから、99年のベターマンは急ぎ足でワイドスクリーン時代に追いつこうとしていたっぽい感じ。
ちょいとピントが甘くて、ちょいと暗い、そんなふうですが、でも作画レベルは高いのであまり気にならない。
とりま今はベターマン観たという日記です。
そのうち続き観て(ガオガイガーは最終決戦ふきんまで視聴進んでいる)、なんかあったら感想でも書きます。
●十話くらい観た
つても、どーも話が見えてこないと思って、例えばアルジャーノンって何よみたいな。
いつものように飯食いながらガチャガチャとみてるし、セリフも時々聞き取れないんで、いろいろと聞き逃したかと思ったが。
とりまBluetoothヘッドホンで「音だけ」二話を聴いてみたところ、確かに起こっている出来事は劇中でもまったくわからない、ということがわかったっつーか。
「わかってることは人が死ぬということだけ」という、大事なことなのだろう二度も言ってた。 誰かのテロなのか、異星人かなにかの干渉か、あるいは自然現象・・・それはねえか。
金持ち大企業の委託であるアカマツがとりあえづ観測用ロボみたいなものを使って現場にいくという感じか。
ベターマンは謎現象にあらわれて助けてくれる、という認識でそこはウルトラマン。
しっかし活躍するべきロボット、覚醒人はなんかね、微妙すぎるリアルロボットです。 なんか微妙すぎて太陽の牙ダグラムをホーフツとさせるつか、ガラットやガオガイガーのマイク部隊と違ってひっくり返ってもビジュアルがあんま変わらないしw
何がおこってるのかわからんということで、引っ張られる話であると同時に、やっぱビミョーでもあるが。
ケッコーつられて、ついつい次の話も観たくなる魅力はある。
その魅力のひとつに、エンディングテーマ曲があるかもしれん。 なんか作詞が監督(米たにヨシトモ)で歌が- ※-mai-・・・ってコメをマイと読ませるってもしかすると・・・とちょい調べたらやっぱり、監督の別名義ですね- ※-mai-は。 富野監督と同じで、何らかの理由で使い分けているのだろう。
コレがスゲーカッコいいっつーか、放送時は1999年か、中二病って言葉、あったのかなこの頃。 まあ良い闇ですw
と、書きながらぐぐったところ、中二病そのものも1999年1月の誕生らしいっすね、ラジオでかような発言があった時期。
あまりに馴染んだ言葉なんで、いつ頃から存在するのかわからなくなってたが、ちょうどベターマンと同時期ですかなるへそ。
ともあれ「米たにヨシトモ」という名前すら知らんかったけど、ひと時代築いたんですね、ガオガイガーはとうぜん大人気だけどベターマンも決して不人気アニメではないようだし。
●とつぜん話飛んで、最後まで観た
いやー謎アニメですね、いろいろセリフ聞き取れなかったこともあるんだけど。
でもまあ、わかった。
基本的なことは解説してあるし、謎の部分もわりと推察しやすい。
ラスト、誰が助けてくれたのか、まあ海底に沈んだふたりもの人間を救えるのはヤツしかいないだろうなという単純な。
なんでかっつーと、食った実の苗床になった人間の記憶に動かされて、ってことでしょうたぶん。
アサミはいちばん可愛いのに、死んじゃって残念ですなとても。 彼女は善意キャリア(即興造語)にされたんですね気の毒に。
逆にいちばん可愛くないというか、よもやスタッフの悪意だろというサクラは、またよくわからない最後で、でも生き残ったのかな。
たぶんアルジャーノンとよばれる怪奇現象がはじまって以来、寝ても覚めてもリアルが悪夢で、ようやっとぐっすり眠れたのではないかという見方もできるが、まあわかりにくいですな。
また集団殺人、集団自殺という謎のアルジャーノン現象から、捜索しているうちに怪獣も現れて、事件がどんどん見えなくなっていったけど、まあけっこうまとまるもんですね話が。
それと、ガオガイガーとの関連は劇中でもけっこーハッキリしてるんですね。
ミラーコーティングの技術転用とかウルテクエンジンとか。
な、なにがおこっているんだ・・・的な、けっこー振り回された作品だけど、実はけっこう楽しかった。
振り回してくれるくらいのパワーがある作品、ということですね要するに。
まあニューロロイドとよばれるロボットは、やっぱ魅力が足りないっすね、やっぱり。
繰り返すが、ダグラムレベルの中途半端なリアルロボで、だいたい戦い方もわかりにくいが、つまりは敵を分析、大気吸引、化学製品を合成してシナプス弾撃って、つまり毒水鉄砲ってこととちゃうのか? 対象にもっとも効果的な毒を生成してぶっかけ、でしょ。
じっさい対生物兵器装甲ほどこした相手には、まわりの壁や床を崩壊させて倒してたし、強酸攻撃でしょうね壁のばあい。
あと生体リキッドを使ったニューロロイドである理由って、説明されてたっけ。 なぜディーゼル発電ではダメなのか。
このアルジャーノン現象には通常発電のロボットは不向きなのか、たぶん聞き逃したっぽい。
でもって結論としては、まあガメラ2 レギオン襲来的な感じで・・・つか以外な話として、人類とベターマンがレギオンみたいな共生関係なのではという。 いや人類どころか地球生命の裏面みたいな? ふたつ揃ってようやっと生きているのか、そーゆー話なのか。
でもってふたつをひとつにして多様性すら不必要な個体だけになればよくね? と考えた人もいたけどムリ! ということなのだろうか。
まーよーするにわからん、ということなんですが。
ちなウィキペディアをよんだら、破滅絶叫(正式名称わすれた)はやっぱりガオガイガー世界のソリタリーウェーブと同じ理屈だと判明。 ホントいろいろつながってるんだな。
ささやくようなセリフで、聞き取れない部分も多々あったので、いつかヘッドホンつけて再視聴したいです。
という感想。
●ぼくの地球を守って
前回観たベターマンのエンディング主題歌は魅力で、まあ中二病の中でも逆に輝いている(書いてる自分も意味不明)な邪気眼、暗黒属性な良曲ですね。 奇しくも中二病という言葉が生まれたその年に、こんな黒い曲があるとは。
で、ウィキペディアで中二病の項目読んでいたら、引っかかったタイトルが「ぼくの地球を守って」。 コミックですね。
ふーん、読んでみたいなと思ってさらに調べると、アニメ化されてること判明。
ふーん、観てみたいなと思って、ダメ元でバンダイチャンネル検索したらあるやん。
見放題プランで全話すぐ観れますがな。 こりゃありがたい。
意外なバンダイチャンネルの有能性が発覚。
1989年のビデオアニメ全六話ですね。
この時代だと「動物のお医者さん」読んでいるので、まあ少女漫画は得意分野ではないが問題ないだろと視聴。
それとタイトルから直感するのは、アニメの「ぼくらの」の元ネタになっている可能性。 だったら先に、観ておいたほうがいいと考えてそのようにした次第。
とゆーわけで、暗黒属性、邪気眼系な探索をはじめたわけですが、ここでちょいと補足。
転生戦士というとどーしても「ムーの白鯨」を思い浮かべるけど、アレってどんなストーリーだっけ。 別に転生戦士ではなくて、単に血筋ってだけだったかもしれない。 だとすると単なる超電子バイオマンなわけで。
まあいいか。
ともあれ、転生戦士には歴史があるわけです。
むしろ昨今の作品群のほうを知らないので、こうして少しでも調べている次第。 1989年のアニメ「ぼくの地球を守って」はちょうどいい素材ですね。
つーわけで、いまんとこ六話のうち二話まで観ました。
ウィキペディアによると転生戦士をネタにしたマンガらしいが、そんなナリキリ少年少女を描いたのではなく、ガチでした。
ナリキリにしては前世情報がシッカリしすぎているし、能力でちゃったし。
つーてもかなりギャグタッチで、やっぱ動物のお医者さんとか読んでいて感覚がけっこーわかるというか、70年代のものであれば少女マンガもちょくちょく読んでますから、抵抗なく入れた。 11人いる! も原作読んでます。
また1989年の、新築の川崎アゼリアもみれて興味深い。
ソレ以前の川崎駅ビルとはまったく雰囲気が違うというか、ほとんど今とかわらないのかな、タイムトラベルして行ってみたい。
それにしても、驚くのがクオリティの高さというか、むろん前年にはAKIRAがあったし、ロボットカーニバルもこのへんだし、高いところは高いのは知ってるが、当時レンタルビデオで観なかったので有名ってほどでもないアニメなのだろう、でもこの作画レベル。
技術力高かったんですね、この頃から。
アホな子供が新体操の真似してリボンクルクルという場面も見事に描いていて。
まあ自分が知らなかっただけで、一部では有名な作品だったらしいので、チカラが入っているのだろうが。
あ、それからPCブラウザでバンダイチャンネルみると、下にレビューが出てくるんだけど、どうやら原作をだいぶん端折ったアニメ化らしいですね、またアニメは六話完結なのかな、でも物語には続きがあるようで。
とにかく現在のアニメが邪気眼や中二病をネタにするように、転生戦士をネタにしたこの作品、楽しめます。
●最後まで観た
とりま六話ぜんぶ観ました。
ラストの件だけど、レビューで知った「話途中」がなるほどとわかった。
どうなるかというと、最後の十分くらいをダイジェスト、という方式でした。 旧アルスラーン戦記と同じですね。
おそらくは原作ファンがアニメで観たい名場面集、ということなんでしょうね、断片的だが印象的みたいな。
でもってそれよか製作年が1989年・・最後はもう1991年とかなってるかもだが、もちろん当時の絵柄であり、それは古臭い上に携帯電話を使わずにストーリーが進行するという、まー当時はまったく普及していなかったのでそりゃそうだが、つまり「昔話」に見えて当然なんです、絵柄と携帯、ふたつの要素がじっさい昔だから。
でも、そうは見えない不思議。
なーんか生活感覚や町並みが今とほとんど変わらないんだよね、この頃になると。
逆に言えば70年代までのアニメ、ドラマ、映画は決定的に何かが違っている。
それが何なのか知りたい。
要は古臭く感じないのだけど、いっぽうで今のアニメと違うというか、むしろ優れている点は自動車などの描きこみですね。
今はお手軽CGで済ますから・・・いやCGがマヅいってわけないんです、お手軽がマヅいって話。
超能力バトルでも地面のえぐれ方でパワーの応酬がどんなものかわかったり、凝ってますね。 まあAKIRAのあとだからそれは当然なのかも知れないけど。
あとは「呪いの遺言と思ってたけど勘違いでした〜」というのは今川監督版ジャイアントロボでも観ましたが、こっちが先か。
ちなみに転生戦士ではなく、まあ特派員みたいな感じですかね、特別な能力があるため特殊任務で月から地球を監視した七人で、バトルできるヤツもたまにいるって話? 向こうの世界をみるに、念動力ひとつあるだけでもそーとー特別と思うが。
またなぜ地球へ降り立つのは禁忌なのかも謎だし、そもそも彼らが監視している地球はいつ時代よ、という。
あとは「彼ら」が地球人に転生したのかその逆なのか・・・未来から過去に転生もありうるわけで。
↑よくわからんが少なくとも21巻はあるってこと?
それらぜーんぶ、匂わせながら途中でたたんだ形です。
まあ残念だけど、テレビアニメ化しないかぎりムリな長編なんでしょうね、色と音がついたサンプルみたいなもので満足するべき。
原作を続き読めば、自動的に色付き音声が脳内再生されるだろうから。
ともあれ、面白い話でした。
という。
●ロボットカーニバル
前回に観た「ぼくの地球を守って」があんがい作画レベル良かったので、このへんの記憶を改める意味でロボットカーニバルを。
ちなバンダイチャンネルで見放題プラン扱いなので、いつでも観れるのでブックマークしてあった。
あとでぐぐったら1987年ですね。
いちおうちゃんとレンタルビデオ店には並んだので、すぐに観たと思う。
AKIRAみたのは一年遅れの1989年だと思うので、それまではたぶん、視聴したアニメの最高クオリティではないかと。
まあ、驚きましたねその作画に。
むろん、アリオン、天空の城ラピュタ、王立宇宙軍オネアミスの翼とか観た後だろうとは思うけど、やっぱり驚いた。
作品そのものは、8本だっけオムニバス方式で、ストーリーを度外視した品評会みたいなもんだと思うけど、他にもいろいろな意味合いがあるアニメで、つまりアニメ作家の好きにさせたらどうなるかという実験とか、アニメで何ができるのかというチャレンジとか。
だもんで主に作画の話になるけど、ホントにスゴいっつーか、やっぱり近年、動かせる人が少なくなってるような印象があったけど、こうして旧い作品みると改めて想う。
静止画状態、止め絵だったら近年のアニメが圧勝なんですけどね止め絵だったら。
あいや今でも動かせる人はいっぱいいて、でもアニメそのものの数が増えたから分散しているだけかも・・・という考察もできるが。
他の考察としては、にわかアニメファンは作画枚数だけ増やせば騙せますしね、右から左へ動かすのに等分してCGみたいに動かせば「それっぽく」見えるし。
つかロボットカーニバルはかなり特別なスペシャルアニメって考え方もある。
このへんは今後、バンダイチャンネルで旧い作品みてさらに研究してみます。
複数あるオムニバスの、どれを語ろうかな。
まずオープニングとエンディングでしょうね・・87年ということは、大友キャラがマジに動いたものをAKIRA以前に目撃したってことになりますな。 幻魔大戦のときとはまた違った感じで。
タイトルがそのままキャラクターというか、移動パレードになるっつーアイデアも楽しいし、文明崩壊後に一部の機械がマジメに職務を続けているっていう定番ネタも面白い。 とにかく迷惑やんw という。
しかしエンディングではようやっと力尽きてロボットカーニバル停止、ブイブイいわせていた黄金時代を夢に見るという。
実を言うと、ハウルの動く城よりコッチのほうが迫力あるような気がするんですよねカーニバルロボット。
じっさいずっと後年の、しかも劇場用宮崎アニメであるハウルの動く城のほうが、凝っていると思うけど、何かがスゴい。
世の中の変化など知ったことではないカーニバルロボットの、有無を言わせぬ押しの強さかもしれない。
でもって「明治からくり文明奇譚〜紅毛人襲来之巻〜」・・なげータイトルなんでコピペですが、コレも語りたい。
オネアミスの翼っぽい人物なのは貞本義行キャラだってさやっぱり。
これは衝撃的な作品というか、マジで街に(下町に)ロボットが現れたらどーなるかをリアルに描いたのが凄くて。
だから二年後になるかな、機動警察パトレイバーTHE MOVIEみたときに、コレを連想したはず覚えてないけど。
でもって自分も過去十年くらいに巨大ロボット小説をpixivに投稿していて、まあダラダラと61話も続けて完結したけど。
自分小説はリアル系ロボットアニメを模倣していて、でも多くの商業アニメより一歩進んでいると自負しているが、何が進んでいるって巨大ロボットが「現場」にたどり着くまでが大変なんだぞと。
現在、100トンを超える空輸力はよっぽど巨大な輸送機しかねえし、同じく100トンを超える輸送力の車両もねえし、2000トンを超える飛行物体はサターンロケットくらいっしょ。
つまり巨大ロボットは自力で歩いていくのが手っ取り早いわけです町中を。
そんなアイデアは、たぶんこのカラクリ神輿からきていると思う。 半日がかりで対峙してましたねアメリカのロボと。
それと背負投げとかやったらどんだけ負荷がかかるか、というシミュレーションもできてますなこの作品。
カラクリ神輿は木製なので果たせず、仮に鋼鉄のロボでやったとしてもエラいことになるだろうなと、その対決をみると想像できるわけで、これも参考になった。
「ニワトリ男と赤い首」にも触れておくと。
当時、有名だったアニメーターなかむらたかし作品となります。 AKIRAのスピーダーチェイスなんかは丸ごとこの人の作風になってたり、他にも赤い光弾ジリオンオープニング、ピーターパンの冒険、迷宮物語などなどで、絵をみれば「あ、あの人か」とわかる稀有な存在みたいな。
街が悪夢のようになってるのをとにかくアニメで描く、ストーリーはたいして要らないって感じですか。
足の長い何かが行列というイメージは、迷宮物語にもあったけど何が元ネタなんでしょうね。 ダリとかの絵にそんなんあったのかな。
ちな近年では映画「ミスト」にもありましたね、そーゆーの。
本来、作家はストーリーもってる人なんだけど、アニメーターはちょい違うようですね。
シーンを、キャラを、いやとにかく絵を描いていたい、なんでもいいから動かしたい、という亡者のような気迫が全般に。
アニメ品評会としては大成功、なのではないだろうかじっさいの業績は知らんが。
とにかくアニメの可能性を見せる、という意味では意義のあることだと思う。
最後に観たのいつだっけ、VHSレンタルだと思うが、久しぶりの視聴となります。
テレビ放送して、それ録画した・・・という記憶もあるようなないような。
バンダイチャンネルでいつでも観れるってのは、いい時代になったとつくづく想う。
という感じで。
●未来ロボ ダルタニアス
コン・バトラーVの続きみよかと思ったが、未だ観たことないこっちを優先。
過去にレンタルビデオでアニメ主題歌集を借りてダビング、擦り切れるまで観たのでオープニングは知ってて、堀江美都子歌うこの曲はお気に入りでした。 そのオープニング映像からも面白そうな作品であると感じていた次第。
で、観はじめて驚きが1995年・・・ずっと未来の物語というか、今では複雑な気持ちですが。
イキナリ、闇市ではじまるという。
え、もう戦火の真っ只中なの? ザンボット3みたいな全国難民状態が。 つか太平洋戦争のあとみたいな。
でもって主人公一味が戦災孤児? スゲーアニメだなコレ。
謎の宇宙人から攻撃されて、敗戦色濃い中で、それでも前向きに生きてるっていうか、逆に景気がいい話運びが不思議。
このとき暴利をむさぼっていたオヤジ、バナナひと皿二万円とかいう闇市のオヤジは、その後レギュラー化してエンディングにも文字通り顔を出しているというのも驚きですが。
戦災孤児たちはそんな中、賭場荒らしならぬ闇市荒らしやってて・・・ほとんどはだしのゲンですな。
そっからひょんなことから落ち延びた宇宙船のクルーになるんだけど、その銀河帝国再興をはかる老人がまた妙で。
見た目は白髪のヒゲ紳士なのだが、まあ賢者っぽいっつーかじっさい博士と名乗っている。 コイツがまたヘンに威厳がなくて。
スグにキレるし軽いんだよね雰囲気が。 見た目に反して。
あとでわかったが、このアール博士だっけ、要するに「うるさいじいや」キャラでした。
内容をいろいろ語りたいが、頭が追いつかないので五話ほどみた感想だけ軽く。
まづ二話くらい観たあとでウィキペディア読んだら、1979年っつーことで、スーパーロボットとしては新しい方です。 制作が東映なのはオープニングみれば作詞が八手三郎・・・東映のチーム名っつーか、最後に東映と書いてあるのでわかることで、以前に本で読んだ「タツノコプロに比べて東映は作画が酷い」というのはホントーだなってわかる。
本編みても、第一話から作画はずいぶん雑なんだけど、それでもスゲえ面白いと感じた。
戦災孤児が主役なんで、不謹慎な自由さがあってとても楽しめる話になってて、第四話までみんなボロを着てました。
敵の先遣隊を倒したことで一時的に地球は勝利し、宇宙船は市民から大歓迎、みんなの寄付でオープニング、エンディングにみられる定番の服を貰い受けたという。 ザンボット3と逆なんですね面白い。
闇市のオヤジはその一時的な勝利に改心したのか、すっかり善良になっちゃって、でも敵本隊の来襲に備えて廃墟の街からキングビアルもといアール博士の宇宙船のまわりに大勢が引っ越してきて、その地球市民の代表なわけです闇市のオヤジ。
たくましいな一般市民は。
ここで主人公の剣人だっけ、字に自信がないが・・・ヤツが銀河皇帝の血筋と判明。
しかしコイツはあくまでも自主独立の戦災孤児なんですな。 運命の押し売りはお断りしますみたいな。
主人公が王族って設定、その後の最強ロボ・ダイオージャに受け継がれたらしいウィキペディアによると。 まあ自分はダイオージャを先に観てるので逆に感じたんですけど。
そんな物語の面白さと同時に、主役メカ、ダルタニアスも面白い。
巨大ロボット、アトラウスで戦い、仲間としてサイボーグのミライオン、ベラリオスを召喚。
あとは戦闘機というかパーツメカと合体するとダルタニアスに。
コレってもしかして勇者王ガオガイガーの元ネタ・・・でしょうね。 オリジナリティの塊のようなガオガイガーだが、「スタイル」は過去の作品からいろいろ借りていると思うので。 そうでなくては巨大ロボットアニメなど熱く語れるものではない。 リスペクトでありオマージュであるかと。
じっさい合体シーンはちょいと似ていますダルタニアスとガオガイガー。
つか先に語ったように東映アニメは作画が雑で、ダルタニアスの変形合体シーンも「玩具化不可能やろ」ってほどガタガタw
まことに残念な部分であり、だからガオガイガーの合体シークエンスはこれを、ファンが、高いクオリティでリメイクしたのでは。
鼻血出るほどスゲえガオガイガーのファイナルフュージョンはそんな意味があるのかと。
ついでにいうとダルタニアスは面白いアニメであるが、合体時の叫び「ダルタニアス〜」はちょい語感が悪いかな。
その点でも「ガオ! ガイ! !ガアアアアアアア!!!」は完璧でしたね。 やっぱり過去を昇華させた作品なのではガオガイガー。
繰り返すようだけど作画はガタガタなんですけどねw
しかし観ていて不快ではないのが不思議。 慣れかな。
ゆうても割と品質が高い方である日本サンライズ(現サンライズ)だって、ザンボットやダイターンのころはけっこう粗い絵でしたし。
とまあそんな感じで。
●二十話くらい観た
えーっと、意外な話として、エンディングテーマはけっこう名曲なんでわ? という疑惑。
他愛のない歌詞なんですけどね、とくに凝った楽曲とも思えないし。
しかし添え物的なものが多いロボットアニメのエンディングテーマにおいて、なぜか頭に残るという・・・。
タイトルは『剣人・男意気』という曲で、やっぱり主題歌ビデオにより聞き慣れた(見慣れた)ものなんだけど、改めて本編の締めとして観ると、来週も(まあ配信だからすぐみれっけど)楽しみというもので。
余談ながら、すぐに思い出せる範囲だと無敵鋼人ダイターン3や無敵ロボ・トライダーG7はコミックソングで、機動戦士ガンダムや無敵超人ザンボット3は哀愁系で、まあザンボットはなかなか印象深いけど、ガンダムはうまく思い出せないくらいの印象度。
そして超時空要塞マクロスに至っては聴くたびにすぐ忘れる。
エルガイムや∀ガンダムはまあ、いい曲だけどインパクトは薄い感じかな。
そうなるとエンディングテーマで印象深い名曲って、なかなか難しいような気がしてきた。
ゆうても確率が低いだけで、アニメの数が多いので結果的に名曲もわりと多い。
すぐに思い浮かぶのは戦闘メカザブングルの「乾いた大地」、劇中の設定である「三日の掟」を歌詞にしたのが良いみたいな串田アキラの名曲で・・・あ、串田アキラゆうたら特撮で名エンディングテーマ多いけど、特撮は別腹ということで。
でもって個人的に好きな機甲界ガリアンの「星の一秒」、なんとも不思議な響きがキレイな曲をあげておく。
そして劇中設定を歌詞にしたといえば聖戦士ダンバインの「みえるだろうバイストン・ウェル」っすね。 なんか有りもしない前世の記憶に干渉してくるくらいの名曲。 言っている自分が意味不明だけど。
他にもあるぞ、銀河烈風バクシンガーの「アステロイド・ブルース」! なんでJ9シリーズでコレだけ名曲なんだw みたいな。
あいやサスライガーのハッピーデイズだっけ、あれもいいけどね。 ブライガーはなんか再放送でちょい観ただけなんで忘れた。
そして銀河漂流バイファムのネバーギブアップ・・・何故かとてつもなく懐かしい気分にさせられます。
超獣機神ダンクーガのバーニング・ラヴに至っては主題歌と同じくらいのパワーで人々に刻まれているようです。
勇者王ガオガイガーはもう本編とリンクした名曲だし、この前みたベターマンはもう凄すぎて笑えてきますなw 暗黒厨ニはカッコ良すぎると逆に引きつり笑いが込み上がってくるんです。
最近のアニメでも革命機ヴァルヴレイヴとか鉄のラインバレルとか、スゲえ名曲が多いっぽい。
まだまだ語りたいんですけどね、確実にロボットアニメから外れるのでこのへんで。
それよか未来ロボダルタニアスとゆーこの作品の、本質がわからなくなって。
いや面白いからいいんだけど、なんか総括したいやん。
エンディングテーマの歌詞からわかるのは、主人公の剣人が銀河帝国の王子であること、祖国を再建すること。
またタイトルやデザインでわかるのは三銃士をモチーフにしていること。
じゃあ、ロボット版騎士道物語なのか、アーサー王伝説なのか、三銃士なのか。
・・・・なんか二十話ほど観た感想として、そうは思えないんです。
うーん、うーん、なんてのかな、そもそも話の出だしが闇市という衝撃的なものだったし、その後も先遣隊を倒したのに生活はさほど変わっていないし、かろうじて発電所をつくって街に明かりは灯ったけど。
なんだろうね、どーしてもロボットアニメ版はだしのゲンとしか思えんとです。
しかし、はだしのゲンほどの悲壮感もないので自動的に雰囲気がど根性ガエルに。
ど根性ガエルも不思議なアニメですよね、二度に渡るアニメ化、そしてキルラキルなど、以降の作品に影響して。
原作もちょっと読んだことあるけど、普通におもしろいマンガです。
とにかく、そんな感じなんですダルタニアス。
まーだから、逆に嬉しいんですけどね、かようなサプライズ、意外性、得した気分。
またロボットアニメも名作になると、生活感がプンプン臭うものなんですが・・・例えば誰かが言ってたんだけどサンライズのアニメには食事シーンが多いそうな。 確かにカウボーイビバップでも貧しそうに食ってたもんねしょっちゅう。
この未来ロボダルタニアスも東映なのにそんな感じです。
なればこれは、あんがい名作じゃん。
ほらほら得した気分と言ったのはそういう意味もあるんです。
あーちなみに、道徳観念や理論は現在のアニメのほうが圧倒的に正しいです。
あらゆる配慮を欠かさず、間違ったらその罪を背負って決して忘れてはならない、うん正しいよ今アニメ。
でもなーぜか昔アニメのほうが面白いと、去年からバンダイチャンネルで旧いの漁ってよっくわかった。 暴言の嵐、間違ってもなかなか懲りない、成長が遅い、でも面白いんだ昔アニメ。
そして再び余談。
繰り返すが絵は雑なダルタニアス、バンクの合体シークエンスもムチャな感じですよね。 一部オープニングで見れるけど。
特にアトラウスの折りたたみ変形は当時に玩具化できたんかいな、思ってYoutubeで(よく通常の検索でなくYoutubeを調べたりします動画でわかりやすく解説してくれる可能性があるので)探したらひとつありました。
ポピーの未来合体ダルタニアス。
ソレみると、けっこー再現できるんですね未来合体。
アトラウスの折りたたみは納得、ガンパーのコックピット収納もあんがい可能なんだなと感心したが。
ベラリオスの足がくるくる巻き込まれるのはさすがに再現不可能ですなw 超合金魂でも出ているダルタニアス、ベラリオス足はたたんで背中に押しやるのが通例となっている様子。
超合金魂はアレだ、オリジナルに可能な限り忠実だと思うんでそうなんだけど、自分だったら新訳未来合体として、ベラリオス足を折り畳まずに伸ばしたまま背中から突き出しておきますね。
このYoutubeで唯一見つかったポピーダルタニアス、何故か玩具の扱いがむっちゃ雑で、コメント欄で叱られてましたw
それは不思議なことで、観るとなにか焦っているようなトークと玩具扱いであり、そんな昔の動画投稿じゃないんですよ、時間制限があるわけでもなし、なにを慌てているんや、という。 あいやYoutube時間制限があった時代でも、編集すればすむ話で。
落ち着きを身につけるべきなのか、あるいは・・・元々雑な扱い方をする人なのか。
観てると「ダルタニアスの変形ジョイントが壊れるんじゃないか?」と心配になりますね、唯一の資料なんでぜんぶ視聴したけど。
とりまここには動画貼り付けしないでおきます。 模範的じゃないから。
逆にいうと、ロボットアニメの(当時の)基本は玩具メーカーの企画であり、変形合体の設計もそうである可能性があって、つまり東映アニメの再現がそんだけ下手だったのかもね。 ボルテスVなんかはけっこー燃える合体してたんだけど。
で、ここからちょいと本編のダルタニアスに話もどして。
実を言うとワタクシ、ロボットアニメファンでありながら、ロボットは無意味と考えてます。 パトレイバーくらいなら納得するし、ボトムズくらいリアルだと歩兵の機械化ともとれるんだけど、他は無意味で。
ガンダムなんか特にそーですね、あの世界、ちゃんと戦闘機も戦車もあるやん。 条約でいろんな兵器が禁止されている世界観ならロボットもあり得るけど、ガンダムはそうではない。 まあ自分なら長距離ミサイルや航空爆撃などが禁止された世界で、主戦力が大砲みたいなところにソレを扱う巨大工兵、という設定にします。 ドイツ軍の列車砲も巨大ロボなら軽々と運用できるやん。
まあいいや、ダルタニアスのようなスーパーロボットだと超エネルギーの筐体としてロボットなんだけど、宇宙戦艦でもいいんだよね別に。 あるいはガンパーをもっと充実した戦闘マシーンみたいな形でも。
それを本気で問うのは野暮だし、何よりアニメを観たいなら誰かに製作してもらう必要性があり、そのために販促ロボが登場するのは自然にも思える大人の事情。
にしても結果的に、なんでアール博士はダルタニアスを合体ロボにしたんやw という疑問になるわけですはい。
テキトーでもいいから説明があればいいのだが、ダルタニアスというアニメには確かなかった。
ちなザンボット3は合体することでイオンエンジンをフルに活用できる、と説明してたっけ。 分割していた意味は不明だが。
だからその後のロボットアニメで、合体が減ったのは別に惜しむことはないですね。 合体に燃えるのは確かだが、いっぽうでそれまでは玩具メーカーの都合だったわけで、ムリに合体メカを出さなくてもいいよ、ロボットアニメの魅力は他にもあるから、ということ。
それを言い換えると、スゲえ燃えるなら合体シーンは有り難いってことでもあり、それもあって玩具化を度外視したビデオアニメのダンガイオーとか出るわけっす。
超獣機神ダンクーガなんかはチャレンジャーでしたよねそう考えると。 スゲえ燃えて玩具化もアリ、ですから。
あとダンクーガはね、12話だっけはじめて合体したとき、あんな強えロボットみたことねえw って驚愕した思い出も。
と、いろんなことを考えさせてくれるダルタニアス。
そんだけでも観る価値があったわけで。
いま二十話くらいだっけ、このあとちゃんと銀河の帝国を復興できるのか、見届けます。
●聖戦士ダンバイン-テレビ編集版
なんだそりゃ、というものがバンダイチャンネルに登場。
いまぐぐって調べます・・・はい調べました。
結果、よくわからんとです、ウィキペディアのダンバインページでも。 たぶん総集編のことだろうか、でも製作年とか記されず。
別なページみたけど、たぶん1988年に出た「再編集版」のことかと。
で、みたけどなーんかHDリマスターなのか鮮やかになったのはいいけど、妙にカラフルですね。 まあダンバインは意外と色鮮やかなデザインワークなんでいいけど。
あとはテレビの音声をシネマモード、つまりサラウンドをオンにしているんだけど、これが響く響く。
じゃあステレオ音声化されているんだなと勝手に解釈。
内容はもちろん、全三話のダイジェストなんですが・・どうも収録し直しているっぽいです。
なんでわかるかというと、もう何度も観て音を耳が覚えているんですね、まづショウ・ザマがオーラロードで強制召喚ですが、そこにチャム・ファウが飛んできて地上に帰れ〜っていちゃもんつけて、その次のガラリア・ニャムヒー台詞でわかった。
今も昔もロボットアニメは新人声優さんを積極的に採用して、予算の都合か新人育成かわからんが、ガラリアの初ゼリフもかなーりたどたどしい印象なんです、それが今回、すらすら言えてる〜って。
なんだっけ「ニー・ギブンに肩入れするミ・フェラリオ!」だっけ。 もっと長いセリフだっけ、すらすら言えたァあああ! って。
ぜんぶの声優さんを再招集して収録したのなら、やっぱ1988年ごろでないか。
5、6年経っているが、まだみんな現役でなおかつ、新人さんはもう慣れた頃合いかと。
ここでイキナリ総括。
聖戦士ダンバインを三話のダイジェストにまとめ、ステレオ音声にて再収録して、今ではHDリマスター(たぶん)となった作品で、じゃあ、ダンバイン入門用にぴったしではないか、という。
これさえ観れば、Amazonにある大量のオーラバトラーフィギュアの価値もわかるってもんでしょ。
実はまだ最初の十分くらいしか観てないけど、まあそんな感じで。
それにしても、ロボットアニメのメイキングというか、製作のインタビュー記事とか読むと、第一話はやっぱ苦労するらしいね。
で、聖戦士ダンバインのばあい、ショウ・ザマが強制召喚されてドレイク館、ラースワウにとらわれた時点で、そーとーな情報量です。
よっく聞かないとわからない説明ゼリフも多いが、ショウ・ザマの身に何がおこったのかは自然にわかることで、疲れた妖精を水牢にもどす、今夜は三人か・・というつぶやき、妖精の力を利用して異世界の勢力が地上の人間を呼び寄せているのか、とわかる。
●第一章を観終わる
いやーあんがいいいっすねダイジェスト。
あ、バンダイチャンネルの説明よく読んだらちゃんと書いてありましたダイジェスト版って。 でも製作年はわからず。
でもまあ、やっぱり1988年でしょうねたぶん。
あんがいいいと言ったのは、声優陣のイメージがあまり変わっていないからでしょう、おそらくいちばん変わったのはチャム・ファウで、たぶん演技が上達して逆に、ミ・フェラリオ特有の器の小ささが表現できていないのかと思うがまあいいやみたいな。
88年説を採用するなら5、6年くらいか本放送が終わってから。 ちょうどいい頃合いなのかも知れない。
これが1989年の機動警察パトレイバー劇場版だと、再収録されたのが1999年だっけ、十年経っているわけで、キャラクターのイメージがガラッとかわって、しかも逆に微妙な演技が再現できていなかったり酷かったw
そもそもパトレイバー劇場版はすでにロボットアニメの創造ではアイデアが出尽くして、あらゆる概念が・・・そこには聖戦士ダンバインが築き上げた「巨大ロボ+ファンタジー」というのも含めて、打ち止めみたいな頃合いで、出演した声優陣はたぶん、パトレイバーを理解していたと思うし、一年ほどビデオシリーズでキャラに馴染んでいたし、だいたい89年だともうデジタルサウンドやん、収録の現場もアナログ時代からもう仕事に慣れていて、とにかく89年の時点で完成度は高い。
なかなか立派なステレオサウンドで、迫力も充分ですこの時代。
だからパトレイバー劇場版を99年に再収録する意義があんのか、という感じでしたねはい。
同窓会だったのだろうか。
.後述:いまぐぐって調べたが、パトレイバーのは「機動警察パトレイバー the Movie サウンドリニューアル版」とゆうらしい。しかしリニューアル版の感想はどうよと調べても、なかなか出てこない。どうも無かったことになっているというか、あくまでもオマケなんでしょう。オリジナルが今でも馴染みってことか。DVD、Blue-rayには付録で収録されていると思うが、わざわざ観る必要性もないみたいな。
それに対し、ダンバインはやり残し、心残りが多かったでしょうね、いちおう当時に出た主題歌、BGMなどの盤は日本サンライズでははじめてなのかな、デジタル収録という時代の節目だったようだけど、ならなおさら、心残りが多いはず。
デジタル収録でアナログ盤レコード出してたのだから、そら心残りあるわな。 放送はモノラルだし。
また複雑な大河ドラマで巨大ロボファンタジーという、リアルロボ系で初めての試みなのかな、声優陣も最初は戸惑ったはず。
88年なら「あれはああゆうアニメなのか」と理解度も増して、正面から取り組めたはず。
で、ダイジェストのあんばいだけど、まあ主要なシーンを切り取って、その間はナレーションですね。
しかしそこで、本編ではみることのなかったアの国周辺のマップが映ったり、なかなかわかりやすいかもしれない。
つか知らない領土も多く、なるへそこんな具合か、全世界がわからんが、ドレイクは世界の半分くらい手に入れるつもりだったのかな。
みたいに、なかなかうまいですねこれは。
大河ドラマを三時間くらいにまとめるのだから、個々のキャラクターはかなり端折ることになり、ナレーション戦術は納得だ。
物語の概略をまとめにして、でもちょっとした名シーンは押さえておきたい、って感じかな。
エンディングテーマはフルでしたが、オープニングは本編と同じショートバージョンで、どうやってステレオ化したかというと、あるんです。 当時・・・ダンバインくらいの時代であれば、ステレオバージョンが。
ちゃんとテレビ用のモノラルと同時に作られ、レコード販売するBGMの・・例えば2巻に収録されるもんです。
だからYoutubeなどでたまにみる旧いアニメオープニングのステレオ化は、それが音源かと。
あるいはステレオの音源をモノラル化したのがテレビでお馴染みのバージョンなのかも知れないが詳細不明。
おっと余談として、ちょい気になったのでガラリア・ニャムヒー役をウィキペディアで調べたが、どうやら総集編では違う声優さんとのことで、じゃあオリジナルの人はどんな方かと思うがwikiページは無い。
なればとウィキペディア以外で調べるも、どうやらアニメ声優をやめたらしく、ある意味「行方不明」ということらしい。 まあいいか。
要は女優業をやめて一般人ということでしょうたぶん。
ともあれ続きみます。
●最後まで観た
一気に観れたっつーか、やっぱ面白いってことですねダンバイン。
ここでようやっと比重がわかったっつーか、ファンならものすごい印象深いシークエンスである「ハイパージェリル」は2巻となっており、つまり最後の決戦に多くの時間をという構成。
皆殺しの富野監督といわれるように、主要キャラが全員整頓されるラスト付近を念入りにダイジェストした形。
ここで(今回のダイジェスト版で)印象深いのはトッド・ギネスの死に様ですね、ああこんな名シーンだったんだ、みたいな。
トッドといえば海上での決戦のほうが記憶に残っていて、でもあのときはオーラボムを呼んで脱出しているんだよね、その後の、ホントーの戦死は物語が忙しすぎて失念していた。 この前バンダイチャンネルで全話みたのに。
あとはニー・ギブンとドレイクは刺し違えだったのかみたいな。
そんなキャラクターの結末を時間制約のわりに丹念に拾ったダイジェスト版ですが、ラストシーンはオリジナルな演出でした。
いや本編どおりなんだけど、テレビ版にはない楽曲が使われて、なおかつ毎度まいどお馴染みなナレーション「それ故に・・・」はスタッフロールのあとという。
説明すると、各話の冒頭に語られるナレーション「それ故にミ・フェラリオの語る・・」がテレビ本編の最終話のさらにラストに来て、長らく観ていたダンバインファンは「繋がったああああああ!」と泣くわけです。 いやまあ泣きはしなかったけど。
で、ダンバインという作品だけど、なーんかガンダム以来リアルロボット系がたくさん作られたけど、ついに完成したって雰囲気。
ガンダムの時点ですでにロボットアニメは、単純に玩具を売るためのツールでなくなっていたけど、それがついに、という意味で。
作品そのものも重要な商品になりうるってことですけどね、ちょうどビデオソフトがちらほら出回りはじめる時期だし。
要はアニメとして、完成度が高くなった初期の作品みたいな。
あいや物語は、例えばボルテスVとか優れていたけど作画は酷かったやん。
ダンバインはだから、第一話から作画は良かったけど、それが最後まで続くわけで。 ゆうても「描ける」人材はまだ少なかったようで、かなり新人が頑張って作画したような印象ですけどねまだまだ。 コレがカウボーイビバップ、ザ・ビッグオー、勇者王ガオガイガーの時代、つまり90年代後半になると、サイコーのクオリティとなる次第。 ある意味、今現在よりレベル高い場面も多い90年代でした。
先ほど語ったハイパージェリルのシーンも、まー作画スゴかったですね、去年までの戦闘メカザブングルと比べても。
つかキャラクターデザイン手がけた湖川友謙は昨年からの続投で、でも「この人こんなに絵がうまかったんだ」と驚いて。
あ、説明すると伝説巨神イデオンを観ていないという個人事情が。
何度か書いたかもだけど、一枚絵だと現在のほうがはるかに上手いんです。 もう比較にならないくらい。
でも動かすととたんに、差がなくなるというか、逆に昔のアニメのほうが良くね? という。
なんというか、動かしても面白くないキャラクターデザインを、今では何の疑問もなく皆が受け入れている印象ですね・・・だからか最近、なーんか単純な構図が多いような気がする。 横位置で横移動で歩くだけとか。
気のせいであってほしいものだが。
あーダンバインの話だっけ、キャラクターデザインは正面から写してもよし、どアップもオッケー、動かしても楽しいという、完璧に近いものですね、まあ描くほうは地獄でしょうが。
ウィキペディアをさっき読んで、面白かったエピソードは、シーラ・ラパーナを作画陣がこぞって描きたがった、という。
当時としては超美女というか、美少女だったということでしょうか、エレ様の立場がねえw
しかし今みてもスタンダード美女ですよねシーラのデザインは。 スタンダードなタイプの絵といえば二年後になるのか、風の谷のナウシカから続くジブリ系がありますが、作画スタッフがシーラを描きたいというのは、珍しかったのかな。
キャラクターは個性的でなくてはならない、とにかく他の作品とは違う顔を描かねばならない、という風潮だったのかもしれない。
ロボットバトルの話すると、後半の「オーラバリアー」「ハイパー化」という設定がつくことで、逆にバランスがとれたような。
まあ意見は人それぞれだと思うけど、自分的にはそう思える。
砲弾やミサイルが当たれば死ぬって、リアル系なら当たり前なんだけど、決着がつけにくいやん。 当たれば死ぬって、当たったらそのキャラクターはそれっきり、だもんで前半では部位破壊、手足被弾などで戦線離脱、という展開がフツーだった。
バリアーとハイパーで、格闘ゲームみたいに思う存分暴れられるように。
ゆう感じで、とにかくいろんな考察させられる一品でした。
でもって調べるうちにこのテレビ編集版と銘打ったものは、OVAの総集編であること、確信もてました。
1988年で間違いないでしょう。 そしてバンダイチャンネルでは先にダンバインのOVA版みたいなのが出てるけど、コレはOVA3巻に一話ずつ入れた新作だとのこと。 正式なタイトルはNew Story of Aura Battler DUNBINE、コピペしなけりゃ書けないタイトルと思いきや、ダンバインは英語表記できますね自分は。 ザブングル(Xabungule)に続いてふたつ目におぼえた英表記ロボでして、率直に「ヅンビネ」と覚えりゃいい話なんです、はい。
もしかするとGundamのほうが先かもしれんが。
もいちど言うけど、このテレビ編集版は本放送の五年後くらいに声優陣を再招集して収録したもの。
正直、各キャラクターを演じる声優さんの中には当時の呼吸を忘れたっぽい方々も散見できますが、主役のショウ・ザマはじめ、メインキャラの声優さんはシッカリしてるので、作品の雰囲気は損なわれてないし、なかなかお得なパッケージ。
できれば、多くの人々に観てもらいたいです。
●New Story of Aura Battler DUNBINE
↑コレに収録されているっぽい
ちょうどいい機会なので総集編の次に観ました。
まづ言っておきたいのは驚愕。
作画の驚愕ですな、出渕裕イメージアートがそのまんまアニメになったオーラバトラーの描写、いやそれ以上ですね。
要するに風の谷のナウシカでの王蟲と同じ手法、なのかな、そんな感じで。
じっさいの作画は王蟲以上にスゲえっつーか、そうなると問題は動かないってことですねw
でもスゴイんだコレが。
いやーホントに1988年の作品かってくらいスゲえけど、キャラはフツーに当時の雰囲気ですね。
昔から決めの止め絵はブラシかけてスゴイ作画ってパターンは多く、このまえ観たボルテスVとかでもフツーにあるけど、美術に匹敵する絵でロボを描くって、テクスチャにおいていちどここで、極めているんですね知らなかった。
次に極めるのはパシフィック・リムのイェーガーで、まあ超大作レベルのCGテクスチャなので、日本のCMやゲームは真似できません。
まあ繰り返すが、テクスチャにおいて極めたが、ほとんど動けないんですけどね。
それでもやっぱり王蟲と同じように複数のパーツでちょっと動かしたりはしてます。 あとはスライドなどの演出で魅せるというのは、考えてみればテレビ本編でもよくやっていたことで、あんがい不自由ないのかもしれない。
そして、決して重度のアニメファンではないにせよ、ロボットアニメなら流れをつかんでいると思っていた自分が知らないってことはですね、その後の作品に反映されていないってことです。
いや例えばパトレイバーのシリーズでも一瞬のどアップで背景並みの描き込みはしますが、あくまでも整備中など、停止しているレイバーを描いたもので、ほとんどを王蟲方式ってのはあまりないんじゃないかな。
という作画での驚愕はおいておいて。
内容ですね、イキナリ、ショット・ウェポンのどアップではじまりましたw
くわっ!! みたいな顔で、なんでショットだとわかるかとゆーと、テレビ本編でも特徴的な面白い顔してるからですヤツは。
別なシーンではショット特有の、ヒゲだか傷だかわからん三本線が顔の左右にちゃんとあったし。
星飛雄馬もそうだけど、なんの線でしょうね。
でもってダンバインにはOVAの外伝があり、それは七百年後が舞台だという知識はあったので、すぐにコレかとわかるナレーション。
いやほんと、ビデオレンタル店に並んだ頃に観ておくべきだった。 どうもダイジェスト版というだけで敬遠してしまうので、付録に新作があっても手が伸びないということらしい。
で、観てすぐにわかるのは、ほらほらバイストン・ウェルじゃん、だから登場人物はみーんな転生ってこと。
シオンはショウ・ザマですね、顎にバッテンあるし。 ラバーンはバーン、声優も同じで称号も黒騎士、ズワースに乗ってるし。
で、ミ・フェラリオは・・・コイツ、シルキー・マウ? オーラロードの禁をやぶった罪でミ・フェラリオにされて七百年、まだやってんだw
というわけで七百年後のバイストン・ウェルなんですが、世界観はあまりおもしろくないっつーか、何の説明もない。
機械文明は禁止なので、ないはずなのに地上の船がたくさん廃墟のように転がってるし、意味不明だ。 つまり七百年の間にふたつの世界に何があったのか、解説する気はないようだ。 まあいいか。
にしても七百年後という途方もない時間が、どうも率直に馴染めない。
で、ショット・ウェポンは何をやっとるのか。
それは三話ある最後の方で明らかになるが、どうやらコイツ、不死の呪いをうけている模様。
あーなんか聞いたことある気がするな、バイストン・ウェルに機械文明を持ち込んだ罪で、罰を与えられたって。 どこで聞いたんだっけ、外伝というかバイストン・ウェルを描いた小説、リーンの翼・・・は時間軸が違うんだっけ。 じゃあ違うな。
うーむ、他の作品とごっちゃになってるのか。 何かの罪で不死の呪いって、そんなアニメ他にあったっけ。 うんいくらでもありそうだな。
あるいは、フェラリオのナックルビーがやっぱオーラロードの罪で人間に変えられていたやん、テレビ本編で。 その知識が「ショット・ウェポンも罰をうけたのだ」という妄想みたいな説に直結したのかもしれない。
で、コイツはわりとどーでもいいんだショット・ウェポン。
何やら核爆弾だろうか、オーラロードに落として逆流させて、そしたら自分は地上に戻れるかも知れない、失敗しても不死の呪いから解放されるかも〜みたいな。
ちなみに不死の呪いから解放されたいって話なら、確実に複数あります。 カウボーイビバップにもあったね、そんなキャラが。
で、その核心と言える部分と、全体のストーリーのかみ合わせがあまり潤滑ではないゆーか、ぎこちないゆうか。
つまり当時の、OVAにありがちな感じなんです、脚本や演出がぎこちなくてじゃっかんモタモタしたりするパターン。
逆に90年代に入って、今川版ジャイアントロボが「鼻血出るほどスゲえエエエエエ!!」ってなったのは、話の流れにもたつきがなくて、勢いが止まらない演出だったから。 むろん作画の良さもあるが、作画がいいだけなら過去にもあったことで、ジャイアントロボは別格だった。
で、今回のダンバイン外伝はどうなのかというと・・・ぜんぶ観終わって思うのだが、ストーリーらしいものなかったんじゃないか。
ただオーラバトラー発掘した、動いた、敵を退けた、そんな感じですから。
しかし王蟲方式のオーラバトラーのお披露目としては成功ですね、つかコレで、フィギュアの世界が急速進化した理由がわかった。
当時のモデラーは、こんなん見せられたら再現するしかないじゃないですか、それで技術が発達して腕も磨いたみたいな。
それとも順序が逆で、どっかの酔狂なモデラーがフジツボみたいなスーパーリアル着色のオーラバトラー造って、それに触発されてこんなアニメができたとか?
いろいろ推察はできるけど、まあいづれ詳しい人の記事をネットで探して読んでみたいものです。
あとは・・・ひとつ考えられるのは風の谷のナウシカっぽいことをやってみたかったとか。
七百年後というトホーもない数字や、やたら廃墟化した地上文明のカケラ、そして最後に物語がタペストリー・・・ともちょい違うのかな、絵画のように描かれたりするところとか似ている。 小さなところでは「流砂に落ちる」という場面とかもあるし。
ま、正直こんだけスゲえ細密画のオーラバトラーは行き過ぎだけどさ、こんなふうにいろいろと、ディティールに凝った絵でテレビ版も観たかったですよね、いや当時(テレビ版は82年だっけ)としては立派な作画だったけど、欲を言えばってこと。
そーゆー意味で、バイストン・ウェルを少しでも凝った描写で描けたってだけで価値はある。
あ、もひとつ思い出したが「機甲界ガリアン 鉄の紋章」という、ガリアンのテレビ版とは全く違う話があって。
何か似ているかというと、新訳とでもいうべきリニューアルみたいなガリアンのデザイン、でもって「戦った、勝った」というあっけない話っぷり、最後は勝っただけで特に感想のないジョルディとチュルルのツーショットとか・・・何となくストーリーが付属物で、それより新しい機甲兵のデザインスゲーよな、という作品の存在感が今回みたダンバイン外伝と似ている次第。
いやーでも面白かったよ、OVAは作画さえ良ければ評価する、という月刊OUTとゆーアニメ雑誌にあった皮肉ですが、マジでそんな感じ。 しかしこの作品のオーラバトラー、アレが噂にきくサーバインなのだろうか。
なんとなく食材みたいなネーミングは印象深いんだけどサーバイン。 劇中、名前は出てこなかったな。
というわけで、楽しみました。
●超電磁マシーン ボルテスV
前にもバンダイチャンネルで観たけどもういちど。
たぶん、ちょーど1年ぶりくらいだと思う。
なんか未来ロボ・ダルタニアスみてたら不思議と気になって視聴、みたいな。
もひとつ気になったこととして左近寺博士というキャラがあって、自分が創作したアマチュア小説「白き流星スワンダーACE」で積極的にパクる予定なんで、再確認という意味もある。
だもんで実は左近寺博士が出てくる16話から数話、観る予定だったのが最後まで観てしまい、こんどは1話から見直して今は七話くらいなのかな、そんな感じです。
それにしても、やっぱ面白いわボルテスV。 世間では「長浜ロマンロボット」というシリーズで考えられているけど、コン・バトラーはともかくダイモスと比べても格段に面白いと思っている。
何がスゴイって徹底したバトルドラマ、観ている間だけ右翼になるのが正しい作法ではないかと思えるくらい。
こんだけバトルに特化した子供向けアニメって実はあまりないのではないか。 いやタツノコプロなど、過去にはあったようだけど。
16話から司令官が左近寺博士と言ったが、それまでは浜口博士、でもって基地ビッグファルコンの初代は剛博士、コレがフツーとは逆で、新しい代になるほどキツいんです、特訓で殺す気か!! ってくらい。
普通は前代が鬼で新しいほど柔和となるもんだが。
でもってスゲー気持ちいですね観ていて。
内容的には先述したようにバトルドラマで、劇中ずっとどりゃあああ!と怒鳴ってるような印象。
また主人公の声優さんがいい声なんだコレが。 それは偶然ではなく、たぶんそうなんでしょうね伝統的に。 ちょっと動画サイトでUFOロボ・ダイアポロンのダイジェストをちょい観たけど、あんな凄まじいB級でも同じです、パイロットの叫び声が重要なんです。
前回に観たときにもこのwikiに感想を書いているはずだが、ボルテスVの戦いっぷりもまた気分がいい。
言い方かえるとムチャクチャなんですが、全力バトルであり、毎度まいどコックピットが貫かれる、という酷い見せ場も定着。
殴る蹴るのラッシュや内蔵武器での徹底抗戦、部分的に分離したり天空剣を発射したり、やりたい放題。
そこに先程いった良い声の叫びが重なるわけで。
物語もまたブレずに突っ切ったというか、要は敵キャラにブレがないんですね。
特にプリンス・ハイネルは最後まで角がある人種が貴族という持論を変えないあたり、信頼できるというか。
逆にいうと改心して生き残られても困るんですけどね、非道な侵略に地球市民は怒り狂っていて、許してくれそうにない雰囲気だったし、ボアザン星の奴隷階級も同じこと。 ハイネルが生きてるとまーたボルテスチームが説得に奔走するのか? 話数の無駄だっての。
その話数の無駄を、今アニメでは平気でやるからな〜。
ジャンギャル将軍も敵ながらアッパレゆうか、死亡回まえの予告ではなんか言葉足らずなナレーションで、まるでジャンギャルが素粒子爆弾を使用したみたいになってるw 顔もなかなか凛々しいのだが、ただコイツ太り過ぎやろ、キャラデザインが旧いってことだけど。
ちなみにハイネルの人気はどうも偶然ではないような気がする。 当時、女子に大人気でその後のアニメでも敵の貴公子が当たり前になるほど影響を与えたが、ウィキペディアをみると宝塚を参考にキャラ造形したそうで、それはつまり女子人気を見込んだってことですよ。
なんとなーく宝塚って女学生の憧れみたいなイメージあるやん、夢幻紳士など、昭和をパロディにした作品でそうなってるので、印象操作されてるかもだが。
あとは細かい話。
キャラクターでわかったのは、ヒロインの岡めぐみがまとめ役というか、他が頑固すぎなのか。
岡めぐみも旧いデザインながら、わりと可愛いよね南原ちずるほど有名ではないし、フィギュアもないと思うけど。
何より忍術の達人で有能過ぎるというのもポイント高いし。 白兵戦では無敵とちがうか。
↑いま探したら南原ちずるはあるが岡めぐみはない
逆にボルテスチームの弱点というか、何度も危機に陥る原因となっている日吉は、まあフツーなら要らんキャラですが、じっさいには他のメンバーほどではないが忍術的なこともこなしてメカに強い、なにより水中では無敵だそうな。
ツインテールかよ! 水中ならツインテールはグドンにも勝てるってかw ちなツインテールのかような都市伝説は「ウルトラマンメビウス」でようやっと物語に取り入れられたが、ボルテスVの日吉にはそんな機会ありませんでした、残念。
そしてプロップガンってか、実写ではないので単なるデザインだけど、これまた面白いのがふたつ。
ひとつは皆がもっているらしい光線銃で、未来的なのだがなーんか南部十四年式に見えるという。 南部十四年式はエアーガンもってたので知ってるが、なるへそ軍手など装着した日本人であっても、苦もなく扱える細いグリップですね。 そして軍手で引けるようトリガーガードはでかいという、面白い形をしているわけで。
もーひとつが拳銃の達人とされている健一(字はあってるのだろうか)が使う銃身がふたつあってシリンダーが四角いピストル。
なんじゃそりゃ。 単純に考えると水平二連銃をリボルバーにしたもの、なのだが、意味あんのかという。
しかもそれは、デザインからの考察であって劇中ではなんの説明もない。 水平二連銃が四角いシリンダーリボルバーということは、合計八発ですね、装弾はシリンダー交換でもできる模様。
そもそも水平二連銃のメリットってなんだっけ。
モデルガンもってるのでいちおう構造は知ってるが、単発では心もとないので二連にしただけに思え、だから上下二連でもいいのだが・・・・うん上下二連でいいやん、シリンダーを四角にしなくても、普遍的な六発リボルバーを上下にしてフツーに12発撃てそうなもんだが。
そう考えると二発同時に発射するくらいしかメリットがなさそだが、繰り返すけどそんな解説は劇中、ない。
まーガンダム以前のロボットアニメを深く考察しても無駄なんですけどねー。
スタッフもよく考えていないだろうし。
似たような例として、敵のボアザン星人が繰り出す獣士にも一貫性がなく、思想が見えない。
単なるロボットの場合もあり、カザリンが担当する生物研究所が創り出す巨大化生物つまり怪獣の場合もあるが、それってやっぱりロボット化していて謎だ。 ハイネルやジャンギャルが操縦している場合もあるのだが、わりと多いのが志願兵のサイボーグ。
あいや、その素性もそうだが、デザインにテーマが見えないので、普遍的な悪いロボットのイメージなのだろう。
ま、ボアザン星人の母艦であるスカールークは名デザインですね、なんかスーパーロボット系の敵母艦として、代表例にしておきたいくらい。 ちなみについ最近までスカイルークだと思っていたが、第一話でシッカリとテロップ出てますなスカールークって。
ちな製作年が1977と、スター・ウォーズと同じ年、ガンダムの前年ってことで、要はロボットアニメも完成度高くなってきた頃だろうか、まあ作画が雑と言ってもボルテスVはけっこー凝ってる方かも知れない、バンクゆうて繰り返し使う絵も多いが、毎回わりと新規に描いていて、必殺技である天空剣も放った数だけバリエーションがあり、例えば戦隊ロボやコン・バトラーVに比べてもシッカリしているみたいな。
怪傑ズバットもこの辺ですよね、時代的に。
いろんなヒーロー、ロボットが登場して市場が飽和状態なところに、気合の入った企画が登場みたいなことだと思う。
とにかくボルテスV、子供の頃に好きだったので今現在、配信のバンダイチャンネルでみると「がっかりするかも」オモたら、逆に「もっていたよりスゲえええええ!」となって嬉しい次第。
という感想。
 ●2019.1.27 日記
●2019.1.27 日記いやー書くこといっぱいあるんだけどね、ひまなくて。
それにしても、Vue2016の件は惜しかったですね、二万円ほど奮発していれば間に合ったのに。
ゆうても希望を捨ててはいません、まづどこかのショップで物理パッケージが残ってるかもだし、また日本語版はいまんとこアナウンスがないんだけど、本家のVueに関して言えば、アレうまくいくはずないんです。
月額19ドルからのクリエイティブクラウドプラン、しかも知らない他のグラフィックソフトと抱合せコース、なんじゃそりゃ、と翻訳で読んでいる素人の自分でも思う。
いづれ改善策が発表されなくてはならない、という感じ。
理想は日本の代理店からの要請で、単独パッケージ版・・ダウンロードのみでもいいんだけど、復活というパターン。
あとはShade3Dだけど、こっちはわりと比較的、敷居が低いゆうか、一万円ほどだし、気持ち次第で買えるみたいな。
中古に関しても、Vueに比べりゃ入手しやすい部類。
ただ、不便はあってもversion11が「使えてしまう」ため、踏ん切りつかんだけ。
あとは・・・先述したように書くこといっぱいあるけど、MacOSをたいした意味もなく1個上のSierraにした件。
ホント意味はないんです、ただMacOSは少しでも新しいほうがいいやん気分的に。そんな感じで、でもHighSierraはトラブった実績があり、いまんとこShade3DもVue6も十年以上前のソフトなんで、現実には少しでも古いほうが確実に動く。
そんな気分と現実の間で揺れていて、ふと気分の方に傾いただけ。
MacOS10.12。 コレがいまんとこ自分の限界です。
ソフトの問題を解決しないと次の時代に進めません。
それと、動画の件も記しておくか。
まーホント、何度も書いたけどこりゃーたいへんですね。
編集しながら矢継ぎ早にイラストを描く、そりゃあたいへんです、はい。
じっさい今、27日なのでまあ2月中にだって無理でしょうね、手がけている第三話は。
それでも少しずつ、確実に進んでいて、一時間二十分ほどの作品となるんだけど、ようやっと三十分超えたのが一週間くらい前だっけ? なんかやればできるもんだなという、いつもの感想。
どちらかというと完成したときよりも、最初は無理! と思っていたのがだんだん手応えを掴んでゆく、その過程のほうが嬉しいですね。
このたぐいはハッキリ覚えているんだけど、十年以上前のボカロ動画ではじめて経験したんだっけ。 ホント最初はマジ無理オモタ。
むろん映画のような出来栄えはやっぱり「無理」なんだけど、自分なりの立ち位置を見つけ出すのも甲斐がある。
あーそうそう、動画の件といや、不具合が発生してますね。
ファイル書き出ししようとしたとたん、iMovieがオチるという、何度も繰り返したけど改善せず、しかしMacOSを更新したのが原因なのかコレ。
他社製の古い製品ならともかく、iMovieでそんな不具合はおかしいですね。
いづれなんとかなるのかな。
ファイル書き出しできんと動画が完成しないんですけど。
という日記。
 ●2019.1.29 iMovieの不具合
●2019.1.29 iMovieの不具合治らんですね再起動ていどじゃ。
どんな不具合かというと、メニューのファイル→共有→ファイル..という部分で、つまり動画を書き出すってことです。 それやったら即、落ちる。
何度やってもすぐ落ちる。
これじゃー動画が完成しないやん。
ちなみに落ちるだけで他には問題ない様子。 データが壊れるとかないなら安心なのだが。
MacOSをSierraにしたせいなのか? まあ困りますな。
しかしじゃあ、Youtubeに投稿みたいなメニューはどうよとテストしたら、こちらはできた。
小さなサイズで投稿テストで、書き出して編集できないから後半の絵ができていない部分は真っ黒なままですが↓
他にもよくシャットダウンするんですSierra。
たぶんセキュリティのためだと思うんだけどね、挙動不審な外部からのアクセスがあったらとりあえず機能停止みたいな。
自分が開発者で、難しくて的確な対処法が思い浮かばなかったばあいそうする。
それは我慢するとして、iMovieが書き出せないなんて根本的なトラブルはやはり困る。
いちどシステム丸ごとTimeMachineバックアップから復元とか試すか・・・などと考え中です。
起動ディスクがすでに三百ギガに達して、めんどいのですが。
という近況。
 ●2019.1.30 バンダイチャンネル
●2019.1.30 バンダイチャンネルHULUをいったん切って、じゃあ貯まりすぎたテレビ録画を消化しようかというところでバンダイチャンネル。
なぜかというと、どーしても蒼き流星SPTレイズナーを観たくなったため。
他にもいろいろあって、超電磁ロボ コン・バトラーVも途中だったよな、予想より面白かったのでぜひ続き観たいし。
レイズナーも第一話は無料なので二度ほど観たが、第二話をみるといろいろ再発見がありますな。
例えばエイジとゲイル先輩のバトル。 ゲイル先輩がドッグファイトでムッチャ強いのは覚えていたが、じっさいゲリラ戦となるとエイジのほうがはるかに強いんだな、これは忘れていた・・・。 だから火星の地上戦で、エイジを取り逃がしたっていうわけで。
他にも時間つぶし的に、作業しながら観れるもんないかと鉄腕アトム白黒版をみたら、想像以上に面白かったりする。
あーゆうてもかなり最初の火星探検の話で、後に映画にもなったし別作家で何らかのマンガ化もされたという、有名エピソードなんだけど、それにしても力が入っている。 冒頭の語り口からもう絵の方にアイデア詰めまくりで、作画もケッコーすげえので心配してしまう。
そんなに張り切って、息が続くのか? という心配だが、これはじっさい杞憂ではないわけで。
鉄腕アトム後半は知らんが、ジャングル大帝では確かに、話が進むとスタッフの忙殺ぶりが絵に見えてきました。
そもそもコレは現在でも言えることなんだけど、テレビアニメという発想自体がムリがある。 毎週放送? 過労死するぞ、という。
今は長期アニメなんて減ったし、アニメ制作そのものもシステムが完成されてきたが、それでもムリを感じる。
そんな手塚治虫の暴走ぶり(たぶんテレビでアニメというのは手塚先生の発案)に、翻弄される人々を描いたマンガもあるそうですな、岡田斗司夫Youtube番組で紹介していた。 タイトルわすれたけど。
そのマンガの内容を一言で語ると、とんでもないムチャな企画しても、原作とプロデューサーが手塚治虫であり、しかもイチバン働いているのが当人なので、誰も文句が言えないそうな。 困ったもんです。
とまあテレビアニメ黎明期のことを想って。
他にも機甲戦記ドラグナーも続き観はじめて、さっそく三本視聴したわけです。
鉄腕アトムは1950年代なのかな? そっからわずか三十年後くらいですかねレイズナーとドラグナーは。
スゴい進歩したもんですが、そっからさらに三十年後の今に至るのは、映像技術の進歩くらいでしょうか。 あいや革新的な作品もあったかもだけど、やっぱ作画や映像の進歩が目立つ。
というアニメの歴史を考える機会を得たわけです思いがけず。
でもって貯まったテレビ録画ですか、これはしばし放置ですな。
ゲゲゲの鬼太郎を二本、未視聴で置いてあります。 重神機パンドーラとバナナフィッシュも途中までだし。
ま、仕方ないですな、レイズナーは急いで観たいので。
という雑談。
 ●2019.1.31 もどした
●2019.1.31 もどしたMacOSをいったん10.12Sierraにしたけど10.11El Capitanにもどした。
いやー2年前はSierraで作業していたと思うんだけどね、こんな不安定バージョンだったっけ。
El Capitanにしても、たまーに長期スリープで回帰失敗とかあるけど、こんな毎日はトラブらないので、わりと安定版。
なんつても、たいがいのことは、ちょい古いOSでも不自由ないので、こんなときは戻すに限る。
で、方法論だけど、何もかもTimeMachineバックアップで簡単にできました。
これは意外というか、記憶と違うというか・・・・。
TimeMachineバックアップってバージョンが違うとなーんもできないと思っていたんですけどね。
SierraからEl Capitanにもどすにも「古いバージョンは復元できません」とか言われるかと。
じっさいにはまったく無問題で、まあバージョンごとの相性とかあるのかもしれない。
またSierraで作業したぶんのデータをほじくり出すのもEl CapitanでフツーにTimeMachine復元できて。
これまた「新しいOSのデータは開けません」とか言われるかと思った。
そんなわけで、バンダイチャンネルでレイズナー観ている間に、ダウングレード完了という次第。
うーんしかし、SierraとHigh Sierraはけっこう見た目のデザインは気に入っているんですけどね、こうも落ちるんじゃ使えない。
最新のモハーベ砂漠はどうなんでしょうね。
↑モハーベ砂漠といやパラサイト・イヴ2
なんであれ、なかなか便利になりましたねMacOSも。
レストアは何十回もやってるが、以前はこーはいかず、クリーンインストールがいちばん手っ取り早かった。
つまりデータは別ディスクに保存するスタイルで。
あとはこのwikiの文章も、テキストエディタでひと月分くらい書き溜めているんですが、こちらはDropboxで復元前の状態になるんで、これまた非常に楽です、はい。
いま復元したiMovieみたけど、ちゃんと最後に編集した状態になってるのを確認、つか新しいバージョンで編集したデータを、やっぱりフツーに読み込んでいるのはたいしたもんだ。
あと書き出しで即オチることもないし、まあ安心安心。
しばらくは10.11El Capitanで行くしかないですね、何度も語ってるけど、新しいiMac買う金ないし、ソレ以前にShade3DとVueを新しくしないと今のOSに対応できないし。
という話。
●余談
ダークモードをいくつかやめました。
まんづEl Capitanにも搭載されている上部メニューバーの反転、たまには焼付き防止にいいかもだが、基本見にくい。
あとはYoutubeのページ、ダークテーマとかもやっぱ見やすいとは言い難くやめちゃった。
Google Chromeのダークテーマはまあいい感じなのでそのままに。
要するにMacOSモハーベの、本格的なダークモードと違い、反転しただけとか黒くしただけとか、そーゆーダークモードじゃダメなんですね。
モハーベ砂漠OS以前の反転メニューとか真っ黒になって逆にどぎついやん。
いい感じにグレーがかったダークモードでないと。 あとはFinderのパーツとかグレーになるわけでもないし疑似ダークモードは。
ダークモードがダメとは思いませんね、先述したようにGoogle Chromeのは真っ黒ではなくいい感じに暗いので悪くないし、他にもiMovieだってわりと以前から黒いけど使いにくくはない。
将来、新しいOSでダークモードをもーいっぺん試してみて、たぶんその時は気にいると思うよ。
そーいやShade3Dのバージョン17体験版もけっこー黒かった気がする。 Shade3Dは確か設定で選べたよな、今は黒がデフォなのか。
この分野、もう二十年前から暗いグレーが普通であって、Shade3Dは白い方だったものです。
グラフィックソフト系が暗いのは理由があるんでしょうね。
それをうけて世間のOSやサイトがダークテーマを採用しはじめたのではないかと想像している。
というわけ。
 ●2019.2.6 やっときたとおもったら
●2019.2.6 やっときたとおもったらえーVue3Dの話です。
Vue2016はマジ惜しいことしましたね〜下位バージョンが二万円まで値下がって、でもすぐに販売停止。
パッケージ版がどこかのショップに残ってないですかね。 電話で聞いてみようかな。
海外の本家サイトでは、すでにクリエイティブクラウド版が登場していたけど、イーフロンティア日本の販売はしばしなかったわけで。
それが、今日ちらっとみたらやっときた次第。
しかしやっときた、と思ったら・・・やっぱ本家と同じ、クリエイティブクラウド版でした。
年間二万円からのプラン、たけえよ。
なぜそんなに高いかというと、プラントファクトリーが付属するからで、なんのこっちゃとYoutubeで調べたら、植生作成ソフトでした。
まあ欲しいっちゃ欲しいね、気に入った林や、あとは茂みを作りたいので。
Vueとプラントファクトリーが抱き合わせということは、相互にデータの入出力ができるのは間違いない。
だが、自分が使うVue6Easelから十年以上、今のVueならデフォルトのプリセットでなーんの不満もないのではないだろうか。
うーん、どー考えても高いよね。
ひとつ、考えているのだが、Vueの他にもShade3Dも更新しないとあかんわけで、こちらはたぶん2010年ごろのバージョン。
Shade3Dも、入出力が少しはパワーアップしている可能性。
ということは、Vueやプラントファクトリーで作成した地形や植生を取り置きしておいて、Shade3Dで使えないか。
それができれば、とりま一年間だけクリエイティブクラウド課金して、あとは作り置きパーツをShade3Dでレンダリング、とか。
かように、いろいろ考えてしまう。
本家がどこの国か知らんけど、日本のユーザはCC好きじゃないと思うんですよ国民性として。
だから日本だけでもパッケージ版を復活して欲しいが、まあどうなるやら。
本家は月額プランもあって、でも19ドルだっけ、やはり割高であり、世界中のユーザが不満だと思うだけど。
だいたい、所有して二年くらいしないと、身につかないと思うんですよ3DCGソフトというものは。 オペレートするだけならすぐに習得もできようが、それで自在に創作できるようになるまでけっこーかかる。
アドビもCCばっかだし、そーゆー風潮なんとかならんのかと。
グダグダ書いていると長くなるので今回はこのへんで。
 ●2019.2.7 参加したいが
●2019.2.7 参加したいがえー何度か書いたけど、動画忙しいっす。
編集しながら、該当する絵を矢継ぎ早に作成ってことで、たいへんっす。
いっぽうpixivなんだけど、絵のソーシャルとゆうサイトで、つまり描く人といいねボタンで支援する人、という場所です。
なんか最近、他のところと同じようにお金を支援、というシステムもできましたが、さすがにコレは利用してません。 ここ数年はYoutubeやニコニコ動画の無料放送を追っかけるのに必死で、pixivは二ヶ月とか投稿しないこともあったりして、まあ気ままにやらせてくれ、ということです。
ついでにいうとpixivを完全に信用したわけでもないんで、ここに個人情報入力したくないし。
要はpixivでムリはしたくないってことで。
でもって投稿者には見えるんだけど、サイトの左に「今日のお題」みたいなものがありますね、創作アイデアなんだけど。
ちな今日は魔法使いか・・・他にも笑顔とかおなかとか、日替わりなんだけど、そんなタグつけないよフツーというお題がいっぱい。
まあコレもつまり、ソーシャルです。 だから今日のお題という作品もけっこう投稿されています。
そんなムリしてソーシャルしなくても・・思うけど、まあいいシステムかもしれない。
出会いたがっている者はいっぱいいるからな。
そんな中、pixivファンタジーみたいな企画が出ました。
ファンタジー大陸か島の、勢力図は投稿数で決まるらしい、なかなか面白そうな企画なんだけど。
いやー参加したいんだけどね、先述したように忙しくてムリw
こーゆーこと、ピアプロ時代にやりたかったなあ・・・自分がやれば良さげなものだが、そんなリーダーシップも企画力もないんでやらんかったが。
つか具体的なアイデアが出そうにないし。
考えてみると気まますぎて、ソーシャルらしいことやっとりませんねこの十年間。
ま、いっか。
ところでじっさい、pixivのファンタジーは具体的にどんなことをするのだろう。
絵を描くにも、元ネタがわからんと手がつけられないのだが。
これもま、いっか。 そーゆーのは時間が経つとわかるかもしれんし、わからんかったら縁がないってことで。
という話。
 ●2019.2.14 物流の進歩
●2019.2.14 物流の進歩なーんかある日、ふと思うたのじゃが。
どこかの何かで、物流革命って文字が目に入ったのがキッカケだっけ。
おそらくそれで、反射的に「物流に革命なんかあるかいな」と考えた次第。
ここ数年はYoutubeの「茂木世界史」略してもぎせかで、繰り返し歴史を耳に入れていて、ラジオ代わりというよりほぼBGM。
親切な誰かがプレイリスト作成してくれているんで、ソレをひとりで何十回、もしかすると百回は繰り返しているかも。 なんせBGMですから。
それでも歴史のディティールはさっぱり覚えないのだが、流れはかなりわかってきたゆうか、二度三度きくだけで身につく。
物流の歴史も同じことで、世界史に何気なーく含まれとるんで、革命などないだろうと想像されるわけ。
だって紀元前から、地中海ではフェニキア人が船で往来して商売してたやん、その頃から現在までってことよ、革命なんかあったか?
革命の定義がわからんが、段階を一足とびでないと革命とは言えないと思う。
フランス革命はラファイエットが用意した順当な段階をすっとばして、ロベスピエールらが時代を急いだのでそう呼べるわけで。
で、物流ね。
時代ごとに船は大きくなり、スピードもアップ。
でもそれってけっきょく順当な進化やん。
そして、物資を目的地に運ぶという命題に変化はないわけだし。
あえて言うなら情報伝達としての電話と、急激なスピードアップの飛行機というものがあるけど、繰り返すが電話発注があっても仕事はかわらんし、まあ安心感と確実性が上がっただけ、飛行機は速いけど量は船にかなわず、あくまでもオプション扱いではないか。
近所の百円均一で売られているバナナは、相変わらず船で運ばれているはず。
むろん冷凍輸送やらインターネットやら、同じことでオプション増えただけ。
だいたいインターネットは電話の一種と考えるべき。
つーわけで。
やっぱり順当進化じゃねえの、今の物流は。
物流革命なんてあるのだろうか、という疑問は、考えただけではわからず。
つかやっぱ、革命の定義がわからんとどうしようもないので、ヒマがあったら今後調べます。
ただ、たいした努力もしていない企業ほど物流革命とか言い出しそうな、そんな根拠のない先入観は確かにあります。
という余談。
 ●2019.2.16 予算くるしい
●2019.2.16 予算くるしいえっと、通常に比べりゃあ、とてつもない格安で創作しているんですが。
それでも予算くるしいと思えてきた今日このごろ。
急務とされるShade3DとVue3Dの更新もそうだけど、まあ当面、必要になってくるのはストレージ。
起動用に外付けのSSD500ギガを使用して、こっちはやりくりするとして、バックアップ用の500ギガが残り150ギガだってさ。
説明すると、最近では旧い外付けハードディスクが格安で買えるが、もう外部電源な装置はなるべくやめよう、と思っていて。
だから外付けハードディスクは基本、バスパワーとなります。 まーそれでも安いんですけどね、五千円あれば500ギガくらい中古と新品ケースの組み合わせできるから。 しかし心もとないってことは、1ギガとか必要っぽいってわけでして。
そして、今後はなるべくSSDにしようという考えもあり。
つまり外付けのバックアップは可能なら「バスパワーSSDで1ギガ以上」となり。 そうなるとちょい高価いかも。
でもって、なんでそんなに容量食うのかというと、製作している動画の絵をみていたらわかった。
読み上げボイスと静止画であり、これでも他の創作に比べるとスゲえ格安なんですけどね、イラスト一枚でけっこー使う。

↑ほんの一瞬でてくる、スゲーくだらねえ一枚。
ヴァルヴレイヴを視聴しはじめたところで、さっそくパロディやらかしたわけですが。
ポスター素材は3.8メガですんだけど、壁を簡単にモデリングしてレタッチして絵になったら、なぜかフォトショップデータは72メガになりました〜デカいな、こんな寒いギャグごときに。
つまり他の絵もそんな感じで、さすがに通常の動画より小さいのだろうが、それでもけっこーデカいデータになりました。
十年前くらいから、なぜかShade3Dのデータも100ギガ超えとか出るようになって、アマチュア3D創作のばあい(自分だけかもだが)テクスチャを小さくした上に徹底して重複させるものなので、100ギガ超えはおかしい。 どうもある時期から、Shade3Dのデータ整頓が下手になったようで・・・たぶんスピードを確保するためなのだろう。
あ、モデルデータはそんなにデカくないと思うよ、iMacG3-223Mhzでやってたころも20メガ超えあったりしたけど、まー仮にそれから十倍のモデリングできるようになったとしても、やっぱり色なしデータは小さいと思う。
ま、今の感じだと今後一年はもちますけどね、それからどうするって話。
だいたい自分の創作は4k時代に対応せず、HDを念頭にやっているわけで、作品サイズはこれから巨大になるのは明らか。
いっぽうアップル社は、値段高い高速SSDを採用しはじめましたね、製品の価値を高くして価格下落を防ぐ、というわけではなく、おそらくは電力抑えたまま性能アップするのにCPUやGPUでは足りずに、SSDの高速化でなんとかしようという考えだと思う。
つまり今後はMacを新しくしても容量不足にさいなまれる可能性。
ただ、あまり悩んではいません。
とりま高速SSDではない、従来の製品はだいぶん安くなってきてるから。 いづれ1ギガもSSDも値下がりするのでは。
↑1万7千円切ってきた〜、もうちょい下がれば手が届くっ
そこは様子見であって、こーゆーIT機器で先を悩んでもしょーがないんです、静観するほうがいい。
またいざとなれば、もー中古の外部電源な外付けを買って急場しのぎでしょうね、コンセントややこしいので減らしたいが仕方ない。
つか手元にいくつか余っていてるし。
とまあそんな近況。
 ●2019.2.19 動画できた
●2019.2.19 動画できたなんかまあ、気がついたらできてました。
予定なんてないんだけど、まあ2月末までかかるかな、と思っていたんでわりと速いかも。
最後の方は、けっこー必要な絵が多くて、例えば壁にかかっている放送用スピーカーなどもモデリングしたんだけど、さすがに手慣れているんでスピーディーに片付いたわけで。
あとは会話シーンなどは喋っているキャラの絵を繰り返し映すだけなので、あと五分以上あると思っていた残りをけっこうさばいたみたいな。
で、今はYoutubeにアップロード中です。4.4ギガあったんで十時間以上かかったのかな。
完了すれば、以下のURLでみれるはづ。
https://youtu.be/HxDocU_yCqk
アップロードに関して言えば、まあ8メガADSLなんでそんな時間です。
だったらじゃあ、動画のサイズを小さくすれば・・・思ったんだけど、これが難しかった今回。
まずiMovieのデフォルト機能で書き出すけど、品質高くしたら80ギガ以上に。 ふざけんな、そんなもの起動ディスクにも保存ディスクにも置いておけないっつーか、アップロードに何日もかかるやん。
で、ならばそこからQuickTime書き出しを試すが、あまり小さくはならず。
さらにオプションをいじって小さくしようとしたら、部分でエラーした。 動きが壊れて巨大なブロックノイズだったり止まったりして。
五回くらい試したのかな、けっきょく最後はiMovieでフツーに書き出し。 とにかく品質落とすだけ、みたいな。
それが4.4ギガ以上というわけですはい。
いやーそれにしても、白き流星スワンダーACEの第三話、膨大な作業量でした。
でもって、いまは第一部の最後となる第四話を改めているんですが、どうも第三話が一番長かったらしい。 またロボットバトル、宇宙戦艦バトル、ロボと宇宙戦艦のバトルと、むちゃくちゃ込み入った内容で、そらたいへんですわ。
まあ静止画メインだからまだ良かったんだろうね、フツーにアニメーションとか個人じゃムリっぽい。 数分間のPVが精一杯でしょう。
それはともかく。
次の第四話は、もすこしアニメーション増やしたいですね、静止画ばかりじゃ画面が退屈だし。
でもって、広告はまったくないというか、広報活動してないんで、第一話の再生数は相変わらず32とかです。
いいんだけど、せっかくなんだし、少しは観てもらいたいもの。
ゆうてもソーシャルなどで宣伝する予定はないんですが、とりまサンプル動画を作ろうかと考え中。
数分間の寸劇で、読み上げボイスと静止画でこんな雰囲気の動画になります、という説明。 これをニコニコ動画なりYoutubeにのっけて、第一話のリンクをつけときゃいいか、みたいな。
とまあ、そんな近況でした。
長くなってきたので次に移動
次はabout-19.4となります。