�������쥯������������åפ�����
�����쥯������������åס�Otto Emmerich Alexander Kapp�ˤ�1800ǯ1��28�������ߤΥХ���������С��ե�������λ��֤��ļ�Į�롼�ȥ����ҥ����奿�åȡ�Ludwigsstadt�ˤǡ�����ˡ�����ؤ��Johann C.W. KAPP��8���ܤλҤɤ�Ȥ������ޤ줿���ľ������Dzᤴ�����Τ��������餯�����ϰ���濴�ԻԤǤ��ä��Х������ȤΥ���ʥ�����dzؤ����ؤ˿ʤߡ�20������ǥץ��ȥ�ζ������˴ؤ�����ʸ�����ι�����������1821ǯ�˴��Ԥ�������Ǥθ����ˡ�ů����ΡפȤʤäƤ���ˡ�
�����θ塢�٤��Ȥ�1828ǯ�ޤǤˤϡ�������Ĺ��̳���������ȥե������Minden�ԤΥ���ʥ�����ξ��ʶ����Ȥʤä����������θ������ʤäƤ���ˡ�
��������1832ǯ�ˤ�Ʊ���������ȻԤΥ���ҡ�����ʥ������Archigymnasium�� �μ��ʶ����Ȥʤꡢ������ǯandoragogik��ǰ�������ظĿͶ���ؤ���ӹ�ȶ���ؤȤ��ƤΥץ�ȥ�ζ����������μ���ů�ء٤�������Ƥ��롣�����ˤ�1854ǯ�ޤǶ�̳���ơ�����ȸ���˽���������
��54�Фǿ������Τϡ�5���̿ή�����ȿưŪ���Ϥη�̤ȹͤ����Ƥ��롣��ϳ�̿�����ˤϲä��ʤ��ä�������̿�ؤζ�����������뤳�Ȥ��ߤ�ʤ��ä��Ȥ�������ϥ������Υ��塼��åҤ�˴̿Ū�ʰܽ���Ԥ���������61ǯ����ٳ��Υե�ǥ���Flundern���϶�˻ҽ��ع���T���chterinstitut�ˤȤ������鵡�ؤ��ߤ������Ĥˤ����ä���63ǯ�ˤϤ��ζ�٤Υ����������Witikon��¼�ʸ��ߤϥ��塼��åһԤ������ˤǥ�������̱����������Ƶ�������69ǯ10��9���˥ե�ǥ��ǻ�����72ǯ�˻�����Ottilie (von) Rappard�Ȥδ֤�4�ͤλҶ���Agnes, Caecilie, Marie, Otto�ˤ��٤��Ƥ��롣
- �ʣ���1534ǯ����Ω���졢1543ǯ�ˤϽ������״�����ɽŪ��ʸ����ԥ���ҥȥ��Ĺ�˾��ۤ����Ȥ��������Τ��륮��ʥ����ࡣ
�ʣ��˰ʾ�˴ؤ��Ƥϥ롼�ȥ����ҥ����奿�åȤ��ϰ�˸���ԡ�Stadtarchivar��Siegfried Scheidig�ᤫ�����Ƥ�������������˴�Ť��Ƶ��Ҥ�����

�����쥯������������åס�Otto Emmerich Alexander Kapp�ˤ�1800ǯ1��28�������ߤΥХ���������С��ե�������λ��֤��ļ�Į�롼�ȥ����ҥ����奿�åȡ�Ludwigsstadt�ˤǡ�����ˡ�����ؤ��Johann C.W. KAPP��8���ܤλҤɤ�Ȥ������ޤ줿���ľ������Dzᤴ�����Τ��������餯�����ϰ���濴�ԻԤǤ��ä��Х������ȤΥ���ʥ�����dzؤ����ؤ˿ʤߡ�20������ǥץ��ȥ�ζ������˴ؤ�����ʸ�����ι�����������1821ǯ�˴��Ԥ�������Ǥθ����ˡ�ů����ΡפȤʤäƤ���ˡ�
�����θ塢�٤��Ȥ�1828ǯ�ޤǤˤϡ�������Ĺ��̳���������ȥե������Minden�ԤΥ���ʥ�����ξ��ʶ����Ȥʤä����������θ������ʤäƤ���ˡ�
��������1832ǯ�ˤ�Ʊ���������ȻԤΥ���ҡ�����ʥ������Archigymnasium�� �μ��ʶ����Ȥʤꡢ������ǯandoragogik��ǰ�������ظĿͶ���ؤ���ӹ�ȶ���ؤȤ��ƤΥץ�ȥ�ζ����������μ���ů�ء٤�������Ƥ��롣�����ˤ�1854ǯ�ޤǶ�̳���ơ�����ȸ���˽���������
��54�Фǿ������Τϡ�5���̿ή�����ȿưŪ���Ϥη�̤ȹͤ����Ƥ��롣��ϳ�̿�����ˤϲä��ʤ��ä�������̿�ؤζ�����������뤳�Ȥ��ߤ�ʤ��ä��Ȥ�������ϥ������Υ��塼��åҤ�˴̿Ū�ʰܽ���Ԥ���������61ǯ����ٳ��Υե�ǥ���Flundern���϶�˻ҽ��ع���T���chterinstitut�ˤȤ������鵡�ؤ��ߤ������Ĥˤ����ä���63ǯ�ˤϤ��ζ�٤Υ����������Witikon��¼�ʸ��ߤϥ��塼��åһԤ������ˤǥ�������̱����������Ƶ�������69ǯ10��9���˥ե�ǥ��ǻ�����72ǯ�˻�����Ottilie (von) Rappard�Ȥδ֤�4�ͤλҶ���Agnes, Caecilie, Marie, Otto�ˤ��٤��Ƥ��롣
- �ʣ���1534ǯ����Ω���졢1543ǯ�ˤϽ������״�����ɽŪ��ʸ����ԥ���ҥȥ��Ĺ�˾��ۤ����Ȥ��������Τ��륮��ʥ����ࡣ
�ʣ��˰ʾ�˴ؤ��Ƥϥ롼�ȥ����ҥ����奿�åȤ��ϰ�˸���ԡ�Stadtarchivar��Siegfried Scheidig�ᤫ�����Ƥ�������������˴�Ť��Ƶ��Ҥ�����

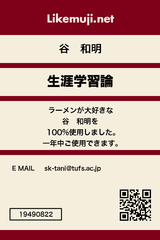

�����Ȥ�