島根大学教授の吉村哲彦氏が自分のtwitterで以下のような暴言をおこない、それが反響を呼んでいるらしい。
吉村氏の発言は(http://matome.naver.jp/odai/2129577175452365001)によると以下のようなものである。
生涯学習という名の老人や主婦の暇つぶしのために税金が使われることが問題なだけ。勉強したい人は好きなだけご自由にやって欲しい。ただ、世間が生涯学習(暇つぶし)の機会を大学に求めると、我々は雑用を抱え込むことになる。そして、本来すべきことが疎かになる
若いときに勉強してない人が年を取ってから勉強を始めても暇つぶしにしかならない。ゆえに、生涯学習という名の下に税金を投入することに意義はない。若いときに運動してない人は、年をとってからの体力低下が著しく、回復はもはや手遅れ。勉強と運動は若いときの蓄えが問われる点で共通。
これに対し、小山彰宏という人が「人類応援ブログ」(http://blog.livedoor.jp/ganbare_zinrui/archives/15...)というところで、以下のように批判している。
2014年10月24日
生涯学習の公共的意義について
島根大学の吉村哲彦教授による「生涯学習なんて無意味だと思う。」という発言が波紋を呼んでいます。
氏の主張は
若いときに勉強してない人が年を取ってから勉強を始めても暇つぶしにしかならない。ゆえに、生涯学習という名の下に税金を投入することに意義はない。
というもので、大学教員のような高度専門知識人になるには、早い段階からの学習が必要であり、高度専門知識人を育てられない生涯学習に税金を投入する意味は無い、というもののようです。
ネットでは
「確かに税金を使う必要はないかもしれない」
「学問をなんだと思ってるんだ」
などなど賛否両論。喧々諤々の議論が行われています。
それらの様を見て自分が思ったのは「生涯学習の公共的意義があまり共有されていないな」
ということです。
賛成派も否定派も、間違った前提で議論を組み立てているように思えます。生涯学習の本当の意義は、高度専門知識人を育てることでも、趣味としての自己実現を助けるためでも、どちらでもありません。
自分もある意味でフリースクールの主催者という「生涯学習」の担い手です。
生涯学習の公共的意義について、当事者がどう考えているのか、少しお話させて頂ければと思います。
【生涯学習の意義その1】
■幅広い層の知的労働者を育てる
地域のカルチャーセンターや放送大学などの「生涯学習」を受け持つ施設、ここにはどんな層の生徒が来ているか、みなさんご存知でしょうか。
吉村氏の言ではほぼ全ての参加者が後期高齢者、というような書き方をされていましたが、実態は全く異なります。
例えば30代、40代の働き盛りのサラリーマンや、10代で働きながら学位取得を目指す人など、実際は「老後の趣味」のような方以外にも幅広い層の生徒が参加しています。
特にサラリーマン組の参加者は目的意識が明確です。
例えば海外赴任が急に決まったサラリーマンが外国語を学びに来たり、現役の警察官や自衛官が幹部候補生試験を受けるために学位を取りに来たり、転職のために必要な資格を取るために必要な講座を取りに来たり、と「仕事に必要な技術を得るため」に生涯学習施設に通う方が多くいらっしゃいます。
実際に僕のフリースクールにも、アフリカへの赴任を前にした方が英語を学びに来ていますし、プログラマーの方が数学を学びに来たりもしています。
大学職員のように本当に高度な専門知識を要する仕事以外にも、世の中には様々な職業があります。そして、それら様々な職業でも、大学職員と同じように知識と技術が求められています。
放送大学などの生涯学習校は、そんな知識と技術を求める労働者に対し、安価で良質な教育機会を提供しています。
もし生涯学習のための施設が存在しなかったらどうなるでしょうか。
私大の夜間部や専門学校などの高額な学費が必要な施設でしか、労働者は仕事に必要な知識を学べなくなってしまいます。その結果何が起こるかといえば、労働者の学習機会の二極化です。
大企業正社員のみが転職・キャリアアップのための機会を得て、その他の大多数の労働者は一生今の仕事を続けざるを得ないような社会。そんな世界が待っています。
幅広い階層の労働者に教育の機会(つまりキャリアアップの機会)を与えるという意味でも、生涯学習には公共的意義が存在します。
【生涯学習の意義その2】
■質の良い有権者を育てる
「質の良い有権者」、つまり各種の学問に通じ、それらに対し理解のある有権者を育てることも生涯学習が持つ重要な役割です。
僕の知る限り、「人文系学部の廃止」や「大学の就職予備校化」のような、反知性主義的な政策に対して最も強く反対の声を上げているのが放送大学やカルチャーセンターの学生たちです。
彼らは学問に対しての人一倍強い想いがあります。その価値を正しく認め、社会全体で育んでいくべきだという考えを持った人たちです。それは「趣味で」勉強している人でも全く変わりません。
つい最近もこんな報道がありました。
国立大学から文系学部が消える!安倍首相と文科省の文化破壊的“大学改革“
現在文部科学省では国公立大学の人文系学部を廃止し、職業教育「のみ」を推進するような大学のあり方を作ろうとしています。
なぜこんな愚かな政策が推進されているかと言えば、政治の担い手である有権者に「反知性主義」的な考え方が広く広まってしまったからでしょう。
自分の理解できないものは必要ない、金儲けに役に立たないものは必要ない、そんな浅薄で目先のことしか考えない考え方が、教育行政にまで根を伸ばしつつあります。
高度専門知識人である大学教授が生きていくためには、大学の存続が必要です。そして大学の存続には、政府による補助金が必要です。そして政府による補助金を確保するためには、大学教育に理解のある有権者が必要なのです。
もし放送大学やカルチャーセンターの学生のような、各種の「学問」に対して理解のある有権者がこの国からいなくなれば、大学のあり方は今とは全く異なってくるでしょう。
そうなってしまえば、失礼ながら吉村教授が奉職されている島根大学などは恐らく10年以内に取り潰されると思います。島根大学だけでなく、全国の地方国立大学、低偏差値の私立大学、それらは全て潰されるか縮小され、旧帝国大学と早慶上智のような一部名門私立大学のみが生き残るような状況になるでしょう。
そんな核戦争後の人類社会のような荒廃を大学にもたらさないためにも、学術に理解ある有権者を育てること、それらを育てるゆりかごたる生涯学習を保持し続けることは学術の未来にとっても必要なのです。
【生涯学習の意義その3】
■「権利」としての学びを保持する
人類史を通して「学術が一部の特権的エリートに独占された時代」というのは数多くの例があります。そのいずれもが、暗い色彩を帯びた時代です。
バラモンに支配された古代インド
キリスト教聖職者に支配された中世ヨーロッパ
それらの時代では、宗教家という特権的知的エリートが「学問」を独占しました。そうすることで、世の成り立ちとその解釈をも独占しました。
学問を独占した知的エリートたちは、自分たちが不正によって富を蓄えることや、女性に乱暴すること、貧しい人から収奪することを学問によって正当化しました。
高度な学問どころか字も読めなかった多くの人たちは、何百年という長い期間を通して彼ら特権的知的エリートに従い続けました。
人間は知的な生き物です。故に、暴力に依らない知識と論理によっても、人間を屈服させ支配させることは可能です。
もし学問が一部の特権的エリートのみのものになったらどうなるでしょうか。
これは過去のような宗教教義の独占という形を取らずとも成立し得ます。
例えばコンピューターや、医療や、発電所のようなインフラ施設について、国民の圧倒的大多数が一切何も理解できないような社会になったらどうなるでしょうか。
サイエンスライターや、新聞の科学欄や、一般向け科学書などが存在しないような時代になったとしたら。
古代インドや中世ヨーロッパのような時代が再来しないと、誰に言えるでしょうか。
学問は、それを独占した物が他の持たざるものを支配できるという意味において、ある意味で貨幣や食料と同じような「資源」としての側面も持っています。
その学問という「資源」を、一部の特権的な階級に独占させないこと、幅広い層に行き渡るよう努力することは、民主主義社会という政体を支えていくために極めて重要なことです。
それは第一に公教育の拡充によって、そして第二に公立図書館や生涯学習校のような「学びへのアクセス」を常に担保し続けていることによってしか達成できません。
生涯学習は、全ての人の「学ぶ権利」を保持し続けるためにも必要なものだと思います。
【最後に】
以上が現場の人間が考える生涯学習の公的な意義です。
生涯学習によって、幅広い層の労働者がキャリアを積むことができます。それは新たなイノベーションや、富の再分配を促進します。
生涯学習によって、学問に理解のある有権者が増え、科学政策、教育政策への良いフィードバックが期待できます。それは大学教員のような高度専門知識人たちが安心して研究を推進できる環境に寄与します。
生涯学習によって、「知識」という資源の独占は防がれ、一部の専門家だけが世界の行末を左右するような独裁的な政体から遠ざかることができます。
「大学教員になれないなら中途半端に勉強なんかしたって無駄だ」というのは、浅薄で視野の狭い愚かな意見です。
人は大学教員になるために学ぶわけではありません。労働者として、有権者として、ひとりの人間として、様々な目的のために学ぶのです。
そして、その様々な人間の、様々な目的のための学びが、社会の様々な箇所を支えている。
「学び」を広く分け与えることによって、より良い社会を実現することができる。僕はそう思っています。
吉村氏の発言は(http://matome.naver.jp/odai/2129577175452365001)によると以下のようなものである。
生涯学習という名の老人や主婦の暇つぶしのために税金が使われることが問題なだけ。勉強したい人は好きなだけご自由にやって欲しい。ただ、世間が生涯学習(暇つぶし)の機会を大学に求めると、我々は雑用を抱え込むことになる。そして、本来すべきことが疎かになる
若いときに勉強してない人が年を取ってから勉強を始めても暇つぶしにしかならない。ゆえに、生涯学習という名の下に税金を投入することに意義はない。若いときに運動してない人は、年をとってからの体力低下が著しく、回復はもはや手遅れ。勉強と運動は若いときの蓄えが問われる点で共通。
これに対し、小山彰宏という人が「人類応援ブログ」(http://blog.livedoor.jp/ganbare_zinrui/archives/15...)というところで、以下のように批判している。
2014年10月24日
生涯学習の公共的意義について
島根大学の吉村哲彦教授による「生涯学習なんて無意味だと思う。」という発言が波紋を呼んでいます。
氏の主張は
若いときに勉強してない人が年を取ってから勉強を始めても暇つぶしにしかならない。ゆえに、生涯学習という名の下に税金を投入することに意義はない。
というもので、大学教員のような高度専門知識人になるには、早い段階からの学習が必要であり、高度専門知識人を育てられない生涯学習に税金を投入する意味は無い、というもののようです。
ネットでは
「確かに税金を使う必要はないかもしれない」
「学問をなんだと思ってるんだ」
などなど賛否両論。喧々諤々の議論が行われています。
それらの様を見て自分が思ったのは「生涯学習の公共的意義があまり共有されていないな」
ということです。
賛成派も否定派も、間違った前提で議論を組み立てているように思えます。生涯学習の本当の意義は、高度専門知識人を育てることでも、趣味としての自己実現を助けるためでも、どちらでもありません。
自分もある意味でフリースクールの主催者という「生涯学習」の担い手です。
生涯学習の公共的意義について、当事者がどう考えているのか、少しお話させて頂ければと思います。
【生涯学習の意義その1】
■幅広い層の知的労働者を育てる
地域のカルチャーセンターや放送大学などの「生涯学習」を受け持つ施設、ここにはどんな層の生徒が来ているか、みなさんご存知でしょうか。
吉村氏の言ではほぼ全ての参加者が後期高齢者、というような書き方をされていましたが、実態は全く異なります。
例えば30代、40代の働き盛りのサラリーマンや、10代で働きながら学位取得を目指す人など、実際は「老後の趣味」のような方以外にも幅広い層の生徒が参加しています。
特にサラリーマン組の参加者は目的意識が明確です。
例えば海外赴任が急に決まったサラリーマンが外国語を学びに来たり、現役の警察官や自衛官が幹部候補生試験を受けるために学位を取りに来たり、転職のために必要な資格を取るために必要な講座を取りに来たり、と「仕事に必要な技術を得るため」に生涯学習施設に通う方が多くいらっしゃいます。
実際に僕のフリースクールにも、アフリカへの赴任を前にした方が英語を学びに来ていますし、プログラマーの方が数学を学びに来たりもしています。
大学職員のように本当に高度な専門知識を要する仕事以外にも、世の中には様々な職業があります。そして、それら様々な職業でも、大学職員と同じように知識と技術が求められています。
放送大学などの生涯学習校は、そんな知識と技術を求める労働者に対し、安価で良質な教育機会を提供しています。
もし生涯学習のための施設が存在しなかったらどうなるでしょうか。
私大の夜間部や専門学校などの高額な学費が必要な施設でしか、労働者は仕事に必要な知識を学べなくなってしまいます。その結果何が起こるかといえば、労働者の学習機会の二極化です。
大企業正社員のみが転職・キャリアアップのための機会を得て、その他の大多数の労働者は一生今の仕事を続けざるを得ないような社会。そんな世界が待っています。
幅広い階層の労働者に教育の機会(つまりキャリアアップの機会)を与えるという意味でも、生涯学習には公共的意義が存在します。
【生涯学習の意義その2】
■質の良い有権者を育てる
「質の良い有権者」、つまり各種の学問に通じ、それらに対し理解のある有権者を育てることも生涯学習が持つ重要な役割です。
僕の知る限り、「人文系学部の廃止」や「大学の就職予備校化」のような、反知性主義的な政策に対して最も強く反対の声を上げているのが放送大学やカルチャーセンターの学生たちです。
彼らは学問に対しての人一倍強い想いがあります。その価値を正しく認め、社会全体で育んでいくべきだという考えを持った人たちです。それは「趣味で」勉強している人でも全く変わりません。
つい最近もこんな報道がありました。
国立大学から文系学部が消える!安倍首相と文科省の文化破壊的“大学改革“
現在文部科学省では国公立大学の人文系学部を廃止し、職業教育「のみ」を推進するような大学のあり方を作ろうとしています。
なぜこんな愚かな政策が推進されているかと言えば、政治の担い手である有権者に「反知性主義」的な考え方が広く広まってしまったからでしょう。
自分の理解できないものは必要ない、金儲けに役に立たないものは必要ない、そんな浅薄で目先のことしか考えない考え方が、教育行政にまで根を伸ばしつつあります。
高度専門知識人である大学教授が生きていくためには、大学の存続が必要です。そして大学の存続には、政府による補助金が必要です。そして政府による補助金を確保するためには、大学教育に理解のある有権者が必要なのです。
もし放送大学やカルチャーセンターの学生のような、各種の「学問」に対して理解のある有権者がこの国からいなくなれば、大学のあり方は今とは全く異なってくるでしょう。
そうなってしまえば、失礼ながら吉村教授が奉職されている島根大学などは恐らく10年以内に取り潰されると思います。島根大学だけでなく、全国の地方国立大学、低偏差値の私立大学、それらは全て潰されるか縮小され、旧帝国大学と早慶上智のような一部名門私立大学のみが生き残るような状況になるでしょう。
そんな核戦争後の人類社会のような荒廃を大学にもたらさないためにも、学術に理解ある有権者を育てること、それらを育てるゆりかごたる生涯学習を保持し続けることは学術の未来にとっても必要なのです。
【生涯学習の意義その3】
■「権利」としての学びを保持する
人類史を通して「学術が一部の特権的エリートに独占された時代」というのは数多くの例があります。そのいずれもが、暗い色彩を帯びた時代です。
バラモンに支配された古代インド
キリスト教聖職者に支配された中世ヨーロッパ
それらの時代では、宗教家という特権的知的エリートが「学問」を独占しました。そうすることで、世の成り立ちとその解釈をも独占しました。
学問を独占した知的エリートたちは、自分たちが不正によって富を蓄えることや、女性に乱暴すること、貧しい人から収奪することを学問によって正当化しました。
高度な学問どころか字も読めなかった多くの人たちは、何百年という長い期間を通して彼ら特権的知的エリートに従い続けました。
人間は知的な生き物です。故に、暴力に依らない知識と論理によっても、人間を屈服させ支配させることは可能です。
もし学問が一部の特権的エリートのみのものになったらどうなるでしょうか。
これは過去のような宗教教義の独占という形を取らずとも成立し得ます。
例えばコンピューターや、医療や、発電所のようなインフラ施設について、国民の圧倒的大多数が一切何も理解できないような社会になったらどうなるでしょうか。
サイエンスライターや、新聞の科学欄や、一般向け科学書などが存在しないような時代になったとしたら。
古代インドや中世ヨーロッパのような時代が再来しないと、誰に言えるでしょうか。
学問は、それを独占した物が他の持たざるものを支配できるという意味において、ある意味で貨幣や食料と同じような「資源」としての側面も持っています。
その学問という「資源」を、一部の特権的な階級に独占させないこと、幅広い層に行き渡るよう努力することは、民主主義社会という政体を支えていくために極めて重要なことです。
それは第一に公教育の拡充によって、そして第二に公立図書館や生涯学習校のような「学びへのアクセス」を常に担保し続けていることによってしか達成できません。
生涯学習は、全ての人の「学ぶ権利」を保持し続けるためにも必要なものだと思います。
【最後に】
以上が現場の人間が考える生涯学習の公的な意義です。
生涯学習によって、幅広い層の労働者がキャリアを積むことができます。それは新たなイノベーションや、富の再分配を促進します。
生涯学習によって、学問に理解のある有権者が増え、科学政策、教育政策への良いフィードバックが期待できます。それは大学教員のような高度専門知識人たちが安心して研究を推進できる環境に寄与します。
生涯学習によって、「知識」という資源の独占は防がれ、一部の専門家だけが世界の行末を左右するような独裁的な政体から遠ざかることができます。
「大学教員になれないなら中途半端に勉強なんかしたって無駄だ」というのは、浅薄で視野の狭い愚かな意見です。
人は大学教員になるために学ぶわけではありません。労働者として、有権者として、ひとりの人間として、様々な目的のために学ぶのです。
そして、その様々な人間の、様々な目的のための学びが、社会の様々な箇所を支えている。
「学び」を広く分け与えることによって、より良い社会を実現することができる。僕はそう思っています。
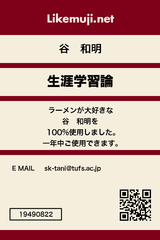

コメントをかく