�����������������ɥ��ĤǤϡ����פ��й�����Ҳ���Ūʸ����������ʤ��줿���ȤϤ����������оݤȤʤäƤ���ʸ�����ߤϡ���졢�����ȥۡ��롢���ڥ�¡���ʪ�ۡ����Ѵۡ���ۡ���̱��ء����Ͷ���ˡ����ڳع��ʤ����ɥ��Ĥ�Ʊ�ͤλ��ߤ�¿���ä����Ĥޤꡢ�磻�ޡ������ʸ����������������Ū��Ƨ����ȯŸ�������Ƥ����Ȥ����褦���Ȥ����ǡ��嵭�ν����ߤΤ�����줫�����ѴۤޤǤ�18��������λ�̱ʸ���β̼¤Ȥ����٤���ΤǤ��롣�����̱ʸ�������̤������Ȥ��ƤȤ館����ȡʼ����Ρˤ�������ݸ�Ƥ������ȡ����줬���������줹�롢���ɥ���ʸ����������ħ���Ȥ����褦���ष���������̱ʸ���ο��ηѾ��Ԥ�ǧ����ޥ륯�������ȡ���ɥ��Ĥˤ����ơ����β���Ϥ���Ѷ�Ū�˿�ʤ��줿�ΤǤ��롣¾������ۡʸ�Ω�ϰ��ۡˡ���̱��ء����ڳع��Ȥ��ä����ߤ�19������Ⱦ��ϫƯ�ԡ�̱�����鱿ư��ȯŸ�ȤȤ��Ÿ���������줬�磻�ޡ�����˸�Ū���ߤȤ��ư��֤Ť�����褦�ˤʤä���ΤǤ��롣�����λ��ߤ˴ؤ��Ƥϡ����ɥ��ĤǤ�ʸ�����ߤθ��IJ����ʤ������Τ⤫�ʤꤢ��Τ��Ф�����Ǥϴ����˸�Ω�λ��ߤȤ�������������߿��⽼�¤��Ƥ�����
�����Τʤ��ǡ����ɥ��ĤˤϤߤ��ʤ����ŵ��Ūʸ�����ߡ����줬��ʸ����Kulturhaus�פǤ��ä���Groschopp: 97�ˡ�ʸ���ۤ�ϫƯ�Ҳ�Ρ�����Ū�����¤��פȤ���20������Ⱦ�˹��ޤä���̱�����Volkshaus�פ�������Ѿ�����Ҳ���Ūʸ�����ߤȤ��ư��֤Ť���졢������Ϥؤηײ�Ū���֤��ʤ��줿������������ǯ��1988ǯ�ʳ������פǤ�1838�ۤ���ư���Ƥ����Ȥ���(IfK:7)���������ε���ɥ��Ŀ���1600����;�Ǥ��ä����顢��1����������λ���̩�٤�1.15�ۤǤ��롣���ܤθ�̱�ۤ�̩�٤�2010ǯ�٤�1.2�ۤǤ��뤫�顢����ˤۤ������������������ʤ���Ƥ������Ȥ��狼�롣�դˤ��Τ褦�ʻ��𤬤��ä�����ˡ��������ɥ��ĤǤ��ϰ襻�������ߤ����֤��Ф����äˣãģդʤ��ݼ�Ū��Ω�줫��Ҳ���Ū�����Ȥ�����Ƚ�����ꡢ1980ǯ��ޤǤϼ����Τ�ʸ����������Ȥ��ư��֤Ť��뤳�Ȥؤι�դ���������ʤ��ä��ΤǤ��롣
����ʸ���ۤϡ���ñ�˸����С����ܤθ�̱�ۤ�ʸ����ۡ�ʸ���ۡ���ˤ������������Ū�ϰ�ʸ�����������ߤǤ��롣�����Ƥλ�̱�˳����줿ʸ�����ߡפȤ��ơֻ�̱����ξ�ס��ֽвȰո��ξ�ס��ּҸ�ȸ�ڤξ�ס��ֻ�̱��ʸ�����ݽ�Ū���ʳء�����Ū�����ݡ��ġ��Ѹ�Ū�ʳ�ư�ξ�פ�ᤶ�����ʵ�§��3��ˡ����Ϥ�������Ƥ�¿�ͤǤ��뤬����Ĺ��Ϥ�Ȥ������翦������ʸ�����ݽѡ����顦�����Ҳ��ϰ迶�����Ҹ��ڤʤ�¿��Ū������Ū���ʤλ��Ȥ�»ܤ��Ƥ�������̱��ʸ��Ū����ο�����ᤶ�������ѼԤΥ���֡ʥ�������˳�ư�ξ�Ȥ�������Ż뤷�Ƥ������Ǥ⡢���ܤθ�̱�ۤ�������Ƥ��롣��ʸ���ۤϤ��ν���ϰ�ˤ���������Ū��ʸ��Ū����Τ���λ��ߡסʵ�§��6��ʣ��ˡˤȤ����ϰ�����͡��ʵ��ء����ΤȤζ�Ư�ˤ��ּҲ���Ū�ϰ��ưsozialistische Gemeinschaftsarbeit�פ���Ĵ����Ƥ��뤳�Ȥϡ��Ҳ���Ū�Ȥ������Ƥ���С���̱�ۤ�����Ʊ��Ǥ���Ȥ����롣
������̱�ۤ����֤���塢1946ǯ�˻Ϥޤ뤬��ʸ���ۤ�Ʊǯ�˥��������������ϰ�����֤���Ϥ��
ʸ���ۤθ�ή�����뤤�Ϥ��η����˱ƶ���Ϳ������Τˤϡ���Ҥέ���̱����ۡ�Volkshaus�ˡפΤۤ��ˡ�����Ϣ���Υ���֡�ʸ�����¡����ʥ�������Ρ��ް��βȡ�Kameradschaftshaus�ˡפʤɤ�����Ȥ�����Groschopp:123-137�ˡ������˶��̤���Τϡ��ݽѡ�ʸ���˻���������ꤷ��ʸ����Ҳ�Ū������Ū��ȯŸ�μ��ʤȤ��ư��֤Ť������Τ������̱���ؤ�ʸ������ڤ�ָ����롢����Ū��̱������Ū�ʳ�ư�Ǥ��롣����ϡ���ɥ��ĤǤϡ�ʸ��Ū�罰��ư��kulturelle Massenarbeit�ˡפȤ���줿��ʸ���ۤϡ��Ҳ���Ū�ʼҲʹַ����Τ�����罰Ūʸ����ư�ξ�Ȥ��ƹ��ۤ��줿�ΤǤ��롣
����ʸ���ۤ����ּ��Τϡ���Į¼�䷴�ʤ������������ءʤ����ϡָ�Ωstaatlich�פ����Τ����ˤ����ǤϤʤ����ȥ�ͧ������ʤɤΡּҲ�Ū�ȿ��פ��Ȥ����֤�����Τ�¿���ä���
�ä˴��Ω��¿�����ꡢ�����⽼�¤��Ƥ�������������1960ǯ��ˤϡ����Ȱ������Ѥ�ͥ�褵�졢��̱���Ф��ĺ�Ū�Ǥ��뤳�Ȥ�����Ȥʤꡢ�����ϰ轻̱�ؤγ����Ȥʤ��������������ɤˤ��ָ�Ω��ʸ���ۤηײ�Ū���¤��ܻؤ����褦�ˤʤä�����������С���ɥ��ļҲ���ԻԲ���ȼ����ϫƯ�Գ���Υ��������ϰ�ʸ�������ؤ�ž�����Ԥ�줿�ΤǤ��롣���Ф�����§�ϡ����Τ褦�ʷ�����ȿ�Ǥ�����Τǡ����Ω���оݤ���������������ǡ���ʸ��������ˤȤ��ơָ�Ω��ʸ�����֤�Ƚ����뤳�Ȥ��ܻؤ���Ƥ��롣������1980ǯ����̤��ơ��ָ�Ω��ʸ���ۿ�������Ū�����ä�����
�ȤϤ����������������ɤˤϽ�ʬ�ʺ���ǽ�Ϥ��ʤ��ä��Τǡ���������ʬ������ʬ������ǯ����ִۤȤ��������μ��ʸ�����ߤ����äǤ��ä��������ˤϡ����å������Ȥ�ǥ������ʤɡ�ʸ�����Ȥ�Ԥ�����Ź�פȤ��ä�����褹��Ȥ�����¿���ä���
�����Ҳ���Ūʸ�����ߤȤ�����������Ƥ���ʸ���ۤϡ�����椨��������¸³�δ����˴٤ä������ߤΤȤ����Ǥϡ����Ѵۡ����Ͱ��̾�������Ĵ������Ū�ʳ�ư�η�³��������Ū���Ի��߲��Ȥ��ä�¾�ˡ�����̱NPO���ΤĤ�ô����Ȥ��뿷�����ϰ�ʸ�������Ȥ��ƺ���������Τ⤢�롣���ξ�硢1970ǯ��ʹߵ����ɥ��Ĥǡֿ������Ҳ�ư�פȤ���ȯŸ���Ƥ�����̱�ˤ��ּҲ�ʸ������soziokulturelle Zentren��꤬��ǥ�ˤʤäƤ��롣
�����Ҳ�ʸ����Siziokultur�ˤϡ����ɥ��Ĥˤ����ơ�����Ū��̱ʸ���濴�ν���Ρֹ���Ūaffirmativ�פ�ʸ������������ֿ�����ʸ�������פ���ǰ�Ȥ������졢����Ū�ˤϡ��Ҳ�ʸ�������Ȥ���¿��ŪŪ���ϰ�ʸ���������̱������Ū�����֡����Ĥ��뱿ư����ɸ��ǰ�Ȥ����ɵᤵ��Ƥ��������ߤǤϡ��Ȥ�������������ʸ��������ʸ̮�ǡ��ϰ��Stadtteil��ʸ���ȼҲ�ʸ����Ʊ��Ū���Ѥ����뤳�Ȥ⤢�롣
�Ҳ�ʸ�����ϰ�ʸ���ϡ�Ʊ���ǤϤʤ�������ɤ⡢�Ҳ�ʸ����֥����ƥ�ˤ�����������ο�̱�ϲ��ס�Habermas, J.�ˤؤ��й�ʸ���λ�ߤȤ��ƤȤ館��ʤ�С��ϰ���̱�Ρ�ϫƯ���ؽ�������פξ�Ȥ��ƺƹ��ۤ���Ȥ������꤬�������濴Ū����ΰ�ĤȤʤ뤳�ȤϤ����ޤǤ�ʤ����Ҳ�ʸ��������¿�������ϰ�ʸ�������Ȥ�����Ω���졢��ǽ���Ƥ��뤳�ȤϷ褷�ƶ����ǤϤʤ���
���������ͤΤ����ʸ���ס����ͤˤ��ʸ���פȤ���ʸ����̱�粽���罰�����ĥ�������ɥ��ĤμҲ�ʸ���ϡ��Ҳ�ʸ�������Ȥ��ƶ��β����Ƥ�����¾������ɥ��Ĥ�ʸ��Ū�罰��ư��ʸ���ۤȤ��Ʒ�¤�����ʸ���ۤȼҲ�ʸ�������Ȥˤϡ�������������ȥץ������뤫���ꡢ�ϰ�ʸ�������Ȥ��Ƥ�����������롣����Ū�����ϡ����Ԥ�����Ȥˤ�ä�����ľ�夫�����֤��줿�Τ��Ф�����Ԥϡ���̱�Υ��˥����ƥ��֤ǡ�1970ǯ��˻�äƻϤ�����֤��줿�Ȥ������ȤǤ��롣
���ߤ����ܤǤϡ���̱�ۤʤɤθ����ϰ�ʸ��������̱�IJ��ʻ�����������٤ʤɡˤ������β���ȤʤäƤ��롣����������Ȥʤ�Τϡ�ʸ�����ؽ��θ��������ϰ�ʸ����ư�μ��Ρ��ϰ�ʸ�������ʡ�����ʸ�����Ҳ�ʸ���ʤɡˡ��ϰ�Ҳ�ؤθ����Ϥδ�Ϳ�Ȥ��ä������Ǥ��롣������ͤ����ǡ������Ϥˤ���ϰ�ʸ���������Ѷ��̤������̤�Ʊ�����θ����Ƥ���ʸ���ۤηи�����ȽŪ��Ƥ��ͭ�פʼ�����Ϳ����Ǥ����������Τ���ˤϡ����Ԥ����Ҳ��������ΰ�ʪ�Ȥ����������Ū�˰������Ȥʤ������θ��¤��ɤ��Ǥ��ä��Τ��ڤ��Ƥ���ɬ�פ����롣��
����ʸ��
Groschopp, Horst; Kulturh���user in der DDR. Vorl���ufer, Konzepte, Gebrauch. Versuch einer historischen Rekonstruktion. In; Ruben, Thomas/ Wagner, Bernd (Hrgs.): Kulturh���user in Brandenburg. Eine Bestandsaufnahme. Potsdam 1994.
Institut f���r Kulturforschung beim Ministerium Kultur (IfK); Kultur in der DDR -Daten-1975-1988. Berlin 1989.
ʸ���ۤβ���ʤ�Ӥ˳�ư�ͼ��˴ؤ��뵬§
��Ωʸ���ۤηײ衢�������軻�˴ؤ��뵬§
�����Τʤ��ǡ����ɥ��ĤˤϤߤ��ʤ����ŵ��Ūʸ�����ߡ����줬��ʸ����Kulturhaus�פǤ��ä���Groschopp: 97�ˡ�ʸ���ۤ�ϫƯ�Ҳ�Ρ�����Ū�����¤��פȤ���20������Ⱦ�˹��ޤä���̱�����Volkshaus�פ�������Ѿ�����Ҳ���Ūʸ�����ߤȤ��ư��֤Ť���졢������Ϥؤηײ�Ū���֤��ʤ��줿������������ǯ��1988ǯ�ʳ������פǤ�1838�ۤ���ư���Ƥ����Ȥ���(IfK:7)���������ε���ɥ��Ŀ���1600����;�Ǥ��ä����顢��1����������λ���̩�٤�1.15�ۤǤ��롣���ܤθ�̱�ۤ�̩�٤�2010ǯ�٤�1.2�ۤǤ��뤫�顢����ˤۤ������������������ʤ���Ƥ������Ȥ��狼�롣�դˤ��Τ褦�ʻ��𤬤��ä�����ˡ��������ɥ��ĤǤ��ϰ襻�������ߤ����֤��Ф����äˣãģդʤ��ݼ�Ū��Ω�줫��Ҳ���Ū�����Ȥ�����Ƚ�����ꡢ1980ǯ��ޤǤϼ����Τ�ʸ����������Ȥ��ư��֤Ť��뤳�Ȥؤι�դ���������ʤ��ä��ΤǤ��롣
����ʸ���ۤϡ���ñ�˸����С����ܤθ�̱�ۤ�ʸ����ۡ�ʸ���ۡ���ˤ������������Ū�ϰ�ʸ�����������ߤǤ��롣�����Ƥλ�̱�˳����줿ʸ�����ߡפȤ��ơֻ�̱����ξ�ס��ֽвȰո��ξ�ס��ּҸ�ȸ�ڤξ�ס��ֻ�̱��ʸ�����ݽ�Ū���ʳء�����Ū�����ݡ��ġ��Ѹ�Ū�ʳ�ư�ξ�פ�ᤶ�����ʵ�§��3��ˡ����Ϥ�������Ƥ�¿�ͤǤ��뤬����Ĺ��Ϥ�Ȥ������翦������ʸ�����ݽѡ����顦�����Ҳ��ϰ迶�����Ҹ��ڤʤ�¿��Ū������Ū���ʤλ��Ȥ�»ܤ��Ƥ�������̱��ʸ��Ū����ο�����ᤶ�������ѼԤΥ���֡ʥ�������˳�ư�ξ�Ȥ�������Ż뤷�Ƥ������Ǥ⡢���ܤθ�̱�ۤ�������Ƥ��롣��ʸ���ۤϤ��ν���ϰ�ˤ���������Ū��ʸ��Ū����Τ���λ��ߡסʵ�§��6��ʣ��ˡˤȤ����ϰ�����͡��ʵ��ء����ΤȤζ�Ư�ˤ��ּҲ���Ū�ϰ��ưsozialistische Gemeinschaftsarbeit�פ���Ĵ����Ƥ��뤳�Ȥϡ��Ҳ���Ū�Ȥ������Ƥ���С���̱�ۤ�����Ʊ��Ǥ���Ȥ����롣
������̱�ۤ����֤���塢1946ǯ�˻Ϥޤ뤬��ʸ���ۤ�Ʊǯ�˥��������������ϰ�����֤���Ϥ��
ʸ���ۤθ�ή�����뤤�Ϥ��η����˱ƶ���Ϳ������Τˤϡ���Ҥέ���̱����ۡ�Volkshaus�ˡפΤۤ��ˡ�����Ϣ���Υ���֡�ʸ�����¡����ʥ�������Ρ��ް��βȡ�Kameradschaftshaus�ˡפʤɤ�����Ȥ�����Groschopp:123-137�ˡ������˶��̤���Τϡ��ݽѡ�ʸ���˻���������ꤷ��ʸ����Ҳ�Ū������Ū��ȯŸ�μ��ʤȤ��ư��֤Ť������Τ������̱���ؤ�ʸ������ڤ�ָ����롢����Ū��̱������Ū�ʳ�ư�Ǥ��롣����ϡ���ɥ��ĤǤϡ�ʸ��Ū�罰��ư��kulturelle Massenarbeit�ˡפȤ���줿��ʸ���ۤϡ��Ҳ���Ū�ʼҲʹַ����Τ�����罰Ūʸ����ư�ξ�Ȥ��ƹ��ۤ��줿�ΤǤ��롣
����ʸ���ۤ����ּ��Τϡ���Į¼�䷴�ʤ������������ءʤ����ϡָ�Ωstaatlich�פ����Τ����ˤ����ǤϤʤ����ȥ�ͧ������ʤɤΡּҲ�Ū�ȿ��פ��Ȥ����֤�����Τ�¿���ä���
�ä˴��Ω��¿�����ꡢ�����⽼�¤��Ƥ�������������1960ǯ��ˤϡ����Ȱ������Ѥ�ͥ�褵�졢��̱���Ф��ĺ�Ū�Ǥ��뤳�Ȥ�����Ȥʤꡢ�����ϰ轻̱�ؤγ����Ȥʤ��������������ɤˤ��ָ�Ω��ʸ���ۤηײ�Ū���¤��ܻؤ����褦�ˤʤä�����������С���ɥ��ļҲ���ԻԲ���ȼ����ϫƯ�Գ���Υ��������ϰ�ʸ�������ؤ�ž�����Ԥ�줿�ΤǤ��롣���Ф�����§�ϡ����Τ褦�ʷ�����ȿ�Ǥ�����Τǡ����Ω���оݤ���������������ǡ���ʸ��������ˤȤ��ơָ�Ω��ʸ�����֤�Ƚ����뤳�Ȥ��ܻؤ���Ƥ��롣������1980ǯ����̤��ơ��ָ�Ω��ʸ���ۿ�������Ū�����ä�����
�ȤϤ����������������ɤˤϽ�ʬ�ʺ���ǽ�Ϥ��ʤ��ä��Τǡ���������ʬ������ʬ������ǯ����ִۤȤ��������μ��ʸ�����ߤ����äǤ��ä��������ˤϡ����å������Ȥ�ǥ������ʤɡ�ʸ�����Ȥ�Ԥ�����Ź�פȤ��ä�����褹��Ȥ�����¿���ä���
�����Ҳ���Ūʸ�����ߤȤ�����������Ƥ���ʸ���ۤϡ�����椨��������¸³�δ����˴٤ä������ߤΤȤ����Ǥϡ����Ѵۡ����Ͱ��̾�������Ĵ������Ū�ʳ�ư�η�³��������Ū���Ի��߲��Ȥ��ä�¾�ˡ�����̱NPO���ΤĤ�ô����Ȥ��뿷�����ϰ�ʸ�������Ȥ��ƺ���������Τ⤢�롣���ξ�硢1970ǯ��ʹߵ����ɥ��Ĥǡֿ������Ҳ�ư�פȤ���ȯŸ���Ƥ�����̱�ˤ��ּҲ�ʸ������soziokulturelle Zentren��꤬��ǥ�ˤʤäƤ��롣
�����Ҳ�ʸ����Siziokultur�ˤϡ����ɥ��Ĥˤ����ơ�����Ū��̱ʸ���濴�ν���Ρֹ���Ūaffirmativ�פ�ʸ������������ֿ�����ʸ�������פ���ǰ�Ȥ������졢����Ū�ˤϡ��Ҳ�ʸ�������Ȥ���¿��ŪŪ���ϰ�ʸ���������̱������Ū�����֡����Ĥ��뱿ư����ɸ��ǰ�Ȥ����ɵᤵ��Ƥ��������ߤǤϡ��Ȥ�������������ʸ��������ʸ̮�ǡ��ϰ��Stadtteil��ʸ���ȼҲ�ʸ����Ʊ��Ū���Ѥ����뤳�Ȥ⤢�롣
�Ҳ�ʸ�����ϰ�ʸ���ϡ�Ʊ���ǤϤʤ�������ɤ⡢�Ҳ�ʸ����֥����ƥ�ˤ�����������ο�̱�ϲ��ס�Habermas, J.�ˤؤ��й�ʸ���λ�ߤȤ��ƤȤ館��ʤ�С��ϰ���̱�Ρ�ϫƯ���ؽ�������פξ�Ȥ��ƺƹ��ۤ���Ȥ������꤬�������濴Ū����ΰ�ĤȤʤ뤳�ȤϤ����ޤǤ�ʤ����Ҳ�ʸ��������¿�������ϰ�ʸ�������Ȥ�����Ω���졢��ǽ���Ƥ��뤳�ȤϷ褷�ƶ����ǤϤʤ���
���������ͤΤ����ʸ���ס����ͤˤ��ʸ���פȤ���ʸ����̱�粽���罰�����ĥ�������ɥ��ĤμҲ�ʸ���ϡ��Ҳ�ʸ�������Ȥ��ƶ��β����Ƥ�����¾������ɥ��Ĥ�ʸ��Ū�罰��ư��ʸ���ۤȤ��Ʒ�¤�����ʸ���ۤȼҲ�ʸ�������Ȥˤϡ�������������ȥץ������뤫���ꡢ�ϰ�ʸ�������Ȥ��Ƥ�����������롣����Ū�����ϡ����Ԥ�����Ȥˤ�ä�����ľ�夫�����֤��줿�Τ��Ф�����Ԥϡ���̱�Υ��˥����ƥ��֤ǡ�1970ǯ��˻�äƻϤ�����֤��줿�Ȥ������ȤǤ��롣
���ߤ����ܤǤϡ���̱�ۤʤɤθ����ϰ�ʸ��������̱�IJ��ʻ�����������٤ʤɡˤ������β���ȤʤäƤ��롣����������Ȥʤ�Τϡ�ʸ�����ؽ��θ��������ϰ�ʸ����ư�μ��Ρ��ϰ�ʸ�������ʡ�����ʸ�����Ҳ�ʸ���ʤɡˡ��ϰ�Ҳ�ؤθ����Ϥδ�Ϳ�Ȥ��ä������Ǥ��롣������ͤ����ǡ������Ϥˤ���ϰ�ʸ���������Ѷ��̤������̤�Ʊ�����θ����Ƥ���ʸ���ۤηи�����ȽŪ��Ƥ��ͭ�פʼ�����Ϳ����Ǥ����������Τ���ˤϡ����Ԥ����Ҳ��������ΰ�ʪ�Ȥ����������Ū�˰������Ȥʤ������θ��¤��ɤ��Ǥ��ä��Τ��ڤ��Ƥ���ɬ�פ����롣��
����ʸ��
Groschopp, Horst; Kulturh���user in der DDR. Vorl���ufer, Konzepte, Gebrauch. Versuch einer historischen Rekonstruktion. In; Ruben, Thomas/ Wagner, Bernd (Hrgs.): Kulturh���user in Brandenburg. Eine Bestandsaufnahme. Potsdam 1994.
Institut f���r Kulturforschung beim Ministerium Kultur (IfK); Kultur in der DDR -Daten-1975-1988. Berlin 1989.
ʸ���ۤβ���ʤ�Ӥ˳�ư�ͼ��˴ؤ��뵬§
��Ωʸ���ۤηײ衢�������軻�˴ؤ��뵬§
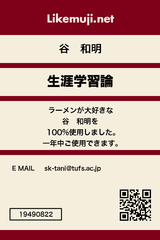

�����Ȥ�