文化と政治を結びつける
Tageszeitung .2002年6月8日号 所収インタビュー(谷訳)
Park Fictionはハンブルクでは「公共空間に芸術を」のモデルプロジェクトです。それが、ドクメンタへの招聘により、今や勲章を授けられたわけです。ことの発端は、ザンクト・パウリ地域で港湾周辺に緑地を残そうと尽力していた地域運動グループです。この政治運動グループにどうして芸術が登場したのでしょうか?
ザビーネ・シュテーヴェサンド:このプロジェクトは港通り近くのバウヴァーゲン広場(Bauwagenplatz)をどうするかという、今は過去のものとなった議論から生じたのです。この問題が解決した後、多くの人々が自問しました。港周辺にまだ場所がある、そこに自分たちでなにか作れるのではないか、と。私たちは建築家たちと協力して最初の公園プランを策定し、都市開発局長との会談を求めました。具体的提案を突きつけて、不意打ちを食らわせたのです。彼らは、ハンブルク市の最貧困地域であるザンクトパウリを、都市開発政策の観点からみて全くといっていいほど無視してきたことを認めざるを得ませんでした。
クリストーフ・シェーファー:僕は1995年にそれに加わった。公園のための抗議運動として、公園にすべきだとされる場所には「ザンクトパウリにPark Fictionを、ベルリンにビート音楽の爆撃を」という看板が掲げられていた。この場所のあちこちは、「港通り100階段公園」とか「港湾労働者公園」とか「ビール缶公園」とかいった名がつけられていた。このユーモアが気に入ったんだ。僕は80年代末から状況主義やアーバニズムに関わってきた。そう、すでに60年代から、芸術から始まりさらにそれを超えて、どうすれば都市を別の形で形成できるかという議論が存在する。
Park Fictionにはそのような潮流を再開・継続する可能性がある、と僕は考えた。貧困住民層のもとでの抑圧・排除のプロセス、それは文化的創造力のある人々がいわゆる劣悪地区に移住することにより開始するものなのだが、そのすべては90年代初めには理論的に解明されていた。従ってここでは、非常に注意深い交流がおこなわれ、そのことによって逆方向に舵を取ることが幾度も試みられたのだ。
では文化シーンという範囲を越えての芸術への関係はPark Fictionではどう表現されているのでしょうか?
シェーファー:Park Fictionは、芸術の自律性を拡大し、公園計画過程に参加してきたすべての人の手の届くものにしたんだ。既成のものに対する対抗モデルを考え出し、現実の強制に縛られないで作り変えていくのは実に楽しい。この楽しみがあるからみんな参加したに違いない。計画のためにすべての参加者のさまざまなやり方や知識が混ぜ合わされた。Park Fictionの芸術への関わりは決して戦術的なものではない。私たちは一般的に従来の芸術と政治との分離に反対なんだ。
芸術的な自律性を住民にまで拡大するということはどのように実行されたのですか?
シュテーヴェサンド:これは上からお膳立てされた参加プログラムではありませんでした。土地は占拠され、単純に利用されたのです。市の部局からの何らかの許可など待つことなく、私たちは端的に建設を始めたのです。
シェーファー:僕たちは計画コンテナを設置した。そこで人々が自分たちのアイデアを提示できるようにね。そして僕たちが携帯用計画事務所(toolsといわれるもので、ジュラルミンカバンにいれた運動用七つ道具:訳者注)を持参して地域の戸別訪問を開始すると、人々は即座にアイデアを発展させだしたのさ。一般的に言って、計画過程は遊びとして組織された。僕たちは公園と政治、公園とそのイデオロギー的背景をテーマとした情報娯楽型の催し物を実施し、庭園文庫を作り、散策を組織した。
この夏に当局による建設が開始しますね。公園はどうあるべきでしょうか?
シュテーヴェサンド:基本となるものは公園内の多様な区画、私たちが部屋とよんでいるものです。人々は非常にさまざまなことを願っています。だから、公園の一帯は多様な利用に開かれているべきです。
椰子の島もつくれるでしょう。劇に出てくるような情景も。空飛ぶ絨毯のように波打つ温室、戸外ソラリウム、焼肉の島、海賊たちの泉、イチゴの家、喫茶庭園、野ばらとバラで作られた迷路も作れます。さらに並木道もあり、そこでは街頭から締め出された活動もできるし「光の道」も付随しています。この「光の道」は区の緑化委員会で名称変更されました(ペルーのテロ組織と同名だという理由で:訳者注)。それは、現在では「黄金の中道」と呼ばれています。
なにはさておき、私たちは公園が非商業主義的でかつ非規制的な場所であるべきと考えます。営利的に経営されるカフェなどあってはならないし、ホームレスやジャンキーの排除があってもいけません。実は、社民・緑連立市政の時点で既にかなり規制案が検討されているのです。アルトナ区とハンブルク中央区はこのプロジェクトのためのあらゆる規則を策定しています。彼らは、騒音公害を少なくしたいと、さらにすべてを監督・管理したいと考えているのです。
昨年秋に選出された保守・極右連立政権が、前政権よりも公園を望んでいないことは確実です。Park Fictionをめぐる政策の風向きが変わらないのは何故ですか?
シェーファー:この地域の都市建設計画はもともと1994年に決定されたものですが、Park Fiction運動によってかなり大幅に改正されてきました。これは偉大な成果です。というのも、ハンブルクにおいて市民運動がはじめて達成した成果だからです。
シュテーヴェサンド:アルトナ区において、改正された新建設計画はCDUも賛成して決定されました。全会派の合意だったのです。
シェーファー:そしていうまでもないことだが、新政権がこのプロジェクトをどうするか、つまりプロジェクトの完全性が損なわれず、Park Fictionという理念が実現されるか否かを、世界が注視している。既にハンブルク市は、対応の遅延により、ドクメンタの分会場をハンブルク市に設置できる好機を逸してしまいました。今や、ハンブルク市がこの夏逃がしてしまったものを見るために、カッセルまで行かなければならないのです。
Park Fictionは芸術的プロジェクトとして認知され、市の外部から招聘されました。これはハンブルク市における「公共空間に芸術を」という独特の施策に負うところが大きいのではないでしょうか?
シェーファー:そう、それは、1997年、当時の文化局のプロジェクト・シリーズである「さらに進めweitergehen」により開始されたんだ。「さらに進め」には以下のような認識の到達点があった。「公共空間に芸術を」政策は単なる都市装飾に留まってはならない。あるいは市のプレステージ政策に基づくイメージ宣伝の道具であってはならない。そうではなくて、芸術家に実験の場を提供するものだ。
あなたはドクメンタでこのプロジェクトをどうプレゼンテーションしますか?
シェーファー:仲間で映画を担当したマルギート・チェンキスの作品「Park fiction: 願望は住居から街頭に出て行く」の上映が中心となる。さらに5つの主要作業概念―「異議申し立て的な土地占有者たち」「情報娯楽」「ツールス」「願望生産」「官僚主義との同床」――に沿って、願望を作り出していった足跡が見えるようにした展示、公園予定地の利用に関するビデオ、プロジェクトに対する市当局や企業の攻撃を描いたビデオもある。
このプロジェクトの経過や地域特有の背景といったことを超えて、何がドクメンタに伝えられるのでしょうか?
シェーファー:公共空間ということの新しい定義、これはどこにでも適用可能なものだ。カッセルの会場で、我々の展示はアーバニズムという重点テーマに組み入れられている。さらに、今年のドクメンタには芸術家の集団作品が多数展示されている。そのうち、例えば、ニューデリーから出品されているRaqsという作品は、都市における土地占拠を扱ったものだ。ここにつながる点がある。もちろんまだ始まりにすぎないけどね。
シュテーヴェサンド:異議申し立て的芸術は世界中に存在します。Park Fictionは、政治と芸術と社会性の交点におけるプロジェクトです。そこからの結論として挙げることができるのは、政治的あるいは異議申し立て的な芸術は、全く異なった人々の知識、経験、活動を平等に交換し、重ね合わせることから生まれるということに関する、新しい理解です。Park Fictionはその実例なのです。
注:
ザビーネ・シュテーブサンド(Sabine Stövesand):Sozialpädagogin。社会文化センターGWAザンクトパウリ所長。ハンブルク州社会文化連盟理事。大学で社会文化運動関係の非常勤講師もしている。Park fictionの市民運動的側面を代表する人物といえる。
クリストーフ・シェーファー(Christoph Schäfer):芸術家。1995年頃から運動に加わってきたが、ParkFictionがハンブルク市文化庁の振興プログラム「公共空間に芸術を」の対象事業として認定されるに伴い、それを担当する芸術家として委嘱される。Park fictionの芸術運動的側面を代表する人物といえる。
バウヴァーゲン広場Bauwagenplatz:ドイツの大都市に存在する、ミニバスタイプの中古自動車を住居にする青年たちが空き地を占拠して形成したアナーキーな群居空間。Bauwagenとは建築現場で作業員が寝泊できるように作られた車両のこと。その中古車を非常に安価で購入し、改修してボヘミアン的に移動生活をする青年たちの集団キャンプ場として形成されたので、このような名称がつけられた。
粗大ゴミ集積場のような雰囲気の場所に数十名の異様な風体で異臭を発する人々が生活しており、日本で言えばホームレスのダンボールハウス集落(上野公園内)に類似した雰囲気である。ただし、住人たちは自己の生き方を肯定的にとらえており、外部社会に対しても積極的に自己主張(左翼的・アナーキスト的傾向)することが多い。当然近隣住民からは歓迎されないことが多く、不法占拠・不衛生などを理由に当局から排除されることもある。極右の襲撃対象ともなることもある。
Tageszeitung .2002年6月8日号 所収インタビュー(谷訳)
Park Fictionはハンブルクでは「公共空間に芸術を」のモデルプロジェクトです。それが、ドクメンタへの招聘により、今や勲章を授けられたわけです。ことの発端は、ザンクト・パウリ地域で港湾周辺に緑地を残そうと尽力していた地域運動グループです。この政治運動グループにどうして芸術が登場したのでしょうか?
ザビーネ・シュテーヴェサンド:このプロジェクトは港通り近くのバウヴァーゲン広場(Bauwagenplatz)をどうするかという、今は過去のものとなった議論から生じたのです。この問題が解決した後、多くの人々が自問しました。港周辺にまだ場所がある、そこに自分たちでなにか作れるのではないか、と。私たちは建築家たちと協力して最初の公園プランを策定し、都市開発局長との会談を求めました。具体的提案を突きつけて、不意打ちを食らわせたのです。彼らは、ハンブルク市の最貧困地域であるザンクトパウリを、都市開発政策の観点からみて全くといっていいほど無視してきたことを認めざるを得ませんでした。
クリストーフ・シェーファー:僕は1995年にそれに加わった。公園のための抗議運動として、公園にすべきだとされる場所には「ザンクトパウリにPark Fictionを、ベルリンにビート音楽の爆撃を」という看板が掲げられていた。この場所のあちこちは、「港通り100階段公園」とか「港湾労働者公園」とか「ビール缶公園」とかいった名がつけられていた。このユーモアが気に入ったんだ。僕は80年代末から状況主義やアーバニズムに関わってきた。そう、すでに60年代から、芸術から始まりさらにそれを超えて、どうすれば都市を別の形で形成できるかという議論が存在する。
Park Fictionにはそのような潮流を再開・継続する可能性がある、と僕は考えた。貧困住民層のもとでの抑圧・排除のプロセス、それは文化的創造力のある人々がいわゆる劣悪地区に移住することにより開始するものなのだが、そのすべては90年代初めには理論的に解明されていた。従ってここでは、非常に注意深い交流がおこなわれ、そのことによって逆方向に舵を取ることが幾度も試みられたのだ。
では文化シーンという範囲を越えての芸術への関係はPark Fictionではどう表現されているのでしょうか?
シェーファー:Park Fictionは、芸術の自律性を拡大し、公園計画過程に参加してきたすべての人の手の届くものにしたんだ。既成のものに対する対抗モデルを考え出し、現実の強制に縛られないで作り変えていくのは実に楽しい。この楽しみがあるからみんな参加したに違いない。計画のためにすべての参加者のさまざまなやり方や知識が混ぜ合わされた。Park Fictionの芸術への関わりは決して戦術的なものではない。私たちは一般的に従来の芸術と政治との分離に反対なんだ。
芸術的な自律性を住民にまで拡大するということはどのように実行されたのですか?
シュテーヴェサンド:これは上からお膳立てされた参加プログラムではありませんでした。土地は占拠され、単純に利用されたのです。市の部局からの何らかの許可など待つことなく、私たちは端的に建設を始めたのです。
シェーファー:僕たちは計画コンテナを設置した。そこで人々が自分たちのアイデアを提示できるようにね。そして僕たちが携帯用計画事務所(toolsといわれるもので、ジュラルミンカバンにいれた運動用七つ道具:訳者注)を持参して地域の戸別訪問を開始すると、人々は即座にアイデアを発展させだしたのさ。一般的に言って、計画過程は遊びとして組織された。僕たちは公園と政治、公園とそのイデオロギー的背景をテーマとした情報娯楽型の催し物を実施し、庭園文庫を作り、散策を組織した。
この夏に当局による建設が開始しますね。公園はどうあるべきでしょうか?
シュテーヴェサンド:基本となるものは公園内の多様な区画、私たちが部屋とよんでいるものです。人々は非常にさまざまなことを願っています。だから、公園の一帯は多様な利用に開かれているべきです。
椰子の島もつくれるでしょう。劇に出てくるような情景も。空飛ぶ絨毯のように波打つ温室、戸外ソラリウム、焼肉の島、海賊たちの泉、イチゴの家、喫茶庭園、野ばらとバラで作られた迷路も作れます。さらに並木道もあり、そこでは街頭から締め出された活動もできるし「光の道」も付随しています。この「光の道」は区の緑化委員会で名称変更されました(ペルーのテロ組織と同名だという理由で:訳者注)。それは、現在では「黄金の中道」と呼ばれています。
なにはさておき、私たちは公園が非商業主義的でかつ非規制的な場所であるべきと考えます。営利的に経営されるカフェなどあってはならないし、ホームレスやジャンキーの排除があってもいけません。実は、社民・緑連立市政の時点で既にかなり規制案が検討されているのです。アルトナ区とハンブルク中央区はこのプロジェクトのためのあらゆる規則を策定しています。彼らは、騒音公害を少なくしたいと、さらにすべてを監督・管理したいと考えているのです。
昨年秋に選出された保守・極右連立政権が、前政権よりも公園を望んでいないことは確実です。Park Fictionをめぐる政策の風向きが変わらないのは何故ですか?
シェーファー:この地域の都市建設計画はもともと1994年に決定されたものですが、Park Fiction運動によってかなり大幅に改正されてきました。これは偉大な成果です。というのも、ハンブルクにおいて市民運動がはじめて達成した成果だからです。
シュテーヴェサンド:アルトナ区において、改正された新建設計画はCDUも賛成して決定されました。全会派の合意だったのです。
シェーファー:そしていうまでもないことだが、新政権がこのプロジェクトをどうするか、つまりプロジェクトの完全性が損なわれず、Park Fictionという理念が実現されるか否かを、世界が注視している。既にハンブルク市は、対応の遅延により、ドクメンタの分会場をハンブルク市に設置できる好機を逸してしまいました。今や、ハンブルク市がこの夏逃がしてしまったものを見るために、カッセルまで行かなければならないのです。
Park Fictionは芸術的プロジェクトとして認知され、市の外部から招聘されました。これはハンブルク市における「公共空間に芸術を」という独特の施策に負うところが大きいのではないでしょうか?
シェーファー:そう、それは、1997年、当時の文化局のプロジェクト・シリーズである「さらに進めweitergehen」により開始されたんだ。「さらに進め」には以下のような認識の到達点があった。「公共空間に芸術を」政策は単なる都市装飾に留まってはならない。あるいは市のプレステージ政策に基づくイメージ宣伝の道具であってはならない。そうではなくて、芸術家に実験の場を提供するものだ。
あなたはドクメンタでこのプロジェクトをどうプレゼンテーションしますか?
シェーファー:仲間で映画を担当したマルギート・チェンキスの作品「Park fiction: 願望は住居から街頭に出て行く」の上映が中心となる。さらに5つの主要作業概念―「異議申し立て的な土地占有者たち」「情報娯楽」「ツールス」「願望生産」「官僚主義との同床」――に沿って、願望を作り出していった足跡が見えるようにした展示、公園予定地の利用に関するビデオ、プロジェクトに対する市当局や企業の攻撃を描いたビデオもある。
このプロジェクトの経過や地域特有の背景といったことを超えて、何がドクメンタに伝えられるのでしょうか?
シェーファー:公共空間ということの新しい定義、これはどこにでも適用可能なものだ。カッセルの会場で、我々の展示はアーバニズムという重点テーマに組み入れられている。さらに、今年のドクメンタには芸術家の集団作品が多数展示されている。そのうち、例えば、ニューデリーから出品されているRaqsという作品は、都市における土地占拠を扱ったものだ。ここにつながる点がある。もちろんまだ始まりにすぎないけどね。
シュテーヴェサンド:異議申し立て的芸術は世界中に存在します。Park Fictionは、政治と芸術と社会性の交点におけるプロジェクトです。そこからの結論として挙げることができるのは、政治的あるいは異議申し立て的な芸術は、全く異なった人々の知識、経験、活動を平等に交換し、重ね合わせることから生まれるということに関する、新しい理解です。Park Fictionはその実例なのです。
注:
ザビーネ・シュテーブサンド(Sabine Stövesand):Sozialpädagogin。社会文化センターGWAザンクトパウリ所長。ハンブルク州社会文化連盟理事。大学で社会文化運動関係の非常勤講師もしている。Park fictionの市民運動的側面を代表する人物といえる。
クリストーフ・シェーファー(Christoph Schäfer):芸術家。1995年頃から運動に加わってきたが、ParkFictionがハンブルク市文化庁の振興プログラム「公共空間に芸術を」の対象事業として認定されるに伴い、それを担当する芸術家として委嘱される。Park fictionの芸術運動的側面を代表する人物といえる。
バウヴァーゲン広場Bauwagenplatz:ドイツの大都市に存在する、ミニバスタイプの中古自動車を住居にする青年たちが空き地を占拠して形成したアナーキーな群居空間。Bauwagenとは建築現場で作業員が寝泊できるように作られた車両のこと。その中古車を非常に安価で購入し、改修してボヘミアン的に移動生活をする青年たちの集団キャンプ場として形成されたので、このような名称がつけられた。
粗大ゴミ集積場のような雰囲気の場所に数十名の異様な風体で異臭を発する人々が生活しており、日本で言えばホームレスのダンボールハウス集落(上野公園内)に類似した雰囲気である。ただし、住人たちは自己の生き方を肯定的にとらえており、外部社会に対しても積極的に自己主張(左翼的・アナーキスト的傾向)することが多い。当然近隣住民からは歓迎されないことが多く、不法占拠・不衛生などを理由に当局から排除されることもある。極右の襲撃対象ともなることもある。
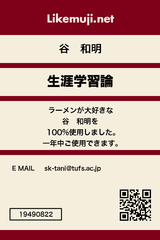

コメントをかく