最終更新:
 otonjji256 2022年06月21日(火) 13:40:08履歴
otonjji256 2022年06月21日(火) 13:40:08履歴
ローズ・コーラ? | ||
Rózsa&Stephen Cola Company ロージャ&スティーヴン・コーラ カンパニー | ||
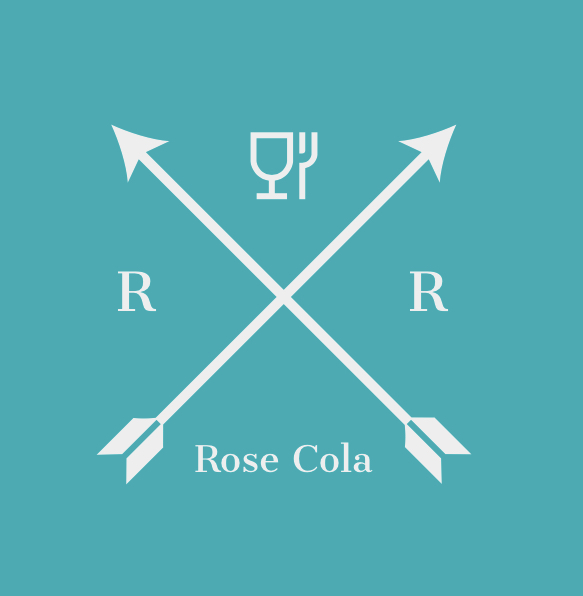 | ||
|---|---|---|
| 詳細情報 | ||
| 種類 | 株式会社 | |
| 業種 | 飲料・食品・薬品 | |
| 設立 | 1902年 | |
| 代表 | ジュリアン・ハートレイ | |
| 本社所在地 | ニスカリマ共和国モルベラント・アム・ハイデン | |
| 資本金 | 8億8000万ドル相当 | |
| 社員数 | 7万3,000人 | |
| 関連会社 | ガレノスグループ(傘下の製薬会社) | |
| 筆頭株主 | エリス・シャーンドル=ウェルト 4.03% | |
| 備考 | 世界有数の清涼飲料水メーカー | |
1905年にニスカリマ出身の薬学者ロージャ・シャーンドル(1885-1912)と、スカセバリアル出身のスティーブン・ウェルト(1880-1958)の2人がコンビを組んで創業した清涼飲料水メーカー。看板商品の「ローズ・コーラ」は世界有数のシェアを誇り、殆どの国のコンビニや自動販売機で売られている。
デニエスタやスカセバリアルなどでは、その支社法人の株価が国の平均株価を測る指標銘柄の一つになっているなど、その影響力は絶大である。
デニエスタやスカセバリアルなどでは、その支社法人の株価が国の平均株価を測る指標銘柄の一つになっているなど、その影響力は絶大である。
創業者の1人であるロージャ・シャーンドルは1885年にニスカリマ帝国(現ニスカリマ共和国)アイリス地方ロイデンの伯爵家に生を受けた。シャーンドル伯爵家は70万エーカーの土地を所有する大地主であり、数多くの学者や政治家を輩出する名家でもあった。
ロージャ本人も恵まれた環境下で優れた才能を開花させ、1897年に国内の最高学府モルベラント帝国大学(現モルベラント大学)で薬学の学位を取得し、1900年には15歳にしてスカセバリアル条約機構のサニエル大学への国費留学生にも選ばれ、同地でPh.Dの資格を取得するなど若くして多くの業績を挙げていた。
一方もう1人の創業者であるスティーヴン・ウェルトは、1880年にソルティア連邦の医者の家に生まれ、哲学者を志してサニエル大学の文学部哲学研究科に進学(当時サニエル大学は理系教育に注力しており、極めて志願者の少ない哲学研究科は廃止の危機にあった)。大学での彼は平々凡々を絵に描いた様な青年であり、彼とロージャの終生の友人であったショーン・ダフネル(1880-1968)によれば、「とても天才には見えなかった」という。
そして、この2人は(回想録によれば)1900年、大学の食堂で運命の出会いを果たすことになる。
ロージャ本人も恵まれた環境下で優れた才能を開花させ、1897年に国内の最高学府モルベラント帝国大学(現モルベラント大学)で薬学の学位を取得し、1900年には15歳にしてスカセバリアル条約機構のサニエル大学への国費留学生にも選ばれ、同地でPh.Dの資格を取得するなど若くして多くの業績を挙げていた。
一方もう1人の創業者であるスティーヴン・ウェルトは、1880年にソルティア連邦の医者の家に生まれ、哲学者を志してサニエル大学の文学部哲学研究科に進学(当時サニエル大学は理系教育に注力しており、極めて志願者の少ない哲学研究科は廃止の危機にあった)。大学での彼は平々凡々を絵に描いた様な青年であり、彼とロージャの終生の友人であったショーン・ダフネル(1880-1968)によれば、「とても天才には見えなかった」という。
そして、この2人は(回想録によれば)1900年、大学の食堂で運命の出会いを果たすことになる。
1900年のある日、ウェルトが1人大学の食堂で定食を食べていると、正面に余りにもそぐわない明るい茶髪の少女が座った。彼女はセットについてきたジュースを一口飲むや顔を顰め、「ニスカリマの方言の中で最も卑俗な罵倒(ウェルト談)」を口にしたと言う。その少女こそがロージャ本人であった。
この時ウェルトは、「彼女が貶していたのが、私の好きなジュースであったので、つい大いに腹を立てて」ロージャに話しかけ、押し問答の果てに大喧嘩に及んだと言う。この最悪な出会いの際にロージャは、
「こんな泥水よりも、もっと美味いものを飲ませてやる!」
と言い放ち、これがローズ・コーラのレシピ開発のきっかけになったと言われている。
そして回想録によれば、彼女が最初のレシピを考案したのが1900年の6月、そしてそれをウェルトが実際に飲み物の形にしたのは8月の頃だったとされる。
初めてそれを飲んだ時の思い出を、彼は思い出深くこう綴っている。
弾ける泡、苦味と刺激の波に次いでやってくる甘味、そしてすっと鼻を抜ける爽やかな香り。何においても私が経験したことの無い美味さであった。そして、言葉の出ない様子の私に対して、ロージャは自慢げに言い放ったのだ
「これが本当のジュースというものよ」
これによって意気投合した2人は、開発した飲み物を製品化する試みを開始し、1902年にシャーンドル伯爵の協力の下最初の製品を開発した。
これはロージャとスティーブンの名前をもじって「ローズ」と名付けられ、そこに原料として使用されていたザンジ?原産のコーラの実を付け加えて「ローズ・コーラ」と命名された。そして、2人は学業の傍らローズ・コーラ販売の事業を始め、伯爵家の知名度にあやかって最初の会社「シャーンドル飲料社」を創業する。
この時ウェルトは、「彼女が貶していたのが、私の好きなジュースであったので、つい大いに腹を立てて」ロージャに話しかけ、押し問答の果てに大喧嘩に及んだと言う。この最悪な出会いの際にロージャは、
「こんな泥水よりも、もっと美味いものを飲ませてやる!」
と言い放ち、これがローズ・コーラのレシピ開発のきっかけになったと言われている。
そして回想録によれば、彼女が最初のレシピを考案したのが1900年の6月、そしてそれをウェルトが実際に飲み物の形にしたのは8月の頃だったとされる。
初めてそれを飲んだ時の思い出を、彼は思い出深くこう綴っている。
弾ける泡、苦味と刺激の波に次いでやってくる甘味、そしてすっと鼻を抜ける爽やかな香り。何においても私が経験したことの無い美味さであった。そして、言葉の出ない様子の私に対して、ロージャは自慢げに言い放ったのだ
「これが本当のジュースというものよ」
これによって意気投合した2人は、開発した飲み物を製品化する試みを開始し、1902年にシャーンドル伯爵の協力の下最初の製品を開発した。
これはロージャとスティーブンの名前をもじって「ローズ」と名付けられ、そこに原料として使用されていたザンジ?原産のコーラの実を付け加えて「ローズ・コーラ」と命名された。そして、2人は学業の傍らローズ・コーラ販売の事業を始め、伯爵家の知名度にあやかって最初の会社「シャーンドル飲料社」を創業する。
しかし、当初この珍奇な飲料水は全くと言っていい程売れず、生産とそれに伴う収益も極めて小規模だった。ロージャ本人が残した数少ない記録によれば、その収益は「私の一月のお小遣いにも劣る」程度しか無く、地元の好事家が偶に買って行く程度の物であったと言う。
また、ロージャ本人もあくまで学業の片手間と考えていた節があり、生産と販売は彼女の大学が休みの時期に限られていた。他方ウェルトは販路拡大の為に尽力していたが、それが元で単位の一部を修得できず、本末転倒であると彼女に叱責される結果となっている。
しかし、1904年に彼女が博士号を取得し、局所麻酔薬リドカインの開発によって名声を博すと流れが変わり始める。大きな麻酔薬効を小さな副作用で得られるリドカインは忽ち世界の医療現場に浸透し、その特許から莫大な収益を得る一方、その開発者であるロージャ自身も注目を浴びることとなる。
これを利用したウェルトは、ローズ・コーラをある種の医薬品であるとして宣伝活動を行い、薬局を中心に販売させることでその知名度を大きく押し上げることに成功した。当時のキャッチコピーは、薬学者としてのロージャのお墨付きを全面に押し出したもので、これを目にした多くの人が安さを目当てに購入し、次いで味に惹かれてリピート購入したと言われている。
尤も、ロージャ本人はこの販売手法に少々嫌悪感を抱いていた様で、ダフネルに対して「詐欺師の手法は好かない」と愚痴をこぼしていた(ダフネルの著書より)。
しかし、いずれにしても彼女の活躍が世界に知られるにつれてローズ・コーラの知名度も上がり、1907年(彼女が薬学者としての優れた功績により、下サニエル共同体から表彰を受けた年)にはニスカリマ指折りの新興企業に成長していた。そしてウェルトは更に販路を拡大するべく、社名を「ロージャ&スティーヴン・コーラ カンパニー」に変更し、1908年には帝国首都に本社ビルを構えて全国的な展開に乗り出した。
また、ロージャ本人もあくまで学業の片手間と考えていた節があり、生産と販売は彼女の大学が休みの時期に限られていた。他方ウェルトは販路拡大の為に尽力していたが、それが元で単位の一部を修得できず、本末転倒であると彼女に叱責される結果となっている。
しかし、1904年に彼女が博士号を取得し、局所麻酔薬リドカインの開発によって名声を博すと流れが変わり始める。大きな麻酔薬効を小さな副作用で得られるリドカインは忽ち世界の医療現場に浸透し、その特許から莫大な収益を得る一方、その開発者であるロージャ自身も注目を浴びることとなる。
これを利用したウェルトは、ローズ・コーラをある種の医薬品であるとして宣伝活動を行い、薬局を中心に販売させることでその知名度を大きく押し上げることに成功した。当時のキャッチコピーは、薬学者としてのロージャのお墨付きを全面に押し出したもので、これを目にした多くの人が安さを目当てに購入し、次いで味に惹かれてリピート購入したと言われている。
尤も、ロージャ本人はこの販売手法に少々嫌悪感を抱いていた様で、ダフネルに対して「詐欺師の手法は好かない」と愚痴をこぼしていた(ダフネルの著書より)。
しかし、いずれにしても彼女の活躍が世界に知られるにつれてローズ・コーラの知名度も上がり、1907年(彼女が薬学者としての優れた功績により、下サニエル共同体から表彰を受けた年)にはニスカリマ指折りの新興企業に成長していた。そしてウェルトは更に販路を拡大するべく、社名を「ロージャ&スティーヴン・コーラ カンパニー」に変更し、1908年には帝国首都に本社ビルを構えて全国的な展開に乗り出した。
1908年-1910年にかけて、ロージャ&スティーヴン・コーラ カンパニーは凄まじい勢いで成長を遂げていった。製品は既にニスカリマを代表するヒット商品となり、一過性のブームの域を超えた名物商品として定着しつつあった。
また、折しも帝国陸軍がロージャの開発した麻酔薬や鎮静剤を救急医療用薬剤に採用したことから、軍の関係者を中心に評判がさらに広がって行き、1910年には正式に軍の駐屯地や基地の酒保において取扱が始まった。
この頃のキャッチコピーは、「いつでもどこでも 5ペニーで」であり、当時の帝国が発行していた小銅貨(ペニーのあだ名がついていた)5枚で何処ででも購入ができると宣伝されていた。
ウェルトは会社の顔兼共同社長として、ロージャに代わって海外を含めて各地を回り、精力的な営業と宣伝活動で売り上げを順調に伸ばしていき、1911年には経済誌に特集が組まれるまでに名声を得た。また、前後する1908年にはパートナーであるロージャとの間に第一子フェレンツ・シャーンドル=ウェルト(1908-1986)、1910年には第二子エリス・シャーンドル=ウェルト(1910-)を儲けるなど私生活でも幸福の極みにあった。
この頃2人は法律上の結婚こそしていなかったが、内外からは事実上の夫婦と見做されており、2人の子供は婚外子ながら正式な子供として扱われ、特別にシャーンドル=ウェルトの複合姓を名乗った。(結婚しなかった理由については様々に推定されているが、理解者であった父伯爵の跡を継いだロージャの長兄が反対したという説が濃厚である)
しかし、この幸福は1912年にロージャが病魔に倒れた事で唐突に終わりを迎えてしまう。
彼女は昔から体が弱かった為幾度と無く病に冒されてきたが、会社創業後は続く激務と子育てによって体力の限界を迎え、それによって結核を発症してしまった。そして、1912年の春に27歳の若さでこの世を去ってしまうのである。
ロージャは死に際して、ウェルトに対して幾つかの助言を遺したとされる。それは主に会社経営の方針についてで、「決して創業者一族が強権を持たぬ様にすること」、「家族と安定を第一に考え、賭けはしないこと」、「社長や富裕の座にこだわらない事」の三箇条であったと言われる。(ウェルト、ダフネル両者の回想録に同じ様な内容が記されている)
そして、ロージャが亡くなった後、ウェルトは今までの様な拡大路線を一度改め、獲得したシェアの維持と新商品の開発に専心し、また彼女の特許権を利用して利益を上げていた製薬会社ガレノスグループの株式を購入するなど、安定思考を強めていった。(後に同グループは傘下入りする)
また、折しも帝国陸軍がロージャの開発した麻酔薬や鎮静剤を救急医療用薬剤に採用したことから、軍の関係者を中心に評判がさらに広がって行き、1910年には正式に軍の駐屯地や基地の酒保において取扱が始まった。
この頃のキャッチコピーは、「いつでもどこでも 5ペニーで」であり、当時の帝国が発行していた小銅貨(ペニーのあだ名がついていた)5枚で何処ででも購入ができると宣伝されていた。
ウェルトは会社の顔兼共同社長として、ロージャに代わって海外を含めて各地を回り、精力的な営業と宣伝活動で売り上げを順調に伸ばしていき、1911年には経済誌に特集が組まれるまでに名声を得た。また、前後する1908年にはパートナーであるロージャとの間に第一子フェレンツ・シャーンドル=ウェルト(1908-1986)、1910年には第二子エリス・シャーンドル=ウェルト(1910-)を儲けるなど私生活でも幸福の極みにあった。
この頃2人は法律上の結婚こそしていなかったが、内外からは事実上の夫婦と見做されており、2人の子供は婚外子ながら正式な子供として扱われ、特別にシャーンドル=ウェルトの複合姓を名乗った。(結婚しなかった理由については様々に推定されているが、理解者であった父伯爵の跡を継いだロージャの長兄が反対したという説が濃厚である)
しかし、この幸福は1912年にロージャが病魔に倒れた事で唐突に終わりを迎えてしまう。
彼女は昔から体が弱かった為幾度と無く病に冒されてきたが、会社創業後は続く激務と子育てによって体力の限界を迎え、それによって結核を発症してしまった。そして、1912年の春に27歳の若さでこの世を去ってしまうのである。
ロージャは死に際して、ウェルトに対して幾つかの助言を遺したとされる。それは主に会社経営の方針についてで、「決して創業者一族が強権を持たぬ様にすること」、「家族と安定を第一に考え、賭けはしないこと」、「社長や富裕の座にこだわらない事」の三箇条であったと言われる。(ウェルト、ダフネル両者の回想録に同じ様な内容が記されている)
そして、ロージャが亡くなった後、ウェルトは今までの様な拡大路線を一度改め、獲得したシェアの維持と新商品の開発に専心し、また彼女の特許権を利用して利益を上げていた製薬会社ガレノスグループの株式を購入するなど、安定思考を強めていった。(後に同グループは傘下入りする)
1914年、ニスカリマでの絶対的優位性を確立したウェルトは本格的な海外進出に乗り出し、初の海外法人である「R&SC Co.スカセバリアル」を設立。既に設置していた海外支社も順次法人化し、巨大な連結企業グループの構築にかかった。
以降会社は多国籍企業として順調に発展を遂げて行き、「ローズ・コーラ」の知名度は世界的なものとなった。
しかし1916年以降、国際緊張の高まりに伴って各国がブロック経済を敷き始めると、ローズ・コーラの帝国の成長は段々と鈍化していき、右肩上がりだった収益は横線を描き始める。これを受けたウェルトは軍隊向けの製品に活路を見出し、自社を軍隊に品物を納入する「御用会社」とする様に運動を行って成功、ニスカリマ帝国軍を中心に友好国一円の軍隊に対して手広く製品を販売する様になった。
この頃既にロージャの開発した新薬の特許は失効又は現地政府の方針で強引に取り上げられるなどして殆ど利益を上げてはいなかったが、それでもその名声は大きく残っており、軍隊はウェルトの会社を極めてスムーズに受け入れた。
軍隊相手の商売は大戦中会社に安定的な収入を提供し、失業者を減らすのに一役買うと共に、1920年の敗戦とその後の戦後復興に「ローズ・コーラ」が大きな影響を与える下地ともなった。帝政崩壊後の混乱の中にあってもウェルトと彼の会社の社員たちは仕事を失うこと無く、また各国向けの輸出は途切れることはなかったのである。
以降会社は多国籍企業として順調に発展を遂げて行き、「ローズ・コーラ」の知名度は世界的なものとなった。
しかし1916年以降、国際緊張の高まりに伴って各国がブロック経済を敷き始めると、ローズ・コーラの帝国の成長は段々と鈍化していき、右肩上がりだった収益は横線を描き始める。これを受けたウェルトは軍隊向けの製品に活路を見出し、自社を軍隊に品物を納入する「御用会社」とする様に運動を行って成功、ニスカリマ帝国軍を中心に友好国一円の軍隊に対して手広く製品を販売する様になった。
この頃既にロージャの開発した新薬の特許は失効又は現地政府の方針で強引に取り上げられるなどして殆ど利益を上げてはいなかったが、それでもその名声は大きく残っており、軍隊はウェルトの会社を極めてスムーズに受け入れた。
軍隊相手の商売は大戦中会社に安定的な収入を提供し、失業者を減らすのに一役買うと共に、1920年の敗戦とその後の戦後復興に「ローズ・コーラ」が大きな影響を与える下地ともなった。帝政崩壊後の混乱の中にあってもウェルトと彼の会社の社員たちは仕事を失うこと無く、また各国向けの輸出は途切れることはなかったのである。
ニスカリマ第一共和制から第二共和制の時期においても、ロージャ&スティーヴン・コーラ カンパニーは成長と膨張を続けていった。ウェルトは戦後の秩序構築の中で様々に活躍し、社会主義諸国に対して新たな市場を開拓すると共に、政府からは自社を経由した外貨収入をちらつかせて支援と商売上の便宜を引き出すなど辣腕を振るった。
これによって「ローズ・コーラ」は社会主義圏までその販路を広げることとなり、名実共に国際企業として世界経済を牽引する大企業へと成長したのである。
この頃同社が占める清涼飲料水のシェアは世界でも指折りの物となり、「飲めない国は無い」とまで言われる程であった。
1952年、創業以来会社を支えてきたウェルトが社長を引退し、学術財団ロージャ・シャーンドル記念財団の理事長に退くと、第2代社長にはショーン・ダフネルが就任した。ダフネルはウェルト程の光彩を放つ大経営者というわけではなかったが、リスクを避けた堅実な経営によって会社を発展させると共に、積極的な製品開発によって新たなヒット商品を世に送り出して行った。
1956年には、ウェルトと共にニスカリマ共和国から勲章を授与されている。(ロージャが1910年に授与されたもの)
1958年にスティーブン・ウェルトが永眠すると、その功労を讃えてニスカリマとスカセバリアルの両国で追悼式典が行われ、サニエル大学の構内にはロージャ・シャーンドルの隣に記念プレートが設置された。(ウェルトは終世サニエル大学の寄付者の1人であった)
1962年にダフネル社長が退任すると、後継者の候補に創業者2人の子供であるフェレンツ・シャーンドル=ウェルトが上がったが、前述の遺言によって立ち消えとなり、ダフネルの信任を受けたゴトロス連邦出身のフレゼリク・シューマンが就任した。(フェレンツは名誉相談役、後に社主に就任し、会社のシンボルとなる)
シューマンは高度に発展していく社会に合わせて社内組織の改革に取り組み、CEOといった現代的な役職の整備に努めた。
また、投資家向けの新たなビジネスプランを数多く考案すると共に、会社を他分野にまたがるコングロマリットに再編することを目指した。
彼の下で行われた事業の中で、特に著名なのは自然保護財団、病院、自動販売機の生産で、これらは現在でも同社が持つ幾つかの顔の一つとして認知されている。
1968年にショーン・ダフネル、1986年にフェレンツ・シャーンドル=ウェルト永眠。社主の地位はエリスが引き継いだ。
1980年、現社長のジュリアン・ハートレイ(ゴトロス出身)がCEOに就任。彼は精力的にビジネスを展開し、シェアのさらなる拡大を目指してさまざまな計画を打ち出している。
これによって「ローズ・コーラ」は社会主義圏までその販路を広げることとなり、名実共に国際企業として世界経済を牽引する大企業へと成長したのである。
この頃同社が占める清涼飲料水のシェアは世界でも指折りの物となり、「飲めない国は無い」とまで言われる程であった。
1952年、創業以来会社を支えてきたウェルトが社長を引退し、学術財団ロージャ・シャーンドル記念財団の理事長に退くと、第2代社長にはショーン・ダフネルが就任した。ダフネルはウェルト程の光彩を放つ大経営者というわけではなかったが、リスクを避けた堅実な経営によって会社を発展させると共に、積極的な製品開発によって新たなヒット商品を世に送り出して行った。
1956年には、ウェルトと共にニスカリマ共和国から勲章を授与されている。(ロージャが1910年に授与されたもの)
1958年にスティーブン・ウェルトが永眠すると、その功労を讃えてニスカリマとスカセバリアルの両国で追悼式典が行われ、サニエル大学の構内にはロージャ・シャーンドルの隣に記念プレートが設置された。(ウェルトは終世サニエル大学の寄付者の1人であった)
1962年にダフネル社長が退任すると、後継者の候補に創業者2人の子供であるフェレンツ・シャーンドル=ウェルトが上がったが、前述の遺言によって立ち消えとなり、ダフネルの信任を受けたゴトロス連邦出身のフレゼリク・シューマンが就任した。(フェレンツは名誉相談役、後に社主に就任し、会社のシンボルとなる)
シューマンは高度に発展していく社会に合わせて社内組織の改革に取り組み、CEOといった現代的な役職の整備に努めた。
また、投資家向けの新たなビジネスプランを数多く考案すると共に、会社を他分野にまたがるコングロマリットに再編することを目指した。
彼の下で行われた事業の中で、特に著名なのは自然保護財団、病院、自動販売機の生産で、これらは現在でも同社が持つ幾つかの顔の一つとして認知されている。
1968年にショーン・ダフネル、1986年にフェレンツ・シャーンドル=ウェルト永眠。社主の地位はエリスが引き継いだ。
1980年、現社長のジュリアン・ハートレイ(ゴトロス出身)がCEOに就任。彼は精力的にビジネスを展開し、シェアのさらなる拡大を目指してさまざまな計画を打ち出している。
1.イシュトヴァーン・シャーンドル伯爵(名誉社主。ロージャの父)
2.フェレンツ・シャーンドル=ウェルト(社主。名誉相談役)
3.エリス・シャーンドル=ウェルト(社主)
4.ノーマン・シャーンドル=ウェルト(フェレンツの息子。名誉相談役)
2.フェレンツ・シャーンドル=ウェルト(社主。名誉相談役)
3.エリス・シャーンドル=ウェルト(社主)
4.ノーマン・シャーンドル=ウェルト(フェレンツの息子。名誉相談役)
タグ













コメントをかく