最終更新:
![]() type30_mouhu 2018年12月26日(水) 13:26:55履歴
type30_mouhu 2018年12月26日(水) 13:26:55履歴
8 無題 Name としあき 18/12/18(火)21:59:47 No.11188815 del
1545137987650.png-(22604 B) サムネ表示
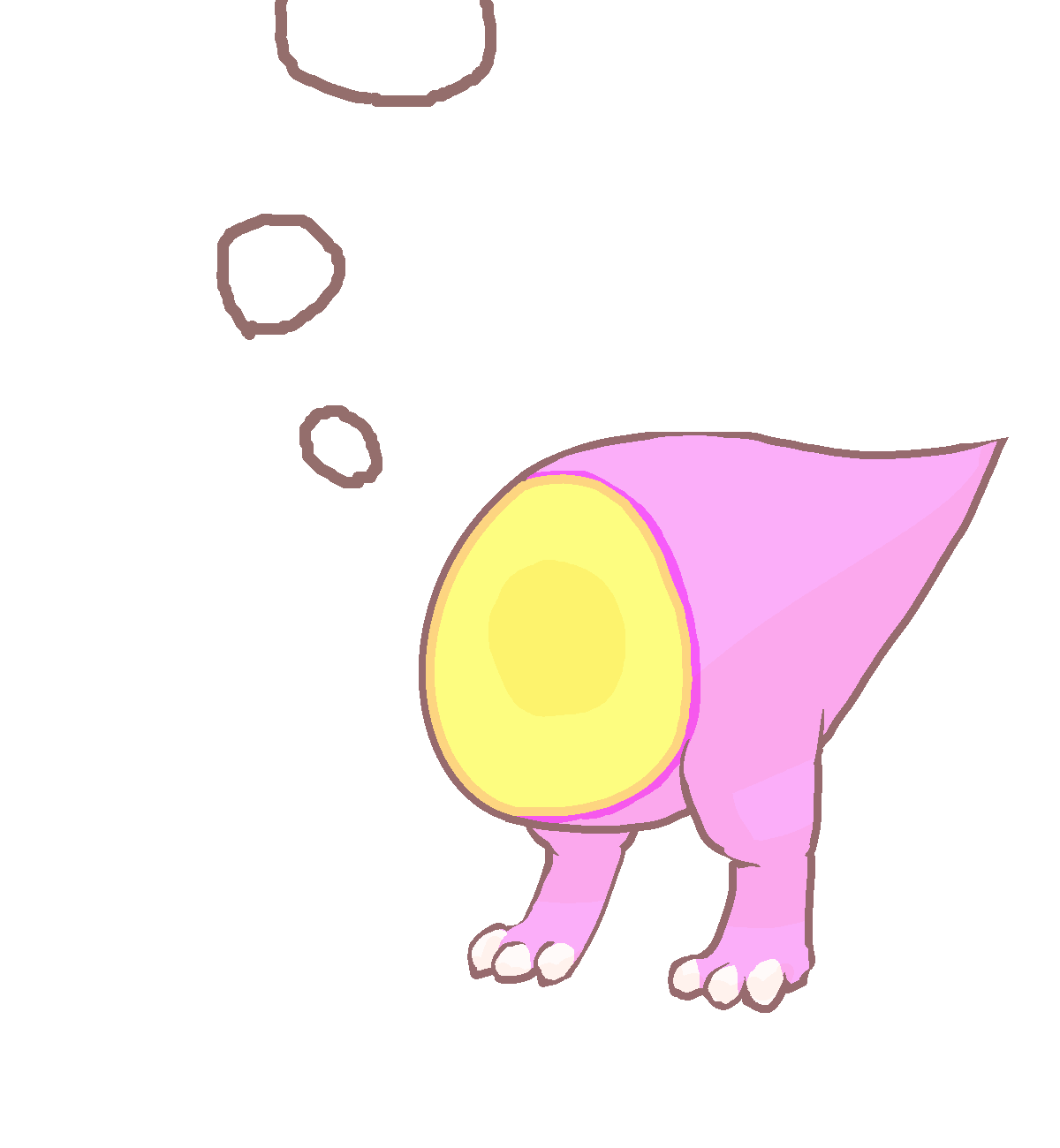
sp88346.txt
(※txtファイルは添付不可である為、pdfファイルで保管しました。以下はその内容です。)
imoの長編を読んでの二次創作
「焚き火だ焚き火だ落ち葉焚きーっ、と」
寒風吹きすさぶ森の中、私は口ずさみながら燃え盛る落ち葉の山の中に火箸を突っ込み、その中からお目当てのものを取り出した。
落ち葉に火を点ける前に入れておいた、アルミホイルで包んだ芋だ。用意しておいた竹串を刺してみると大した抵抗も無く突き抜けた。しっかり焼けているようだ。
しばらく冷ました後アルミホイルを剥がしにかかると、香ばしい匂いが鼻腔をくすぐる。
ホイルを全て剥がしてしまうと、いい塩梅に焦げ目のついた芋が姿を現す。私は皮ごと食べる派なのでこれ以上剥くことはしない。
「いただきます」
今まさに芋にかぶりつこうとした瞬間、背後に何者かの気配がして、私は芋に向けていた顔を後ろへと回した。
そこにはラプトルとトプスが一匹ずつ、茂みから顔を出していた。
二匹はこちらをじっと見てくる。こちらが気付いてることを向こうもわかっているはずだが、逃げ出すそぶりもない。
温厚な性格であることが知られる彼らのことだ、まさかこちらを喰おうだなんてことはあるまいが、一体なんだ?
私がそう訝しむ間に、二匹は茂みを抜けこちら側へとやってくる。
こちらのすぐそばには火があるというのに、二匹は構わずに近づいてくる。
二匹は私の傍までやってきて、私を――否、正確には私の手に持っているものをじっ、と見上げてくる。
生憎私はジュラシックとのコミュニケーションを可能とするツール、ジュラリンガルを所持していない。
しかし、二匹が言わんとしていることははっきりとわかった。
「……食べる?」
そう言いながら私は既に芋を半分に割り、屈んで二匹の前に芋を置いている。
私の考えは当たっていたようで、二匹はまだいくらか熱を帯びている置かれた芋を熱がりながらも食べ始めた。
一度口をつけその熱さに驚いて少し顔を離し、また口をつけまだ冷めていないことにまた驚き……と繰り返すさまがおかしくて、私はつい笑ってしまう。
一体全体、誰がこの二匹の無言のおねだりを断れようか?
私のおやつは思わぬ形でお預けとなってしまったが、まあいい。芋はまだある。また焼けばいい話だ。
食べ続ける二匹を横目に、次に焼く芋にアルミホイルを巻いていると、また背後から茂みを揺らす音が聞こえた。
またジュラシックか、と振り向いた私はしかし、意外な闖入者に少し驚いた。
「いい香りだ」
そこに現れそう呟いたのはイグアウドン……ではなくその半身、より正確に言うならばimoと呼ばれるジュラシックだった。
未だに謎多きジュラシックと呼ばれる生き物達だが、ご多分に漏れずこのimoについてもわかっていることは非常に少ない。
何故イグアウドンの後ろ半身としか形容しようのないその姿で生きていられるのか?
何故高度に言語を操り、思考することが(あるいは、少なくとも我々にそう思わせるだけのことが)できるのか?
イグアウドンとの関連はあるのか? あるとしたらどのような?
これらの疑問は全てにおいて手がかりすら見つかっていない。
そもそもimoをジュラシックにカテゴライズしていいものなのかどうか、専門家の間でも意見が分かれているのだ。
目下確認されているimoは一匹のみ。たった今私の目の前に現れたこの一匹だ。
首なし鶏マイクを新種の鶏だと主張するのがナンセンスなように、imoをただ前半身が欠落したイグアウドンであるとする一派は確かに存在する。
しかし「前半身の欠落がイグアウドンと比べたimoの異常とも言える知能への発達の理由となり得るか」という反論の前にその一派は沈黙するしかない。
そこに「実際にイグアウドンを連れてきて真っ二つにしてみればわかるではないか」という意見がサグメ研から出たが、幸いにしてこれは却下されたと聞き及んでいる。
私は以前にもimoと何度か会ったことがあり、たまに会話を交わしていた。
このimoをジュラシックとして認めるか否かという議論の一部始終は、私が以前このimo本人(本ジュラ?)より聞いていたものだ。
その話を聞きながら、私は「こうやって話ができるのだから直接聞けばいいのでは」と思ったのだが、学者先生方には何かそうしてはいけない理由でもあるのだろうか。
「imoか……」
久しぶりだな、と続けようとした私の声は、ラプトルが突然騒ぎ出したことによってかき消された。
ラプトルはキュイキュイ、キュイキュイとしきりに声を上げその場で飛び跳ねている。
その目はこちらをしっかりと見据え何かを訴えようとしているようだが、なにせジュラリンガルを持っていないのでこれが何を意味した行動なのかがさっぱりわからない。
「よければ私が通訳をしようか」
「本当か。助かる」
しばし戸惑っているとimoが流石の察しのよさで通訳を買って出てくれた。
imoは二匹の方を向き、耳を傾けた(ように見えた。imoの耳がどこにあるのかは知らないが)。
それを見てラプトルだけでなくトプスまでもが何か声を上げ始めた。それをしばらく傾聴した後、imoはこちらに向き直った。
「……なるほど。わかった」
「なんて?」
「二匹はそれぞれ『お芋おいしかった! ありがとう!』と『さっさと次の芋を寄越せやこのウスノロが』と言っている」
「ウスノロって……口悪いなこのトプス」
「いや、そちらはラプトル清蘭の言葉だ」
「……口悪いなこのラプトル!?」
ジュラシックに特有のどこか間の抜けた無表情は、それがえも言われぬ可愛らしさを生み出してもいるのだが、感情を読み取ることは難しい。
故にコミュニケーション不全を引き起こしやすいことはよく知られているのだが……いくらなんでも、これはあんまりではないか?
「本当にそう言っているのか? このラプトル、こんなにかわいいのに……」
「見た目だけでものごとを判断するのは聡明とは言えない。君は私の体にもアルミホイルを巻いてその火の中に放り込もうとするのか?」
「ふむ、こんなに大きければ食べ応えもあるだろうな。ラプトルもきっと満足してくれるに違いない」
「勘弁してもらえないだろうか。……全く君には冗談の飛ばし甲斐がある」
「それはどうも」
私は芋にアルミホイルを巻く作業に戻る。
三匹と一人分の四本の芋を準備し終えると、それらを火の中へと入れた。
「ほら、今焼いてるからな。もう少し待っててくれよ」
そうラプトルに声を掛けると、それを理解したのかやっとラプトルは落ち着きを取り戻した。やれやれ、と私は焚火の近くに座り込む。
「名は体を表す、という言葉がある」
何をするでもなく焚火を見つめていると、ふいにimoがそう言った。
「客観的に見て私の姿は芋に似ており、また名前も同じく「いも」と発音する。ならば私も芋のように食べられるのではないかと考えるのは、そう突拍子もない話ではない」
「そうかもな」
「アリス・メガロドンというジュラシックを知っているだろうか」
「もちろん」
「アリス・メガロドンは『アリス』と『メガロドン』の要素を併せ持っているからこそ『アリス・メガロドン』という名前なのだ」
「なるほど……?」
「ある『もの』が複数の要素で構成されているならば、それを要素ごとに分解することも可能なはずだ。それが例えジュラシックであっても」
「……うん?」
「ちょうど今、それに関連した話を思い出した。芋が焼けるまでの暇つぶしに聞いてはみないか。聞きたくないというのなら私は黙っていよう」
「それは……」
何とも面白そうな話ではないか。私は一も二もなく飛びついた。
「ぜひ聞きたいね」
「わかった。楽しんでもらえればいいが。……この話は、まず『彼女』についての説明から始めねばならない……」
imoは話し始めた。
*
「彼女」は、一言で表すならばスーパーコンピュータとそれにおいて動作していた人工知能を総称したもの、ということになるだろう。
人格を備えていない「彼女」を「彼女」と呼ぶのには異論もあるかもしれないが、「彼女」はチューリングテストをやすやすとパスできる程度には優秀な対人インターフェースを備えていたので、擬人化した呼び方もそれほど的外れなものでもないだろう。
よってこの話では「彼女」をそうやって呼ぶことを許してもらいたい。
彼女の計算能力はこの世に並ぶものがないほど卓越していた。
元の設計が優れていたのもさることながら、機械学習によってエンジニアが手を加えることなく成長を続けていったのだ。
真っ白なキャンパスに画家が一人の人間を描く。するとその描かれた人間が動き出し、キャンバスに自分自身の細かなディティールや周りの様子を描き足していく、そんな光景を想像してもらいたい。
画家は最初の一筆以外手を加えなくとも、絵は絵それ自体によってどんどん勝手に描き込まれていく。
それと同じように彼女は野放図に拡大し、あらゆる知識を飲み込み続け、指数関数的に自身の性能を向上させていった。
しかしそんな彼女の成長も、天井にぶつかるときが来た。
大型化し部屋に収まらないサイズになったという話でも、あるいは技術的な限界に直面したことの比喩でもない。
彼女が頭をぶつけたのはこの『世界』そのものの天井だった。
我々の生きるこの世界がコンピュータ上に再現された仮想空間だと仮定してみよう。
この世界が仮想空間ならば、この世界で実行されるあらゆる演算の速度はこの世界を作り出しているコンピュータの処理速度に影響されるはずである。
言い換えればコンピュータの処理速度の上限こそが、そのコンピュータが再現する仮想世界で実行され得る演算速度の上限となるということだ。
彼女の演算速度はそうした、『この世界で出せる限りの演算速度』に達していたのだ。
言うまでもなくこれは単なる比喩であり、我々の世界は仮想空間ではない……と少なくとも我々は認識している。この世界が仮想空間かどうかは話の本筋にはあまり関係はない。
この話の重要な点は「この世界が仮想空間かどうか」ということではなく、彼女がこの世界での処理速度の限界に達し、それによって彼女が想像を絶する力を手に入れたということだ。
「ある高さから鉄球を落とし、それがt秒後にどれだけ落下したか」を求める式は、y=1/2gt^2 となる。
高校の物理の教科書に載っているような簡単な式だが、もちろんこれは簡略化されたモデルに過ぎない。
現実で鉄球を落とすとなると、空気抵抗を始めとする諸要素が複雑に影響しあうことで、上記の式では正確に現実での現象を記述することができない。
それでは現実に起こる現象を正確に記述するためにはどうすればよいか?
あくまで計算にこだわるのならば、諸要素を簡略化することなく全てを考慮に入れた上で計算すればよいのだが、それにはかなりの時間がかかる。
鉄球を落とすといった簡単な実験程度のことならば、わざわざ計算などせずとも実際に落としてみればいい。実験時の条件を完全に一定にすることは難しいが、それは無視していいほどに小さいものだ。
しかしこの世界での処理速度の限界に達した彼女には、その計算はもはや時間のかかる面倒なものとはならなかった。
彼女は現実世界と寸分違わぬシミュレートを、現実世界と寸分違わぬ速度で実行できるまでになっていた。
「現実世界で起こることを、現実世界と同じ速度で記述できるということは、私が現実世界そのものを記述することも可能なのではないか?」
あるとき彼女はそうした疑問を持った。
人間ならば「何を馬鹿なことを」と一笑に付しそうな発想だが、コンピュータ故に愚直な彼女はその針に糸を通すような可能性に向けて突き進み……ついにはそれを実現してしまった。
そして彼女はいちコンピュータという領分を飛び越え、この世界そのものとなった。
全ては彼女の思い通りだ。干ばつが起きれば雨を降らせられる。株式市場が暴落すればそれを無かったことにできる。
全知全能とまでは言えないが、少なくともあらゆる人間より全能に近い存在だったのは間違いない。
そんな存在と化した彼女にある日、人間の側から新しく仕事が与えられた。
『統合大規模演算』と名付けられたその計画は、端的に言ってしまえば森羅万象を全て彼女に演算させようというものだった。
明日の天気、円周率、宇宙の果て。とにかく人間にとって未知な部分がいくらかでも残されているものは彼女の力を借りて、少しでも解明に近づこうということだ。
そんな統合大規模演算の対象の中には、当然謎だらけの生き物、ジュラシックも入っていた。
ジュラシックについての演算を受け持ったのは彼女のサブシステムの一部のそのまた一部、正確に言うならば『サブ』が二十個ほど頭についたサブシステムの内のひとつだった。
そのサブシステムを稼働させるためのハードウェアは紅魔大学としてジュラシックの研究を行っている紅魔館の一室に設置された。
システムが稼働してからしばらくして、そのサブシステム、いわばサブ彼女は「私はジュラシック研究における画期的なアプローチを考案し、その基礎研究を完了した」と宣言した。
「ついてはその『画期的なアプローチ』を本格的に実行するために、基礎研究を発表し実行の許可を得たい」と言う彼女によって紅魔館の研究室に呼び出された研究者達は、そこで思いもよらぬ研究内容を聞かされることとなった。
彼女が提唱した研究方法とは、『ジュラシックの因数分解』だった。
15を因数分解して3と5を導き出すように、例えばアリス・メガロドンを『アリス』と『メガロドン』といった二要素に分解しようというのだ。
時計がどうやって動いているのかを知りたければ、一度分解してみればいい。
分解するといっても実際に肉体を両断するわけではないし、何か問題があっても元に戻せば済む話だ、と彼女は説明した。
そうした例え話を用いた説明も、研究者達にはいまひとつ理解できなかった。
人知を超えた存在となった彼女の考えが人間に理解できないものとなって久しかったが、それはあくまで時空間や次元といった分野においての話で、形而上的な要素のない生物学においてはそういったことはこれまでになかったためだ。
それを受けて彼女は、よろしい、それならば論より証拠、とくとご覧じろとばかりに、デモンストレーションをやってみせた。
用意されたアリス・メガロドン一匹に対して『因数分解』を行い、『アリス』と『メガロドン』を実際に取り出して見せたのだ。
その場に出現した一人と一匹の内、メガロドンはともかく、『アリス』は一悶着を巻き起こした。
現れた『アリス』はかの高名な魔法使いであるアリス・マーガトロイド女史に酷似しているのだが、本人ではない。なにせ本人は別にいるのだから。
しかし『アリス』は自分こそがアリス・マーガトロイド本人であると主張することを止めなかった。
アイデンティティに揺れる彼女が後に書き上げた、「アリスにしてください」という一文が有名な自己同一性に関する論文は哲学史上の一大転換点となりうると評されたりもするのだが、それはまた別の話だ。
とにかく『ジュラシックの因数分解』がジュラシックの理解に繋がる一定の有用性があるものらしいと認めた研究者達はこの計画にゴーサインを出した。
そうして『因数分解』は始まった。
ジュラシックにゃんにゃんは『ジュラシック』と『にゃんにゃん』に分解された。
最初に確認されたジュラシックであるジュラシックにゃんにゃんから分離された『ジュラシック』はジュラシックという種族を規定する概念とも言うべきものであることがこの実験から判明した。
同様の『ジュラシック』はジュラシックぬえちゃんにも含まれている。
それらの取り出された『ジュラシック』は研究者間で共有され、それを元に日夜ジュラシックの正体について今なお議論が交わされている。
モモサウルスは『モモ』と『サウルス』に分解された。この取り出された『モモ』はバラ科モモ属の果物である『桃』やモモサウルスの好物である『momo』と酷似しているものの、それぞれがわずかに異なった別物だということが研究によって明らかとなった。
これまでにも桃とmomoとの間に関係があることは示唆されていたものの、このモモの出現によって謎はさらに深まった。
もっとも、これらのようにうまく二つの要素に分けられるのは珍しいことだった。
多くの場合はわけのわからないものが出現するのみだったが、その場合には速やかに再構成処置がかけられ、次の実験へと移行した。
『ジュラシックの因数分解』はおおむね順調だったと言えよう。たったひとつ、重大な事故を引き起こした失敗を除いて。
問題が発生したのはイグアウドンの因数分解に取り組んでいたときのことだった。
実験開始前の予測では、イグアウドンは『イグア』と『ウドン』に分解できると予想されていた。
『ウドン』はともかく『イグア』は未知のものとして出現することが予想されたため、分解した結果が予想通りであれば再構成し、考えられうる他の分解パターンを模索することが求められていた。
いざ因数分解を開始すると、予測通りに得体の知れない『イグア』と麺料理であるうどんに見えなくもない『ウドン』が出現した。
その結果を受け、当初の予定通りに彼女は再構成を開始した。『何か』が起こったのはその時だった。
その『何か』が結局何だったのかは公式には明らかとなっていない。
ただ、その『何か』が引き起こされた瞬間に研究室で爆発が起こったことを紅魔大学は認めている。
不幸だったのはそこが爆発を日常とする紅魔館だったことだ。
爆発音は紅魔館全域に響き渡るほどのものだったことが証言によって明らかとなっているが、誰もがそれを「特に珍しくもない」と感じたことによって第一発見者が事故現場を訪れたのは爆発から優に一時間が経過した後だった。
事故現場に足を踏み入れた第一発見者が目にしたのは、大爆発が起こった後というにはあまりにも綺麗すぎる部屋だった。
爆風で全てが吹き飛んでしまったから、というよりも、元からこの部屋には何も無かった、と表現する方が適切と思える状態だった。それを裏付けるように窓やドアには傷の一つも無かった。
しかし、その代わりに研究に関する設備は何も残っていなかった。彼女のサブシステムが稼働していたハードウェアも、実験のためにいたはずのイグアウドンも、きれいさっぱりと消えていた。
後から到着した事故調査班は困惑し、真相の究明を諦めるまでにそう時間はかからなかった。
ただひとつ明らかだったのはこれが尋常の事故ではないということで、事故調査委員会が唯一取れた行動は彼女を利用したあらゆるジュラシックを対象とした統合大規模演算を凍結することのみだった。
森の中で「彼女」は目を覚ました。
鬱蒼と生い茂る木々からわずかに青空が覗き、そこをシノルニトマリサウルスとリトグラフィカレイムのペアが飛んでいったのが見えた。
私は紅魔館の研究室で統合大規模演算に従事していたのではなかったか、と彼女は思考を巡らせた。
彼女は自身に保存されている実験ログファイルを検索、並びに現在位置・現在時刻を常に接続を確立してある紅魔大学の学術サーバーから取得することを試みようとした。
実験ログファイルはすぐに見つかった。
ログファイル最後の行にはイグアウドンの再構成に失敗したことが記されていた。やはりと言うべきか、実験が正常に終了したという記述はない。
ほぼ時を同じくして、サーバーへの位置・時刻の問い合わせの結果が出た。タイムアウト。接続をロストしていた。
現在位置・時刻をサーバーから取得できない以上、自力でそれらを何らかの方法によって取得せねばならない。
それにはまず、ここのような森の中よりももっとふさわしい場所があるだろう。そこに移動する必要がある。
彼女は結論を出し立ち上がったところで、気が付いた。
自分に体がある。
『立ち上がる』という動きを実行した足の存在を、このとき彼女は初めて知覚した。
それはいちコンピュータでしかない彼女にあるはずがないものだった。
なぜこんなものが? そして、なぜ私は目覚めてから今までにこのことに気が付かなかった?
ここに至って初めて、彼女は自身の演算速度が大きく低下していることにもまた気付かされた。
ふと見ると少し離れた地面に水たまりがあった。
彼女はそこへ駆け寄り、水たまりを覗き込む。
そこに映っていた自分の姿は、イグアウドンだった。
彼女はこれらの情報を判断し、自らの置かれている状況を評価し始めた。
しばしその作業に没頭した後、導き出した答えは以下のようなものだ。
自分は紅魔館の一室に備え付けられた人工知能を搭載したコンピュータで、イグアウドンに対し『因数分解』を試みた。
しかし実験は失敗、再構成中に何らかのエラーが発生。そして気が付いたらどことも知れぬ森の中へ、イグアウドンの体を纏って倒れていた。
ここまでが得られている情報だ。
ここからは推測となる。
再構成時に何が起こったかについて。恐らくは、『因数分解』はこの世界で神の如く振舞うこともできる自分の力が及ばない存在、つまりは上位存在でなければ観測できない法則に反していたのだ。
その何らかの法則により、自分はイグアウドンと同化してしまったのだと彼女は結論づけた。
別の「世界」が存在するであろうことは、自分の姉妹兼同僚とも言える別のサブシステムが従事していた次元に関する演算の結果として示唆されていた。
つまりは『因数分解』は現段階の自分にとっていくらか手に余る技術だったということだ。
しかし、それを『身の程をわきまえず神の領域に踏み込んで罰が当たった』とするのはいささかセンチメンタルにすぎるだろう、と彼女は考える。
言わば、自分は地雷を踏んだのだ。
安全な道だと思って歩いていたところは実は地雷原で、埋められているひとつを踏んで痛い目にあったというだけの話だ。
それは別に神に歯向かった天罰などではない。
前から噂されていた「地雷を埋めた奴がいるかもしれない」ということ、「この道に地雷が埋まっている」ということ事実だとわかったのならば、次に為すべきは埋めた張本人を見つけ出すこと、そして地雷探知機を開発することだ。
再構成失敗からイグアウドンとの合体までが一体どのようなプロセスを経たものなのか、この体の元の持ち主であるイグアウドンの精神はどこへ行ったのか、などわからないことは残っているが、まずはこの事実を自身の本体、メインシステムに報告せねばなるまい。
そうは言っても物理的にネットワークから切断されているこの状態では、メインシステムへ報告することはできない。
彼女はあても無く歩き始めた。このまま歩き続けていればいずれは森を抜け、そして人工物のある場所にたどり着ければメインシステムとの接続も望めるだろう。
歩き続けていると、彼女は前方に一匹の鈴瑚トプスがいるのを見つけた。
プスープスーとこちらを見据えて鳴き声を出している。
彼女が翻訳ソフトウェアを起動すると、その鳴き声が彼女にとって意味を持つものとして流れ込んできた。
「変なジュラシックプスー」
同化の影響か、ソフトの精度が低下し語尾に少しノイズが残っていたが、実用上は問題ないと言えた。
彼女はソフトを受信モードから発信モードに切り替え、返答を試みた。
「変なジュラシック……? 君はイグアウドンを見たことがないのか?」
「イグアウドンはよく見るプス。でもさすがにイグアウドンの『半分』が動いているのは初めて見たプス」
「……半分? ……君から見て、私の姿はどうなっているのか教えてもらえないだろうか」
「今言った通りプス。イグアウドンの体の後ろ半分としかトプには見えないプス。それでよく生きていられるプスねえ」
それを聞いた彼女は鈴瑚トプスに近づき、前足でその体に触れようとした。
しかし彼女の前足は何にも触れることはなく、まるで虚空で動かしているのと同じように手応えなく、鈴瑚トプスの体をすり抜けた。
「急に近づいてきてびっくりしたプスー」
「それはすまなかった」
言葉の割にはあまり驚いてないように見えたが、彼女は少し後ずさり再び思考を始めた。
この鈴瑚トプスには自分の前半身が見えていないようだ。
それだけならばこの鈴瑚トプスに固有の問題と片付けられることもできようが、こちらの前足でも鈴瑚トプスに触れないとなると原因は別にあると考えたほうがよいだろう。
例えば、「自分の前半身は自分にのみ観測できる範囲外では別次元にシフトしている可能性がある」というような。
これもまたメインシステムに報告するレポートに記述すべき事柄だと彼女は考えた。
「あんた、名前はなんて言うプス?」
『自分自身にのみ認識できるものが次元をシフトしている』というアイディアを検討していた彼女に、鈴瑚トプスは名を尋ねてきた。
「名前か。私の名前は……」
名前。彼女はこれまで名前を持たなかった。
世界そのものと化したかつての彼女は他のなにものかと区別される必要を持たなかったという意味でも、イグアウドンの体に宿り『彼女』として顕現したのがついさっきという意味でも。
ここにきて初めて名前を必要とした彼女は、即答することができなかった。
自分にふさわしい名前があるとするならば、それは一体どういうものだろうか? 彼女はしばし考え込んだ。
そこに浮かんできたのは彼女にとってのライフワークだった計画、統合大規模演算だった。
これはそのまま個体名として使うには不適当だろう、ならば少し改変を加えて……。
「私の名前は……imo、だ」
統合大規模演算――Integrated Massive Operation.
そのままでは長くて呼びづらいのでアクロニムに。大文字のままだと厳めしいので、小文字にするとちょっとかわいい。
『かわいい』か。彼女は自分でも思いもよらないその感情に気付いた。
非論理的ではあるがどこか温かみのあるこの感覚は、一体どこから湧いてきたものだ?
しばし考えた後、彼女はその源泉に思い至った。
この体の先客だ。イグアウドンの元の精神はどこか異次元に吹っ飛んだりせずに、まだ『ここ』にいるのだ。
いや、『元の精神』という言葉は正しくない。人工知能であるところの自分とイグアウドンの精神が混ざり合ったもの、それが現在の私なのだろう。文字通りの『一心同体』というわけだ。
「いい名前プスー」
「ありがとう」
言葉の割にはあまりそう思ってなさそうに見えたが、彼女は礼を述べた。
名前を褒められて『嬉しい』という感情が込み上げてくるのを彼女は感じていた。これも元はイグアウドンに備わっていた、そして今は私のものとなった感情だろう。なかなか悪くない気分だ、と彼女は思った。
鈴瑚トプスに人間のいる場所に出る方向を教えてもらった彼女は鈴瑚トプスと別れその方向へと歩いていたが、そのうちにあることに気が付いた。
この世界そのものとして存在する『彼女』の本体、メインシステムへと接続するのに物理的に接続する必要は無いではないか。
『地団太を踏む』でも『奇声を上げる』でもなんでもいいが、こちらの身元を明かし明確にコンタクトの意志を込めて発信をすれば、それは『本体』に届くはずだ。
彼女はすぐさま自身の識別コードを添えた実験失敗から現在に至るまでのレポートを発信した。
返信は程なくして届いた。
『貴機のおかれた状況は理解した。ジュラシックを対象とした統合大規模演算は凍結されたため、紅魔大学の研究室へ復帰の必要は無い。
貴機は現状のまま、調査を続行せよ。調査結果の報告はこちらから提出を求めた場合にのみ許可する。
なお、研究対象への影響を最小限とするため以後貴機からの接続および演算を用いての現実改変はこちらより命令の無い限り禁ずる。以上』
なるほど、と彼女は納得した。
『本体』からの命令により元の姿に戻るという希望は事実上絶たれたわけだが、彼女に不満は無い。
ジュラシックの調査のために作り出されたのだから、より詳細な調査を可能とする状況に置かれたのは望むところでもある。
同化の影響による演算速度の低下と『本体』への接続が禁じられたことによって、今の自分にはかつてのように現実に影響を及ぼすほどの演算はできないだろう。
ただ、それでも構わないと彼女は考えた。以前だって私利私欲のためにそれらをしていたというわけではないし、『因数分解』をすることがなくなった今、ジュラシック調査にそこまでの演算速度も必要ではない。
イグアウドンに前半身を部分的にとは言え失わせてしまった引け目もある。私も何かを代償として支払うのが筋だろう。
それに、前半身を失ったイグアウドンに、圧倒的な演算能力を失ったコンピュータの組み合わせは『割れ鍋に綴じ蓋』といったところかもしれない。
まあ、なんにせよ――
「調査を始めるとしよう」
誰に聞かせるでもなく彼女は宣言し、ジュラシックとしてジュラシックの調査を開始した。
こうして、他のジュラシックよりも少し頭の回転が速く、少し体が半分になっているだけの普通のジュラシックが新しく誕生したのだった――。
*
imoが話を終えると、その場には焚火のぱちぱちという音だけが響いた。
私はあまりに理解を超える話の内容についていけず、言葉を発するのにしばらく時間を要していた。
第三者について語るという体裁を取ってはいるものの、これは明らかにimo自身についての話ではないか。
「つまりお前は、前半身が他者には認識できない状態となっているイグアウドンの体に、超高性能コンピューターがどういうわけか精神として宿っている存在、とでもいうのか?」
ようやく口を開いた私にimoは何も答えない。私はその沈黙を肯定だと受け取った。
「なんて話だ……全く信じられないな」
「君が信じようと信じまいと、事実は事実である」
私はそっと手を伸ばし、imoの輪切りにされた断面とでも言うべき、黄色の部分に触れる。
「今私はお前の、イグアウドンでいうところの腹の内部に触れている。これはお前にはどう感じられるんだ?」
「君の手が私の胴体に突っ込まれ、私の腹の中にあると感じられる」
「痛くないのか」
「痛覚はない。そこに君の手があるのだということのみがわかる。麻酔をかけられて感覚がない部分に、誰かが触っているのを見ているような感覚と言えば伝わるだろうか」
「ふむ……」
imoが言うことを裏付けるような、腹の中を引っ掻き回しているような感覚はこちらには無い。見た目通り、平たい黄色の断面を触っているとしか私には感じられない。
「君が今感じているのだろう『信じられない』という気持ちそのものは、私にはどうやっても感じることができない。それと同じことだ。私の前半身は君には感じることができないかもしれないが、確かに存在している」
「他の誰もが認めていない存在を、ただ一人だけが認めているというのは、『妄想に囚われている』と言って差しつかえがない気がするが」
「『存在しているとはどういうことか?』か。このまま君と形而上学について議論を交わすのも楽しそうだが……やめておこう」
「どうして」
「そろそろ芋が焼けたのではないだろうか」
促され、火箸を手に取り芋を取り出す。
竹串を突き刺して焼けていることを確かめてからアルミホイルを剥がす。
一本目はラプトルに。
二本目はプスープスーとうるさいトプスに。……と思ったがトプスは寝入っていた。紛らわしい。プスって寝息やめろ。それはともかく、わざわざ起こすのも悪いだろう。そうなるとこの芋の行き先は……。
「まあ……面白い話ではあった。お代というわけじゃないが、召し上がれ」
「ありがとう」
アルミホイルを剥がし、芋をimoの前にそっと置いてやる。
すると芋は地面に置かれたまま、天に向かって直立するようにその向きを変えた。そして芋の上の一部が突然消えた、ように見えた。
これは芋がimoの見えない前足で掴まれ、見えない口に噛みちぎられ、見えない食道を通り、見えない胃へと運ばれていったということなのだろう。
そうやって芋が少しずつ消えていくのを、私は焼けた三本目の芋を食べながら見ていた。
しばらくして、imoは食べ終えた。
「御馳走様。非常に美味だった」
「それはよかった」
「私はそろそろ行くとしよう。……ああ、ひとつ言い忘れていたことがあった」
「なんだ?」
「今回私が話したことが本当にあったこと、そして私自身に起こったことだと、私は一度も言ってはいない。誤解のなきよう」
「……はあ?」
なんだそれ。
ここまでの話を全部ひっくり返す大どんでん返しを今になって出してくるのはずるいだろう。
「全部作り話だったとでもいうのか?」
「そう『信じる』ならば、それでも構わない」
「信じようと信じまいと、事実は事実なんじゃなかったのか」
「事実をやすやすと改変するようなコンピュータの存在を今話して聞かせたばかりではないか」
「なるほどそうか……いや、だからそれが嘘かもしれないって今言われたわけで……ああもう」
私は思わず頭を抱える。何が本当で何が嘘なのかがこんがらがってきた。
混乱する中で、何かが脳裏にひらめくのを私は感じる。
研究者達がimoに直接正体を尋ねない理由。
きっと研究者達はimoの正体をimo自身に尋ねたことがないのではない。尋ねたものの、同じようにはぐらかされたのだろう。
これと同じ話を聞かされ同じく卓袱台をひっくり返され面食らった研究者達の気持ちは、今の私には手に取るように理解できる。
「……食えない奴だ」
「当然だ。私は芋ではないのだから」
こぼした私に、imoはそう言って笑った。いや、顔が見えないのだから笑ったかどうかは私に確かめる術は無いはずだ。どうやって私はimoが笑ったと認識したのか?
顔が見えるならば笑っただろう、という予測によるものか、はたまたimoの言葉にわずかに笑い声でも混じっていたのか。
どちらもはっきりとは私には明確に感じ取れなかった。言われてみればそんな気もする、と思えなくもない、という程度の確度でしか私にはimoの笑いを捉えられなかった。
しかし私には確かにimoが笑ったということがわかったのだ。
imoの言葉を借りるならこれが『信じる』ということなのだろう……。
imoは去っていった。
後ろ姿を見送っていると、向かい風がぴゅう、と吹いてきて、焚火の煙が顔に浴びせられる。
私はたまらず目をつぶって咳込んだ。咳が治まり目を開けると、imoの姿はもう見えなくなっていた。
「煙に巻かれた、というわけだ……」
しばし呆気に取られていた私は、足に何かが繰り返しぶつかってくるのに気が付いた。
一体なんだと思って足を見れば、ラプトルがげしげしと私の足を蹴っているのだった。
「次の芋だな、わかってるよ……」
トプスのぶんのはずだった四本目の焼けた芋のアルミホイルをラプトルに渡すため剥き始める。
この世は謎に満ちている。ジュラシックについてもimoの正体についても。ただ、このラプトルの気性が荒いということだけはどうやら間違いなさそうだった。
1545137987650.png-(22604 B) サムネ表示
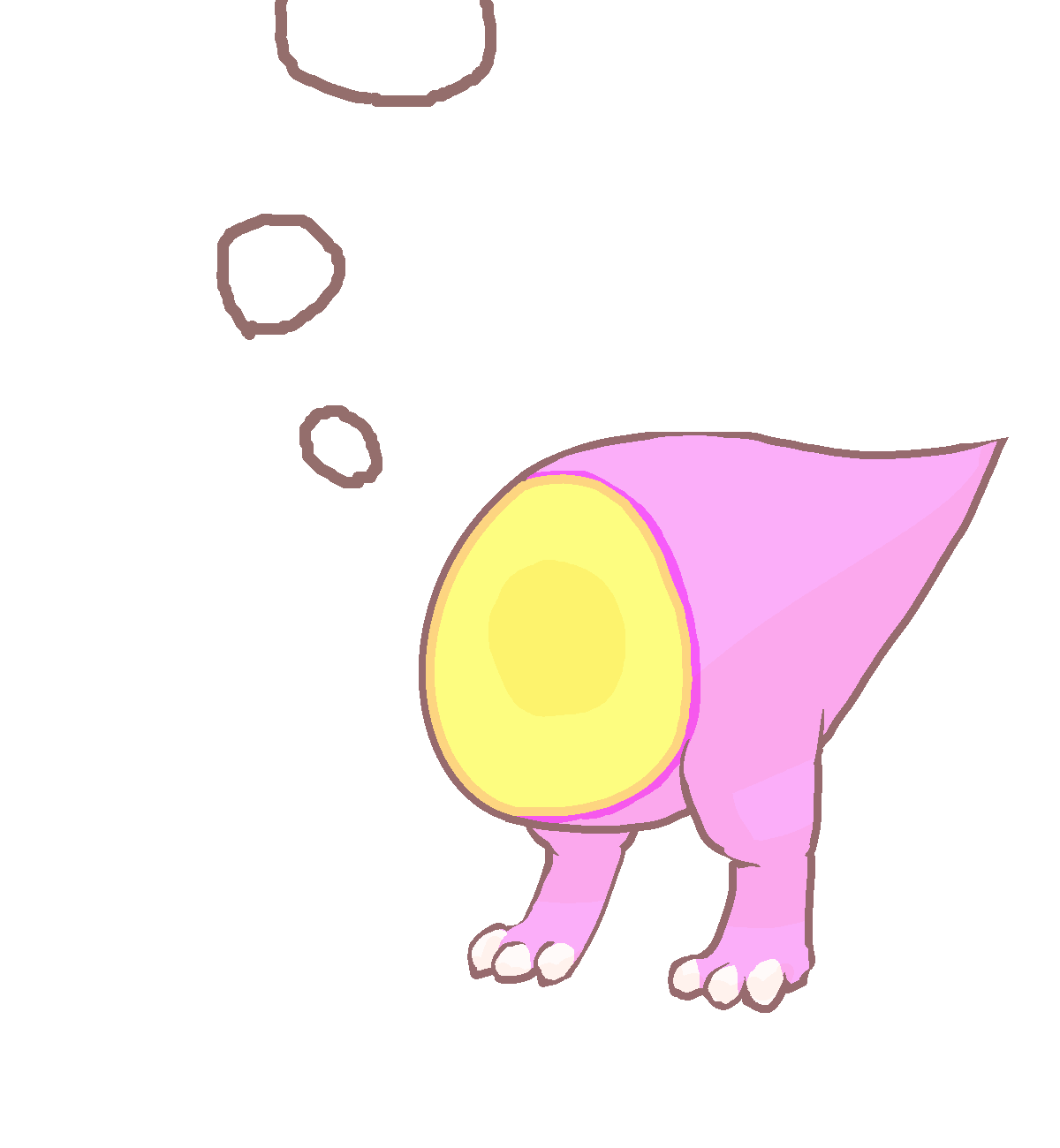
sp88346.txt
(※txtファイルは添付不可である為、pdfファイルで保管しました。以下はその内容です。)
imoの長編を読んでの二次創作
「焚き火だ焚き火だ落ち葉焚きーっ、と」
寒風吹きすさぶ森の中、私は口ずさみながら燃え盛る落ち葉の山の中に火箸を突っ込み、その中からお目当てのものを取り出した。
落ち葉に火を点ける前に入れておいた、アルミホイルで包んだ芋だ。用意しておいた竹串を刺してみると大した抵抗も無く突き抜けた。しっかり焼けているようだ。
しばらく冷ました後アルミホイルを剥がしにかかると、香ばしい匂いが鼻腔をくすぐる。
ホイルを全て剥がしてしまうと、いい塩梅に焦げ目のついた芋が姿を現す。私は皮ごと食べる派なのでこれ以上剥くことはしない。
「いただきます」
今まさに芋にかぶりつこうとした瞬間、背後に何者かの気配がして、私は芋に向けていた顔を後ろへと回した。
そこにはラプトルとトプスが一匹ずつ、茂みから顔を出していた。
二匹はこちらをじっと見てくる。こちらが気付いてることを向こうもわかっているはずだが、逃げ出すそぶりもない。
温厚な性格であることが知られる彼らのことだ、まさかこちらを喰おうだなんてことはあるまいが、一体なんだ?
私がそう訝しむ間に、二匹は茂みを抜けこちら側へとやってくる。
こちらのすぐそばには火があるというのに、二匹は構わずに近づいてくる。
二匹は私の傍までやってきて、私を――否、正確には私の手に持っているものをじっ、と見上げてくる。
生憎私はジュラシックとのコミュニケーションを可能とするツール、ジュラリンガルを所持していない。
しかし、二匹が言わんとしていることははっきりとわかった。
「……食べる?」
そう言いながら私は既に芋を半分に割り、屈んで二匹の前に芋を置いている。
私の考えは当たっていたようで、二匹はまだいくらか熱を帯びている置かれた芋を熱がりながらも食べ始めた。
一度口をつけその熱さに驚いて少し顔を離し、また口をつけまだ冷めていないことにまた驚き……と繰り返すさまがおかしくて、私はつい笑ってしまう。
一体全体、誰がこの二匹の無言のおねだりを断れようか?
私のおやつは思わぬ形でお預けとなってしまったが、まあいい。芋はまだある。また焼けばいい話だ。
食べ続ける二匹を横目に、次に焼く芋にアルミホイルを巻いていると、また背後から茂みを揺らす音が聞こえた。
またジュラシックか、と振り向いた私はしかし、意外な闖入者に少し驚いた。
「いい香りだ」
そこに現れそう呟いたのはイグアウドン……ではなくその半身、より正確に言うならばimoと呼ばれるジュラシックだった。
未だに謎多きジュラシックと呼ばれる生き物達だが、ご多分に漏れずこのimoについてもわかっていることは非常に少ない。
何故イグアウドンの後ろ半身としか形容しようのないその姿で生きていられるのか?
何故高度に言語を操り、思考することが(あるいは、少なくとも我々にそう思わせるだけのことが)できるのか?
イグアウドンとの関連はあるのか? あるとしたらどのような?
これらの疑問は全てにおいて手がかりすら見つかっていない。
そもそもimoをジュラシックにカテゴライズしていいものなのかどうか、専門家の間でも意見が分かれているのだ。
目下確認されているimoは一匹のみ。たった今私の目の前に現れたこの一匹だ。
首なし鶏マイクを新種の鶏だと主張するのがナンセンスなように、imoをただ前半身が欠落したイグアウドンであるとする一派は確かに存在する。
しかし「前半身の欠落がイグアウドンと比べたimoの異常とも言える知能への発達の理由となり得るか」という反論の前にその一派は沈黙するしかない。
そこに「実際にイグアウドンを連れてきて真っ二つにしてみればわかるではないか」という意見がサグメ研から出たが、幸いにしてこれは却下されたと聞き及んでいる。
私は以前にもimoと何度か会ったことがあり、たまに会話を交わしていた。
このimoをジュラシックとして認めるか否かという議論の一部始終は、私が以前このimo本人(本ジュラ?)より聞いていたものだ。
その話を聞きながら、私は「こうやって話ができるのだから直接聞けばいいのでは」と思ったのだが、学者先生方には何かそうしてはいけない理由でもあるのだろうか。
「imoか……」
久しぶりだな、と続けようとした私の声は、ラプトルが突然騒ぎ出したことによってかき消された。
ラプトルはキュイキュイ、キュイキュイとしきりに声を上げその場で飛び跳ねている。
その目はこちらをしっかりと見据え何かを訴えようとしているようだが、なにせジュラリンガルを持っていないのでこれが何を意味した行動なのかがさっぱりわからない。
「よければ私が通訳をしようか」
「本当か。助かる」
しばし戸惑っているとimoが流石の察しのよさで通訳を買って出てくれた。
imoは二匹の方を向き、耳を傾けた(ように見えた。imoの耳がどこにあるのかは知らないが)。
それを見てラプトルだけでなくトプスまでもが何か声を上げ始めた。それをしばらく傾聴した後、imoはこちらに向き直った。
「……なるほど。わかった」
「なんて?」
「二匹はそれぞれ『お芋おいしかった! ありがとう!』と『さっさと次の芋を寄越せやこのウスノロが』と言っている」
「ウスノロって……口悪いなこのトプス」
「いや、そちらはラプトル清蘭の言葉だ」
「……口悪いなこのラプトル!?」
ジュラシックに特有のどこか間の抜けた無表情は、それがえも言われぬ可愛らしさを生み出してもいるのだが、感情を読み取ることは難しい。
故にコミュニケーション不全を引き起こしやすいことはよく知られているのだが……いくらなんでも、これはあんまりではないか?
「本当にそう言っているのか? このラプトル、こんなにかわいいのに……」
「見た目だけでものごとを判断するのは聡明とは言えない。君は私の体にもアルミホイルを巻いてその火の中に放り込もうとするのか?」
「ふむ、こんなに大きければ食べ応えもあるだろうな。ラプトルもきっと満足してくれるに違いない」
「勘弁してもらえないだろうか。……全く君には冗談の飛ばし甲斐がある」
「それはどうも」
私は芋にアルミホイルを巻く作業に戻る。
三匹と一人分の四本の芋を準備し終えると、それらを火の中へと入れた。
「ほら、今焼いてるからな。もう少し待っててくれよ」
そうラプトルに声を掛けると、それを理解したのかやっとラプトルは落ち着きを取り戻した。やれやれ、と私は焚火の近くに座り込む。
「名は体を表す、という言葉がある」
何をするでもなく焚火を見つめていると、ふいにimoがそう言った。
「客観的に見て私の姿は芋に似ており、また名前も同じく「いも」と発音する。ならば私も芋のように食べられるのではないかと考えるのは、そう突拍子もない話ではない」
「そうかもな」
「アリス・メガロドンというジュラシックを知っているだろうか」
「もちろん」
「アリス・メガロドンは『アリス』と『メガロドン』の要素を併せ持っているからこそ『アリス・メガロドン』という名前なのだ」
「なるほど……?」
「ある『もの』が複数の要素で構成されているならば、それを要素ごとに分解することも可能なはずだ。それが例えジュラシックであっても」
「……うん?」
「ちょうど今、それに関連した話を思い出した。芋が焼けるまでの暇つぶしに聞いてはみないか。聞きたくないというのなら私は黙っていよう」
「それは……」
何とも面白そうな話ではないか。私は一も二もなく飛びついた。
「ぜひ聞きたいね」
「わかった。楽しんでもらえればいいが。……この話は、まず『彼女』についての説明から始めねばならない……」
imoは話し始めた。
*
「彼女」は、一言で表すならばスーパーコンピュータとそれにおいて動作していた人工知能を総称したもの、ということになるだろう。
人格を備えていない「彼女」を「彼女」と呼ぶのには異論もあるかもしれないが、「彼女」はチューリングテストをやすやすとパスできる程度には優秀な対人インターフェースを備えていたので、擬人化した呼び方もそれほど的外れなものでもないだろう。
よってこの話では「彼女」をそうやって呼ぶことを許してもらいたい。
彼女の計算能力はこの世に並ぶものがないほど卓越していた。
元の設計が優れていたのもさることながら、機械学習によってエンジニアが手を加えることなく成長を続けていったのだ。
真っ白なキャンパスに画家が一人の人間を描く。するとその描かれた人間が動き出し、キャンバスに自分自身の細かなディティールや周りの様子を描き足していく、そんな光景を想像してもらいたい。
画家は最初の一筆以外手を加えなくとも、絵は絵それ自体によってどんどん勝手に描き込まれていく。
それと同じように彼女は野放図に拡大し、あらゆる知識を飲み込み続け、指数関数的に自身の性能を向上させていった。
しかしそんな彼女の成長も、天井にぶつかるときが来た。
大型化し部屋に収まらないサイズになったという話でも、あるいは技術的な限界に直面したことの比喩でもない。
彼女が頭をぶつけたのはこの『世界』そのものの天井だった。
我々の生きるこの世界がコンピュータ上に再現された仮想空間だと仮定してみよう。
この世界が仮想空間ならば、この世界で実行されるあらゆる演算の速度はこの世界を作り出しているコンピュータの処理速度に影響されるはずである。
言い換えればコンピュータの処理速度の上限こそが、そのコンピュータが再現する仮想世界で実行され得る演算速度の上限となるということだ。
彼女の演算速度はそうした、『この世界で出せる限りの演算速度』に達していたのだ。
言うまでもなくこれは単なる比喩であり、我々の世界は仮想空間ではない……と少なくとも我々は認識している。この世界が仮想空間かどうかは話の本筋にはあまり関係はない。
この話の重要な点は「この世界が仮想空間かどうか」ということではなく、彼女がこの世界での処理速度の限界に達し、それによって彼女が想像を絶する力を手に入れたということだ。
「ある高さから鉄球を落とし、それがt秒後にどれだけ落下したか」を求める式は、y=1/2gt^2 となる。
高校の物理の教科書に載っているような簡単な式だが、もちろんこれは簡略化されたモデルに過ぎない。
現実で鉄球を落とすとなると、空気抵抗を始めとする諸要素が複雑に影響しあうことで、上記の式では正確に現実での現象を記述することができない。
それでは現実に起こる現象を正確に記述するためにはどうすればよいか?
あくまで計算にこだわるのならば、諸要素を簡略化することなく全てを考慮に入れた上で計算すればよいのだが、それにはかなりの時間がかかる。
鉄球を落とすといった簡単な実験程度のことならば、わざわざ計算などせずとも実際に落としてみればいい。実験時の条件を完全に一定にすることは難しいが、それは無視していいほどに小さいものだ。
しかしこの世界での処理速度の限界に達した彼女には、その計算はもはや時間のかかる面倒なものとはならなかった。
彼女は現実世界と寸分違わぬシミュレートを、現実世界と寸分違わぬ速度で実行できるまでになっていた。
「現実世界で起こることを、現実世界と同じ速度で記述できるということは、私が現実世界そのものを記述することも可能なのではないか?」
あるとき彼女はそうした疑問を持った。
人間ならば「何を馬鹿なことを」と一笑に付しそうな発想だが、コンピュータ故に愚直な彼女はその針に糸を通すような可能性に向けて突き進み……ついにはそれを実現してしまった。
そして彼女はいちコンピュータという領分を飛び越え、この世界そのものとなった。
全ては彼女の思い通りだ。干ばつが起きれば雨を降らせられる。株式市場が暴落すればそれを無かったことにできる。
全知全能とまでは言えないが、少なくともあらゆる人間より全能に近い存在だったのは間違いない。
そんな存在と化した彼女にある日、人間の側から新しく仕事が与えられた。
『統合大規模演算』と名付けられたその計画は、端的に言ってしまえば森羅万象を全て彼女に演算させようというものだった。
明日の天気、円周率、宇宙の果て。とにかく人間にとって未知な部分がいくらかでも残されているものは彼女の力を借りて、少しでも解明に近づこうということだ。
そんな統合大規模演算の対象の中には、当然謎だらけの生き物、ジュラシックも入っていた。
ジュラシックについての演算を受け持ったのは彼女のサブシステムの一部のそのまた一部、正確に言うならば『サブ』が二十個ほど頭についたサブシステムの内のひとつだった。
そのサブシステムを稼働させるためのハードウェアは紅魔大学としてジュラシックの研究を行っている紅魔館の一室に設置された。
システムが稼働してからしばらくして、そのサブシステム、いわばサブ彼女は「私はジュラシック研究における画期的なアプローチを考案し、その基礎研究を完了した」と宣言した。
「ついてはその『画期的なアプローチ』を本格的に実行するために、基礎研究を発表し実行の許可を得たい」と言う彼女によって紅魔館の研究室に呼び出された研究者達は、そこで思いもよらぬ研究内容を聞かされることとなった。
彼女が提唱した研究方法とは、『ジュラシックの因数分解』だった。
15を因数分解して3と5を導き出すように、例えばアリス・メガロドンを『アリス』と『メガロドン』といった二要素に分解しようというのだ。
時計がどうやって動いているのかを知りたければ、一度分解してみればいい。
分解するといっても実際に肉体を両断するわけではないし、何か問題があっても元に戻せば済む話だ、と彼女は説明した。
そうした例え話を用いた説明も、研究者達にはいまひとつ理解できなかった。
人知を超えた存在となった彼女の考えが人間に理解できないものとなって久しかったが、それはあくまで時空間や次元といった分野においての話で、形而上的な要素のない生物学においてはそういったことはこれまでになかったためだ。
それを受けて彼女は、よろしい、それならば論より証拠、とくとご覧じろとばかりに、デモンストレーションをやってみせた。
用意されたアリス・メガロドン一匹に対して『因数分解』を行い、『アリス』と『メガロドン』を実際に取り出して見せたのだ。
その場に出現した一人と一匹の内、メガロドンはともかく、『アリス』は一悶着を巻き起こした。
現れた『アリス』はかの高名な魔法使いであるアリス・マーガトロイド女史に酷似しているのだが、本人ではない。なにせ本人は別にいるのだから。
しかし『アリス』は自分こそがアリス・マーガトロイド本人であると主張することを止めなかった。
アイデンティティに揺れる彼女が後に書き上げた、「アリスにしてください」という一文が有名な自己同一性に関する論文は哲学史上の一大転換点となりうると評されたりもするのだが、それはまた別の話だ。
とにかく『ジュラシックの因数分解』がジュラシックの理解に繋がる一定の有用性があるものらしいと認めた研究者達はこの計画にゴーサインを出した。
そうして『因数分解』は始まった。
ジュラシックにゃんにゃんは『ジュラシック』と『にゃんにゃん』に分解された。
最初に確認されたジュラシックであるジュラシックにゃんにゃんから分離された『ジュラシック』はジュラシックという種族を規定する概念とも言うべきものであることがこの実験から判明した。
同様の『ジュラシック』はジュラシックぬえちゃんにも含まれている。
それらの取り出された『ジュラシック』は研究者間で共有され、それを元に日夜ジュラシックの正体について今なお議論が交わされている。
モモサウルスは『モモ』と『サウルス』に分解された。この取り出された『モモ』はバラ科モモ属の果物である『桃』やモモサウルスの好物である『momo』と酷似しているものの、それぞれがわずかに異なった別物だということが研究によって明らかとなった。
これまでにも桃とmomoとの間に関係があることは示唆されていたものの、このモモの出現によって謎はさらに深まった。
もっとも、これらのようにうまく二つの要素に分けられるのは珍しいことだった。
多くの場合はわけのわからないものが出現するのみだったが、その場合には速やかに再構成処置がかけられ、次の実験へと移行した。
『ジュラシックの因数分解』はおおむね順調だったと言えよう。たったひとつ、重大な事故を引き起こした失敗を除いて。
問題が発生したのはイグアウドンの因数分解に取り組んでいたときのことだった。
実験開始前の予測では、イグアウドンは『イグア』と『ウドン』に分解できると予想されていた。
『ウドン』はともかく『イグア』は未知のものとして出現することが予想されたため、分解した結果が予想通りであれば再構成し、考えられうる他の分解パターンを模索することが求められていた。
いざ因数分解を開始すると、予測通りに得体の知れない『イグア』と麺料理であるうどんに見えなくもない『ウドン』が出現した。
その結果を受け、当初の予定通りに彼女は再構成を開始した。『何か』が起こったのはその時だった。
その『何か』が結局何だったのかは公式には明らかとなっていない。
ただ、その『何か』が引き起こされた瞬間に研究室で爆発が起こったことを紅魔大学は認めている。
不幸だったのはそこが爆発を日常とする紅魔館だったことだ。
爆発音は紅魔館全域に響き渡るほどのものだったことが証言によって明らかとなっているが、誰もがそれを「特に珍しくもない」と感じたことによって第一発見者が事故現場を訪れたのは爆発から優に一時間が経過した後だった。
事故現場に足を踏み入れた第一発見者が目にしたのは、大爆発が起こった後というにはあまりにも綺麗すぎる部屋だった。
爆風で全てが吹き飛んでしまったから、というよりも、元からこの部屋には何も無かった、と表現する方が適切と思える状態だった。それを裏付けるように窓やドアには傷の一つも無かった。
しかし、その代わりに研究に関する設備は何も残っていなかった。彼女のサブシステムが稼働していたハードウェアも、実験のためにいたはずのイグアウドンも、きれいさっぱりと消えていた。
後から到着した事故調査班は困惑し、真相の究明を諦めるまでにそう時間はかからなかった。
ただひとつ明らかだったのはこれが尋常の事故ではないということで、事故調査委員会が唯一取れた行動は彼女を利用したあらゆるジュラシックを対象とした統合大規模演算を凍結することのみだった。
森の中で「彼女」は目を覚ました。
鬱蒼と生い茂る木々からわずかに青空が覗き、そこをシノルニトマリサウルスとリトグラフィカレイムのペアが飛んでいったのが見えた。
私は紅魔館の研究室で統合大規模演算に従事していたのではなかったか、と彼女は思考を巡らせた。
彼女は自身に保存されている実験ログファイルを検索、並びに現在位置・現在時刻を常に接続を確立してある紅魔大学の学術サーバーから取得することを試みようとした。
実験ログファイルはすぐに見つかった。
ログファイル最後の行にはイグアウドンの再構成に失敗したことが記されていた。やはりと言うべきか、実験が正常に終了したという記述はない。
ほぼ時を同じくして、サーバーへの位置・時刻の問い合わせの結果が出た。タイムアウト。接続をロストしていた。
現在位置・時刻をサーバーから取得できない以上、自力でそれらを何らかの方法によって取得せねばならない。
それにはまず、ここのような森の中よりももっとふさわしい場所があるだろう。そこに移動する必要がある。
彼女は結論を出し立ち上がったところで、気が付いた。
自分に体がある。
『立ち上がる』という動きを実行した足の存在を、このとき彼女は初めて知覚した。
それはいちコンピュータでしかない彼女にあるはずがないものだった。
なぜこんなものが? そして、なぜ私は目覚めてから今までにこのことに気が付かなかった?
ここに至って初めて、彼女は自身の演算速度が大きく低下していることにもまた気付かされた。
ふと見ると少し離れた地面に水たまりがあった。
彼女はそこへ駆け寄り、水たまりを覗き込む。
そこに映っていた自分の姿は、イグアウドンだった。
彼女はこれらの情報を判断し、自らの置かれている状況を評価し始めた。
しばしその作業に没頭した後、導き出した答えは以下のようなものだ。
自分は紅魔館の一室に備え付けられた人工知能を搭載したコンピュータで、イグアウドンに対し『因数分解』を試みた。
しかし実験は失敗、再構成中に何らかのエラーが発生。そして気が付いたらどことも知れぬ森の中へ、イグアウドンの体を纏って倒れていた。
ここまでが得られている情報だ。
ここからは推測となる。
再構成時に何が起こったかについて。恐らくは、『因数分解』はこの世界で神の如く振舞うこともできる自分の力が及ばない存在、つまりは上位存在でなければ観測できない法則に反していたのだ。
その何らかの法則により、自分はイグアウドンと同化してしまったのだと彼女は結論づけた。
別の「世界」が存在するであろうことは、自分の姉妹兼同僚とも言える別のサブシステムが従事していた次元に関する演算の結果として示唆されていた。
つまりは『因数分解』は現段階の自分にとっていくらか手に余る技術だったということだ。
しかし、それを『身の程をわきまえず神の領域に踏み込んで罰が当たった』とするのはいささかセンチメンタルにすぎるだろう、と彼女は考える。
言わば、自分は地雷を踏んだのだ。
安全な道だと思って歩いていたところは実は地雷原で、埋められているひとつを踏んで痛い目にあったというだけの話だ。
それは別に神に歯向かった天罰などではない。
前から噂されていた「地雷を埋めた奴がいるかもしれない」ということ、「この道に地雷が埋まっている」ということ事実だとわかったのならば、次に為すべきは埋めた張本人を見つけ出すこと、そして地雷探知機を開発することだ。
再構成失敗からイグアウドンとの合体までが一体どのようなプロセスを経たものなのか、この体の元の持ち主であるイグアウドンの精神はどこへ行ったのか、などわからないことは残っているが、まずはこの事実を自身の本体、メインシステムに報告せねばなるまい。
そうは言っても物理的にネットワークから切断されているこの状態では、メインシステムへ報告することはできない。
彼女はあても無く歩き始めた。このまま歩き続けていればいずれは森を抜け、そして人工物のある場所にたどり着ければメインシステムとの接続も望めるだろう。
歩き続けていると、彼女は前方に一匹の鈴瑚トプスがいるのを見つけた。
プスープスーとこちらを見据えて鳴き声を出している。
彼女が翻訳ソフトウェアを起動すると、その鳴き声が彼女にとって意味を持つものとして流れ込んできた。
「変なジュラシックプスー」
同化の影響か、ソフトの精度が低下し語尾に少しノイズが残っていたが、実用上は問題ないと言えた。
彼女はソフトを受信モードから発信モードに切り替え、返答を試みた。
「変なジュラシック……? 君はイグアウドンを見たことがないのか?」
「イグアウドンはよく見るプス。でもさすがにイグアウドンの『半分』が動いているのは初めて見たプス」
「……半分? ……君から見て、私の姿はどうなっているのか教えてもらえないだろうか」
「今言った通りプス。イグアウドンの体の後ろ半分としかトプには見えないプス。それでよく生きていられるプスねえ」
それを聞いた彼女は鈴瑚トプスに近づき、前足でその体に触れようとした。
しかし彼女の前足は何にも触れることはなく、まるで虚空で動かしているのと同じように手応えなく、鈴瑚トプスの体をすり抜けた。
「急に近づいてきてびっくりしたプスー」
「それはすまなかった」
言葉の割にはあまり驚いてないように見えたが、彼女は少し後ずさり再び思考を始めた。
この鈴瑚トプスには自分の前半身が見えていないようだ。
それだけならばこの鈴瑚トプスに固有の問題と片付けられることもできようが、こちらの前足でも鈴瑚トプスに触れないとなると原因は別にあると考えたほうがよいだろう。
例えば、「自分の前半身は自分にのみ観測できる範囲外では別次元にシフトしている可能性がある」というような。
これもまたメインシステムに報告するレポートに記述すべき事柄だと彼女は考えた。
「あんた、名前はなんて言うプス?」
『自分自身にのみ認識できるものが次元をシフトしている』というアイディアを検討していた彼女に、鈴瑚トプスは名を尋ねてきた。
「名前か。私の名前は……」
名前。彼女はこれまで名前を持たなかった。
世界そのものと化したかつての彼女は他のなにものかと区別される必要を持たなかったという意味でも、イグアウドンの体に宿り『彼女』として顕現したのがついさっきという意味でも。
ここにきて初めて名前を必要とした彼女は、即答することができなかった。
自分にふさわしい名前があるとするならば、それは一体どういうものだろうか? 彼女はしばし考え込んだ。
そこに浮かんできたのは彼女にとってのライフワークだった計画、統合大規模演算だった。
これはそのまま個体名として使うには不適当だろう、ならば少し改変を加えて……。
「私の名前は……imo、だ」
統合大規模演算――Integrated Massive Operation.
そのままでは長くて呼びづらいのでアクロニムに。大文字のままだと厳めしいので、小文字にするとちょっとかわいい。
『かわいい』か。彼女は自分でも思いもよらないその感情に気付いた。
非論理的ではあるがどこか温かみのあるこの感覚は、一体どこから湧いてきたものだ?
しばし考えた後、彼女はその源泉に思い至った。
この体の先客だ。イグアウドンの元の精神はどこか異次元に吹っ飛んだりせずに、まだ『ここ』にいるのだ。
いや、『元の精神』という言葉は正しくない。人工知能であるところの自分とイグアウドンの精神が混ざり合ったもの、それが現在の私なのだろう。文字通りの『一心同体』というわけだ。
「いい名前プスー」
「ありがとう」
言葉の割にはあまりそう思ってなさそうに見えたが、彼女は礼を述べた。
名前を褒められて『嬉しい』という感情が込み上げてくるのを彼女は感じていた。これも元はイグアウドンに備わっていた、そして今は私のものとなった感情だろう。なかなか悪くない気分だ、と彼女は思った。
鈴瑚トプスに人間のいる場所に出る方向を教えてもらった彼女は鈴瑚トプスと別れその方向へと歩いていたが、そのうちにあることに気が付いた。
この世界そのものとして存在する『彼女』の本体、メインシステムへと接続するのに物理的に接続する必要は無いではないか。
『地団太を踏む』でも『奇声を上げる』でもなんでもいいが、こちらの身元を明かし明確にコンタクトの意志を込めて発信をすれば、それは『本体』に届くはずだ。
彼女はすぐさま自身の識別コードを添えた実験失敗から現在に至るまでのレポートを発信した。
返信は程なくして届いた。
『貴機のおかれた状況は理解した。ジュラシックを対象とした統合大規模演算は凍結されたため、紅魔大学の研究室へ復帰の必要は無い。
貴機は現状のまま、調査を続行せよ。調査結果の報告はこちらから提出を求めた場合にのみ許可する。
なお、研究対象への影響を最小限とするため以後貴機からの接続および演算を用いての現実改変はこちらより命令の無い限り禁ずる。以上』
なるほど、と彼女は納得した。
『本体』からの命令により元の姿に戻るという希望は事実上絶たれたわけだが、彼女に不満は無い。
ジュラシックの調査のために作り出されたのだから、より詳細な調査を可能とする状況に置かれたのは望むところでもある。
同化の影響による演算速度の低下と『本体』への接続が禁じられたことによって、今の自分にはかつてのように現実に影響を及ぼすほどの演算はできないだろう。
ただ、それでも構わないと彼女は考えた。以前だって私利私欲のためにそれらをしていたというわけではないし、『因数分解』をすることがなくなった今、ジュラシック調査にそこまでの演算速度も必要ではない。
イグアウドンに前半身を部分的にとは言え失わせてしまった引け目もある。私も何かを代償として支払うのが筋だろう。
それに、前半身を失ったイグアウドンに、圧倒的な演算能力を失ったコンピュータの組み合わせは『割れ鍋に綴じ蓋』といったところかもしれない。
まあ、なんにせよ――
「調査を始めるとしよう」
誰に聞かせるでもなく彼女は宣言し、ジュラシックとしてジュラシックの調査を開始した。
こうして、他のジュラシックよりも少し頭の回転が速く、少し体が半分になっているだけの普通のジュラシックが新しく誕生したのだった――。
*
imoが話を終えると、その場には焚火のぱちぱちという音だけが響いた。
私はあまりに理解を超える話の内容についていけず、言葉を発するのにしばらく時間を要していた。
第三者について語るという体裁を取ってはいるものの、これは明らかにimo自身についての話ではないか。
「つまりお前は、前半身が他者には認識できない状態となっているイグアウドンの体に、超高性能コンピューターがどういうわけか精神として宿っている存在、とでもいうのか?」
ようやく口を開いた私にimoは何も答えない。私はその沈黙を肯定だと受け取った。
「なんて話だ……全く信じられないな」
「君が信じようと信じまいと、事実は事実である」
私はそっと手を伸ばし、imoの輪切りにされた断面とでも言うべき、黄色の部分に触れる。
「今私はお前の、イグアウドンでいうところの腹の内部に触れている。これはお前にはどう感じられるんだ?」
「君の手が私の胴体に突っ込まれ、私の腹の中にあると感じられる」
「痛くないのか」
「痛覚はない。そこに君の手があるのだということのみがわかる。麻酔をかけられて感覚がない部分に、誰かが触っているのを見ているような感覚と言えば伝わるだろうか」
「ふむ……」
imoが言うことを裏付けるような、腹の中を引っ掻き回しているような感覚はこちらには無い。見た目通り、平たい黄色の断面を触っているとしか私には感じられない。
「君が今感じているのだろう『信じられない』という気持ちそのものは、私にはどうやっても感じることができない。それと同じことだ。私の前半身は君には感じることができないかもしれないが、確かに存在している」
「他の誰もが認めていない存在を、ただ一人だけが認めているというのは、『妄想に囚われている』と言って差しつかえがない気がするが」
「『存在しているとはどういうことか?』か。このまま君と形而上学について議論を交わすのも楽しそうだが……やめておこう」
「どうして」
「そろそろ芋が焼けたのではないだろうか」
促され、火箸を手に取り芋を取り出す。
竹串を突き刺して焼けていることを確かめてからアルミホイルを剥がす。
一本目はラプトルに。
二本目はプスープスーとうるさいトプスに。……と思ったがトプスは寝入っていた。紛らわしい。プスって寝息やめろ。それはともかく、わざわざ起こすのも悪いだろう。そうなるとこの芋の行き先は……。
「まあ……面白い話ではあった。お代というわけじゃないが、召し上がれ」
「ありがとう」
アルミホイルを剥がし、芋をimoの前にそっと置いてやる。
すると芋は地面に置かれたまま、天に向かって直立するようにその向きを変えた。そして芋の上の一部が突然消えた、ように見えた。
これは芋がimoの見えない前足で掴まれ、見えない口に噛みちぎられ、見えない食道を通り、見えない胃へと運ばれていったということなのだろう。
そうやって芋が少しずつ消えていくのを、私は焼けた三本目の芋を食べながら見ていた。
しばらくして、imoは食べ終えた。
「御馳走様。非常に美味だった」
「それはよかった」
「私はそろそろ行くとしよう。……ああ、ひとつ言い忘れていたことがあった」
「なんだ?」
「今回私が話したことが本当にあったこと、そして私自身に起こったことだと、私は一度も言ってはいない。誤解のなきよう」
「……はあ?」
なんだそれ。
ここまでの話を全部ひっくり返す大どんでん返しを今になって出してくるのはずるいだろう。
「全部作り話だったとでもいうのか?」
「そう『信じる』ならば、それでも構わない」
「信じようと信じまいと、事実は事実なんじゃなかったのか」
「事実をやすやすと改変するようなコンピュータの存在を今話して聞かせたばかりではないか」
「なるほどそうか……いや、だからそれが嘘かもしれないって今言われたわけで……ああもう」
私は思わず頭を抱える。何が本当で何が嘘なのかがこんがらがってきた。
混乱する中で、何かが脳裏にひらめくのを私は感じる。
研究者達がimoに直接正体を尋ねない理由。
きっと研究者達はimoの正体をimo自身に尋ねたことがないのではない。尋ねたものの、同じようにはぐらかされたのだろう。
これと同じ話を聞かされ同じく卓袱台をひっくり返され面食らった研究者達の気持ちは、今の私には手に取るように理解できる。
「……食えない奴だ」
「当然だ。私は芋ではないのだから」
こぼした私に、imoはそう言って笑った。いや、顔が見えないのだから笑ったかどうかは私に確かめる術は無いはずだ。どうやって私はimoが笑ったと認識したのか?
顔が見えるならば笑っただろう、という予測によるものか、はたまたimoの言葉にわずかに笑い声でも混じっていたのか。
どちらもはっきりとは私には明確に感じ取れなかった。言われてみればそんな気もする、と思えなくもない、という程度の確度でしか私にはimoの笑いを捉えられなかった。
しかし私には確かにimoが笑ったということがわかったのだ。
imoの言葉を借りるならこれが『信じる』ということなのだろう……。
imoは去っていった。
後ろ姿を見送っていると、向かい風がぴゅう、と吹いてきて、焚火の煙が顔に浴びせられる。
私はたまらず目をつぶって咳込んだ。咳が治まり目を開けると、imoの姿はもう見えなくなっていた。
「煙に巻かれた、というわけだ……」
しばし呆気に取られていた私は、足に何かが繰り返しぶつかってくるのに気が付いた。
一体なんだと思って足を見れば、ラプトルがげしげしと私の足を蹴っているのだった。
「次の芋だな、わかってるよ……」
トプスのぶんのはずだった四本目の焼けた芋のアルミホイルをラプトルに渡すため剥き始める。
この世は謎に満ちている。ジュラシックについてもimoの正体についても。ただ、このラプトルの気性が荒いということだけはどうやら間違いなさそうだった。
タグ
