最終更新:
![]() kyo_miyato 2017年05月03日(水) 21:46:09履歴
kyo_miyato 2017年05月03日(水) 21:46:09履歴
(1) 延暦13年(794)、「この国、山河襟帯、自然に城を作す。この形勝によりて新号を制すべし。よろしく山背国を改め山城国となすべし。また子来の民、謳歌の輩、異口同辞し、
( )と号す」という詔(みことのり=天皇からの命令)が出された。
(2) 貞観元年(859)に創建された神社( )は、朝廷や武家の崇敬を集め、9月15日に行われる例祭は三勅祭のひとつとされた。
(3)『古今和歌集』の撰者の一人である( )は、日本で最初の仮名文の日記『土佐日記』の作者としても知られる。
(4) 大江山の鬼退治などの伝説・説話で有名な( )は、多田源氏の祖であり満仲の子で、藤原道長に仕えた。
(5) 平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像を囲む長押上に掛けられた( )像は、浄土の空を舞う菩薩の群像で、一体を除く五十一体が国宝に指定されている。
(6) 花背にある寺院( )は、本尊の十一面千手観音坐像(重文)や、閼伽井屋(あかいや)最古の遺構である供水所(重文)で知られる。
(7) 嵯峨野の寺院( )は、藤原定家の歌「忍ばれむ 物ともなしに 小倉山 軒端の松ぞ なれてひさしき」にちなんで軒端寺(のきばじ)とも呼ばれる。
(8) 高山寺の国宝の建造物( )は、明恵(みょうえ)の庵室であったと伝えられ、清滝川を望む高台に位置し、穏やかなたたずまいで知られる。
(9) 親鸞が著した『( )』は、浄土真宗の教義の体系を示した書物で、東本願寺には「坂東本」と呼ばれる自筆本が伝わっており、国宝に指定されている。
(10) 建礼門院が出家したと伝えられる東山の寺院( )には、時宗の開祖である一遍をはじめ歴代の遊行上人(ゆぎょうしょうにん)の木像が安置されている。
( )と号す」という詔(みことのり=天皇からの命令)が出された。
(2) 貞観元年(859)に創建された神社( )は、朝廷や武家の崇敬を集め、9月15日に行われる例祭は三勅祭のひとつとされた。
(3)『古今和歌集』の撰者の一人である( )は、日本で最初の仮名文の日記『土佐日記』の作者としても知られる。
(4) 大江山の鬼退治などの伝説・説話で有名な( )は、多田源氏の祖であり満仲の子で、藤原道長に仕えた。
(5) 平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像を囲む長押上に掛けられた( )像は、浄土の空を舞う菩薩の群像で、一体を除く五十一体が国宝に指定されている。
(6) 花背にある寺院( )は、本尊の十一面千手観音坐像(重文)や、閼伽井屋(あかいや)最古の遺構である供水所(重文)で知られる。
(7) 嵯峨野の寺院( )は、藤原定家の歌「忍ばれむ 物ともなしに 小倉山 軒端の松ぞ なれてひさしき」にちなんで軒端寺(のきばじ)とも呼ばれる。
(8) 高山寺の国宝の建造物( )は、明恵(みょうえ)の庵室であったと伝えられ、清滝川を望む高台に位置し、穏やかなたたずまいで知られる。
(9) 親鸞が著した『( )』は、浄土真宗の教義の体系を示した書物で、東本願寺には「坂東本」と呼ばれる自筆本が伝わっており、国宝に指定されている。
(10) 建礼門院が出家したと伝えられる東山の寺院( )には、時宗の開祖である一遍をはじめ歴代の遊行上人(ゆぎょうしょうにん)の木像が安置されている。
タグ

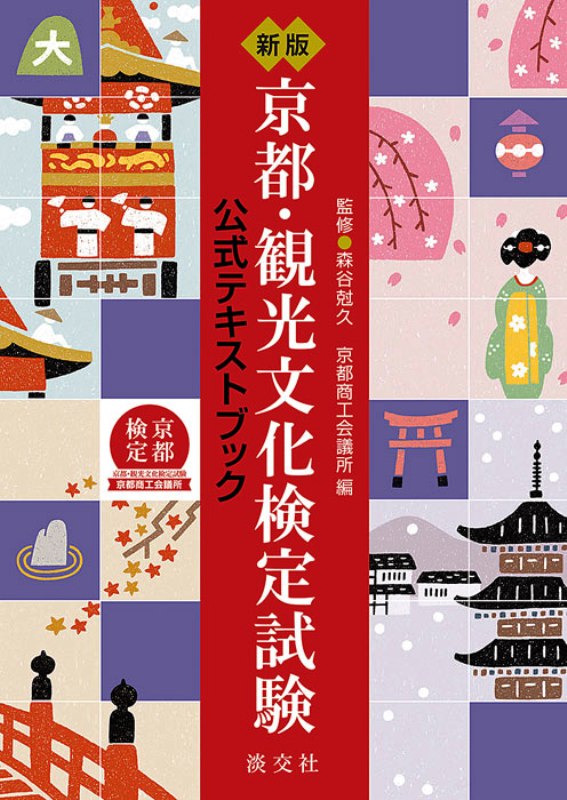
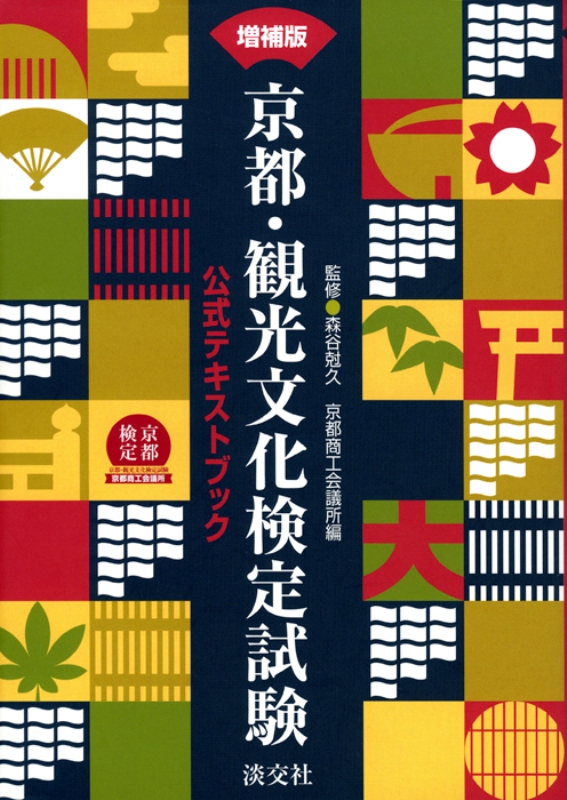
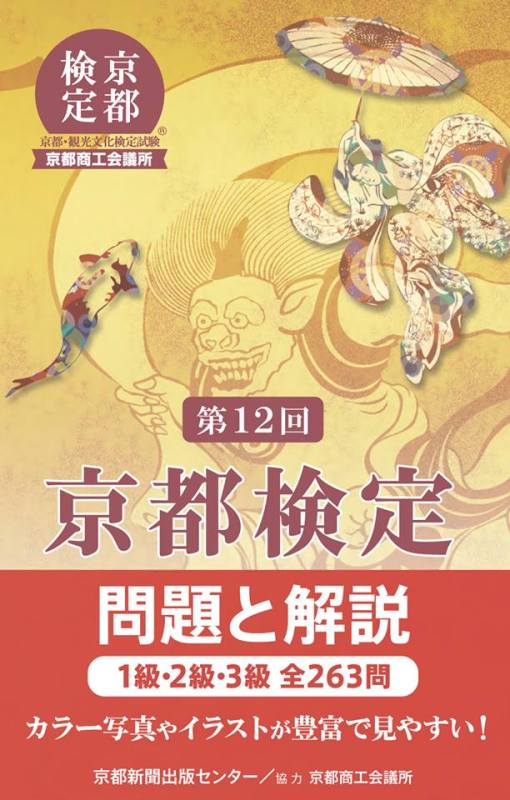
コメントをかく