☆ただし、以下のワードについては、小論文内に必ず含むこと
- 義経が牛若丸として幼少期を過ごした寺
- 童謡で歌われるところの弁慶との決闘の場
- 弁慶との決闘をテーマにした祇園祭の山の名
- 奥州への旅路の無事を祈願したという神社
- 静御前と出会ったとされる場所

解答チェック
《解答例》※これらのポイントうち、赤字のキーワード部分を含む解説を適正に記述することができて正答 公式テキスト[増]52・135・213ページ/[新]64・174・268ページ
◦ 源義経は、平治元年(1159)に源義朝の九男として生まれ、幼名の牛若丸はあまりにも有名である。しかし、平治の乱で父が戦死したことにより、11歳の時に鞍馬寺へと預けられた。
◦ ところが僧として生きることを嫌がって15歳の時に寺から逃げ出し、元服して義経と名を改めた。
◦ 童謡『牛若丸』では、牛若丸と武蔵坊弁慶が京都の五条大橋で睨み合い、決闘したシーンが描かれている。実際に2人が出会い結党したという記録は、真偽も含めて詳細に諸説あり。
◦ また、この決闘をテーマにした祇園祭の橋弁慶山は、牛若丸と弁慶が向き合う人形が載せられており、これは謡曲「橋弁慶」を題材としている。
◦ 今出川智恵光院にある首途八幡宮の社名は、承安4年(1174)に義経が奥州への旅路の無事を祈願したことに由来するとも、寿永年間(1182〜85)に平家追討の首途にあたり、宇佐八幡宮の神霊を
勧請したことにちなむともいわれている。
◦ 養和2年(1182)、神泉苑で行われていた雨乞い神事の際に、白拍子として招いた静御前が舞った姿を見染めた義経が召し抱え、そのまま妾となったといわれている。
◦ その後、義経が兄の頼朝と不仲になり、京へ落ち九州へ向かう際も連れ立って行動した。義経一行が乗った船は、嵐のため難破したが上手く岸に流れ吉野に辿りき、義経とは離れて京に戻ることに
なった。しかし、その途中に何人かの従者に裏切られ、荷物のほとんどを持ち去られて山中をさまよっている時に北条時政の手の者に捉えられて鎌倉へと連れ戻されたあとは、再会できたという
記録は残っていない。
![]() kyo_miyato 2017年05月04日(木) 17:42:46履歴
kyo_miyato 2017年05月04日(木) 17:42:46履歴![]() kyo_miyato 2017年05月04日(木) 17:42:46履歴
kyo_miyato 2017年05月04日(木) 17:42:46履歴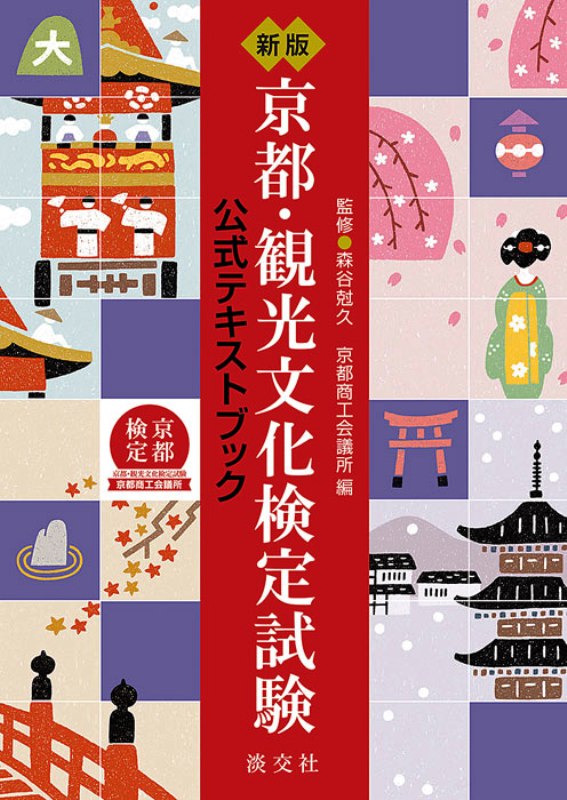
コメントをかく