☆ただし、以下のワードについては、小論文内に必ず含むこと
- 西陣織の起源と考えられる朝廷織部司の後身にあたる織手同業者組織の名称
- 応仁の乱で西陣の名の由来となる西軍を率いた人物
- 徳川政権の産業保護によって保有した高機の推定台数
- 西陣織業者が織物の神を祀った今宮神社の末社
- 大正初期に展示即売施設として建てられた旧西陣織物館(現京都市考古資料館)を設計した人物

解答チェック
《解答例》※これらのポイントうち、赤字のキーワード部分を含む解説を適正に記述することができて正答 公式テキスト[増]28・50・178・186・287ページ/[新]23・60・225・234・350ページ
◦ 西陣織は、平安時代には平安京の朝廷に所属する織部司(おりべのつかさ)を起源とする織り手集団「大舎人座(おおとねりざ)」以来の伝統を誇る。
◦ 平安時代の中頃からは私織も行われ、鎌倉時代から室町時代にかけて、先染めである織物は「大宮絹」の名で知られていた。
◦ 応仁・文明の乱後は、この地に山名宗全らが西軍の陣地を構えたため西陣と呼ばれるようになり、この地域の織手が織る「西陣織」の名称が生まれた。
◦ その西陣織は、江戸時代に徳川政権の京都の都市産業の手厚い保護により、高機7000台を持つといわれるほど日本最大の織物産業地域として発展した。
◦ しかし、江戸中期に「西陣焼け」と呼ばれる大火に襲われ、織機3000台を失い、さらに幕末になると「奢侈品禁止令(しゃしきんしれい)」が唱えられ、呉服や帯など贅沢品を持つことが
禁止とされた。
◦ 一時は衰退産業となっていたが、明治になって佐倉常七らがフランスからジャカード機械織機を輸入し、それを西陣の機大工であった荒木小平が国産化に初めて成功したことをきっかけに、
西陣地区は絹織物の先進地として復活した。
◦ 今宮神社には多くの摂末社があるが、その中でも織姫神社は西陣機業者が祀った末社として有名。
◦ 大正初期に展示即売施設として建てられた旧西陣織物館(現京都市考古資料館)は、本野精吾が設計したもの。
![]() kyo_miyato 2017年05月05日(金) 15:07:47履歴
kyo_miyato 2017年05月05日(金) 15:07:47履歴![]() kyo_miyato 2017年05月05日(金) 15:07:47履歴
kyo_miyato 2017年05月05日(金) 15:07:47履歴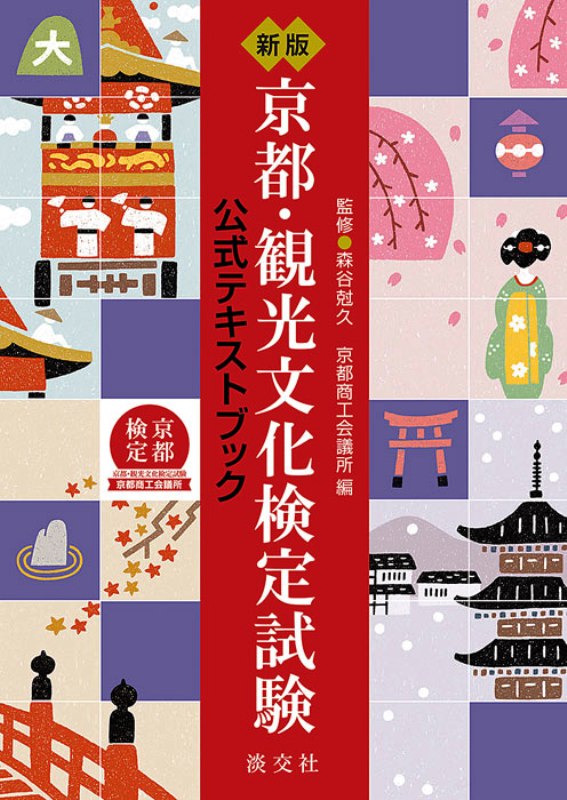
コメントをかく