☆ただし、以下のワードについては、小論文内に必ず含むこと
- 大宝元年(701)に社殿を造営したとされる人物
- 王城鎮護の神として賀茂社と並び称されるときに使われる表現
- 本殿の建築様式
- 境内に湧く名水
- 境外摂社のひとつ

解答チェック
《解答例》※これらのポイントうち、赤字のキーワード部分を含む解説を適正に記述することができて正答 公式テキスト[増]65ページ/[新]80ページ
◦ 松尾大社は、大宝元年(701)に秦忌寸都理(はた の いみきとり)が、松尾山大杉谷の磐座(いわくら)の神霊を勧請して社殿を造営したことに始まる。
◦ 平安遷都後は賀茂社とともに王城鎮護の神となり、「賀茂の厳神、松尾の猛霊」と並び称された。
◦ 応永4年(1397)に建てられた本殿は重要文化財に指定されており、「両流造」と称される珍しい建築様式である。
◦ 古くから酒の神として信仰され、境内に湧く名水「亀の井」は霊泉と呼ばれ、水を醸造の時に混ぜるといつまでも酒が腐らないといわれている。
◦ 松尾大社の境外摂社である月読神社は安産の神として知られ、顕宗天皇3年(487)に創祀され、斉衡3年(856)に桂川の河浜から現在地に移されたとされる。
![]() kyo_miyato 2017年05月05日(金) 14:56:47履歴
kyo_miyato 2017年05月05日(金) 14:56:47履歴![]() kyo_miyato 2017年05月05日(金) 14:56:47履歴
kyo_miyato 2017年05月05日(金) 14:56:47履歴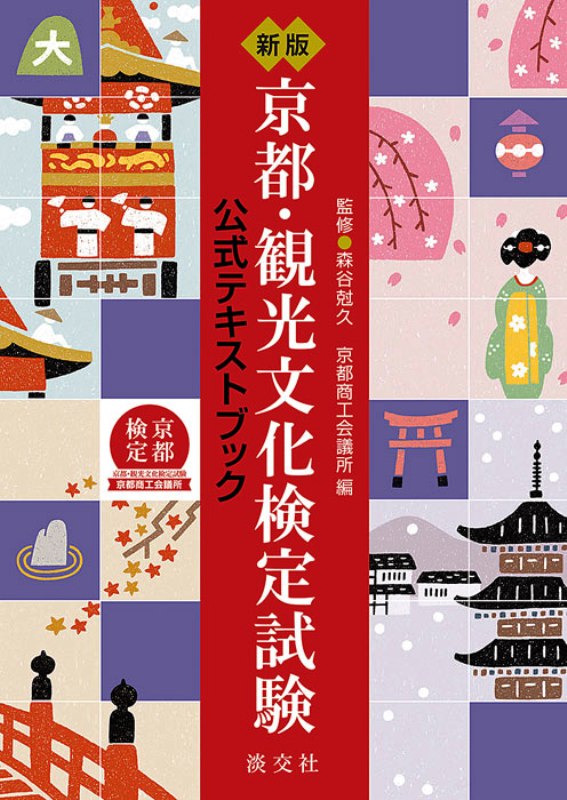
コメントをかく