☆ただし、以下のワードについては、小論文内に必ず含むこと
- 江戸幕府における役職
- 遠州が師事した茶人
- 遠州が主張した好みといわれる茶風
- 遠州作と伝わる国宝の茶室
- 龍光院内に建てた子院

解答チェック
《解答例》※これらのポイントうち、赤字のキーワード部分を含む解説を適正に記述することができて正答 公式テキスト[増]148・160ページ/[新]??ページ
◦ 小堀遠州は本名を小堀政一といい、天正7年(1579)に豊臣秀長の家臣であった小堀正次の長男として生まれた。
◦ 秀長の死後、文禄4年(1595)に秀吉の配下に付くことになり、伏見に移り秀吉の給仕役となり茶席にも度々同行した。そこで、千利休やその後師事することになる古田織部とも出会い
一番弟子となる。
◦ 慶長3年(1598)に秀吉が死去したのちは、正次・政一父子は徳川家康に仕えた。その際、正次は関ヶ原の戦いで勲功を得て備中松山城を賜り、備中松山藩の初代藩主となった。その後、
25歳の時に父の跡を継ぎ、政一も同藩主となった。
◦ 一方、政一も家康に忠実に仕え、慶長13年(1608)には駿府城普請奉行となり、城の修理の責任者を任された。その功で、従五位下遠江守に叙任され、小堀遠州と称するようになった。
◦ その後も、河内国奉行や近江国奉行を歴任し、元和9年(1624)には伏見奉行に任ぜられた。
◦ また、遠州は茶の湯には身分格式が重んじられなければならないと主張し、大名茶人の間で「綺麗さび」と呼ばれる新しい意匠を創出しつつ書院的な茶室を好んだ。
◦ そんな遠州が作った代表的な茶室といわれるのが、大徳寺の塔頭である龍光院の書院にある「密庵席(みったんせき)」(国宝)である。
◦ さらに慶長17年(1612)には龍光院内に孤篷庵(こほうあん)を建て、寛永20年(1643)に庭に茶室「忘筌席(ぼうせんせき)」や書院「直入軒」が造られた。忘筌席の庭には露結の手水鉢と
寄燈籠を近景とし、背後の直入軒の庭を遠景として取り込んだ構成で知られる。
![]() kyo_miyato 2017年05月05日(金) 15:03:07履歴
kyo_miyato 2017年05月05日(金) 15:03:07履歴![]() kyo_miyato 2017年05月05日(金) 15:03:07履歴
kyo_miyato 2017年05月05日(金) 15:03:07履歴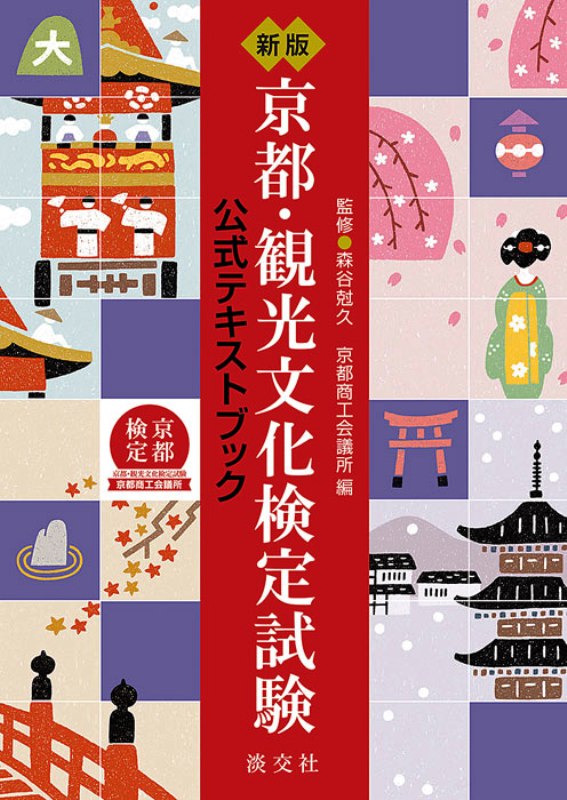
コメントをかく