☆ただし、以下のワードについては、小論文内に必ず含むこと
- 流祖が御殿舞などを学んだ奉公先
- 流儀の紋
- 京都博覧会の余興として「都をどり」を振付した三世家元の本名
- これまで、「都をどり」が開催されてきた会場
- 三世と四世家元をモデルとした戯曲『京舞』の作者

解答チェック
《解答例》※これらのポイントうち、赤字のキーワード部分を含む解説を適正に記述することができて正答 公式テキスト[増]196・200ページ/[新]245・248ページ
◦ 京舞井上流は、寛政年間(1789〜1801)の頃に流祖の井上サトが近衛家で風流舞を学び、「八千代」という名と近衛家の井菱の紋「近衛菱」をもらい流派を築いた。
◦ 明治4年(1871)に開催された第1回京都博覧会の余興(附博覧)として「都をどり」が初めて催され、京舞井上流三世家元の井上八千代こと片山春子によって振り付けされた。
◦ それ以降、「都をどり」は毎年4月1〜30日の1ヵ月間、祇園甲部歌舞練場において芸舞妓が日ごろの研鑽に努める芸事を披露されている。
◦ 北条秀司によって書かれた戯曲『京舞』(昭和37年発行)は、三世春子とその孫で四世愛子をモデルとした笑いあり涙ありの作品として舞台化されている。
◦ なお、四世家元(片山愛子)および当代(観世三千子/愛子の孫)は、「人間国宝」に認定されている。
![]() kyo_miyato 2017年05月05日(金) 16:27:22履歴
kyo_miyato 2017年05月05日(金) 16:27:22履歴![]() kyo_miyato 2017年05月05日(金) 16:27:22履歴
kyo_miyato 2017年05月05日(金) 16:27:22履歴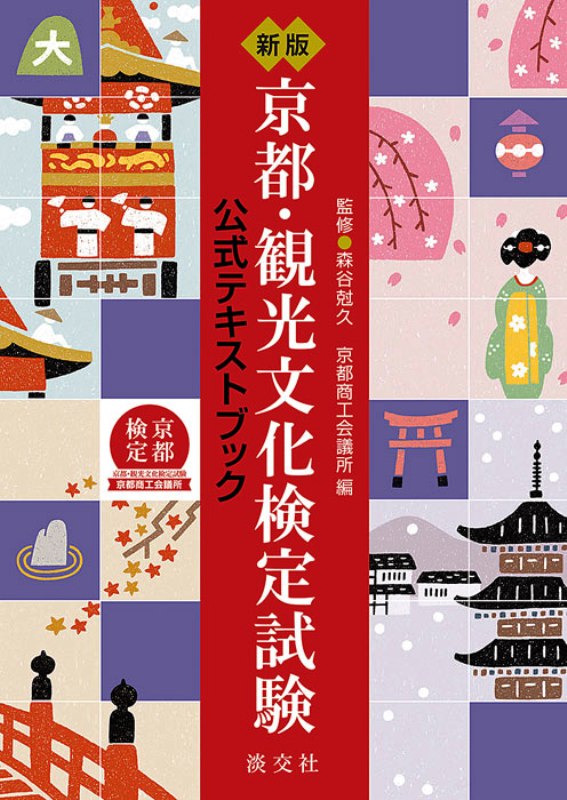
コメントをかく