最終更新:
![]() kyo_miyato 2017年05月05日(金) 15:51:07履歴
kyo_miyato 2017年05月05日(金) 15:51:07履歴
(31) 祇園祭で各山鉾町が行う神事始めを何と呼ぶか。
(32) 五山の送り火の「船形」の点火の合図となる鐘を鳴らしたり、西賀茂船山の山麓で住職が読経を行ったりする寺院はどこか。
(33) 時代祭と同じ日に、京都三大奇祭のひとつが行われる神社はどこか。
(34) 晩年を泉涌寺の近くで過ごしたとも伝わり、その境内に歌碑がある人物は誰か。
(35) 江戸時代後期に煎茶手前を創案し、その家元として公家や文人に煎茶道を流行させ、のちにその喫茶法が『喫茶弁』として出版された人物は誰か。
(36) 江戸時代初め、観世流宗家が江戸に移ったあと、最初に観世京屋敷の管理と諸用向きを取り仕切った観世流ワキ方福王流の家元は誰か。
(37) 江戸時代、宮中への参勤を主として京都で活躍した狂言の和泉流の祖で、尾張徳川家に召し抱えられた人物は誰か。
(38) 京のブランド産品(ブランド京野菜)で、大粒でコクと甘みが特徴の黒大豆の枝豆は何というブランド名で生産されているか。
(39) 鬼に強いといわれ、京町屋の小屋根に祀られる風習がある魔除けの置き物は何か。

(40) 織屋の丁稚と織子のいがみ合いから起きた「撞かずの鐘」伝説が残る寺院はどこか。
(32) 五山の送り火の「船形」の点火の合図となる鐘を鳴らしたり、西賀茂船山の山麓で住職が読経を行ったりする寺院はどこか。
(33) 時代祭と同じ日に、京都三大奇祭のひとつが行われる神社はどこか。
(34) 晩年を泉涌寺の近くで過ごしたとも伝わり、その境内に歌碑がある人物は誰か。
(35) 江戸時代後期に煎茶手前を創案し、その家元として公家や文人に煎茶道を流行させ、のちにその喫茶法が『喫茶弁』として出版された人物は誰か。
(36) 江戸時代初め、観世流宗家が江戸に移ったあと、最初に観世京屋敷の管理と諸用向きを取り仕切った観世流ワキ方福王流の家元は誰か。
(37) 江戸時代、宮中への参勤を主として京都で活躍した狂言の和泉流の祖で、尾張徳川家に召し抱えられた人物は誰か。
(38) 京のブランド産品(ブランド京野菜)で、大粒でコクと甘みが特徴の黒大豆の枝豆は何というブランド名で生産されているか。
(39) 鬼に強いといわれ、京町屋の小屋根に祀られる風習がある魔除けの置き物は何か。

(40) 織屋の丁稚と織子のいがみ合いから起きた「撞かずの鐘」伝説が残る寺院はどこか。
タグ

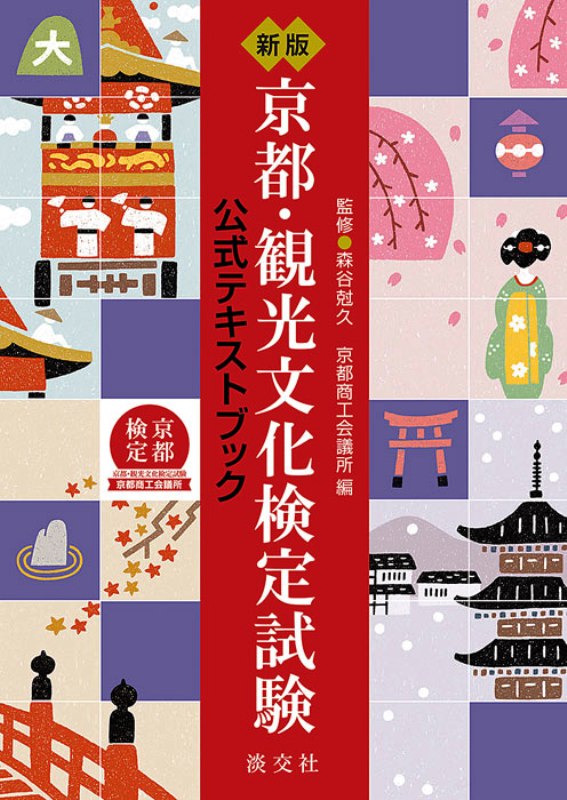
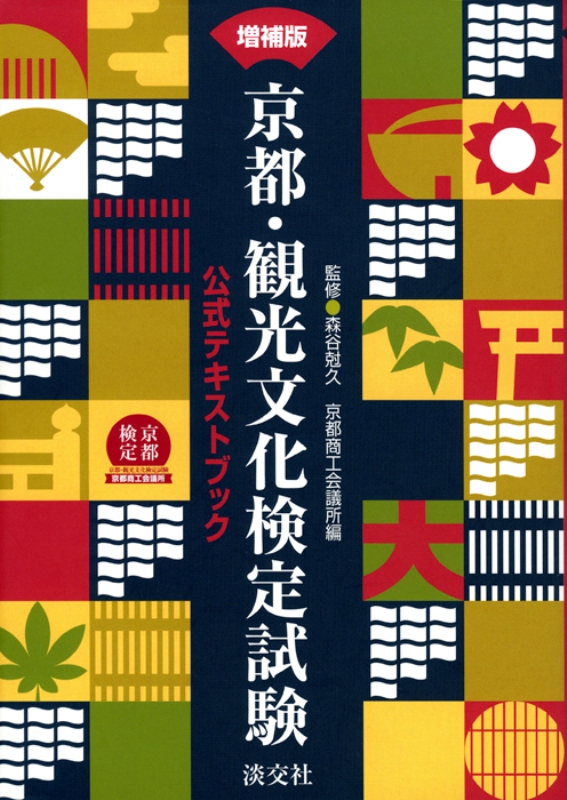
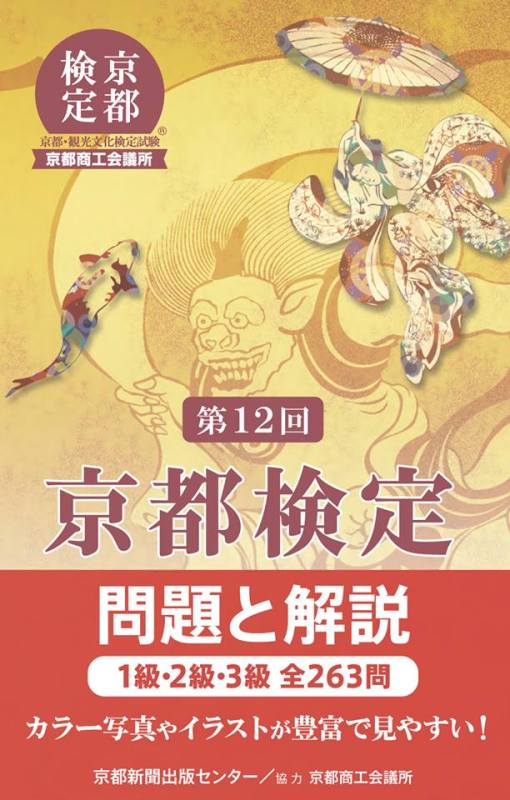
コメントをかく