最終更新:
![]() kyo_miyato 2017年05月05日(金) 16:06:03履歴
kyo_miyato 2017年05月05日(金) 16:06:03履歴
| 「京の七口と街道」とは、出入り口が「七つ」あるという意味ではなく、京と諸国を結ぶ出入り口の総称と考えられる。例えば、公家の近衛信尹の日記『三藐院記(さんみゃくいんき)』は、天正19年(1591)に豊臣秀吉が御土居を築き、そこに「十の口」を設けたと記している。 東海道の東山道に通じる三条口は粟田口とも言い、三条大橋や蹴上付近にあった。現在、三条大橋の西側には『東海道中膝栗毛』の二人の主人公である( 41 )像がある。東国への幹線道と通じるため古くから交通の要衝であり、山城国と近江国の国境に設けられた( 42 )は、小倉百人一首に彩られた蝉丸や清少納言の和歌の歌枕に詠まれている。 御土居の西南に設けられた出入り口は、現在もJR山陰本線( 43 )駅にその名が残る。山陰道へ通じており、かつての国境であった大枝山の( 44 )の峠には、酒天童子のものと伝わる首塚がある。大枝山近辺は都から追放された賊などの棲み処であり、鬼が住まうと信じられていた。 長坂口は清蔵口または北丹波口ともいい、本阿弥光悦が徳川家康から拝領したことで知られる( 45 )の地から長坂峠を越えて杉坂に至る。途中、峠を経由する若狭街道の出入り口は( 46 )口で近隣の町名でその名が残る。慶長4年(1868)に立てられた寺町今出川付近の道標には、比叡山などへ通じていることが刻まれている。 賀茂川に架かる出雲路橋西の鞍馬口は、上賀茂・市原・鞍馬へ至る鞍馬海道の出入り口で、その西にある( 47 )の地蔵堂に祀られる鞍馬口地蔵は、「京の六地蔵めぐり」のひとつである。志賀街道(山中越え)の出入り口である荒神口には正式名称を( 48 )という寺院があり、その通称「清荒神」がその名の由来である。 鳥羽街道(鳥羽の作道)や( 49 )街道の出入り口であった東寺口は、詳細な場所こそ明確ではないが、現在も東寺の西南が京阪国道や国道171号線の起点と なっており、往時が偲ばれる。 五条橋口や竹田口からは伏見街道や竹田海道といった伏見への街道が伸び、さらに道は奈良へと続く。豊臣秀吉が伏見城築城の際に、宇治川に築いた( 50 )橋は幕末の動乱で焼け、現在はその場所に観月橋が架かる。 |
(41) 東海道の東山道に通じる三条口は粟田口とも言い、三条大橋や蹴上付近にあった。現在、三条大橋の西側には『東海道中膝栗毛』の二人の主人公である( )像がある。
(42) 東国への幹線道と通じるため古くから交通の要衝であり、山城国と近江国の国境に設けられた( )は、小倉百人一首に彩られた蝉丸や清少納言の和歌の歌枕に詠まれている。
(43) 御土居の西南に設けられた出入り口は、現在もJR山陰本線( )駅にその名が残る。
(44) 山陰道へ通じており、かつての国境であった大枝山の( )の峠には、酒天童子のものと伝わる首塚がある。大枝山近辺は都から追放された賊などの棲み処であり、鬼が住まう
と信じられていた。
(45) 長坂口は清蔵口または北丹波口ともいい、本阿弥光悦が徳川家康から拝領したことで知られる( )の地から長坂峠を越えて杉坂に至る。
(46) 途中、峠を経由する若狭街道の出入り口は( )口で近隣の町名でその名が残る。慶長4年(1868)に立てられた寺町今出川付近の道標には、比叡山などへ通じていることが
刻まれている。
(47) 賀茂川に架かる出雲路橋西の鞍馬口は、上賀茂・市原・鞍馬へ至る鞍馬海道の出入り口で、その西にある( )の地蔵堂に祀られる鞍馬口地蔵は、「京の六地蔵めぐり」の
ひとつである。
(48) 志賀街道(山中越え)の出入り口である荒神口には正式名称を( )という寺院があり、その通称「清荒神」がその名の由来である。
(49) 鳥羽街道(鳥羽の作道)や( )街道の出入り口であった東寺口は、詳細な場所こそ明確ではないが、現在も東寺の西南が京阪国道や国道171号線の起点となっており、往時が
偲ばれる。
(50) 五条橋口や竹田口からは伏見街道や竹田海道といった伏見への街道が伸び、さらに道は奈良へと続く。豊臣秀吉が伏見城築城の際に、宇治川に築いた( )橋は幕末の動乱で
焼け、現在はその場所に観月橋が架かる。
タグ

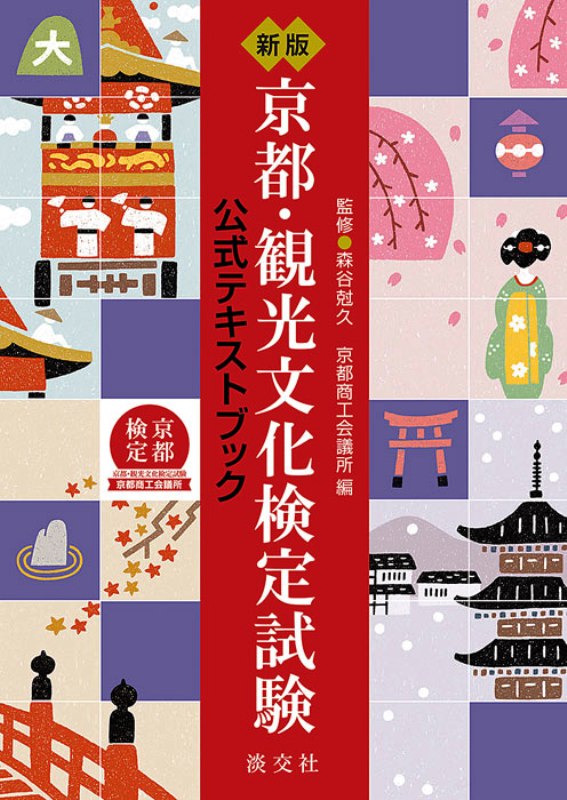
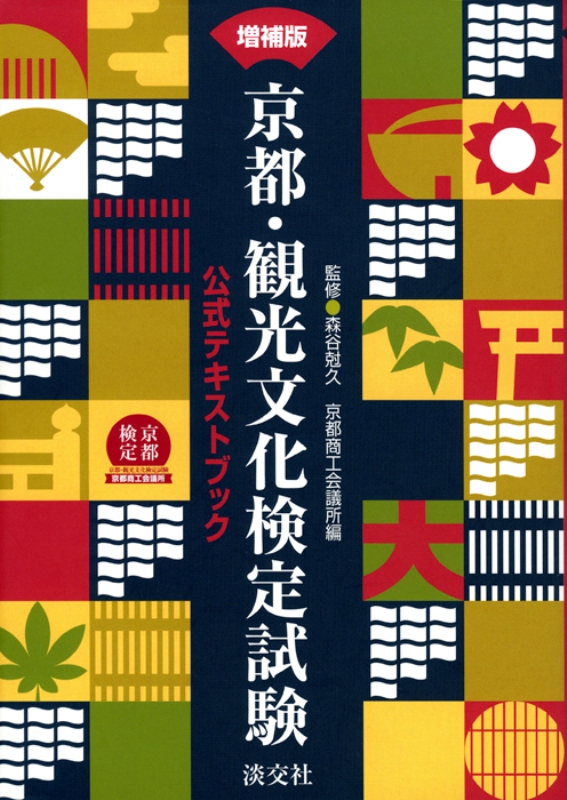
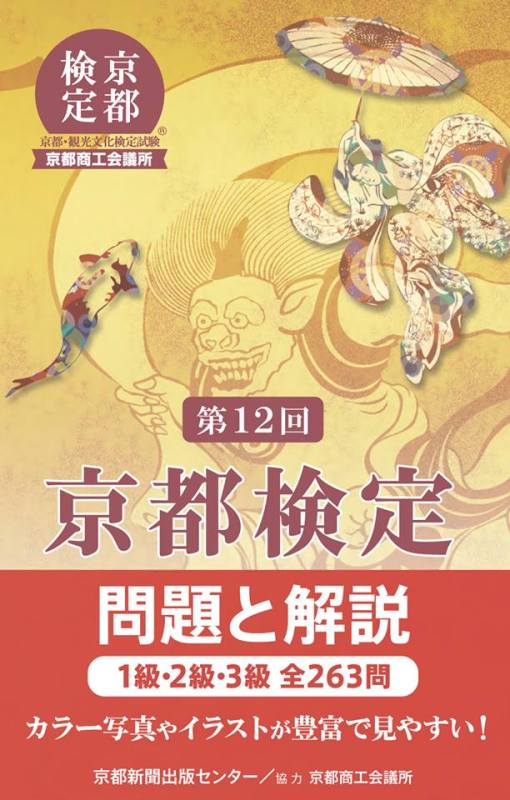
コメントをかく