☆ただし、以下のワードについては、小論文内に必ず含むこと
- 実家の家業
- 特に好んで描いた動物
- 現在は御物になっている相国寺に奉納した代表作
- 「若冲筆投げの間」と呼ばれる放丈がある寺院
- 平成28年に若冲の原画をもとに見送を新調した、祇園祭の鉾の名称

解答チェック
《解答例》※これらのポイントうち、赤字のキーワード部分を含む解説を適正に記述することができて正答 公式テキスト[増]115・168ページ/[新]147・214・216ページ
◦ 伊藤若冲は、正徳6年(1716)に京都の錦小路にあった青物問屋の長男として生まれ、22歳の時に父が他界したため家業を継いだ。
◦ 家業のかたわら30歳を過ぎてから本格的に絵を描くようになり、42歳の時に代表作となる濃彩花鳥画『動植綵絵(さいえ)』シリーズに着手する。
◦ これは、身の回りの動植物を鋭い表現力で描かれたもので、完成まで10年の歳月を要して全30作品からなる構成となっており、現在は相国寺の所蔵となっている。
◦ 若冲の作品といえばやはり「鶏」の絵が代名詞となっており、このほかにも多くの寺院や美術館などに屏風や襖絵、掛け軸としてその作品が残されている。
◦ 特に伏見区桃山の海宝寺の放丈の襖絵に描かれている「群鶏図」は若冲最後の作品といわれ、これ以降は筆を取らなかったことから「若冲筆投げの間」とも呼ばれている。
◦ 平成28年6月、祇園祭の前祭山鉾巡行で先頭を行く長刀鉾に飾られる「見送」が、生誕300年を迎えた伊藤若冲の「旭日鳳凰図」を原画をもとに新調された。
![]() kyo_miyato 2017年05月05日(金) 16:25:22履歴
kyo_miyato 2017年05月05日(金) 16:25:22履歴![]() kyo_miyato 2017年05月05日(金) 16:25:22履歴
kyo_miyato 2017年05月05日(金) 16:25:22履歴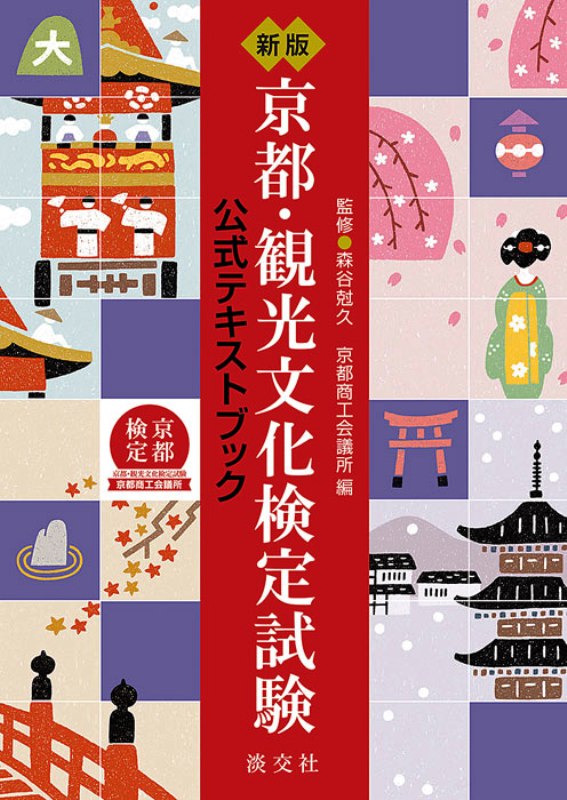
コメントをかく