最終更新:
![]() yayoi82912 2012年08月26日(日) 01:13:35履歴
yayoi82912 2012年08月26日(日) 01:13:35履歴
Junosの検証には大きく分けて3種類の方法がある。
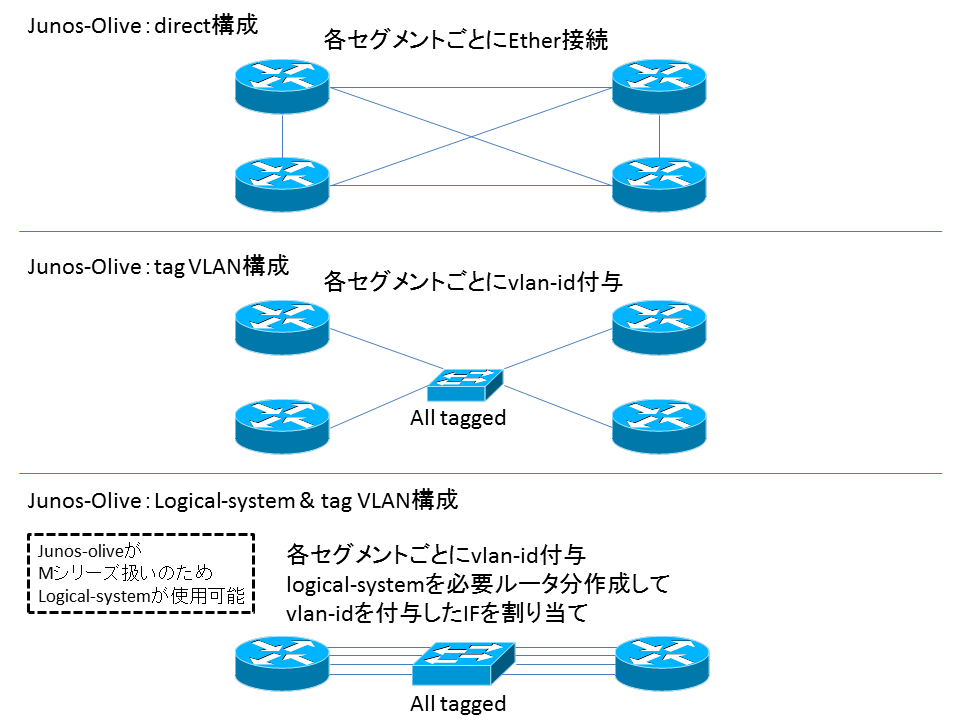
プロミスキャスモード Allow VMs だと他VMからはアクセス可能。
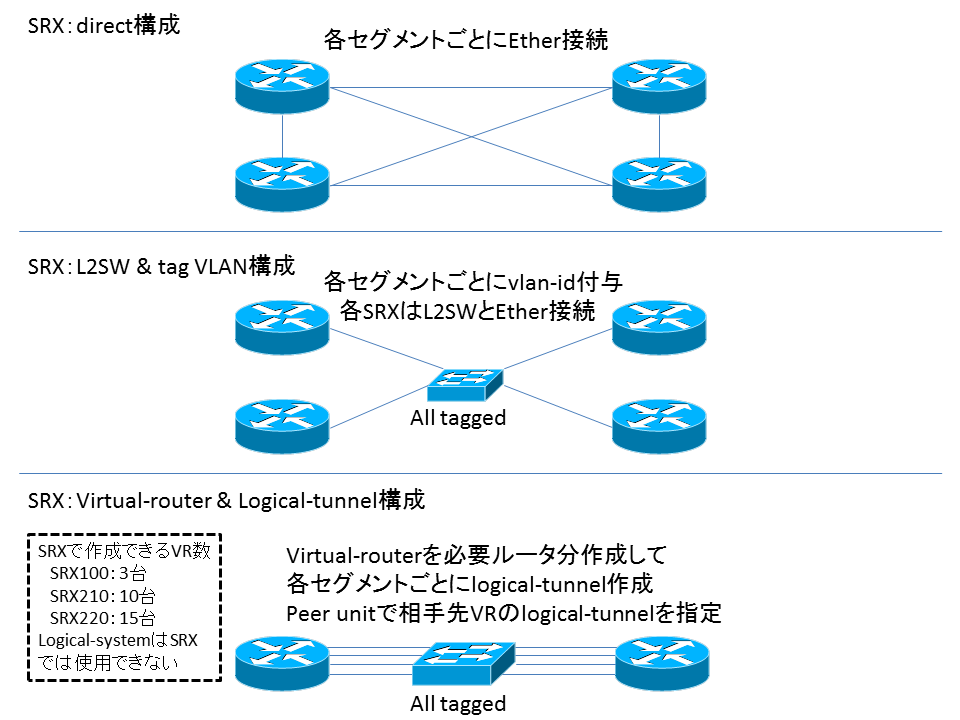
- CertExams版Juniper Network Simulator
- Juniper Olive(いわゆるエミュレーション)
- SRX等の比較的安めのJunos搭載機器(いわゆる実機)
- お手軽:トライアル版なら無料。Windowsインストーラで即使用可能。
- EXシリーズ(Switch)版もあるのでOliveで出来なそうなところは試してみてもいいかも。
- トライアル版では制限が多く、商用版でもあまり込み入ったことはできない。
- あくまでJNCIA-Junos等の作法のお勉強用。
- 買うと $29する。(3000円〜4000円なので安い方か?)
- Mac版は提供されていないのでBootCampや仮想PCにWindowsを入れる必要がある。
- 稼働させるPCの負荷が高い。
- 環境:MacBookAir(CPU Core i5 1.6GHz 2コア, メモリ4GB) BootCampのWindows7 Proffesional 64bitで
- 4台のJUNOS/QEMUホスト(メモリは256MB)を稼働させるとメモリが2.92GB使用中になる。7台くらいが限界か。
- RE, PFE, FPC, PIC, Craft-Interface等が存在しないためハード依存の検証(chassis系)が出来ない。
- VRRPの検証が出来ない。マルチキャストパケットを処理できないのか?
- (Giga/Fast)Ethernetポートしか使用できない。※SRXでも追加モジュールなしだと同じこと。
- Junosの入手が必要
- Oliveとしてのセットアップが面倒。うまくいかないこともある。
- MacだとQEMUのセットアップも必要で面倒。
- tag vlanやlogical-systemだとGNS3画面とは別に論理構成図を用意しないと分からなくなる。
- monitor interface trafficなどで物理IF一覧によるトラフィック変化の確認がしずらい。
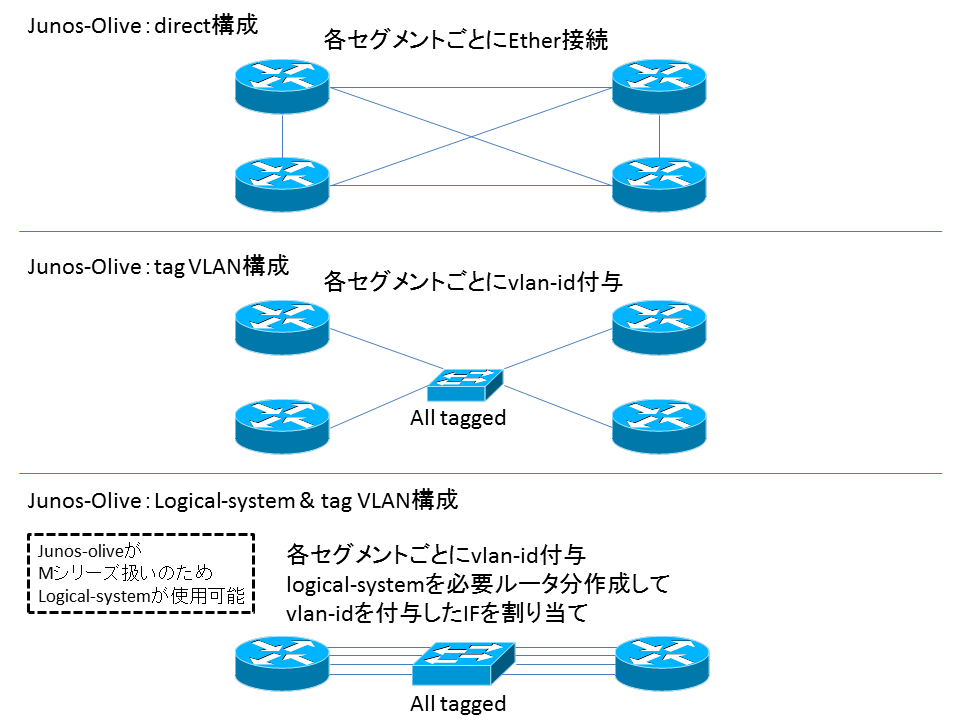
JUNOS 7.4でLogical routerとしてリリースされ
JUNOS 9.3からはLogical systemと名称が改められた。
1台の物理ルータで最大15の論理ルータを作成可能。
Mシリーズ、MXシリーズが対応。
JUNOS 9.3からはLogical systemと名称が改められた。
1台の物理ルータで最大15の論理ルータを作成可能。
Mシリーズ、MXシリーズが対応。
- PC(Windowsの場合)にMicrosoft Loopback Adapterをインストールする。
- 名称をわかりやすい Loopback などに変更する。
- 上記の Loopback のIFにIPアドレスを割り当てる。Default-GWは無くてもいい。
- GNS3にCloudを作る。NIOイーサネット(Generic_NIO)にLoopbackを追加する。
- JUNOS(QEMUホスト)--SW2--SW3--Cloud(Loopback)のように接続する。
- QEMUホストとCloudは直接接続できないのでSW経由とする。
- 今後のホストやルータ追加も考えてSWは念のため多段にしておく。
- JUNOSに em5 unit 0 インタフェースなどを作る。
- 上記のIFに Loopback と同じセグメントのIPアドレスを振る。
- JUNOSにデフォルトルートも設定しておく。
- set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.0.1.1
- Pingは飛ばないがPCからJUNOS側のIPアドレスにJ-WebやSSH等のアクセスが可能。
- J-Webの場合、JUNOSにはset system services web-management http
- ログインユーザIDとパスワードはJUNOS内に設定したものを使用する。
- Logical-systemごとにlogin-classを作ってuserをLogical-systemごとに作ったら便利
- Virtual BoxでWindowsを動作させその中でGNS3を動かす場合
プロミスキャスモード Allow VMs だと他VMからはアクセス可能。
- chassis系等ある程度、ハード依存の検証も可能。
- アクセスするPCの負荷はほとんどない(Telnet,SSH,HTTPなので)
- VPN環境等用意すれば外出先からでも利用可能。
- おそらく、動作はOliveより軽快だろう。(J-Webは怪しいが)
- 外出先からだとネット環境がないと利用できない。
- 出来ればVPN接続した方がいい。
- 台数をそろえるのに結構な費用が掛かる。
- 構成変更は手作業となるので、外出先からだと対応不可。
- L2SWとtag VLANで構成すれば設定変更のみで構成変更は可能。
- 利用の際には電源投入が必要。
- 外出先から思い立った時に使用するには不便。
- 発熱や電力(停電、落雷)等の環境起因での故障の心配がある。
- 基本的に(Giga/Fast)Ethernetポートしか使用できない。
- SRXのSerial IFモジュールもあるが高い。
- ATMやOC-3などはSRXでは対応していない。
- tag vlanやvirtual-routerだと物理構成とは別に論理構成図を用意しないと分からなくなる。
- monitor interface trafficなどで物理IF一覧によるトラフィック変化の確認がしずらい。
- ブランチ用のSRXだとBGP Route Reflectorになれない
- Virtual Routerだと出来ることが限られる可能性あり
- Logical-tunnelだとPoint to Point接続だけでマルチアクセス環境に出来ない?
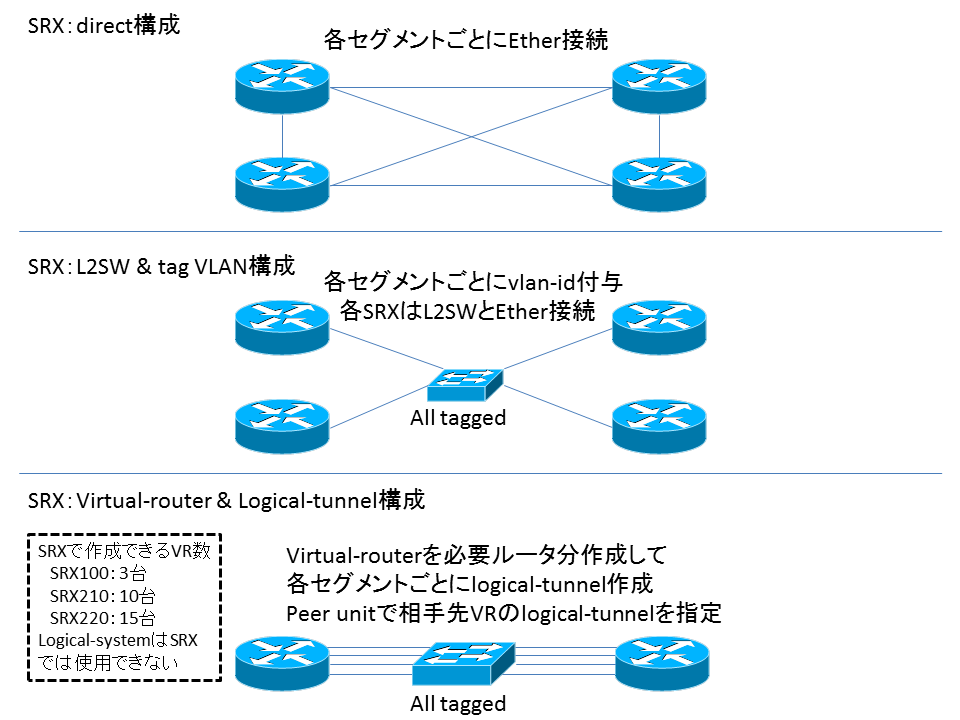
コメントをかく