(11)( )は長岡京遷都の際、桓武天皇の皇后であった藤原乙牟漏(ふじわら の おとむろ)が奈良の春日社の神霊を勧請したこと始まるとされている。

選択肢を表示/非表示
(ア)向日神社
(イ)平野神社
(ウ)松尾大社
(エ)大原野神社

解答チェック
《解答》
大原野神社 公式テキスト[増]64ページ/[新]80ページ
《要点》
延暦3年(784)、長岡京への遷都にあたり、藤原乙牟漏が春日社の神霊を勧請したこと始まる/応仁・文明の乱後、後水尾上皇が荒廃した社殿を再興
《参考》
長岡京遷都?,
大原野神社?
(12) 本殿が神社建築最古の遺構として知られる宇治上神社の境内に湧く名水は「( )」という。

選択肢を表示/非表示
(ア)紫雲水(しうんすい)
(イ)桐原水(きりはらすい)
(ウ)観世水(かんぜすい)
(エ)金色水(こんじきすい)

解答チェック
《解答》
桐原水(きりはらすい) 公式テキスト[増]68ページ/[新]84ページ
《要点》
明治維新まで宇治神社と共に「宇治離宮明神」と呼ばれた/本殿(国宝)は神社建築として最古/境内に湧く「桐原水」は宇治七名水のひとつで唯一現存
《参考》
宇治上神社?,
京都の世界遺産?,
宇治七名水?
(13) 芸能・芸術の上達を祈願する人から崇敬を受けている「芸能神社」は、( )の境内にある。

選択肢を表示/非表示
(ア)梅宮大社
(イ)新熊野神社(いまくまのじんじゃ)
(ウ)白峯神宮(しらみねじんぐう)
(エ)車折神社(くるまざきじんじゃ)

解答チェック
《解答》
車折神社(くるまざきじんじゃ) 公式テキスト[増]64ページ/[新]79ページ
《要点》
車折神社の境内には芸能の神を祀る芸能神社がある/芸能芸術の向上を祈願する人々から篤い信仰
《参考》
車折神社?
(14)( )は、日本三如来のひとつである薬師如来立像(重文)を本尊とし、「因幡堂(いなばどう)」とも称される。

選択肢を表示/非表示
(ア)仁和寺
(イ)六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)
(ウ)平等寺
(エ)法界寺

解答チェック
《解答》
平等寺 公式テキスト[増]??ページ/[新]104ページ(因幡堂の項)
《要点》
日本三如来⇒信州善光寺「阿弥陀如来」・嵯峨清凉寺「釈迦如来」・因幡堂「薬師如来」
《参考》
因幡堂?(平等寺)
(15)「御室(おむろ)」の地名は、先帝の遺志を継いで仁和寺の開基となった( )が出家後、寺内に自らの御室(僧房)を建立したことに由来するといわれている。

選択肢を表示/非表示
(ア)嵯峨天皇(さがてんのう)
(イ)宇多天皇(うだてんのう)
(ウ)花園天皇
(エ)清和天皇

解答チェック
《解答》
宇多天皇(うだてんのう) 公式テキスト[増]89ページ/[新]111ページ
《要点》
真言宗御室派の総本山で、世界文化遺産/仁和4年(888)に宇多天皇が、前年に崩御した父の光考天皇の遺志を継いで創建/昌泰2年(899)に出家し、御室(僧房)を建てたことが地名の由来
《参考》
仁和寺?
(16)「百々御所(どどのごしょ)」とも呼ばれる( )は、歴代皇女ゆかりの人形を春秋公開して供養を行っている。

選択肢を表示/非表示
(ア)慈受院
(イ)大聖寺
(ウ)宝鏡寺
(エ)霊鑑寺

解答チェック
《解答》
宝鏡寺 公式テキスト[増]89・222ページ/[新]111・295ページ
《要点》
百々町にあることから「百々御所」と呼ばれる/毎年、10月14日に一年間に納められた人形の供養を行うことから「人形寺」とも呼ばれる/境内に人形塚がある
《参考》
仁和寺?
(17) 平安初期に平親範(たいら の ちかのり)が平家ゆかりの三寺(平等寺・尊重寺・護法寺)を合併して復興した( )は、その後江戸時代に山科で復興され
紅葉の名所となった門跡寺院である。

選択肢を表示/非表示
(ア)安祥寺(あんしょうじ)
(イ)勧修寺(かじゅうじ)
(ウ)随心院(ずいしんいん)
(エ)毘沙門堂

解答チェック
《解答》
毘沙門堂 公式テキスト[増]75ページ/[新]93ページ
《要点》
鎌倉時代初期に平親範が平等寺・尊重寺・護法寺を合併して復興/出雲寺から伝えられた毘沙門天像を本尊したことから毘沙門堂と称される/春は桜、秋は紅葉の名所
《参考》
毘沙門堂?
(18) 十一面観音立像(国宝)を本尊とする( )は、西国三十三所観音霊場の第17番札所である。

選択肢を表示/非表示
(ア)今熊野観音寺
(イ)頂法寺
(ウ)善峯寺(よしみねでら)
(エ)六波羅蜜寺

解答チェック
《解答》
六波羅蜜寺 公式テキスト[増]83ページ/[新]104ページ
《要点》
本尊は十一面観音立像(国宝)/西国三十三所観音霊場の第17番札所・洛陽三十三所観音霊場の第15番札所/境内に祀られている弁財天は都七福神まいりの札所
《参考》
六波羅蜜寺?
(19) 岩倉門跡とも呼ばれる( )は、磨かれた板の間に映える「床みどり」「床もみじ」で知られる。

選択肢を表示/非表示
(ア)実相院
(イ)円通寺
(ウ)曼殊寺
(エ)妙満寺

解答チェック
《解答》
実相院 公式テキスト[増]70ページ/[新]87ページ
《要点》
寛喜元年(1229)に創建されて以来、代々皇室・摂関家の子弟が入寺したことから「岩倉門跡」とも呼ばれる/「滝の間」に映り込む楓が「床みどり」「床もみじ」と呼ばれ四季折々の風情を見せる
《参考》
岩倉門跡?,
実相院?
(20) 宇治七名園のひとつの朝日茶園であった地に建てられた( )は、淀城主の永井尚政が再興した。

選択肢を表示/非表示
(ア)酬恩庵
(イ)興聖寺(こうしょうじ)
(ウ)石峰寺(せきほうじ)
(エ)萬福寺

解答チェック
《解答》
興聖寺(こうしょうじ) 公式テキスト[増]114ページ/[新]145ページ
《要点》
天福元年(1233)に道元が深草に道場として創建したのが始まり/その後、宇治七名園のひとつの朝日茶園があった宇治山田に、廃絶していたが淀城主の永井尚政が菩提寺として再興
《参考》
興聖寺?
![]() kyo_miyato 2017年05月02日(火) 20:18:11履歴
kyo_miyato 2017年05月02日(火) 20:18:11履歴
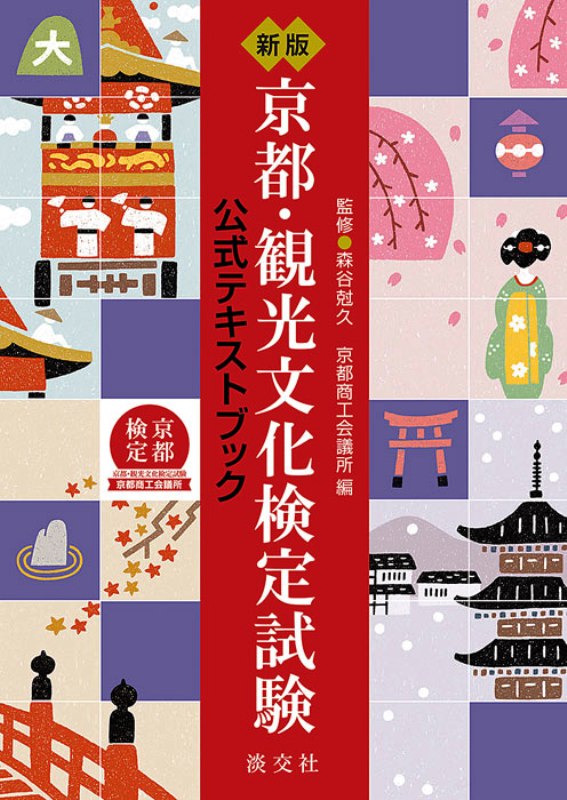
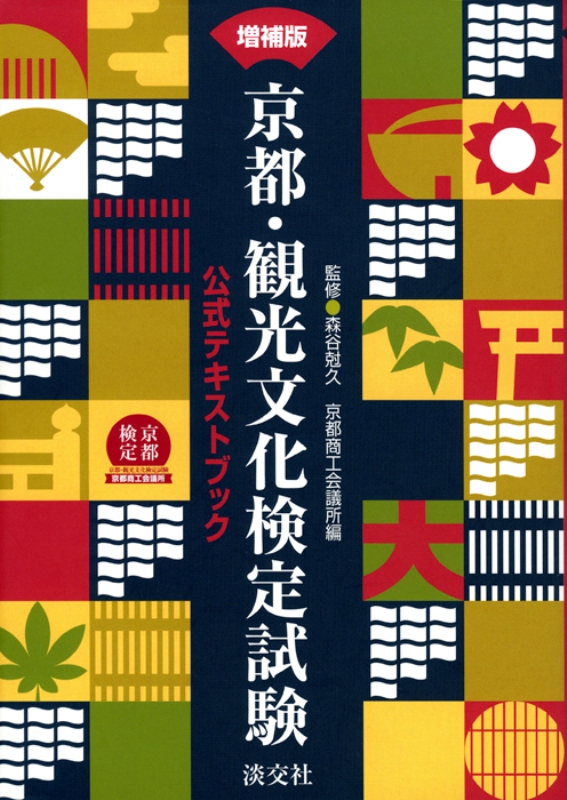
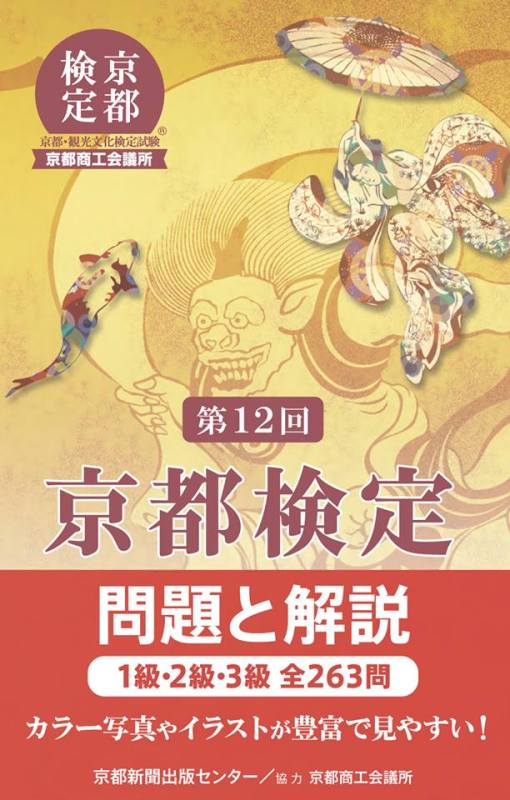
コメントをかく