ギリシャ王国 Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος | |
| 国の標語: Ἐλευθερία ἢ Θάνατος 自由か死か | |
| 国歌: Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν 自由への賛歌 | |
| 公用語 | ギリシャ語 |
| 首都 | ナフプリオ(1832年 - 1834年) アテネ(1834年 - ) |
| 最大の都市 | アテネ |
| 政府 国王 1832年 - 1862年 オソン1世 1964年 - コンスタンティノス2世 首相 1833年 - 1833年 スピリドン・トリクピス 1997年 - ゲオルギオス・ラリス | |
| 面積 総計 ㎢ | |
| 人口 総計 11,210,000人 | |
| GDP 合計 2035億3725万9368.37 US$ | |
| ロンドン議定書により独立 憲法制定 第二共和政成立 王政復古 | 1832年8月30日 1843年9月3日 1924年3月25日 1935年11月3日 |
| 通貨 | ドラクマ(₯) |
| 時間帯 | UTC+2 (DST:+3) |
| ISO 3166-1 | GR/GRC |
| ccTLD | .gr |
| 国際電話番号 | 30 |
1941年のイタリアによるギリシャ侵攻(イタリア・ギリシャ戦争)では旧アルバニア国境まで押し込むがドイツの参戦により降伏し、王国政府残党はエジプト王国首都 カイロで亡命政府を樹立した。
しかし北アフリカ戦線においてエジプトが降伏すると、亡命政府はイギリス首都 ロンドンへ機能を移転することを余儀なくされた。だが、第二次世界大戦における敗北が確立すると亡命政府は解体されてしまった。
しかし戦後もイギリス政府によって秘密裏に支援が行われており、本土帰還を諦めてはいなかった。
しかし北アフリカ戦線においてエジプトが降伏すると、亡命政府はイギリス首都 ロンドンへ機能を移転することを余儀なくされた。だが、第二次世界大戦における敗北が確立すると亡命政府は解体されてしまった。
しかし戦後もイギリス政府によって秘密裏に支援が行われており、本土帰還を諦めてはいなかった。
ギリシャ国(統治政府) 
詳しくは「第三次バルカン戦争」を参照
ギリシャ国は国民から支持を失いつつあり、早急な支持回復が求められていた。そこでギリシャは旧領奪還を掲げて1955年6月2日に起きた第三次バルカン戦争においてセルビア陣営として参戦を決定した。セルビアとの交渉の結果、旧ギリシャ領返還が確約されると反セルビア陣営に宣戦布告した。6月6日、ギリシャはブルガリア占領地域に進軍を開始した。11月1日、アルバニアがコソボ問題により同盟関係が決裂しセルビアにも宣戦布告するとギリシャはアルバニア対応に追われることになった。3月12日にブルガス条約によってセルビア・ブルガリア両国が事実上の停戦状態になるとギリシャ・ブルガリアの戦闘は激化した。しかし、5月9日にブルガリアの離脱が決まるとブルガリア政府はギリシャとの戦闘停止を決定し旧ギリシャ領の返還が明記されたアテネ条約を締結し、両国は休戦協定に調印した。
ギリシャ国は国民から支持を失いつつあり、早急な支持回復が求められていた。そこでギリシャは旧領奪還を掲げて1955年6月2日に起きた第三次バルカン戦争においてセルビア陣営として参戦を決定した。セルビアとの交渉の結果、旧ギリシャ領返還が確約されると反セルビア陣営に宣戦布告した。6月6日、ギリシャはブルガリア占領地域に進軍を開始した。11月1日、アルバニアがコソボ問題により同盟関係が決裂しセルビアにも宣戦布告するとギリシャはアルバニア対応に追われることになった。3月12日にブルガス条約によってセルビア・ブルガリア両国が事実上の停戦状態になるとギリシャ・ブルガリアの戦闘は激化した。しかし、5月9日にブルガリアの離脱が決まるとブルガリア政府はギリシャとの戦闘停止を決定し旧ギリシャ領の返還が明記されたアテネ条約を締結し、両国は休戦協定に調印した。
詳しくはギリシャ内戦を参照
第三次バルカン戦争に勝利したギリシャ国だが、国民からの支持はなかなか回復しなかった。それは新たに首相となったエクター・ツィロニコスが経済政策に失敗しており、戦費返済の課税や奪還した地域の治安悪化などが挙げられる。これらの対応に遅れたことから1956年7月1日にテッサロニキで「56年の反政府運動」が起きた。この運動はツィロニコスの過激な弾圧によってわずか1日で鎮圧されたが、全土各地に影響は普及し各地で潜伏していたレジスタンス残党が蜂起した。
56年の反政府運動に呼応して放棄した共産党・民族解放戦線はエーゲ・マケドニアなどの地域を占領し臨時民主政府結成宣言を行った。同時期、ギリシャ亡命政府もエジプト・アラブ共和国での補給支援を得てクレタ島に上陸し、ギリシャ国政府への事実上の宣戦布告を行った。これによりツィロニコスは失脚。ニコラオス・ブーランタスが首相となり、反政府組織への対応に追われた。ブーランタスは「テッサロニキの戦い」、クレタ島の戦いなど相次いで敗北し亡命政府も上陸作戦を決行し本土へ進出した。この事態にブーランタスはテッサロニキだけでなく、アテネまでもが陥落すればギリシャの歴史・ギリシャ国の正統性は失墜する等としてラリサへの遷都を行った。しかしラリサ市民からは反発を生み、アテネ時代よりも政権は不安定なものとなった。民主政府のテッサロニキ攻略、亡命政府のアテネ入城をもってラリサでも武装蜂起が起き、ギリシャ国政府は亡命政府に対して降伏した。
第三次バルカン戦争に勝利したギリシャ国だが、国民からの支持はなかなか回復しなかった。それは新たに首相となったエクター・ツィロニコスが経済政策に失敗しており、戦費返済の課税や奪還した地域の治安悪化などが挙げられる。これらの対応に遅れたことから1956年7月1日にテッサロニキで「56年の反政府運動」が起きた。この運動はツィロニコスの過激な弾圧によってわずか1日で鎮圧されたが、全土各地に影響は普及し各地で潜伏していたレジスタンス残党が蜂起した。
交戦勢力 | |
| ギリシャ国 ・軍部(過激派) | ギリシャ亡命政府 ・王国軍 ・軍部(穏健派) 臨時民主政府 ・ギリシャ民主軍 民族解放戦線 |
指導者・指揮官 | |
| エクター・ツィロニコス (クレタ島上陸によって失脚) ニコラオス・ブーランタス ・ゲオルギオス・バコス | パウロス1世 ・アレクサンドロス パパゴス ニコラオス ザカリアディス ・マルコス バフィアディス パスカル・ミトレフスキー |
56年の反政府運動に呼応して放棄した共産党・民族解放戦線はエーゲ・マケドニアなどの地域を占領し臨時民主政府結成宣言を行った。同時期、ギリシャ亡命政府もエジプト・アラブ共和国での補給支援を得てクレタ島に上陸し、ギリシャ国政府への事実上の宣戦布告を行った。これによりツィロニコスは失脚。ニコラオス・ブーランタスが首相となり、反政府組織への対応に追われた。ブーランタスは「テッサロニキの戦い」、クレタ島の戦いなど相次いで敗北し亡命政府も上陸作戦を決行し本土へ進出した。この事態にブーランタスはテッサロニキだけでなく、アテネまでもが陥落すればギリシャの歴史・ギリシャ国の正統性は失墜する等としてラリサへの遷都を行った。しかしラリサ市民からは反発を生み、アテネ時代よりも政権は不安定なものとなった。民主政府のテッサロニキ攻略、亡命政府のアテネ入城をもってラリサでも武装蜂起が起き、ギリシャ国政府は亡命政府に対して降伏した。
内戦終結後、ギリシャ国政府関係者の裁判が行われた。しかしこの裁判には臨時民主政府が参加することはなかった。あくまで亡命政府に降伏したからである。
幹部の多くが絞首刑、もしくは無期禁固刑、残りの者は政界永久追放や年金支給無期限延長などが下された。
そしてギリシャ国政府に代わる新政府の樹立が行われ、亡命政府・臨時民主政府の統合が発表。国王 パウロス1世は内戦の英雄 アレクサンドロス・パパゴスを新政府首相に任命した。パパゴスは新政府の閣僚に亡命政府議員を登用。これは臨時民主政府側の反発を生み、しばらくして民主政府は新政府からの離脱を宣言した。
幹部の多くが絞首刑、もしくは無期禁固刑、残りの者は政界永久追放や年金支給無期限延長などが下された。
そしてギリシャ国政府に代わる新政府の樹立が行われ、亡命政府・臨時民主政府の統合が発表。国王 パウロス1世は内戦の英雄 アレクサンドロス・パパゴスを新政府首相に任命した。パパゴスは新政府の閣僚に亡命政府議員を登用。これは臨時民主政府側の反発を生み、しばらくして民主政府は新政府からの離脱を宣言した。
新政府離脱後の臨時民主政府は名を社会国民政府と改め、パパゴスを自称忠臣の独裁者と非難した。だが主な構成組織のギリシャ共産党内で政治争いが起き、パパゴスはこの隙を逃さず社会国民政府を構成する組織の非合法化を発表。各地で構成員が逮捕され始めた。1960年までには主要人物の大半を逮捕し共産党・民族解放戦線は事実上の壊滅状態に陥った。残った幹部も国外逃亡や潜伏し残党として活動を続けたがもはや政府転覆を行えるほどの力を失った。
詳しくは「キプロス共和国」を参照
キプロスが南北で併合された後、共和国政府は解体された。しかしイオアニス・クレリデスは共和国政府をキプロス州へ継承すべきと主張した。
マカリオス3世の共和国政府の解体、クレリデスの共和国政府継承の議論は本土へ持ち込まれ、パパゴス首相は共和国政府継承を主張し、カラマンリス副首相・外務大臣は解体を主張した。
両者の言い分として、
パパゴス陣営は「キプロス共和国はギリシャ人国家として昔より知られているのだから政府継承は正当」であるとし、カラマンリス陣営は「キプロス共和国はトルコ系とギリシャ系の双方に権力があったのだから一方的な継承はオスマンとの対立を生むだけ。そもそも単なる自治体へ政府を継承させるなど国家の根本を揺るがす」と主張した。ギリシャ議会でも大論争を招いたが、最終的にパパゴス政権下では継承を認めないもののキプロス州議会(キプロス代議院)は共和国時代を踏襲ということになった。(これによってトルコ系議席も健在することになってしまった)
後のカラマンリス・ラリス両政権下においても依然として政府継承は認められていない。
マカリオス3世の共和国政府の解体、クレリデスの共和国政府継承の議論は本土へ持ち込まれ、パパゴス首相は共和国政府継承を主張し、カラマンリス副首相・外務大臣は解体を主張した。
両者の言い分として、
パパゴス陣営は「キプロス共和国はギリシャ人国家として昔より知られているのだから政府継承は正当」であるとし、カラマンリス陣営は「キプロス共和国はトルコ系とギリシャ系の双方に権力があったのだから一方的な継承はオスマンとの対立を生むだけ。そもそも単なる自治体へ政府を継承させるなど国家の根本を揺るがす」と主張した。ギリシャ議会でも大論争を招いたが、最終的にパパゴス政権下では継承を認めないもののキプロス州議会(キプロス代議院)は共和国時代を踏襲ということになった。(これによってトルコ系議席も健在することになってしまった)
後のカラマンリス・ラリス両政権下においても依然として政府継承は認められていない。
1996年12月1日、カラマンリス首相の体調悪化説が濃厚となり次期首相をめぐって閣僚や党幹部が動き始めていた。
1997年2月、カラマンリスは一度首相を辞任するも臨時首相として再度就任、その後臨時首相を辞任し4代目首相にゲオルギオス・ラリス(ギリシャ国首相 イオアニス・ラリスを父にもつ)が就任した。6月、テッサロニキで極右の国民戦線による左派諸党連合構成員への暴力事件(初期に被害を受けた民間人は構成員ではないと後に発覚)が発生した。警察による対応も虚しく左派諸党連合は国民戦線へ被害者に代わって報復を宣言。暴動事件へと発展した。当初、政府はあくまで軍の派遣は行わないとしたが状況は次第に悪化し国民戦線によって当市市役所は占拠されテッサロニキ市長など多くの死者を出した。
左派諸党連合穏健派は今回の報復宣言は過激派による独断専行であり穏健派は事態終息を望むとして政府に対して過激派・国民戦線への共同戦線を要請した。
受諾した政府軍は国民戦線への攻撃を強め、残党が籠城するビルが爆発。(集団自決と見られる。)
最終的に、穏健派に属する次席(事実上の指導者)と過激派による和平交渉が行われるが、交渉場所で爆発が発生し連絡が途絶。両派は該当幹部らを死亡したと認定し指導部不在となり崩壊した。後に、両組織残党を対象とした警戒体制が全土で敷かれた。
1997年2月、カラマンリスは一度首相を辞任するも臨時首相として再度就任、その後臨時首相を辞任し4代目首相にゲオルギオス・ラリス(ギリシャ国首相 イオアニス・ラリスを父にもつ)が就任した。6月、テッサロニキで極右の国民戦線による左派諸党連合構成員への暴力事件(初期に被害を受けた民間人は構成員ではないと後に発覚)が発生した。警察による対応も虚しく左派諸党連合は国民戦線へ被害者に代わって報復を宣言。暴動事件へと発展した。当初、政府はあくまで軍の派遣は行わないとしたが状況は次第に悪化し国民戦線によって当市市役所は占拠されテッサロニキ市長など多くの死者を出した。
左派諸党連合穏健派は今回の報復宣言は過激派による独断専行であり穏健派は事態終息を望むとして政府に対して過激派・国民戦線への共同戦線を要請した。
受諾した政府軍は国民戦線への攻撃を強め、残党が籠城するビルが爆発。(集団自決と見られる。)
最終的に、穏健派に属する次席(事実上の指導者)と過激派による和平交渉が行われるが、交渉場所で爆発が発生し連絡が途絶。両派は該当幹部らを死亡したと認定し指導部不在となり崩壊した。後に、両組織残党を対象とした警戒体制が全土で敷かれた。
行政府の長である首相は議会によって選出され国王により任命される。閣僚は首相の指名に基づき国王が任命する。
※ギリシャの首相も参照
※ギリシャの首相も参照
| 代 | 名前 | 在位期間 | 退位理由 |
ヴィッテルスバッハ家 | |||
| 初 | オソン1世 | 1832年 - 1862年 | 革命による廃位 |
グリュックスブルク家 | |||
| 2 | ゲオルギオス1世 | 1863年 - 1913年 | 暗殺 |
| 3 | コンスタンティノス1世 | 1913年 - 1917年 | 対立による廃位 |
| 4 | アレクサンドロス1世 | 1917年 - 1920年 | 崩御 |
| 摂政 | パヴロス・クンドゥリオティス | 1920年 | 辞任 |
| 摂政 | オルガ(ゲオルギオス1世妃) | 1920年 | 辞任 |
| 5 | コンスタンティノス1世(同) | 1920年 - 1922年 | クーデターによる廃位 |
| 6 | ゲオルギオス2世 | 1922年 - 1924年 1935年 - 1947年 | 共和制による廃位 崩御 |
| 7 | パウロス1世 | 1947年 - 1964年 | 崩御 |
| 8 | コンスタンティノス2世 | 1964年 - | |
| 省 | 大臣 | 副大臣 |
| 開発調整省 | ||
| 外務省 | アキレアス・カラマンリス | |
| 国防省 | ザンニス・ザンネタキス | マヌソス・パラギウダキス |
| 内務省 | ||
| 法務省 | ||
| 治安省 | ||
| 文化省 | ||
| 国民教育宗教省 | ||
| 財務省 | ルーカス・パパデモス | |
| 農業省 | ||
| 産業省 | ||
| 商務省 | ||
| 雇用省 | ||
| 社会福祉省 | ||
| 公共事業省 | ||
| 運輸通信省 | ||
| 商船省 | ||
| 北ギリシャ省 | ||
| キプロス省 |
ギリシャ国時代にすべての政党が解散されたことから内戦終結後に政界再編の動きと共に政党も再編の波が到来し自由党・人民党などの主要政党は戦前のように再興した。しかし、内戦の英雄 アレクサンドロス・パパゴスやコンスタンディノス・カラマンリスなどの右派著名政治家が人民党を離党し新党、そして保守党が結成された。一方、自由党も解散し、主だった政治家は中央連盟党を結成した。保守党は内戦勝利やその後の経済政策など様々な功績により現在も政権与党にあり続けている。しかし、1998年5月の選挙で保守党は過半数を取ることができず40年間の単独政権時代は終焉を迎えた。旧中央連盟党主流派で構成される国民連合の新代表 アントニス・サマラスとの協議によって連立政権に合意。保守・連合政権が誕生した。
1997年10月選挙でキプロス島(南部)を地盤とする地方政党の民族党が国政進出を果たした。
1997年10月選挙でキプロス島(南部)を地盤とする地方政党の民族党が国政進出を果たした。
| 党名 | 党首 |
| 保守党(与党) | ゲオルギオス・ラリス |
| 国民連合 | アントニス・サマラス |
| 民主党(野党) | コンスタンディノス・ミツォタキス |
| 新たなギリシャ | ゲオルギオス・アンドレアス・パパドレウス |
| 民族党 | グラフコス・クレリデス |
周辺国とは、キプロスの帰属問題でトルコとは対立関係にある。
ギリシャ民族によるマケドニア王国やギリシャ国内のマケドニア地方(エーゲ・マケドニア)と同じ名称を名乗るマケドニア共和国とも対立状態にあったが、マケドニア共和国が国名をヴァルダル・マケドニア共和国に変更したため、両国の対立状態は1999年時点で解消され、少しずつ薄れている。
ギリシャ民族によるマケドニア王国やギリシャ国内のマケドニア地方(エーゲ・マケドニア)と同じ名称を名乗るマケドニア共和国とも対立状態にあったが、マケドニア共和国が国名をヴァルダル・マケドニア共和国に変更したため、両国の対立状態は1999年時点で解消され、少しずつ薄れている。
かつてはイタリア主導の陣営である欧州・地中海条約機構(EMTO)に加盟し、現在は後継組織のスパツィオ・ヴィターレ(不可欠の領域)に加盟しており軍民双方の関係が深い。
EMTOおよびスパツィオ・ヴィターレ加盟国内ではイタリア、ハンガリーに次ぐGDPを持っている。
EMTOおよびスパツィオ・ヴィターレ加盟国内ではイタリア、ハンガリーに次ぐGDPを持っている。
ブルガリアとは第三次バルカン戦争停戦協定で国境についての条文がなかったことから国境問題は存在していたが現在の国境で確定することで両国合意し解決した。
王政廃止後、ブルガリア王室がギリシャへ亡命。経済協力を目的とするバルカン連合が結成された。
王政廃止後、ブルガリア王室がギリシャへ亡命。経済協力を目的とするバルカン連合が結成された。
ギリシャ軍(ギリシャぐん、ギリシア語: Eλληνικές Ένοπλες Δυνάμεις)は、ギリシャ陸軍、ギリシャ海軍、ギリシャ空軍の3軍で構成されるギリシャ王国の軍隊。管理・運営はギリシャ国防省が担当している。ギリシャはスパツィオ・ヴィターレ(不可欠の領域)、旧欧州・地中海条約機構(EMTO)の加盟国である。
王立陸軍(Βασιλικόν Στρατός)は、ギリシャの陸軍。
詳しくは「ギリシャ王立陸軍」
詳しくは「ギリシャ王立陸軍」
王立海軍(Βασιλικόν Ναυτικόν)は、ギリシャの海軍。戦闘艦艇 隻、補助艦艇 隻と航空機 機を保有する。
詳しくは『ギリシャ王立海軍』を参照
詳しくは『ギリシャ王立海軍』を参照
機体名 | 機数 | 就役期間 |
戦闘機 | ||
| ミラージュ2000 | 42機 | |
| F-16 | 60機 | |
回転翼機 | ||
| AS 332 | 12機 | |
空中消火機 | ||
| ボンバルディア CL-415 | 8機 | |
輸送機 | ||
| CASA C-212 | 2機 | |
無人機 | ||
| HAI Pegasus | 1992年 - | |
| EADS 3 Sigma Nearchos | 1996年 - | |
ギリシャはバルカン半島の国家の中では経済的にもっとも豊かな国である。
ギリシャにおける経済の主力産業はかつて、輸送業(海運業)・観光業が占められ農業・鉱業・鋼業がそれに次いでいた。
しかし大戦後のギリシャはアトラントローパ、第三次バルカン戦争やギリシャ内戦によって海運・観光は衰退し経済に大打撃を与えた。
ギリシャ国時代後半においてのギリシャ経済は主に農業が中心となった。上記の影響で2つの主経済が失われたことから政府は自立政策を画策。
イタリアがアルマーニ人の為に建設した旧イタリア統治地域の工業地帯とインフラ整備されたブルガリア統治地域はギリシャ経済の回復に大きく貢献した。
一方、アテネやドイツ統治地域であった箇所は戦中の食糧徴収に伴う農業推進やパルチザン掃討が影響し国内で貧困な地域となっていた。
内戦後、本土復帰を果たし左派を弾圧し独裁体制を構築したアレクサンドロス・パパゴス政権下において経済回復は主要政策の一つとされ、内戦で没収した土地や財産を使用し国営企業や国内企業への投資や融資を積極的に行った。
後半にはキプロス島分割による緊張状態から軍拡の風潮が到来。国内の工業地帯に多額の支援金が配布され生産体制をより強固にした。
しかし結局のところトルコとの武力衝突は起こらず軍事目的の産業は次第に軍民・民間向けの開発・生産が活発化した。
この頃になると観光業は回復し、海運も過去と比べると低いものの少しずつ回復の傾向を見せている。
ギリシャにおける経済の主力産業はかつて、輸送業(海運業)・観光業が占められ農業・鉱業・鋼業がそれに次いでいた。
しかし大戦後のギリシャはアトラントローパ、第三次バルカン戦争やギリシャ内戦によって海運・観光は衰退し経済に大打撃を与えた。
ギリシャ国時代後半においてのギリシャ経済は主に農業が中心となった。上記の影響で2つの主経済が失われたことから政府は自立政策を画策。
イタリアがアルマーニ人の為に建設した旧イタリア統治地域の工業地帯とインフラ整備されたブルガリア統治地域はギリシャ経済の回復に大きく貢献した。
一方、アテネやドイツ統治地域であった箇所は戦中の食糧徴収に伴う農業推進やパルチザン掃討が影響し国内で貧困な地域となっていた。
内戦後、本土復帰を果たし左派を弾圧し独裁体制を構築したアレクサンドロス・パパゴス政権下において経済回復は主要政策の一つとされ、内戦で没収した土地や財産を使用し国営企業や国内企業への投資や融資を積極的に行った。
後半にはキプロス島分割による緊張状態から軍拡の風潮が到来。国内の工業地帯に多額の支援金が配布され生産体制をより強固にした。
しかし結局のところトルコとの武力衝突は起こらず軍事目的の産業は次第に軍民・民間向けの開発・生産が活発化した。
この頃になると観光業は回復し、海運も過去と比べると低いものの少しずつ回復の傾向を見せている。
タグ

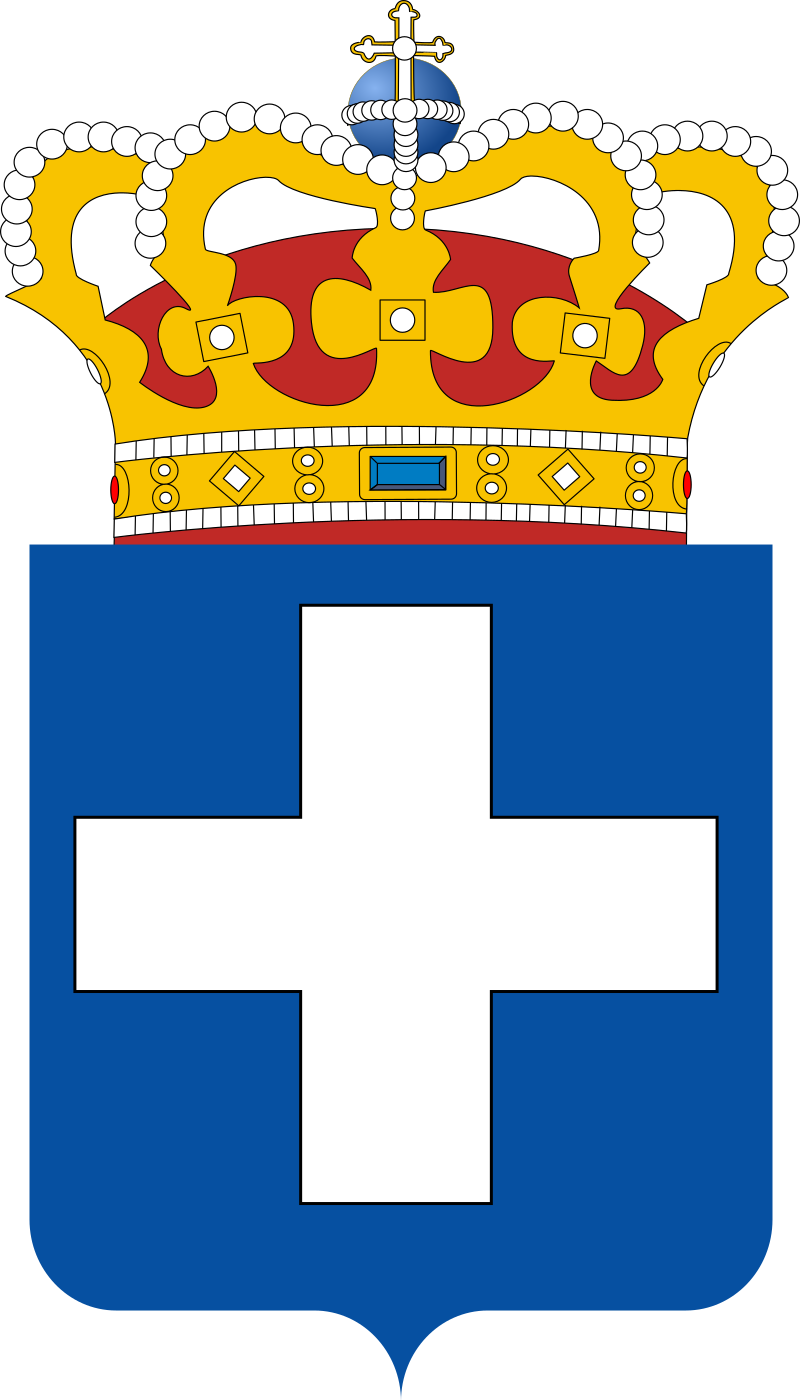



 mitaka334
mitaka334
コメントをかく