変化前
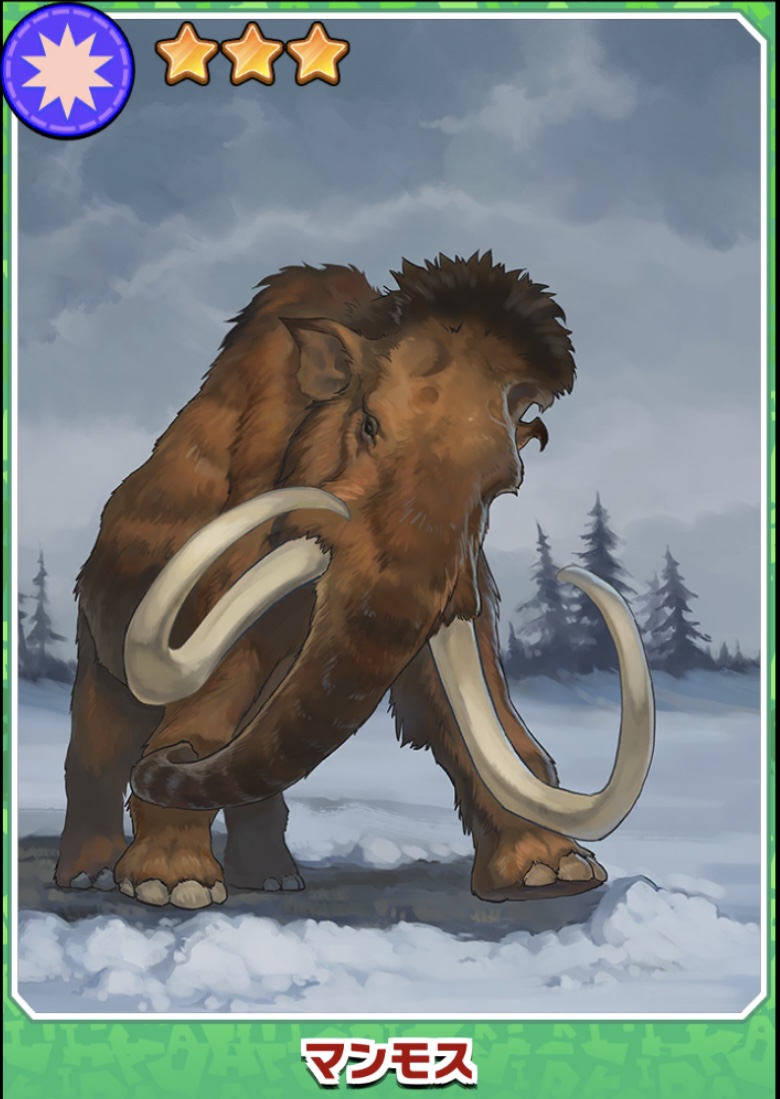
<動物コメント>
◎進化生態学者 松本忠夫
現在、地球上にいるゾウ類はアフリカゾウ、マルミミゾウ、アジアゾウの3種だけですが、古代にはマンモス属がいて(時代変遷とともにいろいろな種がいた)、約1万2千年前の氷河期時代末までは北半球の広範な地域に分布していました。最後に絶滅したコビトマンモスの骨がウランゲル島(カムチャッカ半島より北方、北極海の北緯70度)で発見されましたが、その骨は3700年前頃のものです。
マンモスはアジアゾウに類縁関係が近く、いわば姉妹関係にあります。よく大規模なものに関して、マンモスタンカーとか、マンモス学校、マンモス都市のように、‘マンモス’が使われますが、多くのマンモス類はアジアゾウと比べて大きさはさほど違っていなかったようです。しかし、北米にいたコロンビアマンモスはアフリカゾウぐらいの大きさで、特に雄の牙が長く大変立派でした。
マンモスの遺体が結構な数、シベリアのあちこちの永久凍土層から発見されています。中には骨格はもちろんのこと、筋肉や皮、内臓が立派に残っている個体があります。ケナガマンモスは全身に長い毛がはえていたことが分かっています。おそらく冬になって急激に凍りつつある湿地沼などにはまり込んで氷結したのでしょう(まるで、一頭丸ごとの冷凍肉のようなものですね)。そんな痛いから遺伝情報をつかさどるDNAを取り出し、それを現生のインドゾウに使ってマンモスらしさを一部なりとも復元できないかとの試みがあります。しかし、そんな個体からDNAが取れたとしても、残念ながらそれらのほとんどが短く切断されていますので、その試みはまず実現しそうにはありません。
なお、アメリカのカリフォルニアではタール沼(原油が地表に出てきた自然の池)にはまって死んだマンモスの骨格がまるごと発掘される場所があります。動物個体は普通の状態で死んだ場合、腐敗して骨格は散らばってしまうのがほとんどですが、この場合、きちんとまとまって出てくるのですから、すごいことです。体の柔らかい部分はなくなっていますが、まるで骨格標本のようなものですからね。
ところで、1万年前ぐらい前までの人類は、明らかにマンモスを見ていました。その証拠にヨーロッパでは洞窟絵画でマンモスが描かれているものがけっこうあるのです。また、マンモスの牙や骨を材料にして様々な道具を作っていたようです。マンモスがなぜ絶滅してしまったのか、その原因については、人類による狩猟が絶滅に追い込んだという説、地球的規模の急激な気候変動に耐えられなかったという説、悪質な伝染病がはやったという説などがあります。この頃にいた他の哺乳動物の状況とあわせて考えると、それらの原因が複合的に働いたとする説が有力です。
(2021年5月公開)
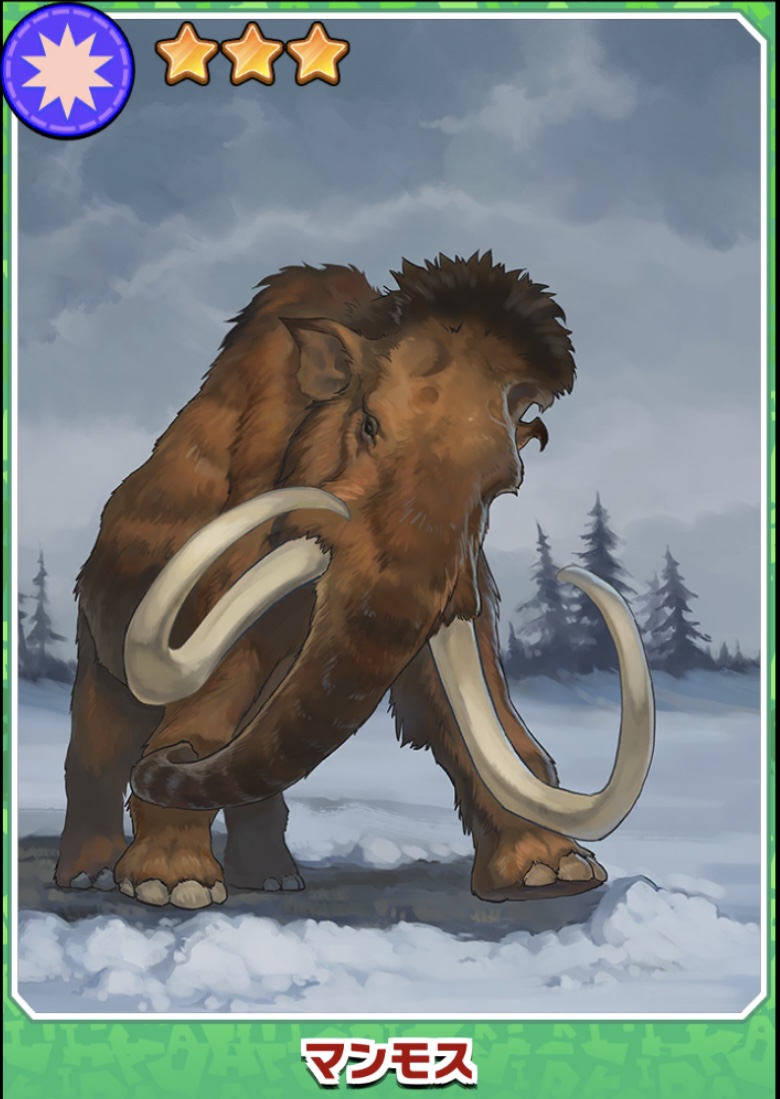
| マンモス | |
|---|---|
| レアリティ | ☆3 |
| 属性 | |
| イラストレータ名 | ナブランジャ |
| とくせい(変化前) | 地形が寒冷地の場合、被ダメージが15%減少する |
| とくせい(変化後) | 地形が寒冷地の場合、被ダメージが20%減少する |
| たいりょく | こうげき | まもり | |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 382 | 134 | 101 |
| Lv.40(無凸最大) | 886 | 310 | 233 |
| Lv.60(完凸最大) |
<動物コメント>
◎進化生態学者 松本忠夫
現在、地球上にいるゾウ類はアフリカゾウ、マルミミゾウ、アジアゾウの3種だけですが、古代にはマンモス属がいて(時代変遷とともにいろいろな種がいた)、約1万2千年前の氷河期時代末までは北半球の広範な地域に分布していました。最後に絶滅したコビトマンモスの骨がウランゲル島(カムチャッカ半島より北方、北極海の北緯70度)で発見されましたが、その骨は3700年前頃のものです。
マンモスはアジアゾウに類縁関係が近く、いわば姉妹関係にあります。よく大規模なものに関して、マンモスタンカーとか、マンモス学校、マンモス都市のように、‘マンモス’が使われますが、多くのマンモス類はアジアゾウと比べて大きさはさほど違っていなかったようです。しかし、北米にいたコロンビアマンモスはアフリカゾウぐらいの大きさで、特に雄の牙が長く大変立派でした。
マンモスの遺体が結構な数、シベリアのあちこちの永久凍土層から発見されています。中には骨格はもちろんのこと、筋肉や皮、内臓が立派に残っている個体があります。ケナガマンモスは全身に長い毛がはえていたことが分かっています。おそらく冬になって急激に凍りつつある湿地沼などにはまり込んで氷結したのでしょう(まるで、一頭丸ごとの冷凍肉のようなものですね)。そんな痛いから遺伝情報をつかさどるDNAを取り出し、それを現生のインドゾウに使ってマンモスらしさを一部なりとも復元できないかとの試みがあります。しかし、そんな個体からDNAが取れたとしても、残念ながらそれらのほとんどが短く切断されていますので、その試みはまず実現しそうにはありません。
なお、アメリカのカリフォルニアではタール沼(原油が地表に出てきた自然の池)にはまって死んだマンモスの骨格がまるごと発掘される場所があります。動物個体は普通の状態で死んだ場合、腐敗して骨格は散らばってしまうのがほとんどですが、この場合、きちんとまとまって出てくるのですから、すごいことです。体の柔らかい部分はなくなっていますが、まるで骨格標本のようなものですからね。
ところで、1万年前ぐらい前までの人類は、明らかにマンモスを見ていました。その証拠にヨーロッパでは洞窟絵画でマンモスが描かれているものがけっこうあるのです。また、マンモスの牙や骨を材料にして様々な道具を作っていたようです。マンモスがなぜ絶滅してしまったのか、その原因については、人類による狩猟が絶滅に追い込んだという説、地球的規模の急激な気候変動に耐えられなかったという説、悪質な伝染病がはやったという説などがあります。この頃にいた他の哺乳動物の状況とあわせて考えると、それらの原因が複合的に働いたとする説が有力です。
(2021年5月公開)
- カテゴリ:
- ゲーム
- けものフレンズプロジェクト

コメントをかく