最終更新:
 otonjji256 2022年12月28日(水) 14:21:24履歴
otonjji256 2022年12月28日(水) 14:21:24履歴
 | |
| 国名 | ドゥク・ユル 大鳳凰国 |
| 面積 | 273,600㎢ |
| 首都 | パルパド(江都城) |
| 指導者 | ペマ・デントゥップ・トゥルバイフ(至聖王)、ドルジ・ヴェツォプ・シンチュラ(国師) |
| 人口 | 約3,600,000人 |
| 言語 | ゲルク語 |
| 経済力 | 中堅 |
| 一人あたり経済力 | 貧困 |
| 軍事力 | 弱小 |
| 通貨 | 両・文 |
ゲルク王国は、大陸中部の山岳地帯を領土とする絶対君主制国家。首都はパルパド。国の周辺を8,000メートル級の高峰を擁する山脈に囲まれ、主要な領域であるドゥク盆地の東西両端に通じるターキン・ナデル両渓谷の峠を除けば、国土に入る手段は空を飛ぶしかない。国土自体も3000-4000メートルの高地にあり、一年を通じて冷涼な気候である。
そうした背景から、長きに渡り鎖国体制を敷いており、外国人の入国を強く規制してきた。
国民の殆どはゲルク教と呼ばれる民族宗教を信仰しており、国王はその聖者として崇敬されている。
国民は日常においては「ドゥク・ユル(鳳凰の国。第2代女王ドゥク姫に由来する)」、「ドゥクパ(鳳凰の民。由来同上)」と称することが多い。(ゲルク王国とは、この国の国王の称号に基づく他称)
政治体制は国王と国師の二頭政治で、実質的には後者が政権を担っている。
そうした背景から、長きに渡り鎖国体制を敷いており、外国人の入国を強く規制してきた。
国民の殆どはゲルク教と呼ばれる民族宗教を信仰しており、国王はその聖者として崇敬されている。
国民は日常においては「ドゥク・ユル(鳳凰の国。第2代女王ドゥク姫に由来する)」、「ドゥクパ(鳳凰の民。由来同上)」と称することが多い。(ゲルク王国とは、この国の国王の称号に基づく他称)
政治体制は国王と国師の二頭政治で、実質的には後者が政権を担っている。
古代までのゲルク王国の歴史は謎に包まれており、殆ど分かっていない。主要な民族であるゲルク人は、紀元前150年ごろに東方から放浪し、現在の居住地に辿り着いたと思われる。(遺伝学・文化人類学的に彼らは周辺の諸国よりも東方の国々との類似性が指摘されている)
現在この地に言及したと思われる最古の資料は、368年に記されたと思われる「高地大蕃地理誌」であり、そこには「雨雪国」なる国が登場する。
この記事によれば、雨雪国は険阻な山岳に囲まれた国であり、相応に豊かではあるものの長い争いによって外部との関わりが殆ど無かった、と記されている。
また、別の史書には「貿易路から外れた辺境の地」という記載があり、当時栄えていた東方から西方を結ぶ交易路からこの地が遠く離れていた点と符合する。
こうした地理的な要因と内部の争いにより、ゲルクの地は長きに渡って外部から孤立し、独自の道を歩んでいた。
なお、文字文化については450年ごろに刻まれたと思われる碑文がパルパド郊外で見つかっており、未解読の「古代ゲルク文字」で彫刻されている。
伝承によれば、パルパドを中心とした歴史ある都市はこの頃に築かれ、「ゾン」と呼ばれる城塞を拠点とした諸侯の争いが始まったとされている。彼らの間には同国人という意識は無く、好き勝手に合従連衡して戦い、ある国が統一に近づくと各国が連合してこれを滅ぼし、それが成るとまた内部で争いが続く、と言った情勢だったと伝わる。
現在この地に言及したと思われる最古の資料は、368年に記されたと思われる「高地大蕃地理誌」であり、そこには「雨雪国」なる国が登場する。
>雨雪国は我が国から西へ一万里離れた庫車国よりも、さらに西の果ての果てへと向かった先の国である。この国は天を支える巨大な山々に囲まれ、険しい峠を越えなければ入ることができない…人々は血の気が多く野蛮であり、互いに嶮岨な城を築いて争い、豊かな財宝を巡って絶え間ない戦争をしている…
この記事によれば、雨雪国は険阻な山岳に囲まれた国であり、相応に豊かではあるものの長い争いによって外部との関わりが殆ど無かった、と記されている。
また、別の史書には「貿易路から外れた辺境の地」という記載があり、当時栄えていた東方から西方を結ぶ交易路からこの地が遠く離れていた点と符合する。
こうした地理的な要因と内部の争いにより、ゲルクの地は長きに渡って外部から孤立し、独自の道を歩んでいた。
なお、文字文化については450年ごろに刻まれたと思われる碑文がパルパド郊外で見つかっており、未解読の「古代ゲルク文字」で彫刻されている。
伝承によれば、パルパドを中心とした歴史ある都市はこの頃に築かれ、「ゾン」と呼ばれる城塞を拠点とした諸侯の争いが始まったとされている。彼らの間には同国人という意識は無く、好き勝手に合従連衡して戦い、ある国が統一に近づくと各国が連合してこれを滅ぼし、それが成るとまた内部で争いが続く、と言った情勢だったと伝わる。
こうした情勢が変わったのは、617年(公的に使われている「聖暦」の元年)辺境のチュカの地で一人の預言者が生まれた時だった。
彼が生まれた時、天の太陽は何度も登っては沈むを繰り返し、山々には三重の虹がかかり、川の魚たちは聖者の到来を喜んで自ら陸地に跳ねて身を捧げたという。
その名はミラレパと言った。彼の名は現在の国名の由来ともなっており、この国の歴史に極めて重大な影響を与えた聖者として最も崇拝されている。
ミラレパはチュカのゾンを支配していたパジョ・ドゥゴムと呼ばれる諸侯の息子として生まれた。当時チュカは周辺国に押されて没落しており、パジョは大国ブムタンに服従の証として彼を送った。
聖暦12年、パジョが不慮の事故によって亡くなると彼がチュカの王位を継ぐ。
聖暦18年。ミラレパはある日の夜にゾンの窓から山の頂を見上げると、ふとそこに常ならぬ輝きを見出した。彼は天の星が落ちてきたのか、と思い臣下が止めるのも聞かずに険しい山を一人で登った。
すると、そこには眩い光りを従えたシャンバラ(ゲルク教における最高神。10万柱の神と聖者を従え、18の化身を通じて世界を収めるとされる)大神が鎮座しており、彼が目の前に来たことに気がつくと、次の様に告げた。
大神シャンバラはそう言って、ミラレパに対して星の様に光る黄帽、決して破れ・焼け落ちることの無い法衣、そして悪魔を退ける為の宝剣を授けたとされる。
この日を境に彼はこの地を王法によって治めることを決め、人々に教えを説くことに生涯を捧げることとなる。
聖暦23年。ミラレパ王は自国の民に教えを説き、彼らを自身の教えに服させた。人々は彼を「黄帽王」(ゲルク・ギャルポ)と呼び、神秘的な力を持つ偉大な王として崇敬した。また、彼らは古代の神々の廟を打ち壊し、ミラレパの為の社を築こうとしたが、彼はこう言って諌めたという。
彼は善政を敷き、その徳を慕った人々がチュカの国に集まったので、国は大いに富み栄えた。伝承によれば、チュカの川底の石は皆黄金に変じ、岩の上に種を蒔いた穀物さえも実り頭を垂れたという。
しかし、その様に栄えるチュカを忌々しく思っていた大国ブムタンの王デルジェは、チュカに対して服従を要求し、尨大な貢納品を納めなければ直ちに攻め滅ぼすと告げた。
少ししてミラレパは、民が拾ってきた石を霊妙な力で黄金の塊に変え、摘んできた雑草を何万石もの穀物とし、紙の人形を兵士に変じさせたと言う。そして彼は、デルジェの前に二十万人の兵士と、彼ら一人一人に箱いっぱいの黄金を運ばせ、何万輌もの車に乗せた穀物の俵を見せた。
デルジェは忽ちのうちに、彼が偉大な神々の加護を受けているのだと悟り、兵士共々武器を捨てて降伏し、今後はチュカに服従して決して逆らわないと誓ったという。
彼が生まれた時、天の太陽は何度も登っては沈むを繰り返し、山々には三重の虹がかかり、川の魚たちは聖者の到来を喜んで自ら陸地に跳ねて身を捧げたという。
その名はミラレパと言った。彼の名は現在の国名の由来ともなっており、この国の歴史に極めて重大な影響を与えた聖者として最も崇拝されている。
ミラレパはチュカのゾンを支配していたパジョ・ドゥゴムと呼ばれる諸侯の息子として生まれた。当時チュカは周辺国に押されて没落しており、パジョは大国ブムタンに服従の証として彼を送った。
聖暦12年、パジョが不慮の事故によって亡くなると彼がチュカの王位を継ぐ。
聖暦18年。ミラレパはある日の夜にゾンの窓から山の頂を見上げると、ふとそこに常ならぬ輝きを見出した。彼は天の星が落ちてきたのか、と思い臣下が止めるのも聞かずに険しい山を一人で登った。
すると、そこには眩い光りを従えたシャンバラ(ゲルク教における最高神。10万柱の神と聖者を従え、18の化身を通じて世界を収めるとされる)大神が鎮座しており、彼が目の前に来たことに気がつくと、次の様に告げた。
>賢明なる王。この世のグル、血も凍る雪山に来たる者、余は汝に楽土を与えん。汝は余の一身にて、その務めを果たさずべからず。転輪の真を広め、百万千万の民をして往生の本願を遂がしむべし
大神シャンバラはそう言って、ミラレパに対して星の様に光る黄帽、決して破れ・焼け落ちることの無い法衣、そして悪魔を退ける為の宝剣を授けたとされる。
この日を境に彼はこの地を王法によって治めることを決め、人々に教えを説くことに生涯を捧げることとなる。
聖暦23年。ミラレパ王は自国の民に教えを説き、彼らを自身の教えに服させた。人々は彼を「黄帽王」(ゲルク・ギャルポ)と呼び、神秘的な力を持つ偉大な王として崇敬した。また、彼らは古代の神々の廟を打ち壊し、ミラレパの為の社を築こうとしたが、彼はこう言って諌めたという。
>古き者どもの家を毀つ勿れ。彼の者らは老いたる賢者にして、至尊のお方の第一の弟子なり。共に祀り、共に仰ぎ見よ
彼は善政を敷き、その徳を慕った人々がチュカの国に集まったので、国は大いに富み栄えた。伝承によれば、チュカの川底の石は皆黄金に変じ、岩の上に種を蒔いた穀物さえも実り頭を垂れたという。
しかし、その様に栄えるチュカを忌々しく思っていた大国ブムタンの王デルジェは、チュカに対して服従を要求し、尨大な貢納品を納めなければ直ちに攻め滅ぼすと告げた。
>傲慢なるデルジェは、チュカの人々を捕え、奴婢として永遠に働かせる、と豪語し、十万人の精鋭を集めて国境に陣を敷いた…しかし、ミラレパ王は落ち着き払い、言う通りにせよ。石を拾い、草を摘み、紙の人形を切り抜くべし。それによって正しきことは成されん、と言った…
少ししてミラレパは、民が拾ってきた石を霊妙な力で黄金の塊に変え、摘んできた雑草を何万石もの穀物とし、紙の人形を兵士に変じさせたと言う。そして彼は、デルジェの前に二十万人の兵士と、彼ら一人一人に箱いっぱいの黄金を運ばせ、何万輌もの車に乗せた穀物の俵を見せた。
デルジェは忽ちのうちに、彼が偉大な神々の加護を受けているのだと悟り、兵士共々武器を捨てて降伏し、今後はチュカに服従して決して逆らわないと誓ったという。
聖暦26年。ブムタン国を下したミラレパは、その後各地の支配者の下を巡って教えを説き、彼らを服従させて行った。ミラレパは教えに帰依した諸侯一人一人に対し、シャンバラ神の化身やそれに従う神々の加護を祈り授け、彼らの末裔がそれぞれの地を安楽の内に治められる様に取り計らったと言う。
そして、41年。彼は遂にドゥク盆地と周辺の山地に割拠していた全ての国々に教えを説いて服従させ、争いの続いていた国土に大いなる平穏をもたらした。
彼が服従させた諸侯の数は大国の主18名、小国の主227名に及び、皆チュカを主君として仰いだ。
これについては長らく事実か伝承かの論争が続いていたが、近年チュカ周辺から、作成場所や時期の異なる多くの遺物が発見されており、同地が古代における王国の中心であった可能性が指摘されている。
その後ミラレパは全土に大いなる善政を敷き、人々は安楽な暮らしを享受した。実りは常に豊かであり、湧くが如く黄金や宝玉が山々から掘り出され、各地の諸侯の宮殿は豪奢に飾られた。神々への祭祀は途切れること無く、徳の高い僧侶達が常に教えを説いて回ったので、悪心を抱く者は蟻一匹に至るまでいなかったと言う。
しかし、聖暦88年。彼は遂に重い病に倒れた。死期を悟った彼はかつて大神から授かった物のうち、法衣と宝剣を持ってくる様に言った。そして、臣下たちに告げた。
カイラス山は、かつてミラレパが神から自らの務めを命じられた聖地である。今でもこの山は王国政府によって厳重に管理され、永久の未踏峰と宣言されている。
そして、彼は最も偉大なる王として、「至聖王」(ジェツン・ギャルポ)と諡された。
そして、41年。彼は遂にドゥク盆地と周辺の山地に割拠していた全ての国々に教えを説いて服従させ、争いの続いていた国土に大いなる平穏をもたらした。
彼が服従させた諸侯の数は大国の主18名、小国の主227名に及び、皆チュカを主君として仰いだ。
これについては長らく事実か伝承かの論争が続いていたが、近年チュカ周辺から、作成場所や時期の異なる多くの遺物が発見されており、同地が古代における王国の中心であった可能性が指摘されている。
その後ミラレパは全土に大いなる善政を敷き、人々は安楽な暮らしを享受した。実りは常に豊かであり、湧くが如く黄金や宝玉が山々から掘り出され、各地の諸侯の宮殿は豪奢に飾られた。神々への祭祀は途切れること無く、徳の高い僧侶達が常に教えを説いて回ったので、悪心を抱く者は蟻一匹に至るまでいなかったと言う。
しかし、聖暦88年。彼は遂に重い病に倒れた。死期を悟った彼はかつて大神から授かった物のうち、法衣と宝剣を持ってくる様に言った。そして、臣下たちに告げた。
>ミラレパ王が宝剣に対し、汝王を守るべし、と命じた。すると宝剣は童子に変じた。王は童子をシンチュラと名付け、パロのゾンを与えた。ついで法衣に命じた、汝教えを守るべし、と。すると法衣は美しい姫君に変じた。王は姫君をドゥクと名づけ、死後の王に命じた。そして王は目を閉じられたが、不思議なことにその体は空を飛んで、遥かなカイラス山の頂に落ちた。人々は、王は大神の元にお帰りになったのだ、と噂しあった…
カイラス山は、かつてミラレパが神から自らの務めを命じられた聖地である。今でもこの山は王国政府によって厳重に管理され、永久の未踏峰と宣言されている。
そして、彼は最も偉大なる王として、「至聖王」(ジェツン・ギャルポ)と諡された。
聖暦89年。ミラレパの遺言を受けたドゥク姫が第2代の黄帽王に就任し、全土を統治することとなった。彼女の名は「ドゥク・ユル」(鳳凰の地、鳳凰国)という別名の由来となっている。
ドゥク姫はブムタン国の王子ユンドゥン・ギャルツェンを王配として迎え、彼の間に4人の姫を儲けた。彼女はそれぞれ各国に嫁ぎ、後継や王妃として国の統治を支えた。
史書に曰く、ドゥク姫の統治は「先王には劣るが、それでも名君たるにふさわしい」ものであったという。しかし、聖暦127年にユンドゥンが死去し、後を追う様にしてドゥク姫も129年に死去すると、統一王国は動揺を始めた。
二人の間には跡継ぎがなく、姫君も全て降嫁してしまっていた為、チュカの君主となる者が不在だったのである。
王を欠いた諸侯らは集まって話し合い、空位となった王座を如何にして埋めるかを協議した。その結果、彼らは「黄帽王の地位は空位として、諸侯による合議制で国を統治する」ことを定め、カイラス山の麓に建立されたフォルナン寺でその旨を神々に誓約した。これが世に言う、「十八侯の盟約」である。彼らはそれぞれ最高神の18の化身の加護を受けた宗教指導者として、また実際に各地のゾンを治める施政者として国を治め、外敵にあっては一致して事に当たり、内部には和親自治をもって治めることを取り決めた。18の有力諸侯らは「ペンロップ」と尊称され、人々の崇敬を集めた。
聖暦145年には、これらの列侯会議のまとめ役として「デシ」の称号が創設され、名目上の全土支配者としての地位を確立した。以降1,000年の長きに渡り、この地ではペンロップとそれによって選出されるデシの選挙王政が続くことになる。
しかし、それは平穏な貴族共和制ではなく、過激な武力衝突をも伴う危ういもので、時に諸外国を巻き込んだ危険な闘争に発展することもあった。
聖暦920年には、諸外国からの武力支援を受けたデシのクンガ・ペルデンが統一の直前まで漕ぎ着けたが、パルパドを中心とした諸侯の同盟に敗れて戦死し、事業は瓦解した。
ドゥク・ユルが再びただ一人の王に統一されるには、聖暦1109年のトゥルバイフ王出現を待たなくてはならなかった。
ドゥク姫はブムタン国の王子ユンドゥン・ギャルツェンを王配として迎え、彼の間に4人の姫を儲けた。彼女はそれぞれ各国に嫁ぎ、後継や王妃として国の統治を支えた。
史書に曰く、ドゥク姫の統治は「先王には劣るが、それでも名君たるにふさわしい」ものであったという。しかし、聖暦127年にユンドゥンが死去し、後を追う様にしてドゥク姫も129年に死去すると、統一王国は動揺を始めた。
二人の間には跡継ぎがなく、姫君も全て降嫁してしまっていた為、チュカの君主となる者が不在だったのである。
王を欠いた諸侯らは集まって話し合い、空位となった王座を如何にして埋めるかを協議した。その結果、彼らは「黄帽王の地位は空位として、諸侯による合議制で国を統治する」ことを定め、カイラス山の麓に建立されたフォルナン寺でその旨を神々に誓約した。これが世に言う、「十八侯の盟約」である。彼らはそれぞれ最高神の18の化身の加護を受けた宗教指導者として、また実際に各地のゾンを治める施政者として国を治め、外敵にあっては一致して事に当たり、内部には和親自治をもって治めることを取り決めた。18の有力諸侯らは「ペンロップ」と尊称され、人々の崇敬を集めた。
聖暦145年には、これらの列侯会議のまとめ役として「デシ」の称号が創設され、名目上の全土支配者としての地位を確立した。以降1,000年の長きに渡り、この地ではペンロップとそれによって選出されるデシの選挙王政が続くことになる。
しかし、それは平穏な貴族共和制ではなく、過激な武力衝突をも伴う危ういもので、時に諸外国を巻き込んだ危険な闘争に発展することもあった。
聖暦920年には、諸外国からの武力支援を受けたデシのクンガ・ペルデンが統一の直前まで漕ぎ着けたが、パルパドを中心とした諸侯の同盟に敗れて戦死し、事業は瓦解した。
ドゥク・ユルが再びただ一人の王に統一されるには、聖暦1109年のトゥルバイフ王出現を待たなくてはならなかった。
聖暦920年、デシであるクンガ・ペルデンが長年の盟約を破り、武力による統一を果たそうとして以降、18諸侯は互いに猜疑心を膨らませ、小規模な戦闘を繰り返していた。
この頃のゲルクの地について、諸外国の記録は皆一様に「未開の封建国。激しい内戦を繰り返している」と記しており、彼らとの外交関係樹立の意欲はほとんど無かった。
そんな中、聖暦1091年に、パルパドのペンロップの後継として生まれたトゥルバイフ・ギャルツェンは、クンガの様な壮大な野望を抱いていた。彼は18諸侯を統一し、ミラレパ、ドゥク姫以来1,000年振りに黄帽王の地位について王国の再統一を果たそうとしていた。
そして、彼にはその力が十全に備わっていたのである。
聖暦1109年。父王の跡を継いだトゥルバイフは、列侯会議において次の様に提議した。
「ミラレパの就いた王の地位を復活させ、統一して諸外国にあたろう」
と。
しかし、列席の諸侯は皆これを一笑に付し、特に隣国のルンツェ国のペンロップであるカンチェンネは公然と彼を「若輩者の痴愚王」と侮辱したと言う。これに激しい怒りを覚えたトゥルバイフは、すぐに領地へ帰ると戦の支度を始め、ルンツェ国に兵を向けた。
当初カンチェンネはトゥルバイフの侵攻を知らされて、よくある諸侯間の小競り合いの延長であり、恐らくは服属する小諸侯のトラブルに際して彼が介入してきたものと楽観視していた。
しかし、パルパド軍が5,000人もの精鋭を連れていると知った彼は、18諸侯の均衡をトゥルバイフが破壊しようとしていることをやっと悟った。だが、時既に遅くパルパド軍は神速の用兵によって忽ちルンツェのゾンを包囲し、20日の攻防の末これを陥落させた。
カンチェンネは侮辱の意趣返しとして髪の毛を全て剃られて僧院に幽閉され、親族は殆どが放逐された。
これを知ったデシのギュルメ・ナムゲル(チュカ国ペンロップ。ドゥク姫の4人の娘の末裔を称した)は急遽列侯会議を招集し、トゥルバイフの暴挙に対応を協議した。しかし、彼はここにも手を打っており、参加した諸侯のうち3名を自派に引き込み、会議を混乱させた。この時彼に協力したパロ国ペンロップのシンチュラ家(宝刀が変じた童子シンチュラの末裔)は、後に功臣筆頭として国政を司ることとなる。
会議が空転を繰り返す間、トゥルバイフは空になった諸侯らの領土を次々に制圧し、聖暦1111年までに5つのゾンを制圧し、ドゥク盆地の3分の1を支配下に置いた。
ここに至って列侯会議は漸くギュルメが直卒する各国の連合軍20,000人余りを派遣し、倍の戦力でトゥルバイフを撃破しようと図った。しかし、彼は密かに諸外国と誼を通じ、1,000梃のライフルや60門の大砲といった最新兵器を輸入し、軍政改革によって軍事力を飛躍的に強化していた。加えてシンチュラ家を中心に会議派の諸侯らを懐柔して軍内を動揺させ、ただでさえ乏しい戦意を大いに低下させていた。
その結果、バヤンカラで行われた両派の決戦はトゥルバイフの決定的勝利に終わり、以降列侯会議派は完全にその力を失った。
そして、聖暦1123年に召集された会議において彼は公的にデシを称し、同年最後に残った会議派の雄ブムタンを下してドゥク盆地の統一を実現した。
翌年の聖暦1124年、新たに取り立てられた6つの国を加えた列侯会議は、デシであるトゥルバイフの国王就任を全会一致で承認。ここに彼は、ミラレパとドゥク姫以来1,000年間空位であった統一ゲルク王の地位に就き、自らをミラレパの生まれ変わりにして、ドゥク姫の末裔たる「至聖王」であると称した。その後、彼は閉鎖的な盆地の気風の払拭と、政治改革に心血を注いだ。
しかし、彼はシンチュラ家といった功臣たちに国土の支配権や鉱山の利権を気前よく分け与えた為、国家の改革は前時代的な守旧派に阻まれて未完に終わり、彼の死後再び水泡に帰した。
聖暦1163年、39年の在位の末にトゥルバイフは薨去した。統一後は功臣同士の政争に悩まされ、幼い王子たちと共に過ごすことのみを慰めにしていたと言う。
第2代至聖王には最初長男のチャンチュプ・ギャルツェン・トゥルバイフが就いたが、5年にして程なく死去。その後列侯会議の推薦により、彼の4番目の子であるプンツォック・チャンチュプ・トゥルバイフが第3代の至聖王に推戴された。まだ6歳であった。
この頃のゲルクの地について、諸外国の記録は皆一様に「未開の封建国。激しい内戦を繰り返している」と記しており、彼らとの外交関係樹立の意欲はほとんど無かった。
そんな中、聖暦1091年に、パルパドのペンロップの後継として生まれたトゥルバイフ・ギャルツェンは、クンガの様な壮大な野望を抱いていた。彼は18諸侯を統一し、ミラレパ、ドゥク姫以来1,000年振りに黄帽王の地位について王国の再統一を果たそうとしていた。
そして、彼にはその力が十全に備わっていたのである。
聖暦1109年。父王の跡を継いだトゥルバイフは、列侯会議において次の様に提議した。
「ミラレパの就いた王の地位を復活させ、統一して諸外国にあたろう」
と。
しかし、列席の諸侯は皆これを一笑に付し、特に隣国のルンツェ国のペンロップであるカンチェンネは公然と彼を「若輩者の痴愚王」と侮辱したと言う。これに激しい怒りを覚えたトゥルバイフは、すぐに領地へ帰ると戦の支度を始め、ルンツェ国に兵を向けた。
当初カンチェンネはトゥルバイフの侵攻を知らされて、よくある諸侯間の小競り合いの延長であり、恐らくは服属する小諸侯のトラブルに際して彼が介入してきたものと楽観視していた。
しかし、パルパド軍が5,000人もの精鋭を連れていると知った彼は、18諸侯の均衡をトゥルバイフが破壊しようとしていることをやっと悟った。だが、時既に遅くパルパド軍は神速の用兵によって忽ちルンツェのゾンを包囲し、20日の攻防の末これを陥落させた。
カンチェンネは侮辱の意趣返しとして髪の毛を全て剃られて僧院に幽閉され、親族は殆どが放逐された。
これを知ったデシのギュルメ・ナムゲル(チュカ国ペンロップ。ドゥク姫の4人の娘の末裔を称した)は急遽列侯会議を招集し、トゥルバイフの暴挙に対応を協議した。しかし、彼はここにも手を打っており、参加した諸侯のうち3名を自派に引き込み、会議を混乱させた。この時彼に協力したパロ国ペンロップのシンチュラ家(宝刀が変じた童子シンチュラの末裔)は、後に功臣筆頭として国政を司ることとなる。
会議が空転を繰り返す間、トゥルバイフは空になった諸侯らの領土を次々に制圧し、聖暦1111年までに5つのゾンを制圧し、ドゥク盆地の3分の1を支配下に置いた。
ここに至って列侯会議は漸くギュルメが直卒する各国の連合軍20,000人余りを派遣し、倍の戦力でトゥルバイフを撃破しようと図った。しかし、彼は密かに諸外国と誼を通じ、1,000梃のライフルや60門の大砲といった最新兵器を輸入し、軍政改革によって軍事力を飛躍的に強化していた。加えてシンチュラ家を中心に会議派の諸侯らを懐柔して軍内を動揺させ、ただでさえ乏しい戦意を大いに低下させていた。
その結果、バヤンカラで行われた両派の決戦はトゥルバイフの決定的勝利に終わり、以降列侯会議派は完全にその力を失った。
そして、聖暦1123年に召集された会議において彼は公的にデシを称し、同年最後に残った会議派の雄ブムタンを下してドゥク盆地の統一を実現した。
翌年の聖暦1124年、新たに取り立てられた6つの国を加えた列侯会議は、デシであるトゥルバイフの国王就任を全会一致で承認。ここに彼は、ミラレパとドゥク姫以来1,000年間空位であった統一ゲルク王の地位に就き、自らをミラレパの生まれ変わりにして、ドゥク姫の末裔たる「至聖王」であると称した。その後、彼は閉鎖的な盆地の気風の払拭と、政治改革に心血を注いだ。
しかし、彼はシンチュラ家といった功臣たちに国土の支配権や鉱山の利権を気前よく分け与えた為、国家の改革は前時代的な守旧派に阻まれて未完に終わり、彼の死後再び水泡に帰した。
聖暦1163年、39年の在位の末にトゥルバイフは薨去した。統一後は功臣同士の政争に悩まされ、幼い王子たちと共に過ごすことのみを慰めにしていたと言う。
第2代至聖王には最初長男のチャンチュプ・ギャルツェン・トゥルバイフが就いたが、5年にして程なく死去。その後列侯会議の推薦により、彼の4番目の子であるプンツォック・チャンチュプ・トゥルバイフが第3代の至聖王に推戴された。まだ6歳であった。
幼年のプンツォック王を補佐する為、列侯会議は3人の摂政を選出した。その筆頭となったのは、功臣第一等として当時グンロンチェンポ(大宰相)を称していたスルカン・ツェテン・シンチュラ(1110年生)であった。彼はトゥルバイフの末娘パドマを娶り、更に南部に広大な領地を有する大貴族として統一後の政治に重きをなしていた。
スルカンはプンツォック王に指示し、トゥルバイフ即位以来、首都知事の役割を果たしていたパルパド・ペンロップの地位を自身に与えさせた。(これは同時に王が直接支配する土地を奪うことで、経済・軍事の基盤を喪失させる意味があった)また、他の摂政や諸侯に対しては、王の居る首都の保護者として支配的に振る舞い、国政を壟断した。
無論これにはまだ強い権力を持っていた功臣の末裔達が強く反発し、同じ摂政の地位にあったチュカ国ペンロップのウマ・デワを立ててスルカンの退任を要求した。
すると、スルカンはこれに対して列侯会議を招集し、その場での弁明を約した。これを受けて功臣達はパルパドに集まったが、これは卑劣な罠であった。
スルカンは彼らが王宮の会議室に入るや扉を閉めさせ、ウマ・デワと彼を立てて抗おうとした6人のペンロップを全員殺害したのである。また、抜け目の無い彼は同時に反対派の支配するゾンに兵を派遣して奇襲し、これを乗っ取らせると王の勅命の名の下に彼らの親族全員を死罪に処した。
これに恐れをなした3人目の摂政、ワンディ・ポダン・ゾンペンは摂政を辞任し、一人のペンロップとしてスルカンの支持を表明した。
聖暦1170年、血の会議と呼ばれたこの事件の後、スルカンは自身の親族を次々と要職につけ、シンチュラ家による国家の支配を固めさせた。1179年には、成長したプンツォック王が謎の死を遂げ、彼とシンチュラ家出身の王妃の間に生まれた王子、ジグミ・プンツォック・トゥルバイフが第4代至聖王に就任した。
スルカンはその下でグンロンチェンポ(大宰相)、デシ(諸侯筆頭)、パルパド・ペンロップ(首都知事)、ダラヴァーイー(国軍最高司令官)を兼任して列侯会議を操り、また血の粛清で空席となったペンロップにシンチュラ家の縁者を据えた。
これによって彼の家門は事実上国土の3分の1以上を自らの支配地とした他、各ペンロップ達の権限を徐々に削り取っていき、中央集権国家の基盤を築き上げた。
(このことから、彼は鳳凰に次ぐ偉大な支配者として、鸞大君の尊称を受けた)
スルカンはプンツォック王に指示し、トゥルバイフ即位以来、首都知事の役割を果たしていたパルパド・ペンロップの地位を自身に与えさせた。(これは同時に王が直接支配する土地を奪うことで、経済・軍事の基盤を喪失させる意味があった)また、他の摂政や諸侯に対しては、王の居る首都の保護者として支配的に振る舞い、国政を壟断した。
無論これにはまだ強い権力を持っていた功臣の末裔達が強く反発し、同じ摂政の地位にあったチュカ国ペンロップのウマ・デワを立ててスルカンの退任を要求した。
すると、スルカンはこれに対して列侯会議を招集し、その場での弁明を約した。これを受けて功臣達はパルパドに集まったが、これは卑劣な罠であった。
スルカンは彼らが王宮の会議室に入るや扉を閉めさせ、ウマ・デワと彼を立てて抗おうとした6人のペンロップを全員殺害したのである。また、抜け目の無い彼は同時に反対派の支配するゾンに兵を派遣して奇襲し、これを乗っ取らせると王の勅命の名の下に彼らの親族全員を死罪に処した。
これに恐れをなした3人目の摂政、ワンディ・ポダン・ゾンペンは摂政を辞任し、一人のペンロップとしてスルカンの支持を表明した。
聖暦1170年、血の会議と呼ばれたこの事件の後、スルカンは自身の親族を次々と要職につけ、シンチュラ家による国家の支配を固めさせた。1179年には、成長したプンツォック王が謎の死を遂げ、彼とシンチュラ家出身の王妃の間に生まれた王子、ジグミ・プンツォック・トゥルバイフが第4代至聖王に就任した。
スルカンはその下でグンロンチェンポ(大宰相)、デシ(諸侯筆頭)、パルパド・ペンロップ(首都知事)、ダラヴァーイー(国軍最高司令官)を兼任して列侯会議を操り、また血の粛清で空席となったペンロップにシンチュラ家の縁者を据えた。
これによって彼の家門は事実上国土の3分の1以上を自らの支配地とした他、各ペンロップ達の権限を徐々に削り取っていき、中央集権国家の基盤を築き上げた。
(このことから、彼は鳳凰に次ぐ偉大な支配者として、鸞大君の尊称を受けた)
一代にして王朝の乗っ取りを完成させた怪物、スルカンの死後、彼の地位は息子のティンリン・スルカン・シンチュラに受け継がれた。彼は父とは異なって温厚な性格で、王であるジグミを尊重し、また諸侯らの関係をうまく調整して平穏に国政を運んだ。
彼が統治した30年ほどの間、王国内は久方ぶりの平穏を享受し、パルパドでは大いに文化や芸術が栄えた。
ティンリンは諸外国からの介入を避ける為に、極力外交関係を結ばず小規模な交易のみを続ける方針を取り、以降この方針が王国の基本的な姿勢となった。また、彼は温厚な支配者ではあったが、無原則に寛容な人物であったわけではなく、刑罰に対する厳しい法典を定め、本格的な司法制度を創設させた。
後に王国の人々は彼の治世を「黄金の箍」と呼んで恐れ含みに賞賛した。
聖暦1211年、ティンリン死去。享年は61歳である。
聖暦1213年、ジグミ王が薨去すると、ティンリンの後を引き継いだマンブジ・ティンリン・シンチュラは、ジグミ王の第3王子であるケサル・ジグミ・トゥルバイフを第5代至聖王に据えた。
ケサルは政治的には全く権力を持っていなかったが、一方で文化面で優れた才能を発揮し、王国の歴史編纂事業を自ら指揮した他、多数の詩歌を作詞作曲し、国民に親しまれた。
マンブジも立場を弁えたケサルの行動には介入すること無く、両家の間は平穏無事であった。また、この間幾つもの政略結婚により、王家とシンチュラ家を中心として宮廷内には血縁による強固な繋がりが設けられ、支配はますます盤石となっていった。
しかし、ケサル王が1236年に、マンブジが1238年に不慮の死を遂げると政界を黒い影が覆い始めることになる。
彼が統治した30年ほどの間、王国内は久方ぶりの平穏を享受し、パルパドでは大いに文化や芸術が栄えた。
ティンリンは諸外国からの介入を避ける為に、極力外交関係を結ばず小規模な交易のみを続ける方針を取り、以降この方針が王国の基本的な姿勢となった。また、彼は温厚な支配者ではあったが、無原則に寛容な人物であったわけではなく、刑罰に対する厳しい法典を定め、本格的な司法制度を創設させた。
後に王国の人々は彼の治世を「黄金の箍」と呼んで恐れ含みに賞賛した。
聖暦1211年、ティンリン死去。享年は61歳である。
聖暦1213年、ジグミ王が薨去すると、ティンリンの後を引き継いだマンブジ・ティンリン・シンチュラは、ジグミ王の第3王子であるケサル・ジグミ・トゥルバイフを第5代至聖王に据えた。
ケサルは政治的には全く権力を持っていなかったが、一方で文化面で優れた才能を発揮し、王国の歴史編纂事業を自ら指揮した他、多数の詩歌を作詞作曲し、国民に親しまれた。
マンブジも立場を弁えたケサルの行動には介入すること無く、両家の間は平穏無事であった。また、この間幾つもの政略結婚により、王家とシンチュラ家を中心として宮廷内には血縁による強固な繋がりが設けられ、支配はますます盤石となっていった。
しかし、ケサル王が1236年に、マンブジが1238年に不慮の死を遂げると政界を黒い影が覆い始めることになる。
聖暦1236年にケサル王が薨去すると、子供のいなかった彼の同母弟ラツンを形式上ケサルの養子として迎え、ラツン・ケサル・トゥルバイフとして第6代至聖王に立てた。しかし、マンブジが正式な後継者を定めぬままに1238年、湯治中に事故死すると、シンチュラ家の中で後継をめぐって争いが始まる。
マンブジの長子であったテンスン・マンブジ・シンチュラはまだ13歳の少年であり、到底重職を兼務して政務は取れなかった。その為一門の有力者たちは、テンスンをデシに据え、その代理人としてマンブジの弟であるプンツォ・ティンリンとヨクサム・ティンリンをそれぞれパルパド・ペンロップ、及びダラヴァーイーとして国政を補佐させることに決した。
が、プンツォは側室の子であるヨクサムが大将軍に就いたことに対して大いに不満を抱き、またヨクサムも不祥事を繰り返していたプンツォを酷く嫌っていた。
この両者はテンスンをデシとして迎えた最初の列侯会議で早速激しい対立を演じ、国政を混乱の極みに陥れた。また、シンチュラ家の一門もそれぞれ2人に与して利益のおこぼれを狙うなどの姑息な行動をとり、数多の陰謀が宮廷に渦巻いていた。
一方、その様子を見ていたその他の臣下たちは、この情勢は王政復古に有利と考え、この機に権勢を誇ったシンチュラ家を打倒することを画策した。その中心となったのは王室の係累に連なる名門の貴族、クルガル・ギャルツェン・センロンである。彼ら王政復古派は、シンチュラ家の相剋に乗じて盟を結び合い、王を奉じて政治の権をその手に復帰させることを企んでいた。
また、復古派に優位に働いたのは、プンツォが自らの支持者を増やす為に売官に踏み切ったことで、復古派は彼の支持者を装って多くのシンパを官職に送り込むことに成功したのだった。
そして、聖暦1243年10月。突如復古派はパルパド他5つの都市で武装蜂起し、王宮とゾンを制圧。当時王宮にいたプンツォを殺害すると、ラツン王を奉じて王政復古を宣言した。彼らはシンチュラ家の7つの大罪を非難し、心ある者は従って賊を討てと全土に呼びかけた。
他方混乱の極みにあったシンチュラ側だったが、意外な人物がそれを収めた。その人物とは、18歳になり立派な青年に成長したテンスンであり、彼は見事な手腕によって一族の混乱を収めたばかりか、叛乱軍に靡こうとする周辺諸侯の忠誠をも繋ぎ止めることに成功した。
テンスンはヨクサムを補佐者として一門の混乱を収めると、すぐに軍を整えて王都パルパドを目指した。他方、王を擁すれば諸侯らが容易く靡くと考えていた復古派にとってはこれは大誤算であり、彼らも慌てて軍備を整えて応戦したが、ヨクサムの指揮する追討軍を前に惨敗の末潰走。
クルガルはラツン王を連れて外国への亡命を図ったが、西側のナデル渓谷に差し掛かったところで追いつかれ、討たれた。
その後ラツン王は自身のさらに異母弟で、ケサル王の末子であるギャツァ・ケサル・トゥルバイフに対して王位を禅譲することを強いられ、その後僧院に生涯幽閉された。
ギャツァ・ケサルはギャツァ・ラツンと名を改めた後、第7代至聖王に即位し、テンスンは正式にシンチュラ家の総帥として国事を総覧することとなった。
マンブジの長子であったテンスン・マンブジ・シンチュラはまだ13歳の少年であり、到底重職を兼務して政務は取れなかった。その為一門の有力者たちは、テンスンをデシに据え、その代理人としてマンブジの弟であるプンツォ・ティンリンとヨクサム・ティンリンをそれぞれパルパド・ペンロップ、及びダラヴァーイーとして国政を補佐させることに決した。
が、プンツォは側室の子であるヨクサムが大将軍に就いたことに対して大いに不満を抱き、またヨクサムも不祥事を繰り返していたプンツォを酷く嫌っていた。
この両者はテンスンをデシとして迎えた最初の列侯会議で早速激しい対立を演じ、国政を混乱の極みに陥れた。また、シンチュラ家の一門もそれぞれ2人に与して利益のおこぼれを狙うなどの姑息な行動をとり、数多の陰謀が宮廷に渦巻いていた。
一方、その様子を見ていたその他の臣下たちは、この情勢は王政復古に有利と考え、この機に権勢を誇ったシンチュラ家を打倒することを画策した。その中心となったのは王室の係累に連なる名門の貴族、クルガル・ギャルツェン・センロンである。彼ら王政復古派は、シンチュラ家の相剋に乗じて盟を結び合い、王を奉じて政治の権をその手に復帰させることを企んでいた。
また、復古派に優位に働いたのは、プンツォが自らの支持者を増やす為に売官に踏み切ったことで、復古派は彼の支持者を装って多くのシンパを官職に送り込むことに成功したのだった。
そして、聖暦1243年10月。突如復古派はパルパド他5つの都市で武装蜂起し、王宮とゾンを制圧。当時王宮にいたプンツォを殺害すると、ラツン王を奉じて王政復古を宣言した。彼らはシンチュラ家の7つの大罪を非難し、心ある者は従って賊を討てと全土に呼びかけた。
他方混乱の極みにあったシンチュラ側だったが、意外な人物がそれを収めた。その人物とは、18歳になり立派な青年に成長したテンスンであり、彼は見事な手腕によって一族の混乱を収めたばかりか、叛乱軍に靡こうとする周辺諸侯の忠誠をも繋ぎ止めることに成功した。
テンスンはヨクサムを補佐者として一門の混乱を収めると、すぐに軍を整えて王都パルパドを目指した。他方、王を擁すれば諸侯らが容易く靡くと考えていた復古派にとってはこれは大誤算であり、彼らも慌てて軍備を整えて応戦したが、ヨクサムの指揮する追討軍を前に惨敗の末潰走。
クルガルはラツン王を連れて外国への亡命を図ったが、西側のナデル渓谷に差し掛かったところで追いつかれ、討たれた。
その後ラツン王は自身のさらに異母弟で、ケサル王の末子であるギャツァ・ケサル・トゥルバイフに対して王位を禅譲することを強いられ、その後僧院に生涯幽閉された。
ギャツァ・ケサルはギャツァ・ラツンと名を改めた後、第7代至聖王に即位し、テンスンは正式にシンチュラ家の総帥として国事を総覧することとなった。
テンスンは家長の地位についた後、プンツォ時代の旧弊を一掃し、国の立て直しに尽力した。売官で官職についたものは速やかに罷免され、権勢を振るった貪官汚吏は厳正に処罰された。
これにより人々はテンスンを「聖なる鞭」と呼び、その辣腕を称賛した。
聖暦1266年、政治の立て直しを完了したテンスンは諸外国に目を向け始める。彼は西側のナデル峠を越えた先にあるドゥアール地方を手中に収めようと画策したのだ。
ドゥアール地方は肥沃で温暖、数十万の人口を養うに足る穀倉地帯であると共に、王政復古派が密かに関係を構築していた土地でもあった。故にテンスンは精強な軍によってこの地を制圧し、国境を平穏にすると共に、国の食糧供給の安定を図ったのである。
1267年、テンスンは自身の弟であるジャンペル・マンブジ・シンチュラを総司令官に命じ、騎兵10,000人と歩兵20,000人を預け、ドゥアールへの遠征を命じた。
ドゥアール地方を支配していた太守、ジャンガ・バハドゥルはゲルク王国の侵攻を受け、周辺諸国の戦力を結集してこれを迎撃することを企図した。そして、国内のシャムシェールの野で決戦を挑むこととし、ジャンペルの軍に向けて移動を開始した。
しかし、ジャンペルは敵の作戦の悉くを読み切っており、彼らが遠路長駆してシャムシェールに至る前に原野を制圧し、準備を整えて待ち構えていたのだ。
そして彼は、ジャンガの軍勢が原野に入ろうと街道の終端に差し掛かったところを急襲して大破し、その後追撃して2,000余の首を挙げる大勝利を収めた。これによってドゥアール地方は制圧され、20,000㎢近い広大な領土が王国の手中に収まった。これを喜んだテンスンは、ジャンペルをドゥアールの総督に任じ、その支配権を委ねたのだった。
これにより人々はテンスンを「聖なる鞭」と呼び、その辣腕を称賛した。
聖暦1266年、政治の立て直しを完了したテンスンは諸外国に目を向け始める。彼は西側のナデル峠を越えた先にあるドゥアール地方を手中に収めようと画策したのだ。
ドゥアール地方は肥沃で温暖、数十万の人口を養うに足る穀倉地帯であると共に、王政復古派が密かに関係を構築していた土地でもあった。故にテンスンは精強な軍によってこの地を制圧し、国境を平穏にすると共に、国の食糧供給の安定を図ったのである。
1267年、テンスンは自身の弟であるジャンペル・マンブジ・シンチュラを総司令官に命じ、騎兵10,000人と歩兵20,000人を預け、ドゥアールへの遠征を命じた。
ドゥアール地方を支配していた太守、ジャンガ・バハドゥルはゲルク王国の侵攻を受け、周辺諸国の戦力を結集してこれを迎撃することを企図した。そして、国内のシャムシェールの野で決戦を挑むこととし、ジャンペルの軍に向けて移動を開始した。
しかし、ジャンペルは敵の作戦の悉くを読み切っており、彼らが遠路長駆してシャムシェールに至る前に原野を制圧し、準備を整えて待ち構えていたのだ。
そして彼は、ジャンガの軍勢が原野に入ろうと街道の終端に差し掛かったところを急襲して大破し、その後追撃して2,000余の首を挙げる大勝利を収めた。これによってドゥアール地方は制圧され、20,000㎢近い広大な領土が王国の手中に収まった。これを喜んだテンスンは、ジャンペルをドゥアールの総督に任じ、その支配権を委ねたのだった。
聖暦1308年。ドゥアール遠征から41年の歳月が経った頃。既にテンスンは1288年に死去して政権の座を息子スーナム・テンスン・シンチュラに譲り、至聖王はギャツァの死後、ケルサン・ギャツァ、サンギェ・ケルサンを経て、幼いイェシェー・ケルサン・トゥルバイフが就いた。
この頃王国は再びの平穏を取り戻しており、人々は豊かな暮らしを満喫していた。しかし、彼らの前に恐ろしい脅威が迫っていることには誰も気がついていなかった。
同年4月、王国の朝廷はアルドノア帝国の使者を迎えることになる。名前をゲオルグ・エッシェンバッハというその使者は、王に対して開国と自由貿易、そしてドゥアール地方を要求したのである。口実としては、彼らが保護したドゥアールの支配者から支配権を譲られた、ということであった。
当然ながらこの無礼な申し出は宮廷の憤激を買い、使者は険悪な雰囲気の中、王国を追い出された。しかし、これは彼らに対して絶好の口実を与えることになってしまった。
翌年1309年、帝国北方総督のジークマイスター公爵は、平和的な使者に対する非礼を咎め、王国に対して公的な謝罪と賠償、そしてドゥアールだけでなく、ナデル峠以西全域の領土の割譲を要求したが王国はこれを黙殺。
6月に至ってジークマイスターは、帝国皇帝の名の下に王国に宣戦を布告した。
帝国軍は近代兵器で武装し、15,000人の戦力と共にドゥアールへ侵攻。対するは総督として現地を支配していたジャンペルの息子、ユルスン・ジャンペル・シンチュラで、20,000人の精強な軍を率いていた。しかし、近代兵器の前に彼らは歯が立たず、幾つかの局地的な勝利の他は戦略的敗北を重ね、10月に至ってドゥアール地方は完全に失陥した。
ユルスンはドゥアールの田畑を焼き払い、収穫物を刈り取って焦土化を図った後、ナデル峠を越えて王国本土へ撤退。同地方を制圧した帝国軍は、総司令官ヴァイクス上級大将の決断により、援軍を加えた後ドゥク盆地への侵攻を開始した。
11月中旬、帝国軍はターキン峠を越えて王国本土への侵攻を開始したが、後世においてこれは極めて重大な戦略的誤算だったと言われている。
何故ならば、ドゥアール失陥の時点で王国政府は帝国の要求を受け入れ、謝罪と賠償を行うことを決めており、あとは外交によって地方の割譲を飲ませることが可能だったからである。しかし、本国の命令を無視したジークマイスターとヴァイクスは、ゲルク王国全土の併呑の野望に取り憑かれ、大きな犠牲を払うことになった。
峠に入った帝国軍は、まず険阻な山岳と身も凍る寒さに迎えられ、多大な犠牲を出した。元来ドゥアールは温暖な平地の面積が多くを占めており、総督府の兵士達もそうした赤道の環境に慣れていた。しかし、ドゥク盆地は標高数千メートルの高地にあり、気候は一年を通じて冷涼である。このことから帝国軍の多くは高山病と慣れない寒さに苦しみ、峠越えで1,000人を超える犠牲者を出した。
また、雪辱に燃えるユルスン率いる王国軍は高い指揮と規律、そして先祖以来の並外れた勇猛さを発揮し、地の利を生かして帝国軍に攻勢を仕掛けた。11月26日、国境のプンツォリン周辺での戦闘で敗北した帝国軍は水源へのアクセスを絶たれ、多大な労力を払って万年雪を飲料水に変えることを強いられた。また、29日には豪雪に見舞われて部隊間の連絡が途絶し、そこを各個撃破の攻撃に遭い各地で大敗を喫した。
12月2日。本格的な冬季の到来を悟ったヴァイクスは遂に撤退を決断。ユルスンによる追撃を躱しながらビシェンシンへと退却した。最終的には20,000人の兵士が動員されたが、その3分の1以上が死傷するという大惨敗であった。
12月16日、王国の使者がビシェンシンを訪れ、ドゥアール地方の割譲を受諾する旨を伝えて和睦を提案すると、厭戦機運高まる帝国はこれを受諾し、国境近くのデワンギリ要塞で調印が行われた。
このデワンギリ条約では、王国がドゥアールを割譲する代わりに、帝国が補償金として10万マルク(現実の価値で約2億円)を毎年半分を紙幣、もう半分を金貨で支払うことが取り決められた。
また、王国政府は帝国に対して外交的配慮を行うこととし、帝国以外の列強に対しては引き続き事実上の鎖国を続けることと、酪農によって得られる産品を政府管理の下安価で輸出することも定められた。
条約締結後、王国政府は外国の力を身をもって思い知ると共に、独立維持の重要性を痛感することとなる。以降彼らは帝国の支援の下軍の近代化と政治改革を推し進め、国力の増進に努めた。
この頃王国は再びの平穏を取り戻しており、人々は豊かな暮らしを満喫していた。しかし、彼らの前に恐ろしい脅威が迫っていることには誰も気がついていなかった。
同年4月、王国の朝廷はアルドノア帝国の使者を迎えることになる。名前をゲオルグ・エッシェンバッハというその使者は、王に対して開国と自由貿易、そしてドゥアール地方を要求したのである。口実としては、彼らが保護したドゥアールの支配者から支配権を譲られた、ということであった。
当然ながらこの無礼な申し出は宮廷の憤激を買い、使者は険悪な雰囲気の中、王国を追い出された。しかし、これは彼らに対して絶好の口実を与えることになってしまった。
翌年1309年、帝国北方総督のジークマイスター公爵は、平和的な使者に対する非礼を咎め、王国に対して公的な謝罪と賠償、そしてドゥアールだけでなく、ナデル峠以西全域の領土の割譲を要求したが王国はこれを黙殺。
6月に至ってジークマイスターは、帝国皇帝の名の下に王国に宣戦を布告した。
帝国軍は近代兵器で武装し、15,000人の戦力と共にドゥアールへ侵攻。対するは総督として現地を支配していたジャンペルの息子、ユルスン・ジャンペル・シンチュラで、20,000人の精強な軍を率いていた。しかし、近代兵器の前に彼らは歯が立たず、幾つかの局地的な勝利の他は戦略的敗北を重ね、10月に至ってドゥアール地方は完全に失陥した。
ユルスンはドゥアールの田畑を焼き払い、収穫物を刈り取って焦土化を図った後、ナデル峠を越えて王国本土へ撤退。同地方を制圧した帝国軍は、総司令官ヴァイクス上級大将の決断により、援軍を加えた後ドゥク盆地への侵攻を開始した。
11月中旬、帝国軍はターキン峠を越えて王国本土への侵攻を開始したが、後世においてこれは極めて重大な戦略的誤算だったと言われている。
何故ならば、ドゥアール失陥の時点で王国政府は帝国の要求を受け入れ、謝罪と賠償を行うことを決めており、あとは外交によって地方の割譲を飲ませることが可能だったからである。しかし、本国の命令を無視したジークマイスターとヴァイクスは、ゲルク王国全土の併呑の野望に取り憑かれ、大きな犠牲を払うことになった。
峠に入った帝国軍は、まず険阻な山岳と身も凍る寒さに迎えられ、多大な犠牲を出した。元来ドゥアールは温暖な平地の面積が多くを占めており、総督府の兵士達もそうした赤道の環境に慣れていた。しかし、ドゥク盆地は標高数千メートルの高地にあり、気候は一年を通じて冷涼である。このことから帝国軍の多くは高山病と慣れない寒さに苦しみ、峠越えで1,000人を超える犠牲者を出した。
また、雪辱に燃えるユルスン率いる王国軍は高い指揮と規律、そして先祖以来の並外れた勇猛さを発揮し、地の利を生かして帝国軍に攻勢を仕掛けた。11月26日、国境のプンツォリン周辺での戦闘で敗北した帝国軍は水源へのアクセスを絶たれ、多大な労力を払って万年雪を飲料水に変えることを強いられた。また、29日には豪雪に見舞われて部隊間の連絡が途絶し、そこを各個撃破の攻撃に遭い各地で大敗を喫した。
12月2日。本格的な冬季の到来を悟ったヴァイクスは遂に撤退を決断。ユルスンによる追撃を躱しながらビシェンシンへと退却した。最終的には20,000人の兵士が動員されたが、その3分の1以上が死傷するという大惨敗であった。
12月16日、王国の使者がビシェンシンを訪れ、ドゥアール地方の割譲を受諾する旨を伝えて和睦を提案すると、厭戦機運高まる帝国はこれを受諾し、国境近くのデワンギリ要塞で調印が行われた。
このデワンギリ条約では、王国がドゥアールを割譲する代わりに、帝国が補償金として10万マルク(現実の価値で約2億円)を毎年半分を紙幣、もう半分を金貨で支払うことが取り決められた。
また、王国政府は帝国に対して外交的配慮を行うこととし、帝国以外の列強に対しては引き続き事実上の鎖国を続けることと、酪農によって得られる産品を政府管理の下安価で輸出することも定められた。
条約締結後、王国政府は外国の力を身をもって思い知ると共に、独立維持の重要性を痛感することとなる。以降彼らは帝国の支援の下軍の近代化と政治改革を推し進め、国力の増進に努めた。
スーナムは聖暦1329年に死去し、地位は息子のツァンヤン・スーナム・シンチュラが引き継いだ。ツァンヤンは古いペンロップ制度の解体を目指して改革を断行したが、彼らを長とする貴族家門と官僚の結びつきは非常に強く、改革は頓挫。その後彼は貴族家門と妥協して、軍事や都市行政の面で改革を進めることとなる。
1333年、ツァンヤンは王都パルパドの都市改造を実行し、ゾンを中核として構築されていた城塞都市の一部を解体し、雑然とした街並みを条坊に再編すると共に、土幕と呼ばれるスラムの撤去を進めた。また、彼はこの街に初の下水道を整備して衛生状況を改善させると共に、住居の整備にも取り組むことで都市景観と居住性の両立を目指した。
その他にも彼は農地改革によって自作農の育成に取り組み、国内経済の振興を図るなど多様な手腕を発揮した。
この頃ゲルク盆地は古来からの諸侯や世襲による知事によって治められる封建制が続いていたが、彼は地方の有力者達を都に移住させて土地支配と切り離し、封建制を解体していった。代わって地方で台頭したのが、ペンロップを筆頭とした領主層の代理人として統治を行う知事・代官らの新領主層と、貴族に数えられない在地土豪層であり、彼らは任免権を直接行使したシンチュラ家と結びつき、強い権限を行使した。
が、こうした土地改革は旧来の貴族層からの反発を買い、1336年にツァンヤンは政変によって地位を追われることになる。後任となったセチュン・スーナム・シンチュラは貴族と強く癒着した人物であり、再び貴族による封建的土地制の復活を目論んでいた。
しかし、ツァンヤンが育成していた世襲によらない現地官僚層がこれに強く反発し、彼の目論見は頓挫する。1346年にセチュンが病死すると、追放されたツァンヤンが再び地位に返り咲いた。
聖暦1349年、イェシェー王が薨去し、第11代至聖王にティデ・イェシェー・トゥルバイフが立つと、ツァンヤンは自ら身を引いて地位を息子のツグツェン・ツァンヤン・シンチュラに譲った。
この頃世界は極めて緊張した時代であり、各地で激しい戦争が続いていた。事実上の王国の保護者であるアルドノア帝国もそれに巻き込まれていたが、王国はその勢力の小ささからそうした戦乱を避けることに成功し、平穏を保った。また、戦火により生産が難しくなった織物や、工業用途での需要が高まったルビーの輸出によって経済は安定すると共に、流入した外国の知識に触発された新たな文化が花開いた。
この時代は「華の時代」と呼ばれ、世界が戦争によって傷つく中、平和を維持した理想的な時代として後世に賞賛されることとなる。
1359年、世界的な混乱が終結した後、帝国は世界各地に保持していた広大な植民地を放棄し、独立を容認する施策に転じた。これによって王国との保護関係も事実上終了し、外交関係がほぼ途絶する。
ツグツェンはその後経済を国内向けに構築し直すことでこの情勢に対応し、王国の再鎖国と伝統を維持する施策をとった。これによって再び彼らは世界に背を向け、山岳に囲まれた盆地の中、固有の文化を守り続けることとなる。
1365年ツグツェンが死去。地位は息子ヴェツォプ・ツグツェン・シンチュラが継承し、父の路線を引き継いだ。1369年にはティデ王も亡くなり、第12代至聖王としてデントゥップ・ティデ・トゥルバイフが即位した。
以後王国の情勢は外に殆ど知られることは無かったが、外部との関係が絶無であったわけではなく、貿易や農業支援の関係で時折外国人が入国し、そこから詳しい情勢が報告されている。
聖暦1377年、デントゥップ王が不慮の死を遂げると、ペマ・デントゥップ・トゥルバイフが僅か2歳にして第13代至聖王に即位。ヴェツォプが摂政を称して全面的に国事を代行した。
1380年、列侯会議が憲法草案の策定を議決。長きに渡り存在しなかった王国のあり方を規定する法律の作成が模索され始めた。
1396年、31年に渡り国に君臨したヴェツォプ摂政が死去。後継には王の姉ジェツン公主を妻とした4男、ドルジ・ヴェツォプ・シンチュラが就任した。また、この頃から積極的に世襲によらない官吏登用が進められる様になる。
1405年、諸外国からの提案により国連に加盟。外国人の入域宣言緩和の議論が本格的に始まる。
1333年、ツァンヤンは王都パルパドの都市改造を実行し、ゾンを中核として構築されていた城塞都市の一部を解体し、雑然とした街並みを条坊に再編すると共に、土幕と呼ばれるスラムの撤去を進めた。また、彼はこの街に初の下水道を整備して衛生状況を改善させると共に、住居の整備にも取り組むことで都市景観と居住性の両立を目指した。
その他にも彼は農地改革によって自作農の育成に取り組み、国内経済の振興を図るなど多様な手腕を発揮した。
この頃ゲルク盆地は古来からの諸侯や世襲による知事によって治められる封建制が続いていたが、彼は地方の有力者達を都に移住させて土地支配と切り離し、封建制を解体していった。代わって地方で台頭したのが、ペンロップを筆頭とした領主層の代理人として統治を行う知事・代官らの新領主層と、貴族に数えられない在地土豪層であり、彼らは任免権を直接行使したシンチュラ家と結びつき、強い権限を行使した。
が、こうした土地改革は旧来の貴族層からの反発を買い、1336年にツァンヤンは政変によって地位を追われることになる。後任となったセチュン・スーナム・シンチュラは貴族と強く癒着した人物であり、再び貴族による封建的土地制の復活を目論んでいた。
しかし、ツァンヤンが育成していた世襲によらない現地官僚層がこれに強く反発し、彼の目論見は頓挫する。1346年にセチュンが病死すると、追放されたツァンヤンが再び地位に返り咲いた。
聖暦1349年、イェシェー王が薨去し、第11代至聖王にティデ・イェシェー・トゥルバイフが立つと、ツァンヤンは自ら身を引いて地位を息子のツグツェン・ツァンヤン・シンチュラに譲った。
この頃世界は極めて緊張した時代であり、各地で激しい戦争が続いていた。事実上の王国の保護者であるアルドノア帝国もそれに巻き込まれていたが、王国はその勢力の小ささからそうした戦乱を避けることに成功し、平穏を保った。また、戦火により生産が難しくなった織物や、工業用途での需要が高まったルビーの輸出によって経済は安定すると共に、流入した外国の知識に触発された新たな文化が花開いた。
この時代は「華の時代」と呼ばれ、世界が戦争によって傷つく中、平和を維持した理想的な時代として後世に賞賛されることとなる。
1359年、世界的な混乱が終結した後、帝国は世界各地に保持していた広大な植民地を放棄し、独立を容認する施策に転じた。これによって王国との保護関係も事実上終了し、外交関係がほぼ途絶する。
ツグツェンはその後経済を国内向けに構築し直すことでこの情勢に対応し、王国の再鎖国と伝統を維持する施策をとった。これによって再び彼らは世界に背を向け、山岳に囲まれた盆地の中、固有の文化を守り続けることとなる。
1365年ツグツェンが死去。地位は息子ヴェツォプ・ツグツェン・シンチュラが継承し、父の路線を引き継いだ。1369年にはティデ王も亡くなり、第12代至聖王としてデントゥップ・ティデ・トゥルバイフが即位した。
以後王国の情勢は外に殆ど知られることは無かったが、外部との関係が絶無であったわけではなく、貿易や農業支援の関係で時折外国人が入国し、そこから詳しい情勢が報告されている。
聖暦1377年、デントゥップ王が不慮の死を遂げると、ペマ・デントゥップ・トゥルバイフが僅か2歳にして第13代至聖王に即位。ヴェツォプが摂政を称して全面的に国事を代行した。
1380年、列侯会議が憲法草案の策定を議決。長きに渡り存在しなかった王国のあり方を規定する法律の作成が模索され始めた。
1396年、31年に渡り国に君臨したヴェツォプ摂政が死去。後継には王の姉ジェツン公主を妻とした4男、ドルジ・ヴェツォプ・シンチュラが就任した。また、この頃から積極的に世襲によらない官吏登用が進められる様になる。
1405年、諸外国からの提案により国連に加盟。外国人の入域宣言緩和の議論が本格的に始まる。
王国の領土は四方を険阻な山岳に囲まれたドゥク盆地を主要な領域としている。国土の大部分が3,000-4,000メートルの高地であり、気候は1年を通じて冷涼である。また、冬には積雪があり、交通路である2つの峠も封鎖され、外界から孤立する。
国土最高峰は7,968メートルのガンケル・プンスム。次いで7,639メートルのミンリンカンリ、そして7,361メートルのカイラス山が続く。この3つの山はそれぞれ、「天地創造の始まりの山」、「王家の守護神が住む山」、「聖者ミラレパゆかりの山」として立ち入りが厳重に禁じられており、いずれも人類未踏の山である。(なお、この3座は1400年に正式に「永久未踏峰」と宣言された)これらの山々には厳重な保護の結果古代からの生態系が残されており、未発見の新種が多数存在すると見られている。
国土をいくつか分割するように高峰から河川が流れており、地下を伏流して低地の諸国へ流れ出る。これらの水は雪解け水を含み非常に冷たい為、水を温めて農業用水にする為の溜池が各地に存在している。
国土最高峰は7,968メートルのガンケル・プンスム。次いで7,639メートルのミンリンカンリ、そして7,361メートルのカイラス山が続く。この3つの山はそれぞれ、「天地創造の始まりの山」、「王家の守護神が住む山」、「聖者ミラレパゆかりの山」として立ち入りが厳重に禁じられており、いずれも人類未踏の山である。(なお、この3座は1400年に正式に「永久未踏峰」と宣言された)これらの山々には厳重な保護の結果古代からの生態系が残されており、未発見の新種が多数存在すると見られている。
国土をいくつか分割するように高峰から河川が流れており、地下を伏流して低地の諸国へ流れ出る。これらの水は雪解け水を含み非常に冷たい為、水を温めて農業用水にする為の溜池が各地に存在している。
ゲルク王国の政治は伝統的な祭政一致の絶対君主制である。元首である至聖王(ジェツン・ギャルポ)が絶対的な権限を握り、その下で各地のゾン(城塞)の主人達が名目上の政治を行う。(形式的封建制)
至聖王は国内で信仰されるゲルク教の最高指導者として崇められており、政治・宗教の最高権威として国を統治してきた。
しかし、第3代王の摂政となったスルカン・シンチュラ以来政治の実権はシンチュラ家によって担われており、彼らは大宰相、大将軍、首都知事など政治・軍事の要職を世襲することで事実上国家の支配者となった。
以降シンチュラ家当主はロンチェン(相国)、ホンタイジ(副王)と尊称され、内にあっては王に代わる統治者として王国内で権勢を振るい、対外的には国師(シャブドゥン)を称し、国家元首に準じる扱いを受けている。
至聖王は国内で信仰されるゲルク教の最高指導者として崇められており、政治・宗教の最高権威として国を統治してきた。
しかし、第3代王の摂政となったスルカン・シンチュラ以来政治の実権はシンチュラ家によって担われており、彼らは大宰相、大将軍、首都知事など政治・軍事の要職を世襲することで事実上国家の支配者となった。
以降シンチュラ家当主はロンチェン(相国)、ホンタイジ(副王)と尊称され、内にあっては王に代わる統治者として王国内で権勢を振るい、対外的には国師(シャブドゥン)を称し、国家元首に準じる扱いを受けている。
ゲルク王国は、18諸侯による政治(ペンロップ制)の伝統を引き継ぎ、土地支配と血縁によって結ばれた貴族層がいまだに政治に強い影響力を持っている。
中でもペンロップと尊称され、国内のゾンを中心に広大な土地を支配する23の大貴族(その筆頭がシンチュラ家)は、王族や貴族間の通婚によって権力を世襲し、国家の重職を独占してきた。また、その下に存在する400余りの下級貴族たちはゲオの知事や軍の指揮官など中流の官吏・軍人を輩出することで国事を担い、民衆を支配した。
下級貴族が領主として直接に土地を支配する支配制度は、聖暦13世紀後期の改革により既に崩壊して久しいが、宮廷貴族に脱皮した彼らは上位の貴族達と結びつき、依然として政治実務に強い実権を保持している。
また、貴族達は領主でこそなくなったが依然として国土の大部分を所有する大土地所有者であり、小作人を使役した過酷な労働から多くの収入を得ている。(こうした大土地所有者の筆頭がシンチュラ家であり、国土の4分の1を一族で知行している)
こうした貴族制は王国の政治の大きな特徴であり、人口の僅か4%の彼らは宗教の裏付けの下、今でも圧倒的な特権を保持して苛烈な政争を繰り広げている。
中でもペンロップと尊称され、国内のゾンを中心に広大な土地を支配する23の大貴族(その筆頭がシンチュラ家)は、王族や貴族間の通婚によって権力を世襲し、国家の重職を独占してきた。また、その下に存在する400余りの下級貴族たちはゲオの知事や軍の指揮官など中流の官吏・軍人を輩出することで国事を担い、民衆を支配した。
下級貴族が領主として直接に土地を支配する支配制度は、聖暦13世紀後期の改革により既に崩壊して久しいが、宮廷貴族に脱皮した彼らは上位の貴族達と結びつき、依然として政治実務に強い実権を保持している。
また、貴族達は領主でこそなくなったが依然として国土の大部分を所有する大土地所有者であり、小作人を使役した過酷な労働から多くの収入を得ている。(こうした大土地所有者の筆頭がシンチュラ家であり、国土の4分の1を一族で知行している)
こうした貴族制は王国の政治の大きな特徴であり、人口の僅か4%の彼らは宗教の裏付けの下、今でも圧倒的な特権を保持して苛烈な政争を繰り広げている。
23人のペンロップと国王からなる国政の最高指導機関。国王は議長役に徹して意見を言わず、主としてペンロップが意見を戦わせる。ペンロップ達の筆頭は「デシ」と称する。
また、国王が空位の際はこの会議によって後継者を決定する。
また、国王が空位の際はこの会議によって後継者を決定する。
官制は民族の故地である中華文化圏の強い影響下で形成され、かつそれが隔絶した山岳下で維持されてきた。一品から九品、そしてそれを正と従に分けた18等級が定められ、それぞれに対応した官職が存在した。
また、官職には文官と武官の区別があり、いくつかの職は特定の家門や家柄・階級が独占及び世襲していた。(所謂貴族とされるのは、五品以上の官品に3代続けて叙された人々で、3代目から貴族として公認された)
貴族の子女たちは成年に達すると原則として自動的に官品を受け、然るのち官吏の仕事を学ぶ国立学校に配属された。娘は官品を受ける時期を目処に見合いが組まれ、同格の貴族へと輿入れした。
行政については至聖王と列侯会議の下、大宰相を頂点とする官僚機構が整備された。
首都パルパドには、大宰相府(大宰相を頂点に、その補佐官と事務を扱う部局で構成される)指揮の下で実際の行政を担う八省と呼ばれる専門部局(中書・吏部・式部・刑部・兵部・民部・工部・蔵部)と、宗室・功臣・宮廷を司る宮内三府、並びに軍令を司る軍機房、そして名義上は国王直属の秘密監察機関である錦衣使庁が設置されて中央政府の機能を果たした他、地方ではペンロップの同意の下、ゲオなどの知事が任命されて政務にあたった。
これらの官は長官・通判官・判官・主典と呼ばれる四等官制を基本とし、各機関の中心部から配下の専門部局まで同様の構造をとっている。(なお、四等官それぞれの名前は各機関で異なり、例えば各省では卿・佐郎・判事・主簿と称される)
国防は全国8ヵ所に拠点を置き、それぞれの将軍(ベイレ)が大将軍の下指揮する「八大営」と、パルパドに駐留して首都防衛を担う「六禁衛」が担う。(通称ゲルク王国陸軍。合わせて約17万騎の兵力を抱えている)
ただ一方で、これらの官制は複雑かつ無駄が多く、実態の存在しない官職や義務の割に対価の過大な官職、著しい役得を生ずる官職などが多数存在し、これらの職を貴族間で闇に売り買いすることが横行して、政治上の大きな問題となっている。
また、官職には文官と武官の区別があり、いくつかの職は特定の家門や家柄・階級が独占及び世襲していた。(所謂貴族とされるのは、五品以上の官品に3代続けて叙された人々で、3代目から貴族として公認された)
貴族の子女たちは成年に達すると原則として自動的に官品を受け、然るのち官吏の仕事を学ぶ国立学校に配属された。娘は官品を受ける時期を目処に見合いが組まれ、同格の貴族へと輿入れした。
行政については至聖王と列侯会議の下、大宰相を頂点とする官僚機構が整備された。
首都パルパドには、大宰相府(大宰相を頂点に、その補佐官と事務を扱う部局で構成される)指揮の下で実際の行政を担う八省と呼ばれる専門部局(中書・吏部・式部・刑部・兵部・民部・工部・蔵部)と、宗室・功臣・宮廷を司る宮内三府、並びに軍令を司る軍機房、そして名義上は国王直属の秘密監察機関である錦衣使庁が設置されて中央政府の機能を果たした他、地方ではペンロップの同意の下、ゲオなどの知事が任命されて政務にあたった。
これらの官は長官・通判官・判官・主典と呼ばれる四等官制を基本とし、各機関の中心部から配下の専門部局まで同様の構造をとっている。(なお、四等官それぞれの名前は各機関で異なり、例えば各省では卿・佐郎・判事・主簿と称される)
国防は全国8ヵ所に拠点を置き、それぞれの将軍(ベイレ)が大将軍の下指揮する「八大営」と、パルパドに駐留して首都防衛を担う「六禁衛」が担う。(通称ゲルク王国陸軍。合わせて約17万騎の兵力を抱えている)
ただ一方で、これらの官制は複雑かつ無駄が多く、実態の存在しない官職や義務の割に対価の過大な官職、著しい役得を生ずる官職などが多数存在し、これらの職を貴族間で闇に売り買いすることが横行して、政治上の大きな問題となっている。
ゲルク王国の政治の特徴の一つに、大貴族やシンチュラ家の縁者を中心に結成された派閥による激しい抗争(「党争」)が挙げられる。
この国の激しい政治的派閥抗争は、王国が長きに渡って外部との通行をほとんど持たず、また近代に入ってからはアルドノア帝国の事実上の保護国として、外からの軍事的脅威がほとんど無く、政治体制が極端に内向化したことから生じたと言われており、この争いによって絶えず政局は不安定な状態に置かれている。
現在政権を握っているのは、大宰相ドルジ・シンチュラを擁し、開国を進めようとする「南方派(開化派とも)」であるが、これに対しドルジの弟で後継者レースに敗れたドゥンカル・シンチュラ(正二品大宰相府監事)を戴く鎖国主義グループの「北方派(斥邪派とも)」がもう一つの大党派として存在している他、南方派の内部でも「大南派」、「小南派」などの細かい派閥が存在しており、常に激しい対立が続けられている。
この国の激しい政治的派閥抗争は、王国が長きに渡って外部との通行をほとんど持たず、また近代に入ってからはアルドノア帝国の事実上の保護国として、外からの軍事的脅威がほとんど無く、政治体制が極端に内向化したことから生じたと言われており、この争いによって絶えず政局は不安定な状態に置かれている。
現在政権を握っているのは、大宰相ドルジ・シンチュラを擁し、開国を進めようとする「南方派(開化派とも)」であるが、これに対しドルジの弟で後継者レースに敗れたドゥンカル・シンチュラ(正二品大宰相府監事)を戴く鎖国主義グループの「北方派(斥邪派とも)」がもう一つの大党派として存在している他、南方派の内部でも「大南派」、「小南派」などの細かい派閥が存在しており、常に激しい対立が続けられている。
国土は伝統的に険阻な土地に建設された「ゾン」と呼ばれる要塞とその城下町を中心に区分されている。かつての戦乱の頃はドゥク盆地全体に53のゾンが存在したとされるが、統一の過程で一国一城の原則が規定され、ゾンは各国に1つのみ、支城となる小さな要塞は「ゲオ」と呼称されることとなった。(ゲオとはいわゆる小国のこと)
ゾンの支配する範囲は「ゾンカク」と呼ばれ、国内に24個存在する。かつてはこのゾンカクの主人がペンロップとして会議に列し、合議によって国を動かしてきた。(現在ではペンロップの支配権後退により、ゾンカク内の区分であるゲオが重視され、形骸化の色を濃くしている)
なお、現在もゾンには寺や政庁が置かれ、整備された城下町は古い建築様式の建物が豊富に残っている。
ゾンの支配する範囲は「ゾンカク」と呼ばれ、国内に24個存在する。かつてはこのゾンカクの主人がペンロップとして会議に列し、合議によって国を動かしてきた。(現在ではペンロップの支配権後退により、ゾンカク内の区分であるゲオが重視され、形骸化の色を濃くしている)
なお、現在もゾンには寺や政庁が置かれ、整備された城下町は古い建築様式の建物が豊富に残っている。
1.パルパド
2.チュカ
3.ダガナ
4.パロ
5.ハ
6.プナカ
7.ルンツェ
8.ブムタン
9.サムツェ
10.モンガル
11.トンサ
12.アルガ
13.カンチー
14.セーナ
15.タナフン
16.ジェムガン
17.チラン
18.サルパン
19.タシガン
20.ノルブガング
21.ユルング
22.シャマル
23.ゾベル
24.カル
それぞれのゾンの下にはゲオと呼ばれる区分があり、時に応じて変わるものの初期は227、現在は248個存在する。
2.チュカ
3.ダガナ
4.パロ
5.ハ
6.プナカ
7.ルンツェ
8.ブムタン
9.サムツェ
10.モンガル
11.トンサ
12.アルガ
13.カンチー
14.セーナ
15.タナフン
16.ジェムガン
17.チラン
18.サルパン
19.タシガン
20.ノルブガング
21.ユルング
22.シャマル
23.ゾベル
24.カル
それぞれのゾンの下にはゲオと呼ばれる区分があり、時に応じて変わるものの初期は227、現在は248個存在する。
国連加盟にあたって王国政府が提出した人口の記録は、今から5年前に行われた調査に基づくもので、凡そ361万7200人。但し、これらはあくまで戸籍に登録された人数であり、それらの存在しない無宿人や正確な統計が難しい被差別集落の人口は計上されていない。国連の試算ではそうした階層まで含めた総人口は400万を超えると推定している。
ゲルク人の名前は基本的に「自身の名前+主に父親の名前」で構成され、一部を除き姓は無い。識別が必要な際は出身や居住地域名を合わせて名乗る。
但し、貴族家門や英傑の子孫を名乗る家は、その開祖となった人物や神々の名前をラストネームとして用いることが多く、家系の由緒を継承している。
(具体例:ペマ・デントゥップ・トゥルバイフ…ペマが個人名、デントゥップが父親の名前、トゥルバイフは開祖トゥルバイフ王に由来。なお、トゥルバイフ王は旧名としてトゥルバイフ・ギャルツェン・ヤクシャを名乗っていた)
但し、貴族家門や英傑の子孫を名乗る家は、その開祖となった人物や神々の名前をラストネームとして用いることが多く、家系の由緒を継承している。
(具体例:ペマ・デントゥップ・トゥルバイフ…ペマが個人名、デントゥップが父親の名前、トゥルバイフは開祖トゥルバイフ王に由来。なお、トゥルバイフ王は旧名としてトゥルバイフ・ギャルツェン・ヤクシャを名乗っていた)
トゥルバイフ家が世襲する至聖王は、国の頂点に立つ存在であると共に、政治と宗教の最高指導者として強大な権力を持つ。初代王トゥルバイフは、自らをして「偉大なる至聖ミラレパの生まれ変わり」とし、「ドゥク・ユル全土の正統にして絶対の統治者」と宣言した。
しかし、偉大な開祖トゥルバイフが亡くなった後、第2代の王が夭折、その後若くして就いた第3代の王の頃に政権はシンチュラ家によって、経済的・軍事的基盤であった直轄領の支配権を乗っ取られ、以降儀礼上・宗教上の最高指導者となっている。
別称・雅称として「グーシ・ノミイ・ハーン」(転輪法王)、「ダルマ・ラージャ」、「ナムギャル・チョレー・ツェンポ」(諸方に勝利せる君主)など多数。
現在の至聖王は第13代ペマ・デントゥップ・トゥルバイフ。
しかし、偉大な開祖トゥルバイフが亡くなった後、第2代の王が夭折、その後若くして就いた第3代の王の頃に政権はシンチュラ家によって、経済的・軍事的基盤であった直轄領の支配権を乗っ取られ、以降儀礼上・宗教上の最高指導者となっている。
別称・雅称として「グーシ・ノミイ・ハーン」(転輪法王)、「ダルマ・ラージャ」、「ナムギャル・チョレー・ツェンポ」(諸方に勝利せる君主)など多数。
現在の至聖王は第13代ペマ・デントゥップ・トゥルバイフ。
国王の子女の他、トゥルバイフの姓を名乗る許しを得た人々は、王族として特権階級の最高位に位置する。男子は「王子」、女子は「公主」(王子の孫は王孫・郡主。公主の子は王族の待遇を受けられないが一部例外あり)と尊称され、彼らは諸侯の上位に置かれ崇敬を受けた。
が、彼らの政治的な権限は皆無に等しく、あくまで俸禄を受けて儀礼的な職務に就くにとどまっており、女子については有力家門に権威付の為に降嫁する習わしで、決して恵まれているわけではない。
が、彼らの政治的な権限は皆無に等しく、あくまで俸禄を受けて儀礼的な職務に就くにとどまっており、女子については有力家門に権威付の為に降嫁する習わしで、決して恵まれているわけではない。
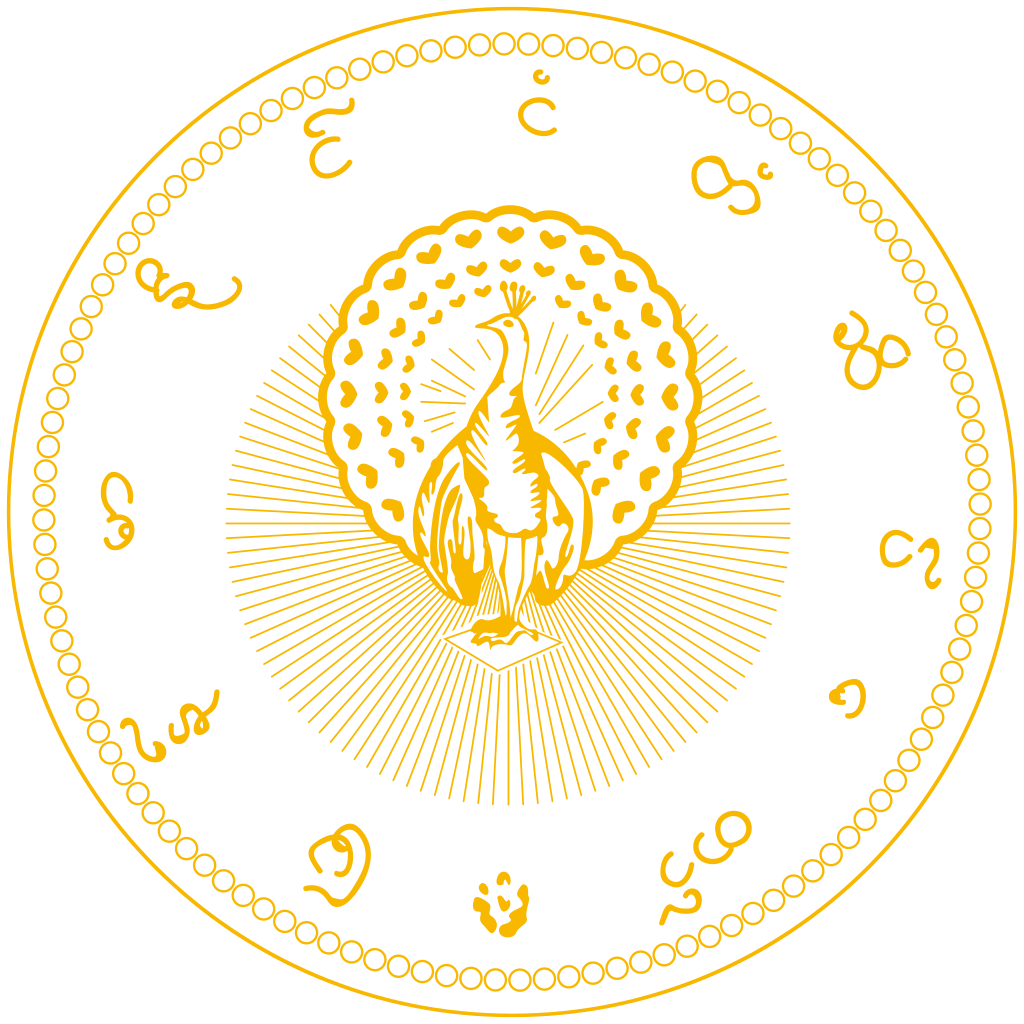 |
また、当主以下一族の有力者は公主をはじめとした王族の子女を妻や夫に迎えることで結びつきを強め、国王のほぼ唯一の外戚としても絶対的な力を得ていた。
そうした彼らの権威はその称号や地位特権にも表れており、当主は尊称としてロンチェン(相国)、ホンタイジ(副王)と呼ばれ、当主正室の子女は自動的に従一品に叙された。また、降嫁した公主と当主との間の子女は特に優遇され、公的に「王孫・郡主」の称号を用い、王族として遇される。(女系によって王族と認定されるのはシンチュラ家の子女が唯一)
現在の当主はドルジ・ヴェツォプ・シンチュラ。妻はパドマ公主だったが、聖暦1389年、一人娘であるアルナ郡主を産む際に産褥死。
現在シンチュラ家の一族は、8つのゾンのペンロップ、全ゲオの約半分の知事職、及び中央の官職の3分の1、そして朝儀に列する大臣級の職に10数名の一門並びに親類縁者を送り込んでいる他、国師として国家の対外代表権を行使するなど、最盛期と謳われるスルカン・ティンリンの時代にも劣らない繁栄の時代を迎えている。
シンチュラ家を筆頭とする貴族達は「ペンロップ」と尊称され、現在も名目上ゾンカクの支配権を世襲する23の有力者を筆頭として、上位の官職や特権を代々受け継いで国の中枢を担ってきた。
彼らは古い中華の習慣に倣って漢風の名前を名乗り、また漢文を学んで使用した。宮廷にも位階ごとの補子を縫い付けた団領袍を着用して出仕し、朝儀や列侯会議を通じて政務を行なった。
現在は大小400余りの家門が貴族として認められており、中央政府の官僚職を独占している。
彼らは古い中華の習慣に倣って漢風の名前を名乗り、また漢文を学んで使用した。宮廷にも位階ごとの補子を縫い付けた団領袍を着用して出仕し、朝儀や列侯会議を通じて政務を行なった。
現在は大小400余りの家門が貴族として認められており、中央政府の官僚職を独占している。
貴族の下で政治や軍事の実務を担う人々。中級から下級の官吏を主に務めている。彼らも特権階級の一部として中華風の服装をし、漢人としての名前を持っていた。
彼らは貴族の下で六品から九品までの役職を務め、実際に技能を活かして政治の執行を担った。中人・士族は名目上は世襲ではなく、試験や実力、才能によって登用されることとなっていたが、時代を経て医学・天文学・外国語・法学・儀典などの特殊な分野は世襲が進む様になり、中でも刑部の傘下で警察業務を行う捕盗庁、同じく訴訟手続きを担当する判官庁の上位官人は多くが職務に精通した一族が世襲した。
なお、名義上は国王の直属(事実上はシンチュラ家直属)となっていた秘密監察官である錦衣使は長官まで含めて中人や士族が任命された。
ちなみに、貴族と共に文字の読み書きや教養のある彼らは、文化の中心的な担い手としても活躍した。
彼らは貴族の下で六品から九品までの役職を務め、実際に技能を活かして政治の執行を担った。中人・士族は名目上は世襲ではなく、試験や実力、才能によって登用されることとなっていたが、時代を経て医学・天文学・外国語・法学・儀典などの特殊な分野は世襲が進む様になり、中でも刑部の傘下で警察業務を行う捕盗庁、同じく訴訟手続きを担当する判官庁の上位官人は多くが職務に精通した一族が世襲した。
なお、名義上は国王の直属(事実上はシンチュラ家直属)となっていた秘密監察官である錦衣使は長官まで含めて中人や士族が任命された。
ちなみに、貴族と共に文字の読み書きや教養のある彼らは、文化の中心的な担い手としても活躍した。
宗教国家でもあるゲルク王国において、僧侶の果たす役割は多岐に渡り、また非常に重い。彼らは僧院で出家した後厳しい修行を重ね、祈りの儀礼や経典を学び、平均15年ほどかけてようやく弟子を取ることが許される。
こうした僧侶は社会的に高い地位を占め、人々から敬われた。また、僧侶を養う為に僧院が開墾した田畑の収穫は無税とされ、托鉢も取るに任せられていた。
しかし、そうした僧侶個人の財産所有や、税金逃れの為の出家は厳しく規制され、原則としてその土地の支配者の許可や相応の知識と覚悟があるかの試験を要したり、あるいは出家の際は個人の財は全て国家に収めることと規定されていた。
また、僧院が密かに商品作物を植えて闇に流していたことが発覚すると、僧院長を含めた僧侶尽くを死罪または賎民降格刑に処すなどの厳正な処罰が実施された。
こうした僧侶は社会的に高い地位を占め、人々から敬われた。また、僧侶を養う為に僧院が開墾した田畑の収穫は無税とされ、托鉢も取るに任せられていた。
しかし、そうした僧侶個人の財産所有や、税金逃れの為の出家は厳しく規制され、原則としてその土地の支配者の許可や相応の知識と覚悟があるかの試験を要したり、あるいは出家の際は個人の財は全て国家に収めることと規定されていた。
また、僧院が密かに商品作物を植えて闇に流していたことが発覚すると、僧院長を含めた僧侶尽くを死罪または賎民降格刑に処すなどの厳正な処罰が実施された。
庶人は国民の約7割を占める最大の階層で、農民や商工業者など多様な人々で構成されている。彼らは街や農村に住み、収穫の一部、または労役として技術を提供していた。
庶人達の多くは農耕や酪農、林業などに従事しており、専門的な商人として経済活動を行う人間は余りいなかった。しかし、パルパドの様な相応の規模を持つ都市に居住した人々は、町人として種々の経済活動に勤しみ、各地の産物を取引して王府や貴族達に売却していた。
また、職人達は各職能ごとに公認の独占団体を作り、労役の分担やそこから得られる利益の分配を行っていた。
庶人達の多くは農耕や酪農、林業などに従事しており、専門的な商人として経済活動を行う人間は余りいなかった。しかし、パルパドの様な相応の規模を持つ都市に居住した人々は、町人として種々の経済活動に勤しみ、各地の産物を取引して王府や貴族達に売却していた。
また、職人達は各職能ごとに公認の独占団体を作り、労役の分担やそこから得られる利益の分配を行っていた。
賎民はいわゆる被差別民である。人口の1割を占める彼らは、その他の立場からは厳格に差別され、非常に不利な扱いを受けていた。具体的な定義は無かったが、幾つかの賤職に従事するものがそう見なされた。具体的には皮革業、乞食、無宿人、妓女及び女衒、芸人、獄吏、処刑人、奴隷などである。
彼らはゾンとそれを中心にした城下町に住むことを許されず、離れた位置に小さな集落を作って暮らしていた。(妓女などは除く。彼女らは便宜上街と区別された別の区画に集住していた)
また、賎民の中でも奴婢と呼ばれた奴隷達は、人間とは看做されず貴族達によって私有され、売買と相続の対象となった。国連に加盟した後はそうした身分制度の改革が求められているが、貴族層の反対は根強く遅々として進んでいない。
但し、こうした賎民層には一般の人々に課せられた義務は存在せず、生きるために働くだけで良かった。また、彼らの中には溜め込んだ財産を元手に金融業を営み、貴族や中人相手に商売を行って大儲けするものもあった。しかし、彼らには冥加金や運上金も含めて、いかなる形の税金や収奪も行われなかった。(賎民の財産さえ穢らわしいと見做された為)
金融業者の多くは皮革業や遊郭の主人、或いは収監者からの賄賂を受け取る機会の多い獄卒であった。
彼らはゾンとそれを中心にした城下町に住むことを許されず、離れた位置に小さな集落を作って暮らしていた。(妓女などは除く。彼女らは便宜上街と区別された別の区画に集住していた)
また、賎民の中でも奴婢と呼ばれた奴隷達は、人間とは看做されず貴族達によって私有され、売買と相続の対象となった。国連に加盟した後はそうした身分制度の改革が求められているが、貴族層の反対は根強く遅々として進んでいない。
但し、こうした賎民層には一般の人々に課せられた義務は存在せず、生きるために働くだけで良かった。また、彼らの中には溜め込んだ財産を元手に金融業を営み、貴族や中人相手に商売を行って大儲けするものもあった。しかし、彼らには冥加金や運上金も含めて、いかなる形の税金や収奪も行われなかった。(賎民の財産さえ穢らわしいと見做された為)
金融業者の多くは皮革業や遊郭の主人、或いは収監者からの賄賂を受け取る機会の多い獄卒であった。
ゲルク王国では、ミラレパによって開かれたゲルク教を中心とした宗教的な文化が当初栄え、後に英雄叙事詩や物語などの文学がついで繁栄した。
これらの担い手は初期は貴族や僧侶であったが、トゥルバイフ朝が成立した後は、下層の官僚や民衆が担い手となった文学・絵画・音楽といった独特の文化が爛熟し、孤立した環境下で外部からの影響も少なく守られてきた。(ルーツとなった中華系文化のテイストが高山に順応して今に残った、と表現される)
文学や物語については、初期の物は中華の文字によって記されてきたが、のちに独自の文字(ミラレパが発明したとされる「ジェツン文字」、及びそれを改良した「トンミ文字」)が使用される様になり、民族の起源や英雄を扱う文学が大いに発展した。
これらの文学作品の中で著名なのは、ミラレパの生涯を綴った「至聖記」、トゥルバイフ朝建国の経緯を記録した「王書」、英雄叙事詩として「マナス王物語」、後期に栄えた民衆の暮らしを描く人情本の傑作、「白雲物語」などである。
これらの担い手は初期は貴族や僧侶であったが、トゥルバイフ朝が成立した後は、下層の官僚や民衆が担い手となった文学・絵画・音楽といった独特の文化が爛熟し、孤立した環境下で外部からの影響も少なく守られてきた。(ルーツとなった中華系文化のテイストが高山に順応して今に残った、と表現される)
文学や物語については、初期の物は中華の文字によって記されてきたが、のちに独自の文字(ミラレパが発明したとされる「ジェツン文字」、及びそれを改良した「トンミ文字」)が使用される様になり、民族の起源や英雄を扱う文学が大いに発展した。
これらの文学作品の中で著名なのは、ミラレパの生涯を綴った「至聖記」、トゥルバイフ朝建国の経緯を記録した「王書」、英雄叙事詩として「マナス王物語」、後期に栄えた民衆の暮らしを描く人情本の傑作、「白雲物語」などである。
ゲルク教は王国内で圧倒的多数派を占める民族宗教で、開祖は初代王ミラレパとされるが、それ以前から信仰されてきた土着宗教の影響が非常に濃く、本当の意味での開祖は存在しない。ミラレパは寧ろ、無秩序に乱立していた教えを整理し、現在に残る宗教と政治が結びついた国家機構と、体系的な信仰を生み出した人物と海外では評価されている。
天地創成・一切万物の根源神シャンバラ(漢語:無量光大神)を頂点とした多神教の形をとり、出家した僧侶達を聖職者として抱える。
信仰の形態は王国各地に様々な分派があるが、輪廻転生や本地垂迹の思想が共通点としてみられる。
天地創成・一切万物の根源神シャンバラ(漢語:無量光大神)を頂点とした多神教の形をとり、出家した僧侶達を聖職者として抱える。
信仰の形態は王国各地に様々な分派があるが、輪廻転生や本地垂迹の思想が共通点としてみられる。
・シャンバラ(最高神。一切万物の根源)
・ヤシャス(シャンバラの化身。神の豊穣と恵みの現れ)
・ヴァジュラ=ダラ(シャンバラの化身。怒りと力の化身にして、堅固な心を象徴する)
・ミジェラルア(シャンバラに対立する魔界の帝王。常にその座を争っているが、日輪の光に追われて闇夜の地下世界に追放された)
・コルネラム(宝石の神。エメラルドのように光り輝く体を持つ)
・ヤシャス(シャンバラの化身。神の豊穣と恵みの現れ)
・ヴァジュラ=ダラ(シャンバラの化身。怒りと力の化身にして、堅固な心を象徴する)
・ミジェラルア(シャンバラに対立する魔界の帝王。常にその座を争っているが、日輪の光に追われて闇夜の地下世界に追放された)
・コルネラム(宝石の神。エメラルドのように光り輝く体を持つ)
ゲルク王国の経済は貨幣経済と物々交換経済が混淆しており、概して中世から近世初期の段階から脱却できていない。
取引は街や街道沿いに設置される市場で行われ、貨幣や物々交換で取引が為される。扱われるのは日用品が主だが、貴族層が暮らす都市部では高級な嗜好品も多く出回る。
特に高価な品物は国内での生産が難しい調度品や茶、白檀などの飲料・香木であり、宗教儀式に用いる目的で主に王府や貴族の多くが大量に購入する。(これらの品物は峠を越えた商人から交易によって仕入れられている)
また、塩は内陸国の為非常に貴重品扱いされており、国内の岩塩鉱山は全て王府直営で厳格に管理され、専売性が敷かれている。
物々交換の場合、主に使用されるのは布の様な持ち運びしやすい財産であり、これらと交換で食料や塩などの必需品を手に入れている。
産業は農林業・鉱業・手工業・酪農などがあるが、中でも鉱業と酪農は非常に大規模に行われている。
取引は街や街道沿いに設置される市場で行われ、貨幣や物々交換で取引が為される。扱われるのは日用品が主だが、貴族層が暮らす都市部では高級な嗜好品も多く出回る。
特に高価な品物は国内での生産が難しい調度品や茶、白檀などの飲料・香木であり、宗教儀式に用いる目的で主に王府や貴族の多くが大量に購入する。(これらの品物は峠を越えた商人から交易によって仕入れられている)
また、塩は内陸国の為非常に貴重品扱いされており、国内の岩塩鉱山は全て王府直営で厳格に管理され、専売性が敷かれている。
物々交換の場合、主に使用されるのは布の様な持ち運びしやすい財産であり、これらと交換で食料や塩などの必需品を手に入れている。
産業は農林業・鉱業・手工業・酪農などがあるが、中でも鉱業と酪農は非常に大規模に行われている。
通貨は金貨・銀貨・銅貨の3種類。金貨・銀貨は共に古代から現在まで秤量貨幣として流通し、「馬蹄」や「鞍型」の形で流通した。これは王国に品位を統一した貨幣を発行する技術が長く存在しなかったこともあるが、貨幣経済がそもそも国内に浸透せず、貴族間の贈答・外国との貿易が主だった使い道であったことに原因がある。(なお、これらの金貨や銀貨は一定の質量で纏められ、包金などの形で流通することも多く、計数貨幣的な側面も持っていた)
民間では銅で作られた銭貨、そして現物(布貨など)が主に流通していた。
銭貨はゲルク王国の中華名である「雨雪国」を取って「雨雪通宝」と銘が打たれ、都市部の日常取引に広く使われた。これらは時期に応じて異なるが、概ね交換比率が定められており、トゥルバイフ王が定めた勅令では「金1両:銀15両:銭1,000文」と規定されていた。(但しこれらは緩やかに変動したほか、現物通貨の相場にも影響を受けた)
民間では銅で作られた銭貨、そして現物(布貨など)が主に流通していた。
銭貨はゲルク王国の中華名である「雨雪国」を取って「雨雪通宝」と銘が打たれ、都市部の日常取引に広く使われた。これらは時期に応じて異なるが、概ね交換比率が定められており、トゥルバイフ王が定めた勅令では「金1両:銀15両:銭1,000文」と規定されていた。(但しこれらは緩やかに変動したほか、現物通貨の相場にも影響を受けた)
伝承にもある様に、ゲルク王国は非常に鉱物資源に恵まれた土地である。国土の内部には豊富な金山と銀山、及びエメラルド、ルビーの鉱山を有しており、これらから産出する鉱物は長く王国の財政を潤してきた。
金山の規模は世界随一であり、数千トンの埋蔵量が存在すると考えられている。また、銀山銅山と合わせて王国の貨幣鋳造の基盤として管理されており、古くから良質な貨幣鋳造を支えていた。
エメラルドやルビーについては、王城の玉座にあしらわれた世界最大級のエメラルドである「聖者の眼」、王笏に嵌め込まれた巨大ルビーである「王者の瞳」などの良質なものが大量に産出しており、現地の王権の象徴として珍重されている。
金山の規模は世界随一であり、数千トンの埋蔵量が存在すると考えられている。また、銀山銅山と合わせて王国の貨幣鋳造の基盤として管理されており、古くから良質な貨幣鋳造を支えていた。
エメラルドやルビーについては、王城の玉座にあしらわれた世界最大級のエメラルドである「聖者の眼」、王笏に嵌め込まれた巨大ルビーである「王者の瞳」などの良質なものが大量に産出しており、現地の王権の象徴として珍重されている。
ゲルク王国の軍事・国防は主に3つの軍が担当し、彼らはその数から俗に「鳳凰17万騎」と渾名される。
3つの軍はそれぞれ国内の各地に駐屯地を構え、各地のゾンを司令部として、駐留アルドノア帝国軍と連携して国防体制を構築している。
各軍の構成は以下の通り
3つの軍はそれぞれ国内の各地に駐屯地を構え、各地のゾンを司令部として、駐留アルドノア帝国軍と連携して国防体制を構築している。
各軍の構成は以下の通り
八大営は王国軍の主力部隊であり、凡そ10万人の戦力を有する。近代編成では師団に相当し、各ゾンで編成された4,000人のジャラン(連隊とも)3個を以って1個大営を構成する。1つの大営が3つのゾンを管轄し、事実上の軍管区としている。
が、その大部分は形骸化、陳腐化によって戦闘能力を失っており、国防面では後述の六禁衛・鸞旗軍が中核を担っている。
が、その大部分は形骸化、陳腐化によって戦闘能力を失っており、国防面では後述の六禁衛・鸞旗軍が中核を担っている。
・江都義興営(パルパド)
・百塔龍驤営(パロ)
・鳳央虎賁営(トンサ)
・聖城神武営(チュカ)
・函谷忠佐営(カンチー)
・虎牢雄武営(ゾベル)
・西岳龍騎営(ジェムガン)
・東岳虎翼営(サルパン)
・百塔龍驤営(パロ)
・鳳央虎賁営(トンサ)
・聖城神武営(チュカ)
・函谷忠佐営(カンチー)
・虎牢雄武営(ゾベル)
・西岳龍騎営(ジェムガン)
・東岳虎翼営(サルパン)
定数1万8,000人。江都将軍の指揮下でパルパドに駐留する首都防衛部隊。
歩兵を司る前後左右の神歩衛と、精鋭騎兵部隊である三千衛、砲兵部隊である神機衛の6つからなる。
前述の八大営が形骸化してからは、現状ほぼ唯一の常備軍部隊となっている。
六禁衛は主にパルパド周辺の駐屯地に衛戍し、都城防衛の最前線となる陣地群を維持する他、市内の治安維持を担当する捕盗庁の支援を行っている。
歩兵を司る前後左右の神歩衛と、精鋭騎兵部隊である三千衛、砲兵部隊である神機衛の6つからなる。
前述の八大営が形骸化してからは、現状ほぼ唯一の常備軍部隊となっている。
六禁衛は主にパルパド周辺の駐屯地に衛戍し、都城防衛の最前線となる陣地群を維持する他、市内の治安維持を担当する捕盗庁の支援を行っている。
約5万3,000人。シンチュラ家が保有する国家公認の私兵であり、事実上の正規軍として国防の中核を担う。
ゲルクでは数少ない重騎兵隊を主力に擁し、凄まじい勇猛果敢さで国内外から大いに恐れられた。
八大営が主に徴兵された兵士で構成されているのに対し、ドルギェルは没落貴族やその子弟、士族達で構成された純然たる戦闘身分であり、その強さは信仰と愛国心、そして何よりも強いシンチュラ家への忠誠心で支えられている。
各部隊を統括する総本営はシンチュラ家の本領、パロ城に置かれており、その他各地に駐屯地を保持している。現在の主な任務は地方の治安維持だが、叛乱や暴動などが発生した際は、機動力を活かして迅速に鎮圧に向かう。(開国後各地で発生した暴動などは、悉く彼らによって鎮定された)
ゲルクでは数少ない重騎兵隊を主力に擁し、凄まじい勇猛果敢さで国内外から大いに恐れられた。
八大営が主に徴兵された兵士で構成されているのに対し、ドルギェルは没落貴族やその子弟、士族達で構成された純然たる戦闘身分であり、その強さは信仰と愛国心、そして何よりも強いシンチュラ家への忠誠心で支えられている。
各部隊を統括する総本営はシンチュラ家の本領、パロ城に置かれており、その他各地に駐屯地を保持している。現在の主な任務は地方の治安維持だが、叛乱や暴動などが発生した際は、機動力を活かして迅速に鎮圧に向かう。(開国後各地で発生した暴動などは、悉く彼らによって鎮定された)
タグ









コメントをかく