最終更新:
 barexam12346hacks 2010年08月12日(木) 16:17:37履歴
barexam12346hacks 2010年08月12日(木) 16:17:37履歴
<前提> 刑事実務基礎科目の共通的到達目標策定の目的
<共通的到達目標−各論−> 第1章 手続追行能力に関する共通的到達目標
1−1 捜査手続
○任意捜査の意義・要件及びその限界を理解し、具体例に即して、任意捜査の要否及び可否を選択し、その選択の理由を説明することができる。
○被疑者及び参考人の取調べについて、手続とその限界及び留意すべき点を説明することができる(被疑者の身柄拘束手続については下記1−3)。
○捜索・差押え、鑑定、検証等の意義・要件を理解し、具体例に即して、強制捜査の要否及び可否を選択し、その選択の理由を説明することができる。
1−2 起訴前弁護
○弁護方針の立案・決定のため、被疑者及び関係者から聴取するなど調査を必要とする重要な事項を、具体例に即して説明することができる。
○被疑者との接見交通権の意義と重要性を理解し、具体例に即して、接見指定の要件の充足の有無を踏まえ、接見交通が制限された場合の対応方法について説明することができる。
1−3 被疑者(被告人)の身柄拘束手続
○被疑者(被告人)の身柄拘束(逮捕、勾留、接見禁止等)手続について、具体例に即して、それぞれの立場からの法的対応を検討し、検討内容を説明することができる。
○身柄拘束中の被疑者(被告人)の身柄拘束からの解放手続(準抗告、抗告、勾留取消請求、保釈等)を、具体例に即して検討し、検討内容を説明することができる。
1−4 公訴提起・追行及び審判対象を巡る問題
○起訴又は不起訴の判断のために重要な事項を、具体例に即して説明することができる。
○公訴の維持・追行及び防禦・弾劾のため、訴訟当事者の立場から、具体例に即して、証拠に基づき構成すべき主張を検討し、説明することができる。
○訴訟における訴因の役割・意義を理解し、具体例に即して、訴因の特定と公訴事実の記載に必要な事項について説明することができる。
○訴因に対する求釈明の役割・意義を理解し、具体例に即して、訴因に対する求釈明の要否及び可否を選択し、その選択の理由を説明することができる。
○公訴事実の同一性の意義・機能を理解し、具体例に即して、訴因変更の要否及び可否、訴因変更命令の要否及び可否を選択し、その選択の理由を説明することができる。
1−5 公判前整理手続
○通常の刑事訴訟手続と裁判員裁判制度による手続及び公判前整理手続に付された事件の手続の相違を説明することができる。
○公判前整理手続が、被告人の防御権に配慮しながら効率的で迅速な証拠調べを実現するための事前準備手続であることの立法趣旨を説明することができる。
○争点を明示し、争点及び証拠を整理することの意義・目的の重要性を理解し、具体例に即して説明することができる。
○公判前整理手続において行われる各種手続(証明予定事実記載書面の提出・送付、証拠開示、証拠請求等)を理解し、具体例に即して、それぞれの立場からの法的対応を検討し、検討内容を説明することができる。
1−6 公判審理及び証拠・証拠調べ手続
○冒頭手続の役割・意義を説明することができる。
○証拠調べ手続に関して、冒頭陳述の意義を説明することができる。
○証拠の類型に応じて証拠能力が与えられる要件を理解し、具体例に即して、その証拠の取調べのために必要な訴訟活動(立証趣旨の説明、証拠意見のあり方、証拠採否の判断等)、証拠の取調べ方法を説明することができる。
○証人尋問における罪体(直接事実、間接事実)立証、信用性の補強・弾劾、書証の証拠能力獲得といった具体的目的に照らし、具体例に即して、尋問すべき事項について説明することができる。
○交互尋問のルールを定めた法令の根拠を理解し、具体例に即して、交互尋問のルールに基づいた尋問方法及び異議申立について、説明することができる。
○被害者に対する配慮及び被害者参加等の証人尋問におけるその他の配慮につい て、被告人の権利保障との関係を踏まえて説明することができる。
○刑事司法における証拠裁判主義及び主要事実の挙証責任が検察官にあること(「疑わしいときは被告人の利益に」)の意義を説明することができる。
○事実認定に関する基本的概念(要証事実と間接事実、直接証拠と間接証拠、証拠の信用性と証拠の証明力、実質証拠と補助証拠等)を理解したうえ、証拠から事実を推認する過程を具体例に即して説明することができる。
○事実認定における証拠の構造(事実認定の骨組み)の重要性を理解し、具体例に即して、その内容を説明することができる。
刑事実務基礎科目は、モデル教材で示される典型的な事例における実務的対応を念頭において、裁判官、検察官、弁護人の視点をも盛り込んだ教育をすることを通じて、法理論が具体的な事案における法的な問題解決の場面でどのような意義を持ちどのように機能するのかを理解させ、法律基本科目で修得する法的な理解力や思考力を深め、実務の基礎的な素養を身につけさせることを目的とする。
<共通的到達目標−各論−> 第1章 手続追行能力に関する共通的到達目標
1−1 捜査手続
○任意捜査の意義・要件及びその限界を理解し、具体例に即して、任意捜査の要否及び可否を選択し、その選択の理由を説明することができる。
○被疑者及び参考人の取調べについて、手続とその限界及び留意すべき点を説明することができる(被疑者の身柄拘束手続については下記1−3)。
○捜索・差押え、鑑定、検証等の意義・要件を理解し、具体例に即して、強制捜査の要否及び可否を選択し、その選択の理由を説明することができる。
1−2 起訴前弁護
○弁護方針の立案・決定のため、被疑者及び関係者から聴取するなど調査を必要とする重要な事項を、具体例に即して説明することができる。
○被疑者との接見交通権の意義と重要性を理解し、具体例に即して、接見指定の要件の充足の有無を踏まえ、接見交通が制限された場合の対応方法について説明することができる。
1−3 被疑者(被告人)の身柄拘束手続
○被疑者(被告人)の身柄拘束(逮捕、勾留、接見禁止等)手続について、具体例に即して、それぞれの立場からの法的対応を検討し、検討内容を説明することができる。
○身柄拘束中の被疑者(被告人)の身柄拘束からの解放手続(準抗告、抗告、勾留取消請求、保釈等)を、具体例に即して検討し、検討内容を説明することができる。
1−4 公訴提起・追行及び審判対象を巡る問題
○起訴又は不起訴の判断のために重要な事項を、具体例に即して説明することができる。
○公訴の維持・追行及び防禦・弾劾のため、訴訟当事者の立場から、具体例に即して、証拠に基づき構成すべき主張を検討し、説明することができる。
○訴訟における訴因の役割・意義を理解し、具体例に即して、訴因の特定と公訴事実の記載に必要な事項について説明することができる。
○訴因に対する求釈明の役割・意義を理解し、具体例に即して、訴因に対する求釈明の要否及び可否を選択し、その選択の理由を説明することができる。
○公訴事実の同一性の意義・機能を理解し、具体例に即して、訴因変更の要否及び可否、訴因変更命令の要否及び可否を選択し、その選択の理由を説明することができる。
1−5 公判前整理手続
○通常の刑事訴訟手続と裁判員裁判制度による手続及び公判前整理手続に付された事件の手続の相違を説明することができる。
○公判前整理手続が、被告人の防御権に配慮しながら効率的で迅速な証拠調べを実現するための事前準備手続であることの立法趣旨を説明することができる。
○争点を明示し、争点及び証拠を整理することの意義・目的の重要性を理解し、具体例に即して説明することができる。
○公判前整理手続において行われる各種手続(証明予定事実記載書面の提出・送付、証拠開示、証拠請求等)を理解し、具体例に即して、それぞれの立場からの法的対応を検討し、検討内容を説明することができる。
1−6 公判審理及び証拠・証拠調べ手続
○冒頭手続の役割・意義を説明することができる。
○証拠調べ手続に関して、冒頭陳述の意義を説明することができる。
○証拠の類型に応じて証拠能力が与えられる要件を理解し、具体例に即して、その証拠の取調べのために必要な訴訟活動(立証趣旨の説明、証拠意見のあり方、証拠採否の判断等)、証拠の取調べ方法を説明することができる。
○証人尋問における罪体(直接事実、間接事実)立証、信用性の補強・弾劾、書証の証拠能力獲得といった具体的目的に照らし、具体例に即して、尋問すべき事項について説明することができる。
○交互尋問のルールを定めた法令の根拠を理解し、具体例に即して、交互尋問のルールに基づいた尋問方法及び異議申立について、説明することができる。
○被害者に対する配慮及び被害者参加等の証人尋問におけるその他の配慮につい て、被告人の権利保障との関係を踏まえて説明することができる。
第2章 実体形成能力に関する共通的到達目標
○刑事司法における証拠裁判主義及び主要事実の挙証責任が検察官にあること(「疑わしいときは被告人の利益に」)の意義を説明することができる。
○事実認定に関する基本的概念(要証事実と間接事実、直接証拠と間接証拠、証拠の信用性と証拠の証明力、実質証拠と補助証拠等)を理解したうえ、証拠から事実を推認する過程を具体例に即して説明することができる。
○事実認定における証拠の構造(事実認定の骨組み)の重要性を理解し、具体例に即して、その内容を説明することができる。

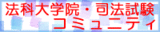
コメントをかく