最終更新:
 barexam12346hacks 2012年04月28日(土) 16:28:32履歴
barexam12346hacks 2012年04月28日(土) 16:28:32履歴
- 過去問は繰り返される。理由まですべていえるように。
- 短答の勉強は,正答率の高い問題を落とさないようにすること(他の受験生との客観的な差をうめること)が目的
- 「過去問を解く→解説を読んで復習→答練」という勉強方法のうち「解説を読んで復習」という部分が,受験生は省きがち。注意する。
- 旧司法試験ほど,択一に力を入れる必要は無い。論文に時間を割いた方がよい。
- 暗記すべきものは,「条文」「過去問(何度も同じものが出題される)」「判例(『重要判例』の最新刊から出題される)」
- 「暗記すべき一冊の本」で勉強するのが効果の高い択一勉強法となる
- 手続関連は条文そのまま聞いてくる。
- 二当事者,裁判所の調整を考える。
- 判例は,問題点と結論をおさえる。詳細までは不要。
- 似ている手続は対比して覚える。狙われる。
- 複雑訴訟は具体例を想定。実は難しくない。
- 要件事実は最低限覚える。
百選は完璧に。事案の概要,問題点,規範,あてはめ,結論まで。丸暗記は難しいので,大まかな規範,あてはめ,判例の射程を。
新しい制度(被害者参加,公判前整理手続)はおさえる。
聞かれやすいところは決まっている(「手続の主体」「裁判所・捜査側のできる手続の対比」「伝聞法則」etc.)ので表にするなどして理解を深める。
新しい制度(被害者参加,公判前整理手続)はおさえる。
聞かれやすいところは決まっている(「手続の主体」「裁判所・捜査側のできる手続の対比」「伝聞法則」etc.)ので表にするなどして理解を深める。
条文は具体的な事例を想定しながら。
それぞれの訴えの要件,長所,短所,具体例等をおさえる。
百選の事案の概要,問題点,理由,結論をおさえる。判例の射程距離を考えながら結論を理解する。
引っかかりやすい条文は「表」化して対比するなど工夫を。
各訴訟類型の違い
新しくできた制度は特に重要(H18改正)
準用条文は,出題側がだしやすい。
それぞれの訴えの要件,長所,短所,具体例等をおさえる。
百選の事案の概要,問題点,理由,結論をおさえる。判例の射程距離を考えながら結論を理解する。
引っかかりやすい条文は「表」化して対比するなど工夫を。
各訴訟類型の違い
新しくできた制度は特に重要(H18改正)
準用条文は,出題側がだしやすい。

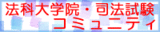
コメントをかく