最終更新:
 barexam12346hacks 2010年08月20日(金) 17:18:58履歴
barexam12346hacks 2010年08月20日(金) 17:18:58履歴
総則
物権
担保物権
債権総論
債権各論
物権
担保物権
債権総論
債権各論
相手方において能力者であると誤信し誤信を強めているとも思える状況があるから,単なる黙秘といえども詐術をした者として取消が制限されるのではないか,詐術(21条)の意味が問題となる。
思うに,取消権が制限されるのは,保護に値しないだけでなく,禁反言にも触れるからである。
とすれば,単に制限行為能力者であることを黙秘しているのみでは「詐術」があるとはいえない。
しかし,積極的に詐欺の手段を用いた場合に限定するならば,相手方の保護に十分でない。
そこで,黙秘も一定の場合には「詐術」にあたる。
具体的には,黙秘が行動と相まって能力者でありと相手方に誤信させ,もしくは能力者であるとの誤信を強めるという事情が認められるときには黙秘も詐術にあたると解すべきである。
(short ver.)
21条は,取引安全の要請から例外的に制限行為能力の取消権を制限した規定である。
したがって,同条の「詐術」とは,限定的に解すべきであって,単に制限行為能力者であることを黙秘していただけでは足りず,他の言動と相まって相手方を誤信させ,または誤信を強めた場合をいう。
思うに,取消権が制限されるのは,保護に値しないだけでなく,禁反言にも触れるからである。
とすれば,単に制限行為能力者であることを黙秘しているのみでは「詐術」があるとはいえない。
しかし,積極的に詐欺の手段を用いた場合に限定するならば,相手方の保護に十分でない。
そこで,黙秘も一定の場合には「詐術」にあたる。
具体的には,黙秘が行動と相まって能力者でありと相手方に誤信させ,もしくは能力者であるとの誤信を強めるという事情が認められるときには黙秘も詐術にあたると解すべきである。
(short ver.)
21条は,取引安全の要請から例外的に制限行為能力の取消権を制限した規定である。
したがって,同条の「詐術」とは,限定的に解すべきであって,単に制限行為能力者であることを黙秘していただけでは足りず,他の言動と相まって相手方を誤信させ,または誤信を強めた場合をいう。
権力能力なき社団は法人としての実体を有していることからできる限り法人に準じた取扱いをすべきである。
そこで,権力能力なき社団に帰属する債務は団体の構成員に総有的に帰属するとともに,団体の総有財産だけがその責任財産となり,構成員各自は取引の相手方に対し直接には個人的債務ないし責任を負わないと解すべきである。
そこで,権力能力なき社団に帰属する債務は団体の構成員に総有的に帰属するとともに,団体の総有財産だけがその責任財産となり,構成員各自は取引の相手方に対し直接には個人的債務ないし責任を負わないと解すべきである。
そもそも,代表権の公証の方法がなく,登記官にも審査権限が無いのに団体名義の登記を認めると,団体名を利用した虚無人名義の登記が発生するおそれがある。
よって団体名による登記は許されない。
よって団体名による登記は許されない。
違法な目的は動機の部分にあるにすぎないので,民法90条を直接適用することはできないが,当該行為によって違法な結果が生ずることを考えると,行為全体が反社会性を帯びるものといえる。
他方,違法な動機は相手方には認識不可能な場合もあり,常に無効とすると取引の安全を害する。
そこで,動機の違法性の程度と相手方の関与ないし認識の程度を総合考慮して当該行為の有効性を判断すべきである。
他方,違法な動機は相手方には認識不可能な場合もあり,常に無効とすると取引の安全を害する。
そこで,動機の違法性の程度と相手方の関与ないし認識の程度を総合考慮して当該行為の有効性を判断すべきである。
94条2項は,権利者が自らの意思で虚偽の外観を作出した場合,その意思表示の外径を信じて取引関係に入った第三者を保護することで取引の安全を図った規定である。
したがって,同項の「第三者」とは虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者であって,虚偽表示の外形にもとづいて新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいう。
したがって,同項の「第三者」とは虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者であって,虚偽表示の外形にもとづいて新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいう。
無過失まで要求する趣旨か,条文上明らかでなく問題となる。
この点,明文にない要件を付加することは第三者の保護に欠ける。また,虚偽表示をした者の帰責性は強く,過失ある者でも保護に値する。
よって,第三者の保護要件として無過失は要求されないと考える。
この点,明文にない要件を付加することは第三者の保護に欠ける。また,虚偽表示をした者の帰責性は強く,過失ある者でも保護に値する。
よって,第三者の保護要件として無過失は要求されないと考える。
94条2項の第三者として保護されるためには,登記など対抗要件の具備は必要か,条文上明らかでなく問題となる。
思うに,94条2項は,虚偽表示による法律行為も第三者との関係では,有効なものとみるものである。
とするならば,第三者はしょうけい取得によって目的物を取得した者ということができ,対抗関係とならない。
よって,保護要件として登記の具備はは要求されないと考える。
思うに,94条2項は,虚偽表示による法律行為も第三者との関係では,有効なものとみるものである。
とするならば,第三者はしょうけい取得によって目的物を取得した者ということができ,対抗関係とならない。
よって,保護要件として登記の具備はは要求されないと考える。
この点,文言上許容し得る。
かつ,転得者も前主が権利者と信頼することはありうる。
となると,転得者を無権利者と直接取引した者と区別して扱う理由はない,
よって,「第三者」には転得者も含まれると考えるべきである。
かつ,転得者も前主が権利者と信頼することはありうる。
となると,転得者を無権利者と直接取引した者と区別して扱う理由はない,
よって,「第三者」には転得者も含まれると考えるべきである。
この点,悪意者を保護する必要は無いからといって,無効主張の復活を認めることは法律関係の早期安定の要請に反する。
また,無効主張により善意者が悪意者から追奪担保責任を問われるおそれがある。
よって,転得者は善意者たる地位を承継した者とみて,善意者が現れた以降は,悪意者の存在に関わらず,無効主張は制限されると考える。
ただし,悪意者が善意者を介在させ脱法的な権利取得を図るおそれがあるような事情が認められる場合には,例外的に無効主張が認められると考える。
また,無効主張により善意者が悪意者から追奪担保責任を問われるおそれがある。
よって,転得者は善意者たる地位を承継した者とみて,善意者が現れた以降は,悪意者の存在に関わらず,無効主張は制限されると考える。
ただし,悪意者が善意者を介在させ脱法的な権利取得を図るおそれがあるような事情が認められる場合には,例外的に無効主張が認められると考える。
当事者間に「通謀」がない以上,94条2項を直接適用することはできない。
もっとも,権利者たる外観を信頼した第三者を保護し,取引の安全を図る必要がある。
そもそも,94条2項の趣旨は,権利外観法理に求められるところ,かかる趣旨からすれば,当事者間に通謀がなくとも,1)虚偽の外観が存在し,2)虚偽の外観作出について真の権利者に帰責性があり,3)第三者がその外観を信頼した場合にはその第三者は保護に値する。
そして,第三者の信じた外観が真の権利者の意思に基づいている場合には,真の権利者の帰責事由の大きさを考慮し,3)の第三者の信頼は,善意であれば足り,無過失を要しないと解する。
もっとも,権利者たる外観を信頼した第三者を保護し,取引の安全を図る必要がある。
そもそも,94条2項の趣旨は,権利外観法理に求められるところ,かかる趣旨からすれば,当事者間に通謀がなくとも,1)虚偽の外観が存在し,2)虚偽の外観作出について真の権利者に帰責性があり,3)第三者がその外観を信頼した場合にはその第三者は保護に値する。
そして,第三者の信じた外観が真の権利者の意思に基づいている場合には,真の権利者の帰責事由の大きさを考慮し,3)の第三者の信頼は,善意であれば足り,無過失を要しないと解する。
動機の錯誤は「錯誤」(95条)にあたり,無効とならないか。
錯誤とは,効果意思と表示に不一致がある場合をいうから,意思の形成過程にすぎない動機の錯誤は95条の「錯誤」に含まれず,錯誤無効を主張できないのが原則である。
もっとも,表意者の保護という95条の趣旨は動機の錯誤にもあてはまる。取引の安全の要請も図る必要がある。
そこで,動機も明示または黙示に表示された場合には法律行為の内容となりうるから,「要素」に関するものである限り,動機の錯誤も錯誤無効の主張ができると解する。
錯誤とは,効果意思と表示に不一致がある場合をいうから,意思の形成過程にすぎない動機の錯誤は95条の「錯誤」に含まれず,錯誤無効を主張できないのが原則である。
もっとも,表意者の保護という95条の趣旨は動機の錯誤にもあてはまる。取引の安全の要請も図る必要がある。
そこで,動機も明示または黙示に表示された場合には法律行為の内容となりうるから,「要素」に関するものである限り,動機の錯誤も錯誤無効の主張ができると解する。
無効は本来誰でも主張できるものであるが,表意者保護という95条の趣旨から錯誤無効に関しては表意者のみが主張しうると解する。
もっとも,表意者が錯誤を認めている場合には第三者に無効を主張させたとしても表意者の意思に反しない。
そこで,表意者が意思表示の瑕疵を認めている場合には表意者自らが当該意思表示の無効を主張する意思がなくても,第三者は表意者に対する債権を保全するため錯誤無効を主張できる。
もっとも,表意者が錯誤を認めている場合には第三者に無効を主張させたとしても表意者の意思に反しない。
そこで,表意者が意思表示の瑕疵を認めている場合には表意者自らが当該意思表示の無効を主張する意思がなくても,第三者は表意者に対する債権を保全するため錯誤無効を主張できる。
錯誤が相手方の詐欺によって引き起こされた場合でも,表意者は「重過失」(95条但書)ある者として無効主張を制限されるか。
思うに,95条但書により無効主張が制限されるのは,意思表示の相手方を保護し,取引の安全を図るためである。
しかし,錯誤の存在について悪意ある者を保護する必要はない。
よって,相手方が表意者の錯誤について悪意であるなら,錯誤についても重過失ある表意者も無効主張は制限されないと考える。
そして,詐欺者は表意者が錯誤に陥っていることについて,当然に悪意であるといえる,
よって表意者は無効の主張を制限されないことになる。
思うに,95条但書により無効主張が制限されるのは,意思表示の相手方を保護し,取引の安全を図るためである。
しかし,錯誤の存在について悪意ある者を保護する必要はない。
よって,相手方が表意者の錯誤について悪意であるなら,錯誤についても重過失ある表意者も無効主張は制限されないと考える。
そして,詐欺者は表意者が錯誤に陥っていることについて,当然に悪意であるといえる,
よって表意者は無効の主張を制限されないことになる。
無効な行為を取消しの対象とすることはできるか。
この点,無効な行為を取り消すことはできないとも思える。
しかし,無効・取消は自然的存在ではなく,法律行為の効力を否定するための法的な理論構成の手段に過ぎない。
とすると,無効な行為の取消も論理的には可能である。また,無効な意思表示をした表意者には取消を認めた方がその保護に値する。
よって表意者には無効と取消しの選択的主張を認めるべきである。
この点,無効な行為を取り消すことはできないとも思える。
しかし,無効・取消は自然的存在ではなく,法律行為の効力を否定するための法的な理論構成の手段に過ぎない。
とすると,無効な行為の取消も論理的には可能である。また,無効な意思表示をした表意者には取消を認めた方がその保護に値する。
よって表意者には無効と取消しの選択的主張を認めるべきである。
そもそも96条3項の趣旨は詐欺により取り消された意思表示を有効なものとして信じて取引関係に入った者を保護して取引の安全を図る点にある。
かかる趣旨からすれば,「第三者」とは取消しによる遡及的無効によって権利を侵害される者,すなわち取消し前に意思表示に関し新たな独立した法律上の利害関係を有するに行った者をいうと解すべきである。
かかる趣旨からすれば,「第三者」とは取消しによる遡及的無効によって権利を侵害される者,すなわち取消し前に意思表示に関し新たな独立した法律上の利害関係を有するに行った者をいうと解すべきである。
相手方と通じて本人を騙している場合には,もはや代理人として行動したものとはいえない。むしろ相手方の意思表示の伝達期間(使者)として行動したというべきであって,代理人と相手方がなした意思表示は本人に対する一種の心裡留保といえる。
したがって,原則として意思表示は93条本文により有効であり,本人が相手方の真意を知り又は知り得べき場合であれば同条但書により無効となる。
したがって,原則として意思表示は93条本文により有効であり,本人が相手方の真意を知り又は知り得べき場合であれば同条但書により無効となる。
101条1項は代理における意思表示の瑕疵の有無は代理人について判断されると規定している。
したがって,代理人を欺罔した場合には,その代理行為は取り消すことができる(96条1項)。
ただし,例外的に本人が詐欺の事実を事前に知っていたにもかかわらず放置していた等の特段の事情がある場合には,101条2項が適用され,本人は代理行為を取り消すことができない。
したがって,代理人を欺罔した場合には,その代理行為は取り消すことができる(96条1項)。
ただし,例外的に本人が詐欺の事実を事前に知っていたにもかかわらず放置していた等の特段の事情がある場合には,101条2項が適用され,本人は代理行為を取り消すことができない。
本人を欺罔しても代理人の意思表示には影響がないため,本人は代理行為を原則として取り消せない(101条1項)。
ただし,相手方の詐欺に基づいて代理人に代理権を付与したり,欺罔された本人の指図によって代理人の意思表示の内容が変更された場合には,本人への詐欺によって代理人の意思表示に影響が生じているので,取消すことができると解する。
ただし,相手方の詐欺に基づいて代理人に代理権を付与したり,欺罔された本人の指図によって代理人の意思表示の内容が変更された場合には,本人への詐欺によって代理人の意思表示に影響が生じているので,取消すことができると解する。
表見代理を定めた民法109条等と無権代理人の責任を定めた民法117条とはその要件・効果も異なる別個の規定である。したがって,取引の相手方は表見代理の主張と無権代理人の責任追及のいずれを選択することも自由であり,無権代理人は表見代理の成立を抗弁として自己の責任を免れることはできない。
本人が追認拒絶をした場合,無権代理行為の効果は本人に効果帰属しないことが確定する。したがって,その後に無権代理人が本人を相続したとしても,すでに確定した効果不帰属についても何ら影響を及ぼすものではないから,無権代理行為は有効とならない。
また,本人がなし,すでに確定している追認拒絶の効果を無権代理人が主張することは,それ自体では信義則に反するものとまではいえない。
また,本人がなし,すでに確定している追認拒絶の効果を無権代理人が主張することは,それ自体では信義則に反するものとまではいえない。
本人が無権代理人の相続をした場合,本人には本人たる地位と無権代理人たる地位が併存することになる。
したがって,本人は当初から有していた本人たる地位に基づき,無権代理行為の追認を拒絶することができる。
したがって,本人は当初から有していた本人たる地位に基づき,無権代理行為の追認を拒絶することができる。
本人が無権代理人を相続した場合,本人は本人たる地位と無権代理人たる地位が併存することになる。
したがって,本人は,相続によって承継した無権代理人たる地位に基づき,117条の責任を負う。ただし,相続という偶然の事情によって本来受けられる以上の保護を相手方に与える必要はないので,117条の責任の内容としては金銭債務の履行を除き,損害賠償に限り,履行請求はなしえないと解する。
したがって,本人は,相続によって承継した無権代理人たる地位に基づき,117条の責任を負う。ただし,相続という偶然の事情によって本来受けられる以上の保護を相手方に与える必要はないので,117条の責任の内容としては金銭債務の履行を除き,損害賠償に限り,履行請求はなしえないと解する。
最初の相続で無権代理人の地位を承継し,後の相続で本人の地位を承継していることから,無権代理人が本人を相続したと同様の法律上の効果を生じ,追認を待たずに法律行為は当然に有効となる。
109条は本人が受験表示行為をなしていたことをもとに表見代理の成立を認める規定であるが,法定代理の場合には本人が授権行為をなすことは考えられない。
したがって,109条は法定代理には適用されない。
したがって,109条は法定代理には適用されない。
110条は,取引の安全を保護するための規定であるから,かかる規定の成立要件たる基本代理権とは原則として司法上の代理権であると解する。とすると,単なる公法上の行為についての代理権は基本代理権に当たらないのが原則である。
もっとも,例えば登記申請行為が私法上の契約による債務一環としてなされるように,公法上の行為が特定の私法上の取引行為の一環としてなされる場合には,取引の安全を図る必要がある。
したがって,かかる場合には公法上の行為についての代理権も基本代理権にあたる。
もっとも,例えば登記申請行為が私法上の契約による債務一環としてなされるように,公法上の行為が特定の私法上の取引行為の一環としてなされる場合には,取引の安全を図る必要がある。
したがって,かかる場合には公法上の行為についての代理権も基本代理権にあたる。
民法110条は,代理人の代理権限を信頼した者を保護する規定である。
他方,転得者は前主の権利を信頼して取引関係に入ることはあっても,無権代理行為の当事者ではない以上,代理人の代理権限を信頼して取引関係に入るということは通常考えられない。
したがって,110条の第三者とは,直接の相手方に限られ,転得者は含まれないと解する。
他方,転得者は前主の権利を信頼して取引関係に入ることはあっても,無権代理行為の当事者ではない以上,代理人の代理権限を信頼して取引関係に入るということは通常考えられない。
したがって,110条の第三者とは,直接の相手方に限られ,転得者は含まれないと解する。
民法110条は,代理人の権限逸脱の場合に,代理人の代理権限に対する信頼を保護する規定であるところ,代理人が直接本人名義で行為をした場合には相手方が代理権限を行使することはないので,この場合に110条を直接適用することはできない。
もっとも,代理人であると信じた場合と本人であると信じた者が実は代理人であった場合とで相手方の保護の必要性は異ならないし,越権行為である点について両者は共通している。
そこで,代理人が直接本に名義で越権行為をした場合には110条類推適用して相手方を保護すべきである。
もっとも,代理人であると信じた場合と本人であると信じた者が実は代理人であった場合とで相手方の保護の必要性は異ならないし,越権行為である点について両者は共通している。
そこで,代理人が直接本に名義で越権行為をした場合には110条類推適用して相手方を保護すべきである。
共同生活体である夫婦の一方と取引関係に立った第三者の保護を図るため,761条は夫婦の一方が日常生活についてなした法律行為につき,夫婦の他方もそれによって生じた債務について連帯責任を負う旨規定している。
かかる連帯責任を負わせる前提として,同条は夫婦相互間の日常の家事に関する法律行為につき法定の代理権を定めており,ここでいう日常家事行為とは,個々の夫婦がそれぞれ共同生活を営むうえで通常必要おな法律行為を指すものと解される。そして,同条の第三者が保護を図った規定であることから,その判断にあたっては,夫婦間の内部事情や行為の個別的な目的のみを重視するのではなく,客観的にその法律行為の種類や性質等をも考慮して判断すべきである。
かかる連帯責任を負わせる前提として,同条は夫婦相互間の日常の家事に関する法律行為につき法定の代理権を定めており,ここでいう日常家事行為とは,個々の夫婦がそれぞれ共同生活を営むうえで通常必要おな法律行為を指すものと解される。そして,同条の第三者が保護を図った規定であることから,その判断にあたっては,夫婦間の内部事情や行為の個別的な目的のみを重視するのではなく,客観的にその法律行為の種類や性質等をも考慮して判断すべきである。
761条は夫婦相互間の日常の家事に関する法律行為につき法定代理権を定めているが,かかる代理権を基本代理権として110条の直接適用を認めてしまうと,夫婦の財産的独立性を規定した762条の趣旨を没却して妥当でない。
他方,客観的な事情も交えて判断するとはいえ日常家事の範囲は必ずしも明確ではないから,当該行為が日常家事の範囲に含まれると過失なく信じた第三者を保護する必要性もある。
そこで,当該越権行為の相手方である第三者がその行為を夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当の理由あるときに限り,民法110条の趣旨を類推適用して第三者の保護を図るべきである。
他方,客観的な事情も交えて判断するとはいえ日常家事の範囲は必ずしも明確ではないから,当該行為が日常家事の範囲に含まれると過失なく信じた第三者を保護する必要性もある。
そこで,当該越権行為の相手方である第三者がその行為を夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当の理由あるときに限り,民法110条の趣旨を類推適用して第三者の保護を図るべきである。
まず,162条や167条が「取得する」「消滅する」と規定していることから,時効制度は単なる訴訟法上の制度ではなく,実体法上の効果を生じさせるものといえる。
他方,145条が時効の利益を受ける者の意思を尊重していることから,時効が援用されるまでは時効の効果は確定的に発生しないものと解する。
そして,当事者意思の尊重と合理的な説明という観点から,援用しないことを解除条件とするのではなく,援用することを停止条件として時効の効果が発生するものと解すべきである。
他方,145条が時効の利益を受ける者の意思を尊重していることから,時効が援用されるまでは時効の効果は確定的に発生しないものと解する。
そして,当事者意思の尊重と合理的な説明という観点から,援用しないことを解除条件とするのではなく,援用することを停止条件として時効の効果が発生するものと解すべきである。
まず,時効の完成後,時効の完成を知ったうえで債務の承認を行った場合には「放棄」(146条)にあたり,もはや時効を援用することはできない。
他方,時効完成後,時効の完成を知らずに承認を行った場合には,時効の利益を享受しないという積極的な意思表示がなされたとはいえないので,放棄にあたらない。
もっとも,いったん債務を承認した以上,債権者はもはや時効の援用は許されないとの期待を有するのが通常であり,かかる債権者の期待を保護する必要がある。そこで,債務の承認という時効による債務消滅の主張と相容れない行為をした債務者は,時効完成の事実を知らなかったとしても,信義則(1条2項)に照らし,もはや援用は許されないと解する。
他方,時効完成後,時効の完成を知らずに承認を行った場合には,時効の利益を享受しないという積極的な意思表示がなされたとはいえないので,放棄にあたらない。
もっとも,いったん債務を承認した以上,債権者はもはや時効の援用は許されないとの期待を有するのが通常であり,かかる債権者の期待を保護する必要がある。そこで,債務の承認という時効による債務消滅の主張と相容れない行為をした債務者は,時効完成の事実を知らなかったとしても,信義則(1条2項)に照らし,もはや援用は許されないと解する。
162条は,「他人の物」と規定しているので,自己の物を時効取得することはできないようにも思える。
しかし,権利関係の立証の困難を救済するという時効制度の趣旨からは当然に自己物の時効取得を認めるべきである。また,第三者に二重譲渡がなされて登記が移転されてしまった場合のように,自己物であっても時効取得を認める実益はある。
したがって,自己物であっても時効取得することは認められる。
しかし,権利関係の立証の困難を救済するという時効制度の趣旨からは当然に自己物の時効取得を認めるべきである。また,第三者に二重譲渡がなされて登記が移転されてしまった場合のように,自己物であっても時効取得を認める実益はある。
したがって,自己物であっても時効取得することは認められる。
たしかに,永続した事実状態の尊重という時効制度の趣旨は,一般的に債権にはあてはまらない。
しかし,債権の中でも賃借権は,継続的給付を目的とするものであり,かつ占有を不可欠の要素とするものであるから例外的に永続する事実状態を観念しうる。
また,不動産賃借権は物権である地上権と同様の機能を有している。
したがって,「所有権以外の財産権」(163条)には,不動産賃借権も含まれ,時効取得が認められる。
しかし,債権の中でも賃借権は,継続的給付を目的とするものであり,かつ占有を不可欠の要素とするものであるから例外的に永続する事実状態を観念しうる。
また,不動産賃借権は物権である地上権と同様の機能を有している。
したがって,「所有権以外の財産権」(163条)には,不動産賃借権も含まれ,時効取得が認められる。
目的不動産の所有権者の時効中断の機会を確保するために,不動産賃借権時効取得の要件としては,1)目的物の継続手的な用益という外形的事実が存在し,2)それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていること(具体的には賃料を支払い続けていたこと)が必要である。
期限の利益喪失約款付債権は,履行を怠った場合に期限の利益を失うとの約款が付されているだけであって,それぞれの債権には履行期限の定めが設定されている。そして期限のある債務の消滅時効の起算点は履行期から進行するものとされている。
他方,期限のない消滅時効と同旨して時効の起算点を早めることで履行を怠った債務者を保護する必要はないし,不履行とともに当然に債権全額の消滅時効が進行してしまうと,債権者は債権全額の請求を強制されることになって妥当でない。
したがって,債権者が残額全部を請求したときから時効期間は進行すべきである。そして残額全部の請求をしない場合には,それぞれの履行期からそれぞれの債権の消滅時効が進行するものと解する。
他方,期限のない消滅時効と同旨して時効の起算点を早めることで履行を怠った債務者を保護する必要はないし,不履行とともに当然に債権全額の消滅時効が進行してしまうと,債権者は債権全額の請求を強制されることになって妥当でない。
したがって,債権者が残額全部を請求したときから時効期間は進行すべきである。そして残額全部の請求をしない場合には,それぞれの履行期からそれぞれの債権の消滅時効が進行するものと解する。
176条は「当事者の意思表示のみによって,その効力を生ずる」と規定し,意思主義を定めている。したがって,売主の所有に属する特定物を目的とする売買においては,特にその所有権の移転が将来なされるべき約旨に出たものでない限り,買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずる。
177条は登記による画一的処理によって不動産取引の安全を図った規定である。
したがって,177条の「第三者」とは,不動産取引の安全を図る必要がある者,すなわち当事者若しくはその包括承継人以外の者であって,不動産に関する物権の得喪,変更の登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者をいう。
したがって,177条の「第三者」とは,不動産取引の安全を図る必要がある者,すなわち当事者若しくはその包括承継人以外の者であって,不動産に関する物権の得喪,変更の登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者をいう。
177条は自由競争のもとで取引の安全を図った規定である,
そして,単に他の者への売買の事実を知っていたというだけでは自由競争の範囲を逸脱した取引とは言えない。
したがって,悪意であっても「第三者」には含まれる。
もっとも,単なる悪意を超えて,第一譲受人に危害を加える意図で取引関係に入ったような背信的悪意者の場合には,もはや自由競争の範囲を逸脱しており,「第三者」にはあたらない。
そして,単に他の者への売買の事実を知っていたというだけでは自由競争の範囲を逸脱した取引とは言えない。
したがって,悪意であっても「第三者」には含まれる。
もっとも,単なる悪意を超えて,第一譲受人に危害を加える意図で取引関係に入ったような背信的悪意者の場合には,もはや自由競争の範囲を逸脱しており,「第三者」にはあたらない。
そもそも背信的悪意者が「第三者」にあたらないのは,無権利者だからではなく,その者の強い背信性ゆえに登記の欠缺を主張する正当な利益が認められないためである。
そして,権利は移転するが,背信性は一身専属的なものであるから個別に当事者ごとに判断するべきである。
とすれば,背信的悪意者からの転得者は,その転得者自体に著しい背信性がない限り,「第三者」にあたる。
そして,権利は移転するが,背信性は一身専属的なものであるから個別に当事者ごとに判断するべきである。
とすれば,背信的悪意者からの転得者は,その転得者自体に著しい背信性がない限り,「第三者」にあたる。
不動産に関する権利の帰属を登記によって決すれば,画一的な処理が可能となり,もって不動産取引の安全を図ることができる。
他方,取消しの遡及的無効は原状回復のための擬制に過ぎず,一種の復帰的物権変動が生じたとみることも可能である。
そこで,取消後の第三者と取消権者との関係は対抗問題として扱い,登記を先に備えた者が優先すると解すべきである。
他方,取消しの遡及的無効は原状回復のための擬制に過ぎず,一種の復帰的物権変動が生じたとみることも可能である。
そこで,取消後の第三者と取消権者との関係は対抗問題として扱い,登記を先に備えた者が優先すると解すべきである。
時効取得者は,時効完成後に当時の所有者から所有権の移転を受けた者とみることができる。
したがって,時効取得者は,時効完成前に譲り受けた第三者とは当事者類似の関係に立ち,登記なくして権利を主張できる。
これに対して,時効完成後に譲り受けた第三者との関係では,時効取得時の登記名義人を起点とした二重譲渡と同視されるので,時効取得者は登記なくして第三者に対抗できる。
したがって,時効取得者は,時効完成前に譲り受けた第三者とは当事者類似の関係に立ち,登記なくして権利を主張できる。
これに対して,時効完成後に譲り受けた第三者との関係では,時効取得時の登記名義人を起点とした二重譲渡と同視されるので,時効取得者は登記なくして第三者に対抗できる。
共同相続人は自らの相続分についてのみ権利を有しており,他者の相続分については何ら権利を有しない。
したがって,共同相続人の一部が自らの相続分を超えて第三者の相続財産たる不動産を処分したとしても,他の共同相続人は,自己の相続分につき,登記なくして第三者に対抗できる。
したがって,共同相続人の一部が自らの相続分を超えて第三者の相続財産たる不動産を処分したとしても,他の共同相続人は,自己の相続分につき,登記なくして第三者に対抗できる。
遺産分割の遡及効により害される者を保護するという909条但書の趣旨より,同規定によって保護される「第三者」とは,相続開始後遺産分割前に生じた第三者をいい,遺産分割後に生じた第三者は含まれない。
とすると,遺産分割の遡及効によって,相続財産ははじめから一切他の共同相続人には帰属していなかったことになり,遺産分割後の第三者は無権利者と取引をした者ととして保護されないようにも思える。
しかし,遺産分割により権利帰属が終局的に確定することから,遺産分割後は直ちに登記すべきであり,これを怠った共同相続人は不利益を受けてもやむを得ない。
また,遺産分割の遡及効(909条本文)は,権利承継を説明するための法技術に過ぎず,共同相続人全員で行われる遺産分割は,最終的な権利帰属の決定を直接の目的としており,意思表示による新たな物権変動と同視できる。
したがって,遺産分割は「物権の得喪及び変更」にあたり,177条が適用され,遺産分割前の相続分を超えた権利について相続開始後に生じた第三者に対抗するには登記が必要となる。
とすると,遺産分割の遡及効によって,相続財産ははじめから一切他の共同相続人には帰属していなかったことになり,遺産分割後の第三者は無権利者と取引をした者ととして保護されないようにも思える。
しかし,遺産分割により権利帰属が終局的に確定することから,遺産分割後は直ちに登記すべきであり,これを怠った共同相続人は不利益を受けてもやむを得ない。
また,遺産分割の遡及効(909条本文)は,権利承継を説明するための法技術に過ぎず,共同相続人全員で行われる遺産分割は,最終的な権利帰属の決定を直接の目的としており,意思表示による新たな物権変動と同視できる。
したがって,遺産分割は「物権の得喪及び変更」にあたり,177条が適用され,遺産分割前の相続分を超えた権利について相続開始後に生じた第三者に対抗するには登記が必要となる。
939条は相続放棄の効力として遡及効を定めている。そして939条の趣旨からは,債務超過した相続財産の負担から相続人を解放する点にあり,かかる趣旨からすれば,相続放棄の遡及効は貫徹されなければならない。
また,放棄の有無は,家庭裁判所で確認できること(938条),放棄できる期間が短期間であって(915条1項),第三者が登場する可能性が小さいことから第三者保護の必要性は小さい。
したがって,相続放棄の遡及効は絶対的であり,放棄の前後を問わず,何人に対しても登記なくしてその効力を主張できると解する。
また,放棄の有無は,家庭裁判所で確認できること(938条),放棄できる期間が短期間であって(915条1項),第三者が登場する可能性が小さいことから第三者保護の必要性は小さい。
したがって,相続放棄の遡及効は絶対的であり,放棄の前後を問わず,何人に対しても登記なくしてその効力を主張できると解する。
抵当権とは,目的物の交換価値を把握し,被担保債権を優先的に回収する担保物権である。
したがって,抵当不動産の交換価値把握の実現が妨げらられ,抵当権の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは抵当権が侵害されたというべきである。
したがって,抵当不動産の交換価値把握の実現が妨げらられ,抵当権の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは抵当権が侵害されたというべきである。
抵当権は被占有担保権であり原則として直接自己への明渡は認められないのが原則である。
もっとも,抵当権も物権である以上,排他性を有しており,第三者の占有によって抵当権が侵害されている場合,抵当権者は当該占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として占有の排除を求めることができる。
そして,妨害排除の実効性を保つため,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,抵当権者は,妨害排除請求の内容として直接自己への抵当不動産の明渡を求めることができると解すべきである。
もっとも,抵当権も物権である以上,排他性を有しており,第三者の占有によって抵当権が侵害されている場合,抵当権者は当該占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として占有の排除を求めることができる。
そして,妨害排除の実効性を保つため,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,抵当権者は,妨害排除請求の内容として直接自己への抵当不動産の明渡を求めることができると解すべきである。
抵当お兼は目的物の交換価値を把握する権利であって,使用収益する権限を有するものではない。
したがって,第三者の占有によって抵当権の侵害が生じたとしても,抵当権者は第三者の占有によって下落した目的物の交換価値について損害賠償を請求することはできるが,賃料額相当の損害を請求することができない。
したがって,第三者の占有によって抵当権の侵害が生じたとしても,抵当権者は第三者の占有によって下落した目的物の交換価値について損害賠償を請求することはできるが,賃料額相当の損害を請求することができない。
抵当権が目的物の使用収益を設定者のもとに留めつつ目的物の交換価値を把握する担保物権であることから,抵当権は当該目的物の全交換価値について及ぶことが望ましい。
そこで,「附加してこれと一体となっている物」(370条)とは,広く経済的観点から,抵当権の目的不動産と一体性を有し,その目的不動産の効用を全うさせるものをいうと解すべきである。
そこで,「附加してこれと一体となっている物」(370条)とは,広く経済的観点から,抵当権の目的不動産と一体性を有し,その目的不動産の効用を全うさせるものをいうと解すべきである。
価値支配権たる抵当権の本質からは,いったん抵当権の目的とされた以上,その価値を把握された物は目的不動産から分離されたとしても抵当権の効力が及んでいると解するべきである。
もっとも,抵当権の効力が及んでいることを知らずに分離物について取引関係に入った第三者を保護する必要性もある。
そこで,分離物の抵当権の対抗要件である登記による公示の衣に包まれている場合,すなわち分離物が抵当不動産上に存在する場合にのみ効力を第三者に対応することができると解すべきである。
もっとも,抵当権の効力が及んでいることを知らずに分離物について取引関係に入った第三者を保護する必要性もある。
そこで,分離物の抵当権の対抗要件である登記による公示の衣に包まれている場合,すなわち分離物が抵当不動産上に存在する場合にのみ効力を第三者に対応することができると解すべきである。
「物の給付をするのに必要な行為」(401条2項)とは何を指すか,明文上明らかでなく問題となる。
思うに,種類物債権の目的物が特定すると債務者は無限の調達義務を負うから解放されるので,同「行為」とはかかる利益を受けるに値する行為を指すというべきである。
具体的には,持参債務の場合は現実の提供,取立債務の場合は準備・通知のみならず目的物確定のための分離まで必要と解する。
また,瑕疵ある者の提供では利益を受けるに値する行為にあたらず,この場合特定はしないと解する。
タール事件 最判昭和30年10月18日
差戻控訴審判決 札幌高函館支判昭和37年5月29日
思うに,種類物債権の目的物が特定すると債務者は無限の調達義務を負うから解放されるので,同「行為」とはかかる利益を受けるに値する行為を指すというべきである。
具体的には,持参債務の場合は現実の提供,取立債務の場合は準備・通知のみならず目的物確定のための分離まで必要と解する。
また,瑕疵ある者の提供では利益を受けるに値する行為にあたらず,この場合特定はしないと解する。
タール事件 最判昭和30年10月18日
差戻控訴審判決 札幌高函館支判昭和37年5月29日
債権者に受領遅滞があるとき,債務者は債権者に債務不履行責任を追及できるか。受領遅滞の法的性質とその要件・効果が問題となる。
この点,反対説は受領遅滞を債務不履行の一態様とするが,債権は権利であって義務ではなく,一般に債権者は受領義務を負うものではない。
そして413条の受領遅滞は給付に債権者の行為が必要でこれがされないために債務者が履行義務を免れないのが公平に反することから認められた法定の制度であると解する。
したがって,受領遅滞責任の要件として債権者の帰責性は不要であり,その効果として損害賠償請求や解除はできない。
もっとも,具体的な場合に信義則(1条2項)条受領義務があると認定できる場合には,かかる受領義務に基づき損害賠償請求や解除をなしうると解する。
この点,反対説は受領遅滞を債務不履行の一態様とするが,債権は権利であって義務ではなく,一般に債権者は受領義務を負うものではない。
そして413条の受領遅滞は給付に債権者の行為が必要でこれがされないために債務者が履行義務を免れないのが公平に反することから認められた法定の制度であると解する。
したがって,受領遅滞責任の要件として債権者の帰責性は不要であり,その効果として損害賠償請求や解除はできない。
もっとも,具体的な場合に信義則(1条2項)条受領義務があると認定できる場合には,かかる受領義務に基づき損害賠償請求や解除をなしうると解する。
債務者の「責めに帰すべき事由」(415条)に,履行補助者の故意過失が含まれるかが問題となるも,含まれると解する。
なぜなら,債務者は履行補助者を利用して利益をあげているのだから,そこから生じる負担も負うべきであるといえ(報償責任の法理),履行補助者の故意過失も信義則条債務者の故意過失と同視できるといえるからである。
同居の妻や転借人にも同様の議論が妥当する。
なぜなら,債務者は履行補助者を利用して利益をあげているのだから,そこから生じる負担も負うべきであるといえ(報償責任の法理),履行補助者の故意過失も信義則条債務者の故意過失と同視できるといえるからである。
同居の妻や転借人にも同様の議論が妥当する。
416条の趣旨は,損害の公平な分担を図る点にあり,同条は相当因果関係理論を具体化したものと解する。
すなわち,1項により債務不履行と相当因果関係の範囲にある通常損害について債務者に責任を負わせることで,そして2項で当事者に予見可能性がある特別損害について債務者に責任を負わせることで損害の公平を図ったものと解する。
なお,2項の「当事者」とは,争いあるも債務者のことを指すと解する。債務者にとり予見可能であったことならば,債務者に責任を負わせても酷ではないからである。
すなわち,1項により債務不履行と相当因果関係の範囲にある通常損害について債務者に責任を負わせることで,そして2項で当事者に予見可能性がある特別損害について債務者に責任を負わせることで損害の公平を図ったものと解する。
なお,2項の「当事者」とは,争いあるも債務者のことを指すと解する。債務者にとり予見可能であったことならば,債務者に責任を負わせても酷ではないからである。
思うに,債務不履行時に発生する損害であれば債務者に責任を負わせても不測の事態とはならないから,原則として債務不履行時を基準として損害を算定すべきであると考える。
そして履行期以後に目的物価格が高騰している場合は,416条2項の特別損害として考えて損害を算定すべきと解する。
また,目的物の価額がいったん高騰して下落した場合は(中間最高価格),価格の高騰と高騰価額で債権者が転売したであろうことを特別事情として債務者が予見可能であった場合に高騰価額をもって損害とすることができると解する。
そして履行期以後に目的物価格が高騰している場合は,416条2項の特別損害として考えて損害を算定すべきと解する。
また,目的物の価額がいったん高騰して下落した場合は(中間最高価格),価格の高騰と高騰価額で債権者が転売したであろうことを特別事情として債務者が予見可能であった場合に高騰価額をもって損害とすることができると解する。
債権者代位権の趣旨は債務者の責任財産の保全にあることから,代位権行使により債務者に財産が戻ればよいとも思えるが,債務者は第三債務者に対して金員や動産の自己への給付を求めることができる。なぜなら,債務者が受領を拒絶した場合,本制度の実効性が失われ責任財産保全という趣旨が果たされないからである。
その結果として,債権者は給付物の返還義務と,自己の債務者への債権を相殺することにより事実上の優先弁済を受けることができる。
もっとも,不動産についての所有権移転登記請求を自己に直接移せとはいえないと解する。なぜなら,債務者の受領拒絶があり得ず,債務者名義に戻して強制執行をかければ本制度の目的を十分達成できるからである。
その結果として,債権者は給付物の返還義務と,自己の債務者への債権を相殺することにより事実上の優先弁済を受けることができる。
もっとも,不動産についての所有権移転登記請求を自己に直接移せとはいえないと解する。なぜなら,債務者の受領拒絶があり得ず,債務者名義に戻して強制執行をかければ本制度の目的を十分達成できるからである。
金銭債権以外の特定債権保全のために債権者代位権を行使できるか。
思うに,条文上被保全債権は金銭債権に限定されておらず,また425条は423条を含めていないので債権者代位権を転用する社会的必要性があれば認めれると解する。もっとも,特定債権の保全の必要性は債務者の無資力を前提としないのでこの場合無資力要件は不要と解する。
思うに,条文上被保全債権は金銭債権に限定されておらず,また425条は423条を含めていないので債権者代位権を転用する社会的必要性があれば認めれると解する。もっとも,特定債権の保全の必要性は債務者の無資力を前提としないのでこの場合無資力要件は不要と解する。
債権者取消権の法的性質について一次的には形成権である見るべきである。法文上詐害行為を取り消す権利であることは明らかだからである。
しかし,単に取り消しただけでは,責任財産の保全という債権者取消権の目的を達成できない。
よって,財産の返還という請求権の性質も含むと解する。
すなわち,形成権と請求権を併有すると解する。
しかし,単に取り消しただけでは,責任財産の保全という債権者取消権の目的を達成できない。
よって,財産の返還という請求権の性質も含むと解する。
すなわち,形成権と請求権を併有すると解する。
返還請求の内容としては現物の返還請求が原則であり,現物返還が不可能な場合に価額賠償をすることができる。その相手方は受益者ないし転得者である。
また,返還請求を行使する際,取消債権者は自己へ返還請求を行うことができると解する。これができないとして債務者が受領を拒絶すれば本制度の実効性を損なうからである。
そのため,取消債権者は目的物の債務者への返還債務と自己の債務者への債務者への債権を相殺することにより事実上の優先弁済を受けることができる。
また,取消権の行使は債務者の財産権行使の自由な意思私的自治を強度に制限することになるため,その効果の範囲をできるだけ制限する必要がある。
したがって,債権者と受益者,債権者と転得者との関係で法律行為が無効となるのみで,債務者との関係では無効とならない(相対的取消)。その結果として,受益者は債務者に債務不履行責任(415条)や担保責任(561条)などの契約責任を追及することはできない。ただし,目的物を有償で取得した受益者は,債務者に対し不当利得返還請求(704条)ができる。
また,取消の範囲も原則として被保全債権に限られ,例外的に目的物不可分の場合のみ全体の取消を認めるべきである。
また,返還請求を行使する際,取消債権者は自己へ返還請求を行うことができると解する。これができないとして債務者が受領を拒絶すれば本制度の実効性を損なうからである。
そのため,取消債権者は目的物の債務者への返還債務と自己の債務者への債務者への債権を相殺することにより事実上の優先弁済を受けることができる。
また,取消権の行使は債務者の財産権行使の自由な意思私的自治を強度に制限することになるため,その効果の範囲をできるだけ制限する必要がある。
したがって,債権者と受益者,債権者と転得者との関係で法律行為が無効となるのみで,債務者との関係では無効とならない(相対的取消)。その結果として,受益者は債務者に債務不履行責任(415条)や担保責任(561条)などの契約責任を追及することはできない。ただし,目的物を有償で取得した受益者は,債務者に対し不当利得返還請求(704条)ができる。
また,取消の範囲も原則として被保全債権に限られ,例外的に目的物不可分の場合のみ全体の取消を認めるべきである。
本制度の目的は債務者の責任財産の保全をして債権者の強制執行を実効化させる点にあるから,「債権者を害する法律行為」にあたるかは,本行為が強制執行の実行性を害するか実質的に判断するため,債務者の主観と客観を総合的に考慮して判断すべきである。
より具体的に見れば,一部債権者の弁済はそもそも履行行為であるし,消極財産の減少も伴うので原則として詐害行為ではなく,例外的に一部の債権者と通謀して他の債権者を害するような弁済がされた場合は詐害行為となると解する。
不動産の適正価額での売却は,不動産を消費・隠匿・散逸のしやすい金銭に変えるものであり実質的には責任財産減少といえ,原則として詐害行為に当たると解する。例外的に有用の費用にあてるための売却ならばこれにあたらない可能性がある。
代物弁済も本来の弁済とは異なるし,適正価額での弁済となるか算定困難であるので原則として詐害行為にあたると解する。
より具体的に見れば,一部債権者の弁済はそもそも履行行為であるし,消極財産の減少も伴うので原則として詐害行為ではなく,例外的に一部の債権者と通謀して他の債権者を害するような弁済がされた場合は詐害行為となると解する。
不動産の適正価額での売却は,不動産を消費・隠匿・散逸のしやすい金銭に変えるものであり実質的には責任財産減少といえ,原則として詐害行為に当たると解する。例外的に有用の費用にあてるための売却ならばこれにあたらない可能性がある。
代物弁済も本来の弁済とは異なるし,適正価額での弁済となるか算定困難であるので原則として詐害行為にあたると解する。
特定債権を被保全債権として,債権者取消権を行使できるか。
本件では,譲渡の時期が,債務不履行による損害賠償請求権発生前であるため,詐害行為が被保全債権発生の前になされており問題となる。
思うに,債権者代位権の場合と異なり,取消権の効果は「すべての債権者の利益」(425条)のために生じ債務者の総責任財産を保全するためのものであることが条文上明らかであり,金銭債権保全のためにしか用いることができない。
もっとも,特定債権も不履行の場合には損害賠償債権に転じるのでから,究極的には金銭債権として債務者の一般財産により担保される必要がある。
そこで,取消権行使時において金銭債権となっていれば,特定債権を被保全債権として取消権を行使できると解する。
本件では,譲渡の時期が,債務不履行による損害賠償請求権発生前であるため,詐害行為が被保全債権発生の前になされており問題となる。
思うに,債権者代位権の場合と異なり,取消権の効果は「すべての債権者の利益」(425条)のために生じ債務者の総責任財産を保全するためのものであることが条文上明らかであり,金銭債権保全のためにしか用いることができない。
もっとも,特定債権も不履行の場合には損害賠償債権に転じるのでから,究極的には金銭債権として債務者の一般財産により担保される必要がある。
そこで,取消権行使時において金銭債権となっていれば,特定債権を被保全債権として取消権を行使できると解する。
条文上明らかでなく問題となる。
思うに,譲渡禁止特約が債権的効力を有するのは本条がなくても当然であるし,特約を譲受人にこれを対抗できないとする法がざわざわ本条項を定めた意味がない。
そこで,特約は準物権的効力を有し,特約違反の譲渡は無効となると解する。
思うに,譲渡禁止特約が債権的効力を有するのは本条がなくても当然であるし,特約を譲受人にこれを対抗できないとする法がざわざわ本条項を定めた意味がない。
そこで,特約は準物権的効力を有し,特約違反の譲渡は無効となると解する。
466条2項但書の「善意の第三者」に過失がある者が含まれるか問題となる。
思うに,債権は自由譲渡性があるのが原則である(466条1項)し,譲渡禁止特約は公示性が乏しく譲受人がその存在を認識するのは困難であるから債権の譲受人の主観的保護要件は緩やかに考えるべきである。
したがって,善意の第三者には過失がある者も含むと解する。
もっとも,重過失は取引通念上悪意と同視しうる。
そこで,「善意」とは善意無重過失を指すと解する。
思うに,債権は自由譲渡性があるのが原則である(466条1項)し,譲渡禁止特約は公示性が乏しく譲受人がその存在を認識するのは困難であるから債権の譲受人の主観的保護要件は緩やかに考えるべきである。
したがって,善意の第三者には過失がある者も含むと解する。
もっとも,重過失は取引通念上悪意と同視しうる。
そこで,「善意」とは善意無重過失を指すと解する。
譲渡禁止特約付債権を譲り受けた者が特約につき悪意であった場合でも,債務者が当該譲渡について承諾を与えた場合,債権譲渡の効力はどうなるか。
思うに,譲渡禁止特約は,誰が債権者なのか不明確になり二重払いの危険を負うなどの不利益を防ぐという専ら債務者の利益のためのものである。
とすれば,利益の放棄は自由であり,債務者が承諾すれば特約違反の譲渡も有効であると解する。
思うに,譲渡禁止特約は,誰が債権者なのか不明確になり二重払いの危険を負うなどの不利益を防ぐという専ら債務者の利益のためのものである。
とすれば,利益の放棄は自由であり,債務者が承諾すれば特約違反の譲渡も有効であると解する。
債権が差押えられたうえ,転付命令がなされると債権が券面額で差押債権者に移転し,債権譲渡と類似の効力が発生する。
そこで,譲渡禁止特約がある場合には差押えができないのではないか。
思うに,差押えは公権的な執行手段であり,特約によって差押えを免れることができるとなると,私人が各自で差押禁止債権を創出することができることになってしまい,強制執行秩序を害する。
そこで,譲渡禁止特約ある債権についても差押えをすることができると解する。
そこで,譲渡禁止特約がある場合には差押えができないのではないか。
思うに,差押えは公権的な執行手段であり,特約によって差押えを免れることができるとなると,私人が各自で差押禁止債権を創出することができることになってしまい,強制執行秩序を害する。
そこで,譲渡禁止特約ある債権についても差押えをすることができると解する。
思うに,民法が無留保承諾に切断抗弁の効力を与えた趣旨は,債務者の承諾という事実に公信力を与え,承諾を信頼して債権を取得した者を保護して債券取引の安全を図る点にある(公信力説)。
そこで,譲受人は取引通念上保護に値する主観,すなわち善意無過失を要すると解する。
そこで,譲受人は取引通念上保護に値する主観,すなわち善意無過失を要すると解する。
担保付債権が弁済により消滅したのち,債権譲渡と異議なき承諾がされた場合,担保も復活するか。明文なく問題となる。
思うに,担保があるとの債権譲受人の期待を保護し,債券取引安全を図る一方で,担保権消滅に利害関係がある第三者に意義なき承諾による不測の損害を及ぼすべきではない。
そこで,債務者自身が設定した担保物権については復活し,物上保証人が設定した担保物件や保証債務は復活しないと解する。
なぜなら,前者は承諾した本人だから不測の損害とはいえず,後者には自己の関知しないところで生じた意義なき承諾による不測の損害を及ぼすべきではないからである。
また,抵当不動産の承諾前の第三取得者や後順位抵当権者との関係では,抵当権は復活せず,承諾後の第三取得者や後順位抵当権者との関係では復活すると解する。
なぜなら,前者は自己が関知しないところで生じた異議なき承諾による不測の損害を及ぼすべきではなく,後者は承諾による担保の復活を知り得たのだから譲受人保護を優先してもよいと考えるからである。
思うに,担保があるとの債権譲受人の期待を保護し,債券取引安全を図る一方で,担保権消滅に利害関係がある第三者に意義なき承諾による不測の損害を及ぼすべきではない。
そこで,債務者自身が設定した担保物権については復活し,物上保証人が設定した担保物件や保証債務は復活しないと解する。
なぜなら,前者は承諾した本人だから不測の損害とはいえず,後者には自己の関知しないところで生じた意義なき承諾による不測の損害を及ぼすべきではないからである。
また,抵当不動産の承諾前の第三取得者や後順位抵当権者との関係では,抵当権は復活せず,承諾後の第三取得者や後順位抵当権者との関係では復活すると解する。
なぜなら,前者は自己が関知しないところで生じた異議なき承諾による不測の損害を及ぼすべきではなく,後者は承諾による担保の復活を知り得たのだから譲受人保護を優先してもよいと考えるからである。
両者とも確定日付ある通知を備えた場合の優劣が467条からは明らかでなく問題となる。
思うに,同条1項が債務者への通知やその承諾を対抗要件としたのは債権の帰属に関する債務者の認識を通して債務者に一種の公示機能を営ませようとした点にある。
とすると,債務者が債権譲渡を認識した時点,すなわち確定日付ある譲渡通知の先後で優劣を決すべきである(到達時説)。
同条2項が確定日付を要求した趣旨は,債権譲渡人と一方譲受人よる通知日時の偽装を可及的に防止しようとしたにすぎないと解する。
では,確定日付ある通知が同時到達した場合はどうか。
この場合,到達時説からは譲受人間の優劣を決することはできないが,債務者に対する対抗要件は備えているので両者との全額請求でき,片方に弁済がんされれば債権は消滅すると解する。同時到達という偶然の事情で債務者に弁済拒絶を許すべきではないからである。
この場合,公平の観点から,弁済を受けられなかった譲受人は全額弁済を受けた他方の譲受人に対し不当利得返還請求として按分請求ができると解する。
思うに,同条1項が債務者への通知やその承諾を対抗要件としたのは債権の帰属に関する債務者の認識を通して債務者に一種の公示機能を営ませようとした点にある。
とすると,債務者が債権譲渡を認識した時点,すなわち確定日付ある譲渡通知の先後で優劣を決すべきである(到達時説)。
同条2項が確定日付を要求した趣旨は,債権譲渡人と一方譲受人よる通知日時の偽装を可及的に防止しようとしたにすぎないと解する。
では,確定日付ある通知が同時到達した場合はどうか。
この場合,到達時説からは譲受人間の優劣を決することはできないが,債務者に対する対抗要件は備えているので両者との全額請求でき,片方に弁済がんされれば債権は消滅すると解する。同時到達という偶然の事情で債務者に弁済拒絶を許すべきではないからである。
この場合,公平の観点から,弁済を受けられなかった譲受人は全額弁済を受けた他方の譲受人に対し不当利得返還請求として按分請求ができると解する。
債権譲渡の第三者対抗要件により債権二重譲渡の優劣が決した場合,債務者もこれに拘束されて優先譲受人のみに弁済する義務を負う。
もっとも,債務者が誤って劣後譲受人に弁済した場合,債務者は債権準占有者に対して弁済したとして有効な弁済にならないか(478条)。
思うに,478条の趣旨は債権受領権者のような外観を信じて弁済した債務者を保護する点にある。
とするならば,劣後債権者も債権受領権者のような外観を有しているのだから,弁済債務者は同様の保護に値する。
そこで,債務者が債権の帰属の優劣につき善意無過失者なら有効な弁済となる解する。
この場合,優先譲受人は劣後譲受人に不当利得返還請求権をすることができる。
もっとも,債務者が誤って劣後譲受人に弁済した場合,債務者は債権準占有者に対して弁済したとして有効な弁済にならないか(478条)。
思うに,478条の趣旨は債権受領権者のような外観を信じて弁済した債務者を保護する点にある。
とするならば,劣後債権者も債権受領権者のような外観を有しているのだから,弁済債務者は同様の保護に値する。
そこで,債務者が債権の帰属の優劣につき善意無過失者なら有効な弁済となる解する。
この場合,優先譲受人は劣後譲受人に不当利得返還請求権をすることができる。
代理人を詐称する者に弁済をした場合,「債権の準占有者」(478条)に弁済したとして有効とならないか。
思うに,同条の趣旨は,履行を強制され債権帰属についての調査の暇のない,債権受領者の外観を信じて弁済をした債務者の保護の点にある。
そして,債権者ではない者が債権者の外観を装う場合と代理人の外観を装う場合において,弁済を強制された債務者を保護する必要性は変わらない。
そこで,詐称代理人も「準占有者」に含まれて有効な弁済となると解する。
思うに,同条の趣旨は,履行を強制され債権帰属についての調査の暇のない,債権受領者の外観を信じて弁済をした債務者の保護の点にある。
そして,債権者ではない者が債権者の外観を装う場合と代理人の外観を装う場合において,弁済を強制された債務者を保護する必要性は変わらない。
そこで,詐称代理人も「準占有者」に含まれて有効な弁済となると解する。
弁済提供の趣旨は自らのなすべきことをした誠実な債務者の責任を解放する点にあり,債務者はかかる恩恵に見合うことをしたといえなければならない。
そのため,原則として債務の本旨にしたがった現実の提供がなくてはならないが(本文),債権者があらかじめ受領を拒んだ場合や履行に債権者の行為を要する場合は,現実の提供は無意味ないし不可能であるので,弁済の準備と通知をしてその受領を催告すれば足りる(但書)。
もっとも,債務者が受領拒絶の意思を明白にしている場合,催告をさせても無意味なので催告をしないでも弁済の提供となると解する。
そのため,原則として債務の本旨にしたがった現実の提供がなくてはならないが(本文),債権者があらかじめ受領を拒んだ場合や履行に債権者の行為を要する場合は,現実の提供は無意味ないし不可能であるので,弁済の準備と通知をしてその受領を催告すれば足りる(但書)。
もっとも,債務者が受領拒絶の意思を明白にしている場合,催告をさせても無意味なので催告をしないでも弁済の提供となると解する。
銀行Aは,BのAに預けてある定期預金を担保に,Bに金銭貸付をした。ところが,預金の出捐者は実はCだった。
この場合,まず,銀行は誰が預金者あっても特に利害を有しないので預金者は実質的出捐者Cであると解する(客観説・判例同旨)。
そして,預金担保債権貸付の担保設定・相殺予約・貸付・相殺という一連の行為を全体としてみると,金銭貸付は定期預金の期限前解約による払戻し,すなわち銀行による弁済と実質的に同視することができる。
そこで,銀行が貸付時点で預金の帰属につき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたのであれば478条を類推適用し真実の預金者(B)にその相殺を対抗できると解する。
最判昭和59年2月23日民集38巻3号445頁
この場合,まず,銀行は誰が預金者あっても特に利害を有しないので預金者は実質的出捐者Cであると解する(客観説・判例同旨)。
そして,預金担保債権貸付の担保設定・相殺予約・貸付・相殺という一連の行為を全体としてみると,金銭貸付は定期預金の期限前解約による払戻し,すなわち銀行による弁済と実質的に同視することができる。
そこで,銀行が貸付時点で預金の帰属につき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたのであれば478条を類推適用し真実の預金者(B)にその相殺を対抗できると解する。
最判昭和59年2月23日民集38巻3号445頁
弁済による代位では,債権の一部について弁済があった場合でも,弁済者は弁済した価額に応じて債権者の権利を行使できる(502条1項)。
(否定説)
そこで,一部弁済者は担保権の実行も可能か。
この点,502条「債権者とともにその権利を行使する」との文言上からは,抵当権も弁済した割合に応じて行使が許されると思われる。
しかし,抵当権の実行は一度に行われるので,代位権を実行すると債権者も配当加入せざるを得なくなる。とすると,債権者は不利な時期に担保権の実行を強いられることになりかねず,その抵当権実行の自由が害されるおそれがある。
以上から,一部弁済者による抵当権の代位は否定すべきである。
(肯定説)
しかし,抵当権は不可分性があり,一部のみを行使することは不可能である。そこで,一部弁済者は抵当権の実行も可能かが問題となる。
この点,債権者による抵当権行使の自由を害することを理由に,抵当権の行使について消極的に考える立場もある。
しかし弁済による代位は他人のために弁済する者を可及的に保護すべく定められた制度である。
にもかかわらず,債権の確保において有効な権利である抵当権の行使が制限されるとなると代位弁済者の保護に十分でない。
そもそも,条文上も「債権者とともにその権利を行使する」(502条1項)とその範囲に限定は無いから,抵当権などの担保物権をのぞいて考える根拠が薄弱である。
以上から,一部弁済者による抵当権の代位は肯定すべきである。
大決昭和6年4月7日 「債権の一部について代位弁済をした者は,債権者の権利の分割行使が可能であれば,債権者とは別個に債権者の有する抵当権を実行できる」
(Short ver.否定説)
債権の一部を弁済した者は,単独で担保権の実行をすることもできるか。
502条1項が,債権者とともにその権利を行使することができる,としていることから問題となる。
思うに,これができるとすると抵当目的物の価額が低いときなど債権者にとって不利な時期に担保権実行を強いられる可能性があるし,全額弁済まで担保目的物価値をすべて把握できるとすると担保物権の不可分性(296条)に反しかねない。
そこで,できないと解する。
(否定説)
そこで,一部弁済者は担保権の実行も可能か。
この点,502条「債権者とともにその権利を行使する」との文言上からは,抵当権も弁済した割合に応じて行使が許されると思われる。
しかし,抵当権の実行は一度に行われるので,代位権を実行すると債権者も配当加入せざるを得なくなる。とすると,債権者は不利な時期に担保権の実行を強いられることになりかねず,その抵当権実行の自由が害されるおそれがある。
以上から,一部弁済者による抵当権の代位は否定すべきである。
(肯定説)
しかし,抵当権は不可分性があり,一部のみを行使することは不可能である。そこで,一部弁済者は抵当権の実行も可能かが問題となる。
この点,債権者による抵当権行使の自由を害することを理由に,抵当権の行使について消極的に考える立場もある。
しかし弁済による代位は他人のために弁済する者を可及的に保護すべく定められた制度である。
にもかかわらず,債権の確保において有効な権利である抵当権の行使が制限されるとなると代位弁済者の保護に十分でない。
そもそも,条文上も「債権者とともにその権利を行使する」(502条1項)とその範囲に限定は無いから,抵当権などの担保物権をのぞいて考える根拠が薄弱である。
以上から,一部弁済者による抵当権の代位は肯定すべきである。
大決昭和6年4月7日 「債権の一部について代位弁済をした者は,債権者の権利の分割行使が可能であれば,債権者とは別個に債権者の有する抵当権を実行できる」
(Short ver.否定説)
債権の一部を弁済した者は,単独で担保権の実行をすることもできるか。
502条1項が,債権者とともにその権利を行使することができる,としていることから問題となる。
思うに,これができるとすると抵当目的物の価額が低いときなど債権者にとって不利な時期に担保権実行を強いられる可能性があるし,全額弁済まで担保目的物価値をすべて把握できるとすると担保物権の不可分性(296条)に反しかねない。
そこで,できないと解する。
同一事故で双方に物損だけが生じた場合にも相殺は許されないか。
509条が受働債権が不法行為によって生じた場合の相殺を禁止していることから問題となる。
思うに,同条の趣旨は現実の給付を保証することにより被害者の現実の救済をするとともに,債権者による不法行為の誘発を阻止することにある。
とすると,物損については,被害者に現実の給付を保証する必要性を欠くし,同一事故による不法行為債権発生の場合,不法行為の誘発の阻止も無関係である。
そこで,同一事故で双方物損の場合に限っては,509条が適用されず相殺が許されると解する。
509条が受働債権が不法行為によって生じた場合の相殺を禁止していることから問題となる。
思うに,同条の趣旨は現実の給付を保証することにより被害者の現実の救済をするとともに,債権者による不法行為の誘発を阻止することにある。
とすると,物損については,被害者に現実の給付を保証する必要性を欠くし,同一事故による不法行為債権発生の場合,不法行為の誘発の阻止も無関係である。
そこで,同一事故で双方物損の場合に限っては,509条が適用されず相殺が許されると解する。
受働債権の差押時に自動債権の弁済期が未到来で受動債権の弁済期が到来しており,差押後に自動債権の弁済期を待って第三債務者が相殺した場合,これを差押債権者に対抗できるか。
思うに,511条は文言上弁済期の先後を問うていないし,相殺制度は受働債権につきあたかも担保を有しているような機能を有しており,これに対する期待は尊重されるべきである。
そこで,511条を制限適用せず,自働債権が受働債権差押後に取得されたものでなければ双方の弁済期の先後を問わずに相殺をしてこれに差押債権者に対抗できると解する。
思うに,511条は文言上弁済期の先後を問うていないし,相殺制度は受働債権につきあたかも担保を有しているような機能を有しており,これに対する期待は尊重されるべきである。
そこで,511条を制限適用せず,自働債権が受働債権差押後に取得されたものでなければ双方の弁済期の先後を問わずに相殺をしてこれに差押債権者に対抗できると解する。
同種の債権債務の対立が生じた後に受働債権が債権譲渡された場合,債務者は譲渡債権者との間で相殺適状があったことを抗弁できるか。468条2項の「事由」として譲受人に主張できるかどうかが問題となる。
思うに,相殺適状が生じた後はこれによって債権債務を決済したと期待するのが通常であるからその期待を保護する必要があるし,現代社会では相殺の担保的機能を重視すべきである。
そこで,債権譲渡通知前に譲渡人に対する自働債権を有していれば,弁済期の先後を問わずに相殺ができると解する。
思うに,相殺適状が生じた後はこれによって債権債務を決済したと期待するのが通常であるからその期待を保護する必要があるし,現代社会では相殺の担保的機能を重視すべきである。
そこで,債権譲渡通知前に譲渡人に対する自働債権を有していれば,弁済期の先後を問わずに相殺ができると解する。
債権譲渡がなされ,債務者が譲渡人と譲受人双方の間に債権を有する場合,譲渡人も譲受人も相殺をなしうることになるが,いずれを優先すべきか。
思うに,債権回収に熱心な債権者を保護すべきであるし,片方が相殺すれば債権は遡及的に消滅するので,もうは片方の相殺はできなくなる。
そこで,相殺の意思表示を先にした方の相殺が優先すると解する。
思うに,債権回収に熱心な債権者を保護すべきであるし,片方が相殺すれば債権は遡及的に消滅するので,もうは片方の相殺はできなくなる。
そこで,相殺の意思表示を先にした方の相殺が優先すると解する。
売買目的物が契約時にすでに滅していた場合,契約が無効である以上,売主は買主に不法行為責任しか負わないとも思える。
しかしこれでは挙証責任や時効期間の点で不利であるし,滅失が契約の前か後かで債務風履行責任を追及できるかの結論が形式的に分かれるのは均衡を失する。
思うに,契約を締結した者は一般市民とは異なり,信義則に基づく特別な社会的接触関係に入ったといえ,無効な契約を締結して相手方に損害を被らせない信義則上の義務を負い,一定の場合にはかかる義務違反として債務不履行責任を負うというべきである。
具体的には,1)契約内容が原始的不能であり,2)売主がかかる不能を知らないことにつき過失があり,3)相手方が善意,であれば債務不履行責任が発生し,買主が契約成立を信頼したために発生する損害,すなわち信頼利益につき賠償責任を負うと解する。
しかしこれでは挙証責任や時効期間の点で不利であるし,滅失が契約の前か後かで債務風履行責任を追及できるかの結論が形式的に分かれるのは均衡を失する。
思うに,契約を締結した者は一般市民とは異なり,信義則に基づく特別な社会的接触関係に入ったといえ,無効な契約を締結して相手方に損害を被らせない信義則上の義務を負い,一定の場合にはかかる義務違反として債務不履行責任を負うというべきである。
具体的には,1)契約内容が原始的不能であり,2)売主がかかる不能を知らないことにつき過失があり,3)相手方が善意,であれば債務不履行責任が発生し,買主が契約成立を信頼したために発生する損害,すなわち信頼利益につき賠償責任を負うと解する。
契約締結前の準備段階の過失による買主となるべき者が損害を被った場合,債務不履行に基づく損害賠償請求が認められるか。
この点,契約締結がない以上債務不履行責任が成立しないがのが原則である。
しかし,契約準備段階に入った者は,一般市民とは異なる特別な社会的接触関係に入ったといえ,一定の場合に相手方の信頼を裏切り損害を被らせない信義則上の義務を負うというべきである。
具体的には,1)相手方の信頼を惹起する先行行為の存在があり,2)契約が相当程度成熟していた等の事情を考慮して義務違反の有無を判断すべきと解する。
この点,契約締結がない以上債務不履行責任が成立しないがのが原則である。
しかし,契約準備段階に入った者は,一般市民とは異なる特別な社会的接触関係に入ったといえ,一定の場合に相手方の信頼を裏切り損害を被らせない信義則上の義務を負うというべきである。
具体的には,1)相手方の信頼を惹起する先行行為の存在があり,2)契約が相当程度成熟していた等の事情を考慮して義務違反の有無を判断すべきと解する。
被用者が仕事中に事故があって負傷ないし死亡した場合,使用者に対して債務不履行責任を追及できないか。不法行為責任のみでは挙証責任や時効期間の点で被用者に不利ともいえ,債務不履行責任を認める根拠が問題となる。
思うに,ある法律関係に基づいて特別な関係に入った当事者間は,相手方の安全に配慮して損害を被らせないようにする信義則上の義務を負うと解する。
そして,一般に使用者は雇用契約上の付随義務として,仕事場において被用者が損害を被らず被用者の安全を配慮する義務を信義則上負うといえ,かかる義務違反が認められれば,被用者側は使用者に対して債務不履行責任を追及することができる。
なお,不法行為に基づく請求権と債務不履行に基づく請求権は,使用者側の便宜で選択すればよく,請求権競合となると解する。
思うに,ある法律関係に基づいて特別な関係に入った当事者間は,相手方の安全に配慮して損害を被らせないようにする信義則上の義務を負うと解する。
そして,一般に使用者は雇用契約上の付随義務として,仕事場において被用者が損害を被らず被用者の安全を配慮する義務を信義則上負うといえ,かかる義務違反が認められれば,被用者側は使用者に対して債務不履行責任を追及することができる。
なお,不法行為に基づく請求権と債務不履行に基づく請求権は,使用者側の便宜で選択すればよく,請求権競合となると解する。
双務契約の無効・取消しの場合,双方が負う不当利得請求権につき,同時履行の抗弁権は認められないか。
思うに,同時履行の抗弁の趣旨は,当事者の公平を図る点にあるところ,この場合も双務契約の場合と同様公平を図る必要があるし,両債務は双務契約によるものではないが,もともと一つの契約から派生したものである。
そこで,533条を類推して認められると解する。
思うに,同時履行の抗弁の趣旨は,当事者の公平を図る点にあるところ,この場合も双務契約の場合と同様公平を図る必要があるし,両債務は双務契約によるものではないが,もともと一つの契約から派生したものである。
そこで,533条を類推して認められると解する。
一度履行の提供をした当事者が後日再度履行請求をした場合,同時履行の抗弁を奪うために履行の提供は継続しなければならないか。
思うに,同時履行の抗弁の趣旨は,双務契約における履行上の牽連関係を保持し公平を図る点にある。
とすると,一度履行の提供をしても両債務の牽連関係は残るから,以前同条の趣旨は妥当し,またこれを認めないとすると再度請求してきた側の当事者が無資力に陥っていた場合,履行した側に酷である。
そこで,再度請求した当事者は再度自身履行の提供をしなければならず,相手方は履行の提供があるまで,自己の履行を拒絶できると解すべきである。
思うに,同時履行の抗弁の趣旨は,双務契約における履行上の牽連関係を保持し公平を図る点にある。
とすると,一度履行の提供をしても両債務の牽連関係は残るから,以前同条の趣旨は妥当し,またこれを認めないとすると再度請求してきた側の当事者が無資力に陥っていた場合,履行した側に酷である。
そこで,再度請求した当事者は再度自身履行の提供をしなければならず,相手方は履行の提供があるまで,自己の履行を拒絶できると解すべきである。
534条1項による債権者主義の帰結はあまりに具体的妥当性に欠けるとも思われることから,同条項の適用を制限すべきではないか。
思うに,条文上適用は制限されていないし,所有者は危険を負担するとの原則からは契約締結時に所有権移転とともに危険も買主に移転するというべきであり,また本規定は任意規定であるので,特約で排除することが可能である。
したがって,適用は制限すべきではない(無制限説)。
思うに,条文上適用は制限されていないし,所有者は危険を負担するとの原則からは契約締結時に所有権移転とともに危険も買主に移転するというべきであり,また本規定は任意規定であるので,特約で排除することが可能である。
したがって,適用は制限すべきではない(無制限説)。
思うに,解除の趣旨は履行を果たさない不誠実な債務者との双務契約の拘束から債権者を解放する点にあり,そうだとすると解除により契約が遡及的に無効となると考えるのが直接的である(直接効果説)。
とすると,「第三者」とは解除の遡及効により害される者を保護して,取引の安全を図るという点にその趣旨があるから,「第三者」とは解除された契約を前提にして解除前に新たな権利を取得した者をいうと解する。
なお,仮に債務不履行があっても解除されるかはわからないため,「第三者」として保護されるためには主観は問題となるず,悪意でもこれにあたる。
もっとも,何らの落ち度のない解除権者の犠牲により保護される以上,権利保護要件として第三者対抗要件を備える必要があると解する。
とすると,「第三者」とは解除の遡及効により害される者を保護して,取引の安全を図るという点にその趣旨があるから,「第三者」とは解除された契約を前提にして解除前に新たな権利を取得した者をいうと解する。
なお,仮に債務不履行があっても解除されるかはわからないため,「第三者」として保護されるためには主観は問題となるず,悪意でもこれにあたる。
もっとも,何らの落ち度のない解除権者の犠牲により保護される以上,権利保護要件として第三者対抗要件を備える必要があると解する。
売買目的物が,売買契約解除後に第三者に譲渡された場合
思うに,545条1項但書の「第三者」は解除前の第三者を指すから,本件転得者はこれにあたらない。
もっとも,転得者が常に保護されないとすると取引の安全を著しく害するため,転得者保護のための法律構成が問題となる。
思うに,解除による契約関係の遡及的無効も法的擬制であり,元所有者への復帰的物権変動を観念できるのであって,かかる物権変動と転得者への取引による物権変動があるといえ,中間者を起点とした二重譲渡関係があるといえる。そこで,両者の優劣は対抗要件たる所有権移転登記の具備で決するべきと解する。
思うに,545条1項但書の「第三者」は解除前の第三者を指すから,本件転得者はこれにあたらない。
もっとも,転得者が常に保護されないとすると取引の安全を著しく害するため,転得者保護のための法律構成が問題となる。
思うに,解除による契約関係の遡及的無効も法的擬制であり,元所有者への復帰的物権変動を観念できるのであって,かかる物権変動と転得者への取引による物権変動があるといえ,中間者を起点とした二重譲渡関係があるといえる。そこで,両者の優劣は対抗要件たる所有権移転登記の具備で決するべきと解する。
解除のためには,期間の定めのない債務を遅滞に陥れる催告と,541条の催告と二重の催告が必要に思えるも,不要と解する。
なぜなら,債務者が履行遅滞にあることは解除発生の要件であって,催告の要件ではなく,両催告は一度の催告で兼ねることができるからである。
なぜなら,債務者が履行遅滞にあることは解除発生の要件であって,催告の要件ではなく,両催告は一度の催告で兼ねることができるからである。
相当期間を定めず,また相当でない期間を示して催告した場合にも解除権は発生するか。
思うに,541条が解除の手続的要件として相当期間を定めた催告を要求した趣旨は,債務者に翻意して履行する最後の機会を与える点にある。
したがって,催告さえあれば,上記趣旨は満たされ,催告があり客観的に相当な期間さえ経過すれば介助犬は発生すると解する。
思うに,541条が解除の手続的要件として相当期間を定めた催告を要求した趣旨は,債務者に翻意して履行する最後の機会を与える点にある。
したがって,催告さえあれば,上記趣旨は満たされ,催告があり客観的に相当な期間さえ経過すれば介助犬は発生すると解する。
「当事者」「履行の着手」の文言の意義が明文上必ずしも明らかでなく問題となる。
思うに,同条が約定解除の時期を制限した趣旨は,履行に着手した当事者は相手方の債務も履行されることに対して期待をもつので,かかる期待を保護し,不測の損害を与えない点にある,と解する。
とすれば,「当事者」とは解除をされる相手方を指すのであり,履行に着手した本人から解除をすることは構わないと解する(判例同旨)。
また,解除権の行使が制限されるのであるから,履行の着手が外部から認識可能なものでなければ今度は解除者の解除への期待を害する。
そこで,「履行の着手」とは,客観的に外部から認識できる形で履行行為の一部をなし,又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合をいうと解する(判例同旨)。
思うに,同条が約定解除の時期を制限した趣旨は,履行に着手した当事者は相手方の債務も履行されることに対して期待をもつので,かかる期待を保護し,不測の損害を与えない点にある,と解する。
とすれば,「当事者」とは解除をされる相手方を指すのであり,履行に着手した本人から解除をすることは構わないと解する(判例同旨)。
また,解除権の行使が制限されるのであるから,履行の着手が外部から認識可能なものでなければ今度は解除者の解除への期待を害する。
そこで,「履行の着手」とは,客観的に外部から認識できる形で履行行為の一部をなし,又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合をいうと解する(判例同旨)。
手付が交付された場合,571条1項により解約手付であることが推定されるが,違約金条項があることは,かかる推定を覆すことになるのか。
この点,解約手付は契約の拘束力を弱めるもので,違約手付はこれを強めるものとして両者は矛盾すると考えれば,推定は排除されるとも思える。
しかし,手付が低額であるような場合,違約手付もその額だけで清算しようとするのであるから,必ずしも契約の拘束力を強めるとはいえず,両者は一般的に矛盾するとはいえない。
したがって,推定は排除されないと解する。
この点,解約手付は契約の拘束力を弱めるもので,違約手付はこれを強めるものとして両者は矛盾すると考えれば,推定は排除されるとも思える。
しかし,手付が低額であるような場合,違約手付もその額だけで清算しようとするのであるから,必ずしも契約の拘束力を強めるとはいえず,両者は一般的に矛盾するとはいえない。
したがって,推定は排除されないと解する。
この点,特定物取引においては,目的物に瑕疵があっても現状で引き渡せば足りる(483条)ことから債務不履行責任は問えず,買主に酷な結果となる。そこで,有償契約の等価的均衡を保つために特定物売買の場合に特に定められた無過失責任が担保責任であると解する。
そうだとすれば,不特定物取引の瑕疵物の提供があった場合には買主は依然完全履行請求ができるため,同責任を認める必要はなく,不特定物売買に担保責任規定は適用されないと解する。
そうだとすれば,不特定物取引の瑕疵物の提供があった場合には買主は依然完全履行請求ができるため,同責任を認める必要はなく,不特定物売買に担保責任規定は適用されないと解する。
目的物に法律上の制限があった場合に「瑕疵」があるといえ,570条の適用があるか。
思うに,瑕疵とは目的物が通常有する品質・性能を欠いていることをいい,目的物に法律上の制限がある場合もこれにあたる。
したがって,法律上の瑕疵も同条の瑕疵に含まれ,この場合566条ではなく570条が適用されると解する。
思うに,瑕疵とは目的物が通常有する品質・性能を欠いていることをいい,目的物に法律上の制限がある場合もこれにあたる。
したがって,法律上の瑕疵も同条の瑕疵に含まれ,この場合566条ではなく570条が適用されると解する。
土地賃借権の売買がされた場合,買主は土地の瑕疵についても売主に担保責任を追及できるか。570条の「瑕疵」の適用が問題となる。
思うに,売買目的物は土地賃借権であるし,土地の瑕疵は,賃貸人の修繕義務を追及すべきである(606条1項)。
したがって,この場合の土地の瑕疵は「瑕疵」にあたらず,担保責任の追及はできないと解する。
思うに,売買目的物は土地賃借権であるし,土地の瑕疵は,賃貸人の修繕義務を追及すべきである(606条1項)。
したがって,この場合の土地の瑕疵は「瑕疵」にあたらず,担保責任の追及はできないと解する。
担保責任と錯誤の成立が競合する場合,どのように考えるか。
この点,判例は両者が競合する場合,担保責任規定を排除するが,担保責任が成立する場合はほとんど錯誤も成立するのであり,錯誤を優先適用すると法が担保責任についてあえて短期の除斥期間を定めた趣旨が没却される。
そこで,担保責任規定は錯誤規定の特則であると考え,担保責任規定を優先して適用すべきと解する。

この点,判例は両者が競合する場合,担保責任規定を排除するが,担保責任が成立する場合はほとんど錯誤も成立するのであり,錯誤を優先適用すると法が担保責任についてあえて短期の除斥期間を定めた趣旨が没却される。
そこで,担保責任規定は錯誤規定の特則であると考え,担保責任規定を優先して適用すべきと解する。
古い判例なのでその射程は疑問。事案もやや特殊。論文の場合,判例に従って錯誤無効としてしまうとその後が続かない。この論点は要検討。
担保責任に基づく損害賠償請求の範囲は信頼利益までか,履行利益を含むか。
思うに,担保責任は特定物については現状引渡しで履行となる(483条)ことから有償契約の等価的均衡を図るため,法が得に認めた責任である。
そして,同責任は無過失責任であるから履行利益まで含めると過大な責任となりかえって不公平な結果となりかねないし,そもそも原始的一部不能があるのだから,契約通りの履行は観念できない。
そこで,信頼利益に限ると解する。
思うに,担保責任は特定物については現状引渡しで履行となる(483条)ことから有償契約の等価的均衡を図るため,法が得に認めた責任である。
そして,同責任は無過失責任であるから履行利益まで含めると過大な責任となりかえって不公平な結果となりかねないし,そもそも原始的一部不能があるのだから,契約通りの履行は観念できない。
そこで,信頼利益に限ると解する。
賃貸借契約終了後の目的物明渡請求と敷金返還請求権は同時履行の関係にあるか。
思うに,敷金契約は賃借人の目的物明渡までの一切の債務を担保する趣旨でなされるのであるし,明渡しがなされてはじめて敷金の返還額が確定する。
そこで,敷金返還請求権は目的物明渡時に発生し,明渡しのない段階では未だ敷金返還請求権は発生していないため,賃借人は同時履行の抗弁権を主張して明渡を拒むことはできないと解する。
思うに,敷金契約は賃借人の目的物明渡までの一切の債務を担保する趣旨でなされるのであるし,明渡しがなされてはじめて敷金の返還額が確定する。
そこで,敷金返還請求権は目的物明渡時に発生し,明渡しのない段階では未だ敷金返還請求権は発生していないため,賃借人は同時履行の抗弁権を主張して明渡を拒むことはできないと解する。
二重賃貸借がなされた場合,両賃借人間の優劣は対抗要件具備の戦後で決するべきと解する。
なぜなら,対抗要件を備えた不動産賃借権は物権に対してすら対抗可能なのであるから,債権たる賃借権の場合にもなおさら対抗力を有するといえるからである。
なぜなら,対抗要件を備えた不動産賃借権は物権に対してすら対抗可能なのであるから,債権たる賃借権の場合にもなおさら対抗力を有するといえるからである。
賃借権に基づく妨害排除請求権は認められるか。
思うに,所有権その他物権に妨害排除請求が認められるのは直接的・排他的支配権を有しているからである。
とすれば,通常の債権はこれを有しないから妨害排除請求を認めることができないが,賃借権の場合対抗要件を具備すれば直接的・排他的支配権を有することになるといえ,対抗力を備えた不動産賃借権については妨害排除請求も認められると解する。
思うに,所有権その他物権に妨害排除請求が認められるのは直接的・排他的支配権を有しているからである。
とすれば,通常の債権はこれを有しないから妨害排除請求を認めることができないが,賃借権の場合対抗要件を具備すれば直接的・排他的支配権を有することになるといえ,対抗力を備えた不動産賃借権については妨害排除請求も認められると解する。
612条2項は,賃借人の賃借権無断譲渡・目的物無断転貸につき賃貸人の解除権を認めているが,背信性が全くない場合も解除できるか。
思うに,同条が無催告解除を認めるのは,賃貸借契約が個人的信頼関係を基礎とする継続的契約であることから,無断譲渡等がなされ使用形態に変更が生じるときは,この信頼関係が類型的にみて高度に破壊されるといえるからである。
とすれば,無断譲渡・転貸がなされても,賃借人の背信的行為と認めるに足りない特段の事情があり,これを賃借人が主張立証すれば例外的に解除権の行使は制限されると解する。
思うに,同条が無催告解除を認めるのは,賃貸借契約が個人的信頼関係を基礎とする継続的契約であることから,無断譲渡等がなされ使用形態に変更が生じるときは,この信頼関係が類型的にみて高度に破壊されるといえるからである。
とすれば,無断譲渡・転貸がなされても,賃借人の背信的行為と認めるに足りない特段の事情があり,これを賃借人が主張立証すれば例外的に解除権の行使は制限されると解する。
承諾転貸がなれていた場合,賃貸人と賃借人の間の原賃貸借が合意解除された場合,特段の事情がない限り賃貸人は解除をもって転借人に対抗できないと解する。
なぜなら,対抗できるとすると居住基盤を失う転借人の保護に欠けるし,賃借人は自己の権利を放棄しても他人の権利を害することができないという398条や598条の法理に反し,信義則上許されないといえるからである。
他方,賃貸人が賃借人の債務不履行を理由に解除したときは,転貸借は履行不能により終了し,転借人は転借権を賃貸人に対抗できないと解する。
なぜなら,債務不履行があるのに転借人の存在により賃貸人の解除権が制限されるのは今度は賃貸人に酷だからである。
もっとも,この債務不履行解除をする場合,転借人に第三者弁済の機会を与えるために催告を要するかにつき争いあるも,明文にない解除の要件を付け足すことにより賃貸人の解除権が制限されるいわれはなく,催告は不要と解する。
そして,この場合,転貸人の貸す債務は,原賃貸人から転借人に明渡請求があったときに社会通念上履行不能となり消滅し,継続的契約の特殊性から転貸借契約自体が終了すると解する。
なぜなら,対抗できるとすると居住基盤を失う転借人の保護に欠けるし,賃借人は自己の権利を放棄しても他人の権利を害することができないという398条や598条の法理に反し,信義則上許されないといえるからである。
他方,賃貸人が賃借人の債務不履行を理由に解除したときは,転貸借は履行不能により終了し,転借人は転借権を賃貸人に対抗できないと解する。
なぜなら,債務不履行があるのに転借人の存在により賃貸人の解除権が制限されるのは今度は賃貸人に酷だからである。
もっとも,この債務不履行解除をする場合,転借人に第三者弁済の機会を与えるために催告を要するかにつき争いあるも,明文にない解除の要件を付け足すことにより賃貸人の解除権が制限されるいわれはなく,催告は不要と解する。
そして,この場合,転貸人の貸す債務は,原賃貸人から転借人に明渡請求があったときに社会通念上履行不能となり消滅し,継続的契約の特殊性から転貸借契約自体が終了すると解する。
708条の意義が明文から明らかでなく問題となる。
思うに,708条の趣旨は自ら不法なことをした者がこれによって生じた損失を取り戻すために法の助力を求めるのは許さないとするクリーンハンズの原則を根拠とするものであり,90条とその根拠をともにする。
とすれば,「不法」とは公序良俗違反をいい,単なる強行法規違反を含まないと解する。
思うに,708条の趣旨は自ら不法なことをした者がこれによって生じた損失を取り戻すために法の助力を求めるのは許さないとするクリーンハンズの原則を根拠とするものであり,90条とその根拠をともにする。
とすれば,「不法」とは公序良俗違反をいい,単なる強行法規違反を含まないと解する。
708条の「給付」とは何をしたことを指すのか,明文から明らかでなく問題となる。
思うに,一部の給付がなされた段階で本条が適用されるとすると,給付を受ける側が本条を利用して終局的給付を受けることができるようになり,不法な行為に法の助力を与えないとする本条の趣旨に反する。
そこで,「給付」とは終局的な給付を指すと解し,未登記不動産については引渡し,既登記不動産については引渡しおよび登記,動産については占有改定以外の引渡しがないと「給付」とはいえないと解する。
思うに,一部の給付がなされた段階で本条が適用されるとすると,給付を受ける側が本条を利用して終局的給付を受けることができるようになり,不法な行為に法の助力を与えないとする本条の趣旨に反する。
そこで,「給付」とは終局的な給付を指すと解し,未登記不動産については引渡し,既登記不動産については引渡しおよび登記,動産については占有改定以外の引渡しがないと「給付」とはいえないと解する。
708条の要件を満たした場合,給付者は不当利得返還請求によって給付物の返還を求めることができない。にもかかわらず,所有権に基づく返還請求を認めてしまえば同条の効果を骨抜きにしてしまうため,この場合かかる返還請求権は認められない(同条項類推)。
そして,返還請求権が認められない所有権を給付者のもとにとどめても意味がないため,返還請求が認められないことの反射的効果として受給者に所有権が移転すると解する。
そして,返還請求権が認められない所有権を給付者のもとにとどめても意味がないため,返還請求が認められないことの反射的効果として受給者に所有権が移転すると解する。
不当利得返還請求が認められるか。
・(中間者を介しているものの)利得と損失との間に社会通念上の因果関係が認められる。
・「法律上の原因なく利得を得た」といえるか。
思うに,不当利得制度は実質的公平を実現するためにあるから,契約全体をとしてみ受益者が対価関係なしに利得を得たといる場合には「法律上の原因なく」といえる解する。
・(中間者を介しているものの)利得と損失との間に社会通念上の因果関係が認められる。
・「法律上の原因なく利得を得た」といえるか。
思うに,不当利得制度は実質的公平を実現するためにあるから,契約全体をとしてみ受益者が対価関係なしに利得を得たといる場合には「法律上の原因なく」といえる解する。
騙取金による弁済がされた場合,被騙取者は弁済受領者が騙取金という自己の損失のもとに利得を得たとして不当利得返還請求できるか。
まず,利得と損失の因果関係は社会通念上の因果関係があればよく,弁済を解しても認められる。
次に,「法律上の原因がない」とは正義公平の理念からみて,財産価値の移動をその当事者間において正当化するだけの実質的相対的理由がないという意味と解する。
したがって,弁済受領者に弁済金が騙取金であることにつき悪意あるいは重過失がある場合にはこれがないといえ,不当利得返還請求をなしうると解する。
まず,利得と損失の因果関係は社会通念上の因果関係があればよく,弁済を解しても認められる。
次に,「法律上の原因がない」とは正義公平の理念からみて,財産価値の移動をその当事者間において正当化するだけの実質的相対的理由がないという意味と解する。
したがって,弁済受領者に弁済金が騙取金であることにつき悪意あるいは重過失がある場合にはこれがないといえ,不当利得返還請求をなしうると解する。
被害者の近親者は,被害者の生命侵害以外の場合にも固有の慰謝料請求ができないか。711条が生命侵害の場合に限っているようにも読めるため問題となる。
思うに同条の趣旨は,被害者死亡の場合に近親者が甚大な精神的苦痛を受けることに鑑み近親者の立証責任を軽減する点にあり,慰謝料請求の原因を生命侵害時に限る趣旨ではない。
そこで,近親者が被害者の生命を侵害された場合に比肩する程度の精神的苦痛を被るといえるような場合には,709・710条にもとづき慰謝料請求ができると解する。
思うに同条の趣旨は,被害者死亡の場合に近親者が甚大な精神的苦痛を受けることに鑑み近親者の立証責任を軽減する点にあり,慰謝料請求の原因を生命侵害時に限る趣旨ではない。
そこで,近親者が被害者の生命を侵害された場合に比肩する程度の精神的苦痛を被るといえるような場合には,709・710条にもとづき慰謝料請求ができると解する。
711条列挙者以外の者は慰謝料請求できないか。
思うに同条の趣旨は,被害者死亡の場合に近親者が甚大な精神的苦痛を受けることに鑑み近親者の立証責任を軽減する点にあり,請求権者を限定する趣旨ではない。
そこで,711条列挙者に準じる立場にある者については711条を類推適用して,立証責任の負担を軽減するべきである。
思うに同条の趣旨は,被害者死亡の場合に近親者が甚大な精神的苦痛を受けることに鑑み近親者の立証責任を軽減する点にあり,請求権者を限定する趣旨ではない。
そこで,711条列挙者に準じる立場にある者については711条を類推適用して,立証責任の負担を軽減するべきである。
被害者が死亡すると権利能力を失い,損害賠償請求権を取得することはないと考えると権利は相続することはできないとも思える。
しかし,これでは受傷した場合と比べて不均衡であるし,不法行為と死の間に観念的には時間間隔を認めることができ,損害賠償請求権の取得を観念できる。
そこで,死亡により生じた逸失利益や慰謝料も相続することができる。
なお,慰謝料請求権は一身専属権であり,本人の行使の意思によらず発生するか,本人の意思によらず当然に相続されるか問題となるも,慰謝料請求権も単純な金銭債権であるため本人の意思表示の有無にかかわらず不法行為時に当然に発生して当然に相続されると解する。
しかし,これでは受傷した場合と比べて不均衡であるし,不法行為と死の間に観念的には時間間隔を認めることができ,損害賠償請求権の取得を観念できる。
そこで,死亡により生じた逸失利益や慰謝料も相続することができる。
なお,慰謝料請求権は一身専属権であり,本人の行使の意思によらず発生するか,本人の意思によらず当然に相続されるか問題となるも,慰謝料請求権も単純な金銭債権であるため本人の意思表示の有無にかかわらず不法行為時に当然に発生して当然に相続されると解する。
不法行為により間接的に損害を受けるにすぎない者からの損害賠償請求は原則的に認められない。これを認めれば損害賠償の範囲が広がりすぎ,不法行為者に酷だからである。
もっとも,ある会社の社長が不法行為により受傷した場合,その会社が個人会社で,社長に会社の機関としての代替性がなく,両者が経済的に一体をなすような事実関係があるときは,会社は社長の就労不能により被った会社の営業上の逸失利益につき不法行為者に対して損害賠償請求できると解する。
もっとも,ある会社の社長が不法行為により受傷した場合,その会社が個人会社で,社長に会社の機関としての代替性がなく,両者が経済的に一体をなすような事実関係があるときは,会社は社長の就労不能により被った会社の営業上の逸失利益につき不法行為者に対して損害賠償請求できると解する。
責任能力のある未成年者から不法行為を受けたが,加害未成年者が無資力である場合,親権者に損害賠償できないか。
未成年者は責任能力があるから,714条による責任追及できないことから問題となる。
この点については,親権者は未成年者の監護義務(820・857条)を負っているのであるから,親権者に監督上の不注意があればかかる監護義務違反と相当因果関係のある範囲内で親権者に709条による不法行為責任を追及できる。
未成年者は責任能力があるから,714条による責任追及できないことから問題となる。
この点については,親権者は未成年者の監護義務(820・857条)を負っているのであるから,親権者に監督上の不注意があればかかる監護義務違反と相当因果関係のある範囲内で親権者に709条による不法行為責任を追及できる。
「事業の執行について」(715条)の意義が明文上明らかでなく問題となる。
思うに,715条の趣旨は,他人を利用して利益を受けている以上そこから生じる損失も負担するべきという報償責任の法理のもと,損害の公平な分担を図る点にある。
かかる趣旨からすると,被害者は広くそれが職務行為だと信じた者まで保護されるべきであり,事業執行やこれと密接関連ないし付随業務のみならず,行為の外形を基準として職務に属するといえるものを含むと解する(外形標準説)。
ただし,上述の理論は外形を信頼した者を保護する趣旨であるので,その内実につき悪意重過失がある場合は使用者は責任を負わないと解する。
思うに,715条の趣旨は,他人を利用して利益を受けている以上そこから生じる損失も負担するべきという報償責任の法理のもと,損害の公平な分担を図る点にある。
かかる趣旨からすると,被害者は広くそれが職務行為だと信じた者まで保護されるべきであり,事業執行やこれと密接関連ないし付随業務のみならず,行為の外形を基準として職務に属するといえるものを含むと解する(外形標準説)。
ただし,上述の理論は外形を信頼した者を保護する趣旨であるので,その内実につき悪意重過失がある場合は使用者は責任を負わないと解する。
使用者責任を果たした使用者は,715条3項により被用者に求償することができるが,求償額は制限されないか。
この点,使用者責任が代位責任であることを強調すれば全額求償できるとも考えられるが,使用者は被用者を使用して利益を得ている以上,その事業の執行につき生じた損害を使用者が全く負担しないのは公平ではない。
そこで,労働環境や労働条件など様々な事情を総合的に考慮して,求償は信義則上相当な限度に制限されると解する。
この点,使用者責任が代位責任であることを強調すれば全額求償できるとも考えられるが,使用者は被用者を使用して利益を得ている以上,その事業の執行につき生じた損害を使用者が全く負担しないのは公平ではない。
そこで,労働環境や労働条件など様々な事情を総合的に考慮して,求償は信義則上相当な限度に制限されると解する。
過失相殺における「過失」(722条2項)があるといえるためには責任能力が前提となるか。
思うに,同条の趣旨は,損害の公平な分担から被害者にも不注意等があり損害の発生に寄与した場合にこれを考慮する点にある。
とすれば同条の過失が認められるためには責任能力がなくてもよく,事理弁指揮能力があれば足りると解する。
思うに,同条の趣旨は,損害の公平な分担から被害者にも不注意等があり損害の発生に寄与した場合にこれを考慮する点にある。
とすれば同条の過失が認められるためには責任能力がなくてもよく,事理弁指揮能力があれば足りると解する。
被害者以外のものに過失があった場合,過失相殺の対象とはならないか。
この点,過失相殺の趣旨は,損害の公平な分担のため被害者にも不注意等があり損害の発生に寄与した場合にこれを考慮する点にあるから,被害者側の一定の者に過失がある場合はこれを考慮した方が公平であるといえる。
そこで,被害者と身分上・生活関係上一体をなすと認められる関係にある者の過失は過失相殺の対象となると解する。
この点,過失相殺の趣旨は,損害の公平な分担のため被害者にも不注意等があり損害の発生に寄与した場合にこれを考慮する点にあるから,被害者側の一定の者に過失がある場合はこれを考慮した方が公平であるといえる。
そこで,被害者と身分上・生活関係上一体をなすと認められる関係にある者の過失は過失相殺の対象となると解する。
被害者の身体的素因により損害が発生または拡大した場合,過失相殺規定の類推適用により加害者責任の減額が認められないか。
思うに,過失相殺の趣旨は,被害者側の事情が損害の発生に寄与した場合に,これを考慮して損害の公平な分担を図る点にあるから,このような場合にも類推適用の余地がある。
もっとも,身体的特徴については真に極端なものを除いては個々人の個体差としてその存在が予定されているといえるからこれを考慮すべきではない。
そこで,損害賠償額の算定にあたり被害者の身体的疾患は考慮することができるが(722条2項類推適用),それが疾患に至らない程度の身体的特徴にすぎない場合は斟酌できないと解する。
思うに,過失相殺の趣旨は,被害者側の事情が損害の発生に寄与した場合に,これを考慮して損害の公平な分担を図る点にあるから,このような場合にも類推適用の余地がある。
もっとも,身体的特徴については真に極端なものを除いては個々人の個体差としてその存在が予定されているといえるからこれを考慮すべきではない。
そこで,損害賠償額の算定にあたり被害者の身体的疾患は考慮することができるが(722条2項類推適用),それが疾患に至らない程度の身体的特徴にすぎない場合は斟酌できないと解する。

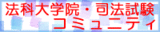
コメントをかく