最終更新:
 barexam12346hacks 2010年08月19日(木) 15:41:28履歴
barexam12346hacks 2010年08月19日(木) 15:41:28履歴
- 争点を中心に書く→論点主義,人権パターンの消滅
- (原告の立場で,あるいは被告(人)の立場で)当事者に有利な主張を徹底して述べる
- 違憲審査基準は,事例に応じて柔軟に選択。それこそが実務家
- 法令違憲と適用違憲の峻別と答案化
(新司法試験)論文試験の戦略(sunさんのブログ「新・単なる勉強記録」より) 
本番で目標とする答案は
目標答案=平均的合格答案+上位合格答案
#マニアックな答案を書くのではなく,平均的合格答案の条件を満たしたうえで
http://yaruze08.seesaa.net/article/107991656.html
目標答案=平均的合格答案+上位合格答案
#マニアックな答案を書くのではなく,平均的合格答案の条件を満たしたうえで
http://yaruze08.seesaa.net/article/107991656.html
上位合格答案=配点事項をほとんど拾っている答案
なお,配点事項は,
- 過去問の出題趣旨・ヒアリング・再現答案を分析すること
- 問題文の事実・誘導に沿って書くこと
#配点事項を見抜けたからといって,それを答案に示せなければ点数にはならない。
そのためには、まずは、問題文を読んでも何を書いたらいいのか分からない、あさってなことを書いてしまう、という段階をクリアしなければなりません。処方箋としては、知識・処理パターンを多く身に付けることしかないと思います。
一方,平均的合格答案については,普通の答案構成をする。
普通の答案構成の仕方は,
知識としてストックされている判例・裁判例のうち、最も近いと思われるものを持ってきて、問題文の事案との対比をしつつ考えていくことです。
さらに重要なのは、上記の作業を誘導に乗りつつ行うことです。今年も、公法系ではあからさまな誘導が付いていました。その誘導文をよく読んで、そこから絶対に外れないようにしなければなりません。
http://yaruze08.seesaa.net/article/107991739.html
迷ったときは原則として書く。
ただし,他の事項と矛盾を生じさせる場合や,時間不足でそれを書くことで他のより重要なものを書けなくなる場合には書かない。
実際に構成するにあたっては、書くか書かないか迷ったときはどうするか、と言う問題が出てきます。ここでは、採点基準が減点式なのか、加点式なのか、という大問題に直面しますね。僕は、再現答案の分析などから、「原則として加点式であり、無駄なことを書いても無益的記載事項としてスルーされる。しかし、それを書くことにより他の記載事項と矛盾を来す場合には、その事項において減点(=必要な点数がもらえない)されることもあるし、裁量点に影響することもある。」という説を立ててそれに従うことにしました。
http://yaruze08.seesaa.net/article/107992453.html
1.文面的には…
1)問題提起
問題提起には配点があるかは分かりませんが、問題の所在を適切に指摘している答案は非常に読みやすいですし、全体としてのまとまりも出てくるように思います。ただし、問題提起は前菜に過ぎませんので、長くなりすぎないようにコンパクトにすることが必要です。
具体的な問題提起の書き方については、教科書・判例や、答案の書き方の本、再現答案を読むなりして自分なりの書き方を身に付けてください。書き方は問題によりけりなので、何よりもたくさん書いて慣れることです。
こう書くと何でも問題提起をしたくなってしまう人が出てきてしまうかもしれませんが、もちろん法律の文言に素直に当てはまるような事例については、問題提起などする必要はありませんよ。何事も臨機応変に、ということです。
2)法律論
- 条文と絶対に書かなければならないキーワードを押さえる必要がある
- そのキーワードは,これも教科書を読むなどして勉強するしかない
- 論証パターンや定義を暗記する必要はなく,各論証・定義のキーワードだけを押さえ,答案を書く際に文章として再現する
- ただし,有名論点・重要な定義は丸暗記必要
- 規範の理由は,原則として簡単に書く。例外は理由の必要もないようなものについては書かない。
- 争いがあり問題文からしてそこを厚く書いてほしそうなときには,時には反対論も挙げつつ長々と書く(要は臨機応変)
3)あてはめ
可能な限り全事実を拾った上で、それぞれの事実について自分なりの評価を加えるようにしていました。新司法試験では事実が増えた分、不要な事実も混じっているとの説もありますが、僕はそうは考えず、拾いまくることにしていました。
2. 答案を書くスピードをあげる
-脳の出力速度(文章をひねり出す力)を上げること
-字を書くスピードを上げること
脳の出力速度を上げるためには、まずは記憶されている知識を、脳の記憶の貯蔵庫から取り出す速度を上げなければなりません。それには、必要な知識を繰り返しインプット・アウトプットしておくことしかないでしょう。
次に、キーワードを繋いで文章をひねり出す速度を上げることができるでしょう。それには、ただひたすら慣れるしかありません。つまり、答案を書きまくることです。
字を書くスピードを上げるためには、書くために必要な手の筋肉を付けること、そして適切な筆記具を選ぶことが必要です。前者については、これも答案練習を繰り返すうちに、だんだんと早くなってきます。後者は、各自いろいろなペンを試してみて、自分にあったものを選ぶしかないでしょう。
なおお勧めのペンは
http://yaruze08.seesaa.net/article/107993751.html
- 読みやすい文字であること
- 読みやすい文章であること
- 条文を正確に引用していること
- 基本的な判例が正確に引用されていること
- 基本的な知識が正確に書かれていること
- 論理的な文章になっていること
- 流れのよい答案であること(接続詞)
- 基本的な論点について正確に論証されていること
- 問題文にきちんと答えていること
- 聞かれたことだけに答えていること
p.146より引用

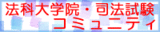
コメントをかく