筆者の主観になりますが、日本の大会や掲示板では中国の要塞環境などに比べてパクリを禁止する風潮が強かったと考えています。
(筆者が掲示板を見るようになったのが2012年以降なので、2012年に入る前の環境については掲示板のログを見ての内容となっています)
つまり、パクリが禁止される風潮とは当時日本の掲示板での環境そのものなのではないかという前提が成り立つと考えています。
(前提として、パクリの規制を激化させた場合を想定した話なので、実際に現在何かしらの企画でこういう事例があるのではないか!と異議を唱える旨ではありません。)
あくまで1意見ですがパクリの規制を強くした場合、パクリに抵触することなく大会に出せる要塞は何があるのかを前提に要塞を作ることになります。
これはすでに何かしらの要塞タイプで活躍をしたことのある場合には同じ要塞タイプを作った際にリメイクといえるのに対して
新たに参入する者にとって大きなハードルとなると考えられます。
要塞の研究が進んだ2022年現在においても、強い要塞は構成が似ることが顕在化していますが、
それは2012年当時でもすでにあり強い要塞は要塞タイプとともに構成がある程度固まっている状況でした。
具体例を挙げるとすると、教科書要塞群が典型例といえます。
教科書要塞群は2012年当時では教科書群2.0がすでに完成され、3.0の作成が始められた時期でしたが
要塞タイプごとに定番の構成が確立されていることになります。
これはをお手本として考えて、要塞の連戦や改良につなげられればこの上なく効果的であり、
いわゆる教科書になり得る要塞群だと思いますが、似た構成で作る際にパクリ判定を受けるリスクになりえると考えられます。
また、後述する最適化の項目でも触れる予定ですが、
パクリの判定には「原作を超えないアイデアの盗作」という所が大きく絡んでいると考えられます。
要塞の研究は激化し年々完成度が上がっている点を考慮すると、
パクリの規制が厳しすぎれば自作を主張できる要塞タイプが非常に少なくなるのではないかという懸念があります。
(筆者が掲示板を見るようになったのが2012年以降なので、2012年に入る前の環境については掲示板のログを見ての内容となっています)
つまり、パクリが禁止される風潮とは当時日本の掲示板での環境そのものなのではないかという前提が成り立つと考えています。
(前提として、パクリの規制を激化させた場合を想定した話なので、実際に現在何かしらの企画でこういう事例があるのではないか!と異議を唱える旨ではありません。)
あくまで1意見ですがパクリの規制を強くした場合、パクリに抵触することなく大会に出せる要塞は何があるのかを前提に要塞を作ることになります。
これはすでに何かしらの要塞タイプで活躍をしたことのある場合には同じ要塞タイプを作った際にリメイクといえるのに対して
新たに参入する者にとって大きなハードルとなると考えられます。
要塞の研究が進んだ2022年現在においても、強い要塞は構成が似ることが顕在化していますが、
それは2012年当時でもすでにあり強い要塞は要塞タイプとともに構成がある程度固まっている状況でした。
具体例を挙げるとすると、教科書要塞群が典型例といえます。
教科書要塞群は2012年当時では教科書群2.0がすでに完成され、3.0の作成が始められた時期でしたが
要塞タイプごとに定番の構成が確立されていることになります。
これはをお手本として考えて、要塞の連戦や改良につなげられればこの上なく効果的であり、
いわゆる教科書になり得る要塞群だと思いますが、似た構成で作る際にパクリ判定を受けるリスクになりえると考えられます。
また、後述する最適化の項目でも触れる予定ですが、
パクリの判定には「原作を超えないアイデアの盗作」という所が大きく絡んでいると考えられます。
要塞の研究は激化し年々完成度が上がっている点を考慮すると、
パクリの規制が厳しすぎれば自作を主張できる要塞タイプが非常に少なくなるのではないかという懸念があります。
こちらも想定の話になるので今現在どこどこの企画の判定が甘すぎる!など異議を唱える旨ではないです。
パクリを広く許容した場合、戦術について100時間研究し新たな要塞を作ろうとも、
1時間の研究の中で強いと思った要塞を偶然見つけて大会に転用しようとも同じ戦績を上げられます。
これは戦術の研究に時間をすることに価値を感じなくなる懸念があります。
パクリによって戦術を研究する価値が損なわれてしまうことがもったいないとは感じます。
が、それはあくまで要塞を作り、研究をする上での評価軸だとも考えます。
要塞は自分で作り、研究するだけでなくほかの楽しみ方があってよいと思いますが、
「その一つに大会環境を読み、適した要塞を選出することで勝つ面白さ」があってもよいと考えています。
長年、要塞で勝つためにどんな研究が必要かを考える癖がついてしまっているので、
あくまで勝ちに固執した価値観に寄っていますが、要するにもともとそういうものとして考えれば楽しめるのではないかということです。
パクリを広く許容した場合、戦術について100時間研究し新たな要塞を作ろうとも、
1時間の研究の中で強いと思った要塞を偶然見つけて大会に転用しようとも同じ戦績を上げられます。
これは戦術の研究に時間をすることに価値を感じなくなる懸念があります。
- 作ることに特化した評価軸
パクリによって戦術を研究する価値が損なわれてしまうことがもったいないとは感じます。
が、それはあくまで要塞を作り、研究をする上での評価軸だとも考えます。
要塞は自分で作り、研究するだけでなくほかの楽しみ方があってよいと思いますが、
「その一つに大会環境を読み、適した要塞を選出することで勝つ面白さ」があってもよいと考えています。
長年、要塞で勝つためにどんな研究が必要かを考える癖がついてしまっているので、
あくまで勝ちに固執した価値観に寄っていますが、要するにもともとそういうものとして考えれば楽しめるのではないかということです。
主観に寄りすぎてもよくないとは思いつつ、
主観がないことには書けない手前あくまで個人の考えをここに記しておくと結論としてはどっちでも良いと思っています。
信念がないのかといわれればそうかもしれませんが、
企画や大会ごとに違ってよいと考えています。
これは、そもそも企画者や大会主催者の提示するルールに納得いかないのであれば参加者自体集まらないと考えているためです。
一方で大会や企画を主催しルールを制定する以上、何かしらの不平や不満はあり、
全員が納得するルールというのもこれまた難しいものだと感じています。
つまり、大会や企画を主催する以上はこの反感を買おうとも貫き通す覚悟が一定必要だと考えていますが、
それでもなお開くという意思があるのであればそれはどの方針であれ興味はわきますし応援もしたくなるという考えです。
あくまで個人の考えでしかないので他人に押し付けるつもりはありませんが、
そんなこんなで大会主催者と自分とではパクリの判定が違う事例があるなと思いつつもそれも含めて面白いです。
大会や企画がたくさん出てくれるのを楽しみにしてます。
主観がないことには書けない手前あくまで個人の考えをここに記しておくと結論としてはどっちでも良いと思っています。
信念がないのかといわれればそうかもしれませんが、
企画や大会ごとに違ってよいと考えています。
これは、そもそも企画者や大会主催者の提示するルールに納得いかないのであれば参加者自体集まらないと考えているためです。
一方で大会や企画を主催しルールを制定する以上、何かしらの不平や不満はあり、
全員が納得するルールというのもこれまた難しいものだと感じています。
つまり、大会や企画を主催する以上はこの反感を買おうとも貫き通す覚悟が一定必要だと考えていますが、
それでもなお開くという意思があるのであればそれはどの方針であれ興味はわきますし応援もしたくなるという考えです。
あくまで個人の考えでしかないので他人に押し付けるつもりはありませんが、
そんなこんなで大会主催者と自分とではパクリの判定が違う事例があるなと思いつつもそれも含めて面白いです。
大会や企画がたくさん出てくれるのを楽しみにしてます。
パクリの判定について極端に二つに寄せて書きましたが、そうなると大会や企画ごとに基準を明確にしておくことが大事だと考えられます。
具体的な基準の例としては以下のようなものがあげられると思います
・完全なパスワード一致はNG
・80%以上ユニットの配置が一致する場合はNG
・要塞タイプや戦術ごとに配置が一致しても大丈夫な基準を定める
・主催者の主観と個人の偏見で決定
・パクリの疑いがあるものは主催者から参加者へ連絡を行い、参加者が主催者を納得させられれば参加許可を出す。(連絡がつかないか納得させられなければ参加取り消し)
・原作者に許可を得ているものは許可する
・すべてのパクリを許可する
等など。
いずれにしても、要塞の投稿を受け付け始めてから締め切りまでに一定の基準を提示しておいた上で、
それらを企画進行の期間貫きとおすことが公平な進行を行う上で必要だと思われます。
具体的な基準の例としては以下のようなものがあげられると思います
・完全なパスワード一致はNG
・80%以上ユニットの配置が一致する場合はNG
・要塞タイプや戦術ごとに配置が一致しても大丈夫な基準を定める
・主催者の主観と個人の偏見で決定
・パクリの疑いがあるものは主催者から参加者へ連絡を行い、参加者が主催者を納得させられれば参加許可を出す。(連絡がつかないか納得させられなければ参加取り消し)
・原作者に許可を得ているものは許可する
・すべてのパクリを許可する
等など。
いずれにしても、要塞の投稿を受け付け始めてから締め切りまでに一定の基準を提示しておいた上で、
それらを企画進行の期間貫きとおすことが公平な進行を行う上で必要だと思われます。
要塞の盗作・パクリであるかどうかの一つの基準にユニットの一致度合いがあげられます。
・原作が最適化されている場合
・師弟関係によって受け継いだ戦術、技術
・過去作のリメイク、アレンジ
・要塞タイプや戦術特有の性質
等によって判別がつかない場合があります。
場合によっては説明できない配置のほうが少ないことがあります。
この場合、完全に一致する配置があろうとも「パクリによるものだ」と結論付けるのが困難です。
それは既存要塞を何かしらの要塞群と連戦し、その中でユニットごとの役割や強みを学ぶ方法です。
他人の作成した要塞を連戦することで、ユニットごとの役割や強みを説明できるため、
パクリと言い切るのが難しくなります。 つまり、連戦から学ぶことはとても重要であるということです。
その一方で、師弟関係によって戦術や技術が受け継がれることもあります。
これは引退する前に伸びしろがありそうな新規勢がいるときに割とある現象だと思われます。
師弟関係とまでいかなくとも、鑑定スレによって培われる技術や経験も、
ある程度これに似通ったところがあり、助言した人と鑑定を受けた人で要塞の作りがどこかしら似るという現象があります。
この場合、要塞の作りが似たときに原作者や企画進行者ががどう考えるかでパクリ判定が変わるところですが、
要塞を作るうえで重視するポイントや考え方が似れば、おのずと要塞の作りも似る部分があると思われますので、ある程度は仕方ないのではないかとも考えられます。
連戦から要塞を学んだ場合、実際のところ0から要塞を考えて作らなくても
既存要塞をリメイク、アレンジすることで強くできてしまう例が存在します。
これは、要塞タイプが持つ強みを理解しているとほぼすべての要塞に言えてしまう共通の内容になりますが、
要塞タイプごとにそれぞれ次のようなポイントがあるのではないかと考えられます。
- 効果的かどうか
- あまり効果のない場合
・原作が最適化されている場合
・師弟関係によって受け継いだ戦術、技術
・過去作のリメイク、アレンジ
・要塞タイプや戦術特有の性質
等によって判別がつかない場合があります。
- 原作が最適化されている場合
場合によっては説明できない配置のほうが少ないことがあります。
この場合、完全に一致する配置があろうとも「パクリによるものだ」と結論付けるのが困難です。
- 要塞の性質はどのようにわかるか
それは既存要塞を何かしらの要塞群と連戦し、その中でユニットごとの役割や強みを学ぶ方法です。
他人の作成した要塞を連戦することで、ユニットごとの役割や強みを説明できるため、
パクリと言い切るのが難しくなります。 つまり、連戦から学ぶことはとても重要であるということです。
- 師弟関係によって受け継いだ戦術、技術
その一方で、師弟関係によって戦術や技術が受け継がれることもあります。
これは引退する前に伸びしろがありそうな新規勢がいるときに割とある現象だと思われます。
師弟関係とまでいかなくとも、鑑定スレによって培われる技術や経験も、
ある程度これに似通ったところがあり、助言した人と鑑定を受けた人で要塞の作りがどこかしら似るという現象があります。
この場合、要塞の作りが似たときに原作者や企画進行者ががどう考えるかでパクリ判定が変わるところですが、
要塞を作るうえで重視するポイントや考え方が似れば、おのずと要塞の作りも似る部分があると思われますので、ある程度は仕方ないのではないかとも考えられます。
- リメイク、アレンジ
連戦から要塞を学んだ場合、実際のところ0から要塞を考えて作らなくても
既存要塞をリメイク、アレンジすることで強くできてしまう例が存在します。
これは、要塞タイプが持つ強みを理解しているとほぼすべての要塞に言えてしまう共通の内容になりますが、
要塞タイプごとにそれぞれ次のようなポイントがあるのではないかと考えられます。
- 盾玉対策
例えば、射玉をx8ドット間隔で配置した場合盾玉に連続して攻撃をできますが、
射玉をx9ドット間隔よりも広げて配置してしまうと、攻撃の途中で盾玉が復帰してしまいます。
射玉の攻撃力は6であることを考えると、最低でもx6ドット以上離して配置するのがコスパが良く、
x8ドットいかに収めて配置することで盾玉相手の突破性能が高まることがわかります。
このように、盾玉対策の観点から射玉を使ったタゲの場合はx6〜8ドットずらしでの配置になることは必然的であるといえます。
- 壁玉対策
多くの要塞では防御に壁玉を使われますが、壁玉対策を考えると砲玉の配置はある程度規則性を持ったものになります。
砲玉の行動間隔は120Fなので、等間隔で弾幕を作ろうとすると
砲玉1体では120F間隔、
砲玉2体では60F間隔
砲玉3体では40F間隔
砲玉4体では30F間隔 でそれぞれ作れることがわかります。
対して壁玉の行動間隔は60Fです。
つまり、壁玉のバリアが途切れてから復帰するまでに60Fかかるということになります。
砲玉は行動間隔が120Fなので、2体いれば60F間隔で攻撃できることがわかり、
壁玉に強い配置を考えると必然的に60F間隔で着弾する配置になってしまいます。
この時、発射間隔が60Fでなくても、砲玉の角度や発射位置を調整することで50Fや70F間隔でも壁玉の復帰阻止をできるため、
完全にx60ドットずらしである必要性はないです。
勝ちたい相手に強くしたいとき、勝ちたい相手に60F間隔で着弾する配置になってしまうというだけなので、
タゲの射玉のx6〜8ドットずらしほど必然性はないと考えられます。。
突撃に限った話ではないですが、突撃では特に乗り込み耐性が大事だと考えることができます。
突撃は激突時のダメージを利用して攻撃ができますが、この攻撃手段は単純ながら広い要塞タイプに勝ち筋を作れます。
一方で、要塞タイプの弱点補完として補助乗りは大体のの要塞タイプで使えます。
簡単な乗り込みには負けないことが防御の固さにつながりやすく、
広い要塞タイプに勝ち筋を持てる突撃の性質から考えると乗り込み対策の重要性は高いといえます。
したがって、簡単な乗り込み対策として以下のような内容が一致しやすいと考えられます。
薙玉が土台に乗り込んでくる場合、
y191のコアまたはy261の要塞壁は薙玉の攻撃を食らわなくなります。
槍玉が土台に乗り込んでくる場合、
y118のコアまたはy188の要塞壁は槍玉の攻撃を食らわなくなります。
同じく、地面に落ちた近接ユニットの攻撃を食らわない配置も一致することが多いですが、
これらは無駄な攻撃を受けないように意識すると一致する内容であり、必然的に似るものだと考えられます。
他にも、近乗りやラビッツ、全速対応遠乗りなどを局所的に対策する方法がありますが、
好みが分かれそうな気もしたので今のところ掲載をしていません。
突撃は激突時のダメージを利用して攻撃ができますが、この攻撃手段は単純ながら広い要塞タイプに勝ち筋を作れます。
一方で、要塞タイプの弱点補完として補助乗りは大体のの要塞タイプで使えます。
簡単な乗り込みには負けないことが防御の固さにつながりやすく、
広い要塞タイプに勝ち筋を持てる突撃の性質から考えると乗り込み対策の重要性は高いといえます。
したがって、簡単な乗り込み対策として以下のような内容が一致しやすいと考えられます。
- 近接攻撃を食らわない配置
薙玉が土台に乗り込んでくる場合、
y191のコアまたはy261の要塞壁は薙玉の攻撃を食らわなくなります。
槍玉が土台に乗り込んでくる場合、
y118のコアまたはy188の要塞壁は槍玉の攻撃を食らわなくなります。
同じく、地面に落ちた近接ユニットの攻撃を食らわない配置も一致することが多いですが、
これらは無駄な攻撃を受けないように意識すると一致する内容であり、必然的に似るものだと考えられます。
他にも、近乗りやラビッツ、全速対応遠乗りなどを局所的に対策する方法がありますが、
好みが分かれそうな気もしたので今のところ掲載をしていません。
乗り込み戦術では着地や移動の直後に攻撃できるように調整されることが多いです。
これは、
・薙玉をはじめとした近接ユニットは、一度攻撃を始めると移動や死亡に関係なく攻撃を空間に残せる
(※見た目の上では攻撃範囲が消えるが、ダメージ判定は行われる)
・砲玉や導玉、射玉や核玉などの遠距離攻撃ユニットは体力が10と比較的少なく、隙となる着地や移動後の待機時間が極力少ないほうが高い火力を出しやすい
などの点から必然的になりやすいです。
また、遠壁に乗せる場合は着地直後に攻撃できる配置がすでに開拓されており、
近壁によって乗り込ませる場合でも薙玉や槍玉などでは着地直後に攻撃できる配置が発見されているため、
これらの配置は特に一致しやすいと考えられます。
これは、
・薙玉をはじめとした近接ユニットは、一度攻撃を始めると移動や死亡に関係なく攻撃を空間に残せる
(※見た目の上では攻撃範囲が消えるが、ダメージ判定は行われる)
・砲玉や導玉、射玉や核玉などの遠距離攻撃ユニットは体力が10と比較的少なく、隙となる着地や移動後の待機時間が極力少ないほうが高い火力を出しやすい
などの点から必然的になりやすいです。
また、遠壁に乗せる場合は着地直後に攻撃できる配置がすでに開拓されており、
近壁によって乗り込ませる場合でも薙玉や槍玉などでは着地直後に攻撃できる配置が発見されているため、
これらの配置は特に一致しやすいと考えられます。
複合要塞の場合、勝てる範囲を広げる組み合わせの関係上配置が一致せずとも
構成が似ることが多々あります。
設計思想が似ている場合や、勝率を測る連戦対象が同じ場合は似た構成になることが多いので、
連戦対象の要塞群を有名なものしか使っていない場合には複合要塞でも要塞の構成が似ることがあります。
構成が似ることが多々あります。
設計思想が似ている場合や、勝率を測る連戦対象が同じ場合は似た構成になることが多いので、
連戦対象の要塞群を有名なものしか使っていない場合には複合要塞でも要塞の構成が似ることがあります。
- 特化的な役割
星玉、魔玉、射玉、忍玉などによるコア位置ごとの特化攻撃が顕著な例ですが、
これらは役割が特化的であるため、「勝ちたいと思われる要塞」が共通であるときに似た構成になることがあります。
例えば、強い要塞にはx54+60nの壁玉(ダメージを受けた後に最速で復帰する配置)が使われることが多いため、
これに特化的に強いx73+250nの星玉やx15+150nの魔玉などが同じような使われ方をすることがあります。
タグ

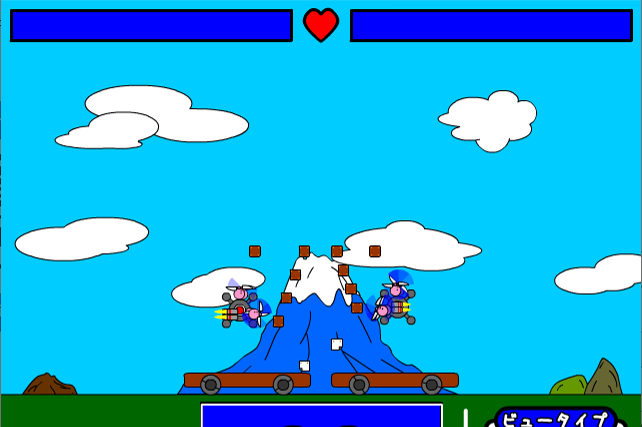

コメントをかく